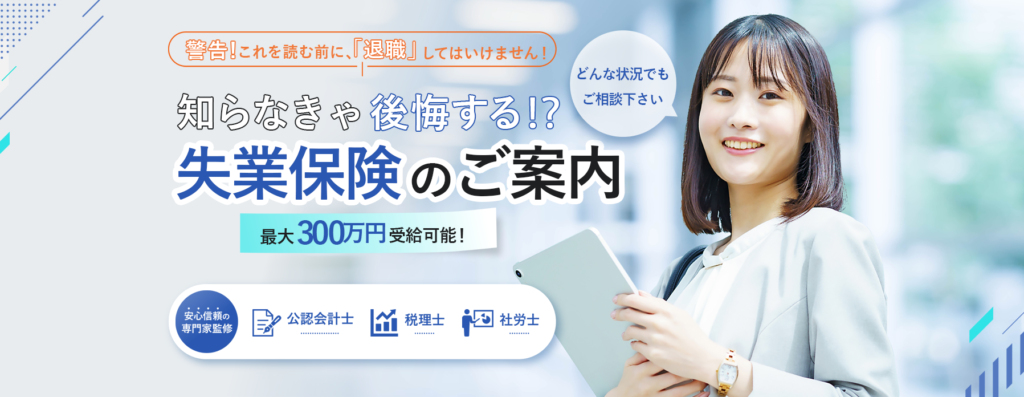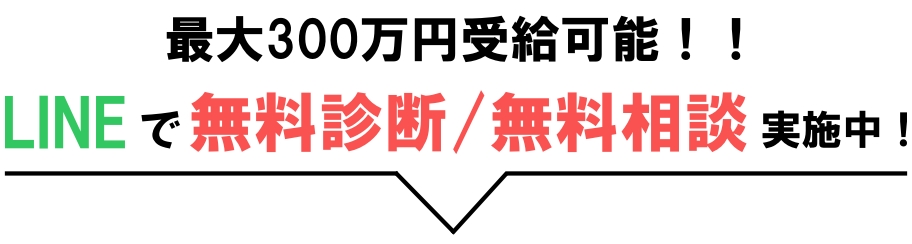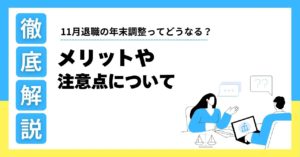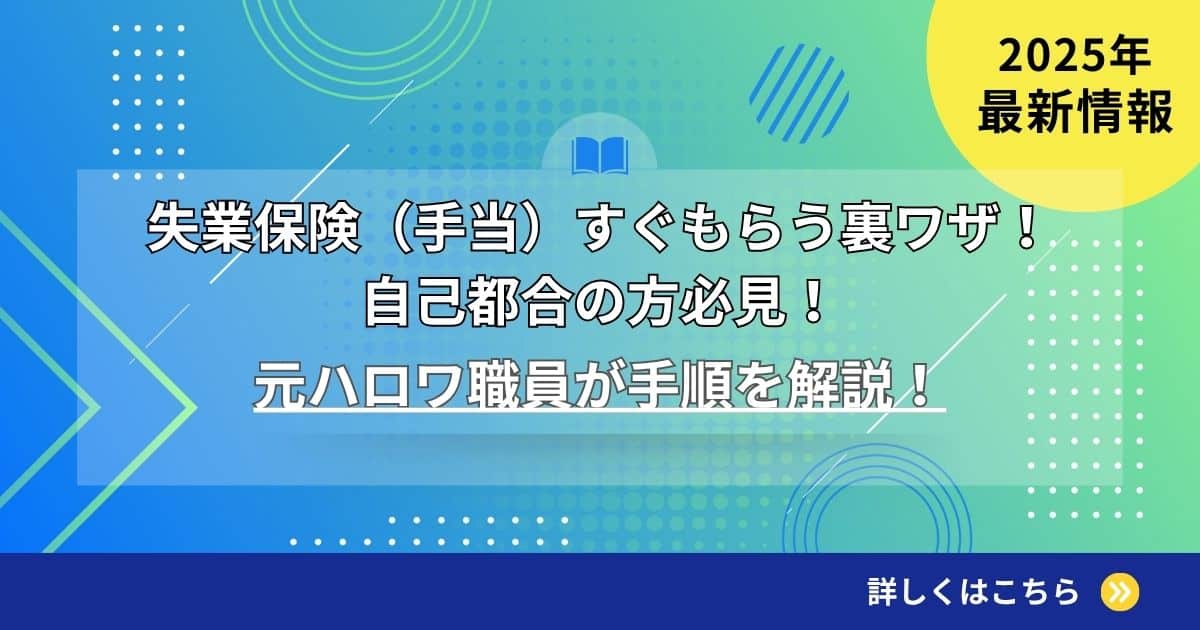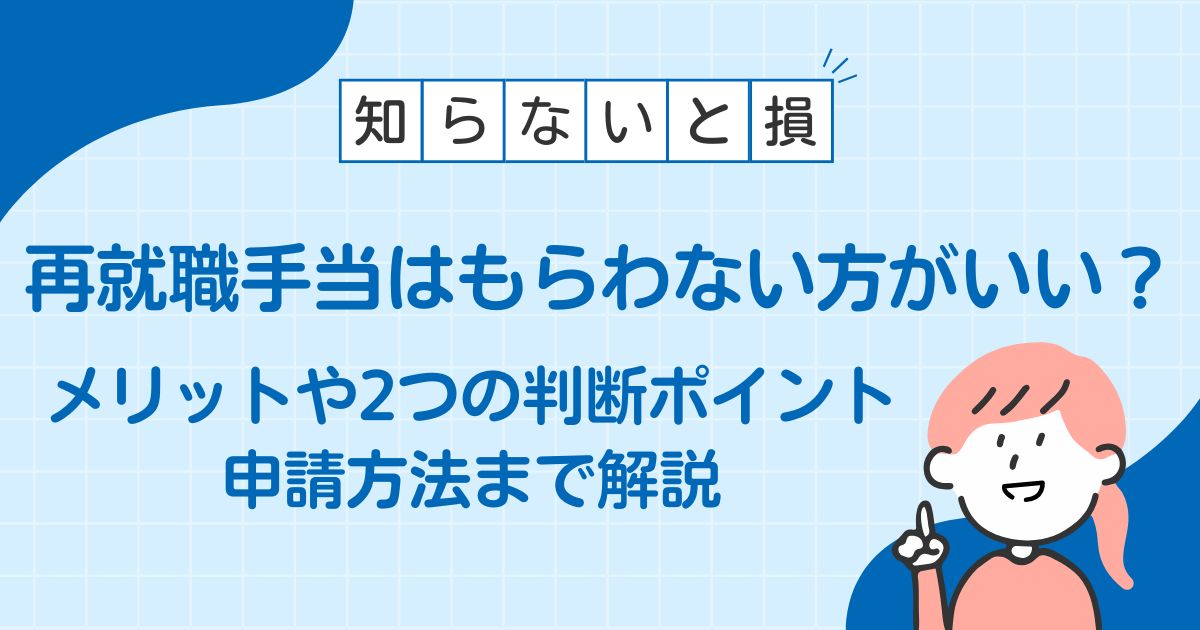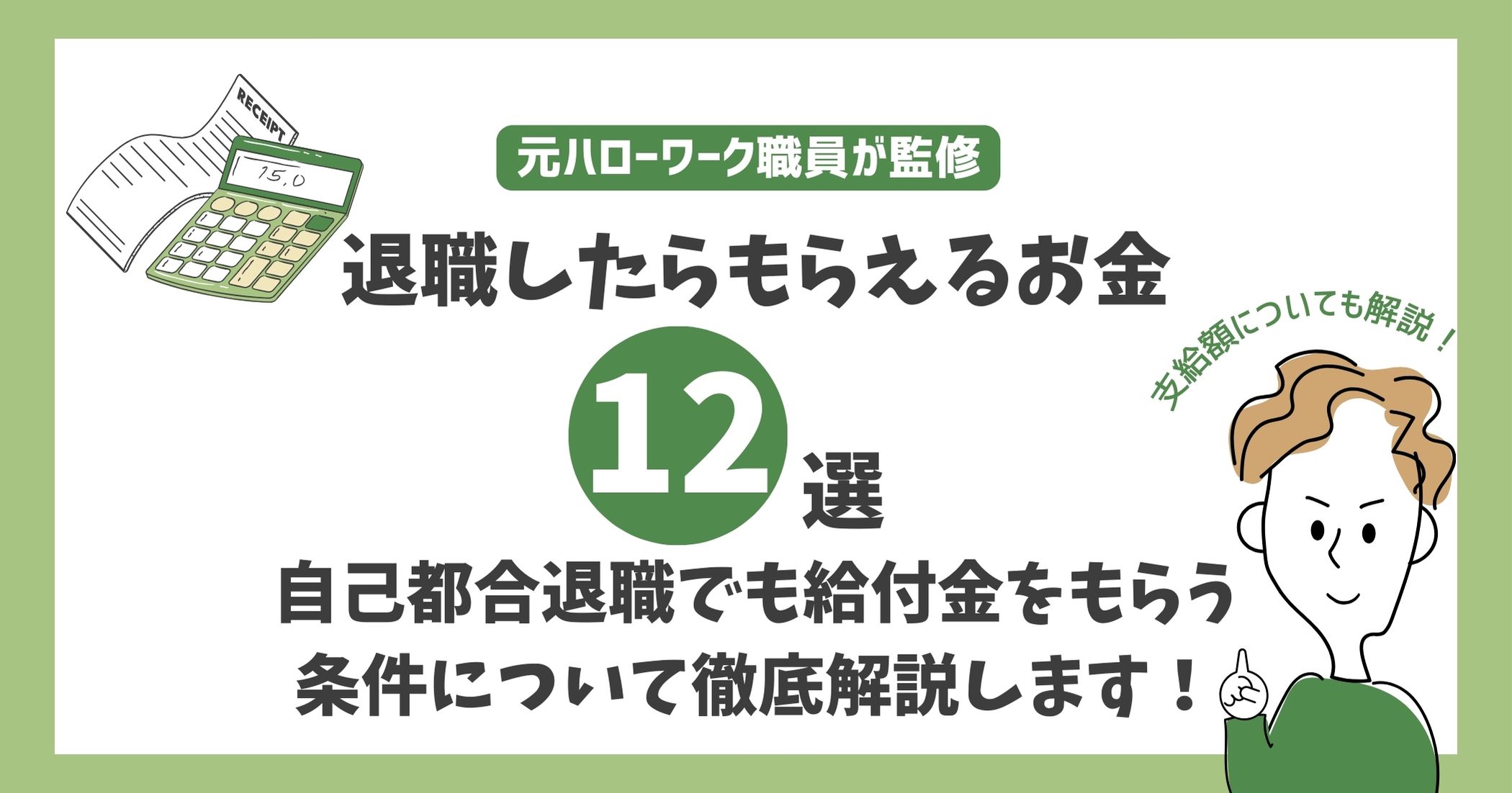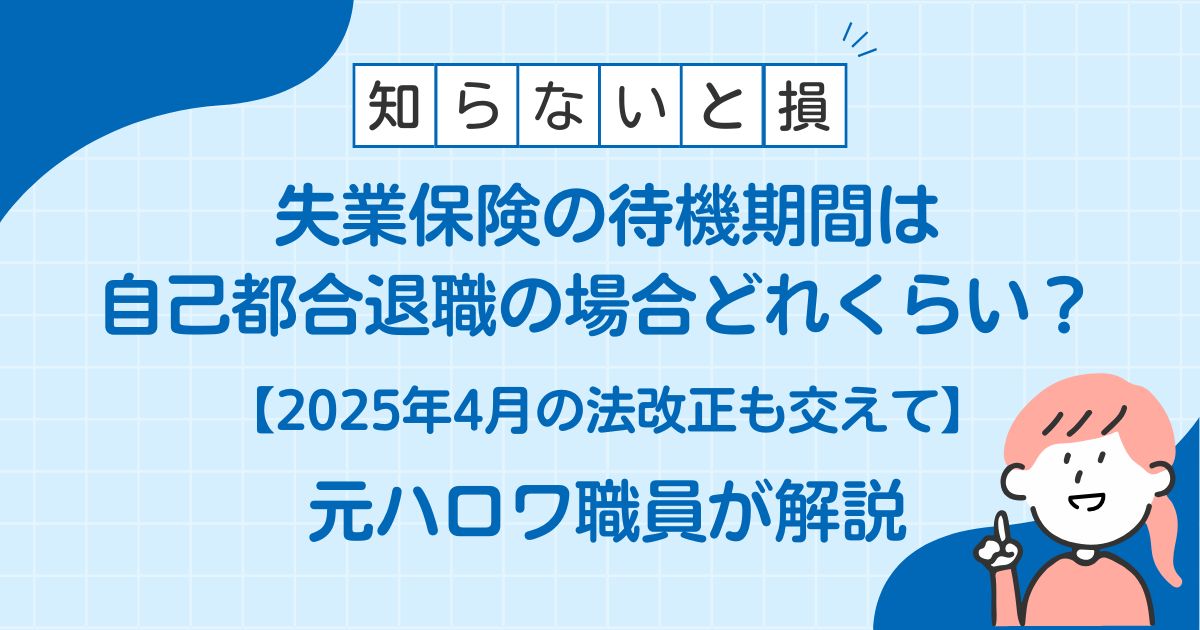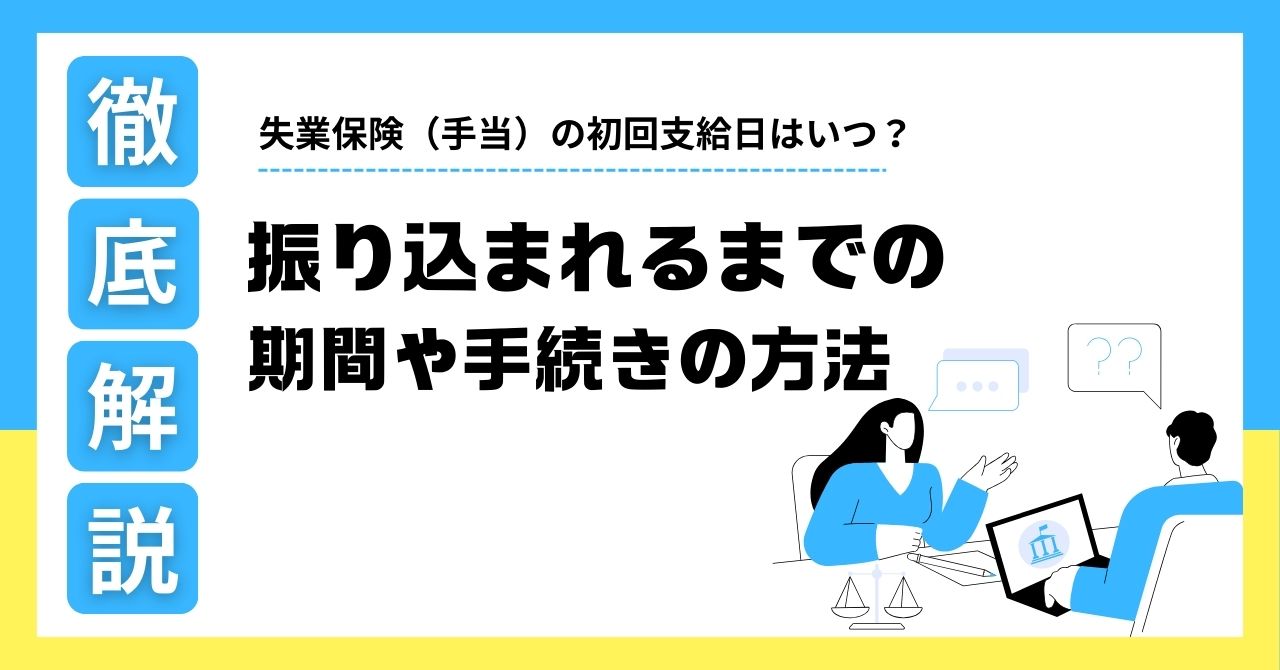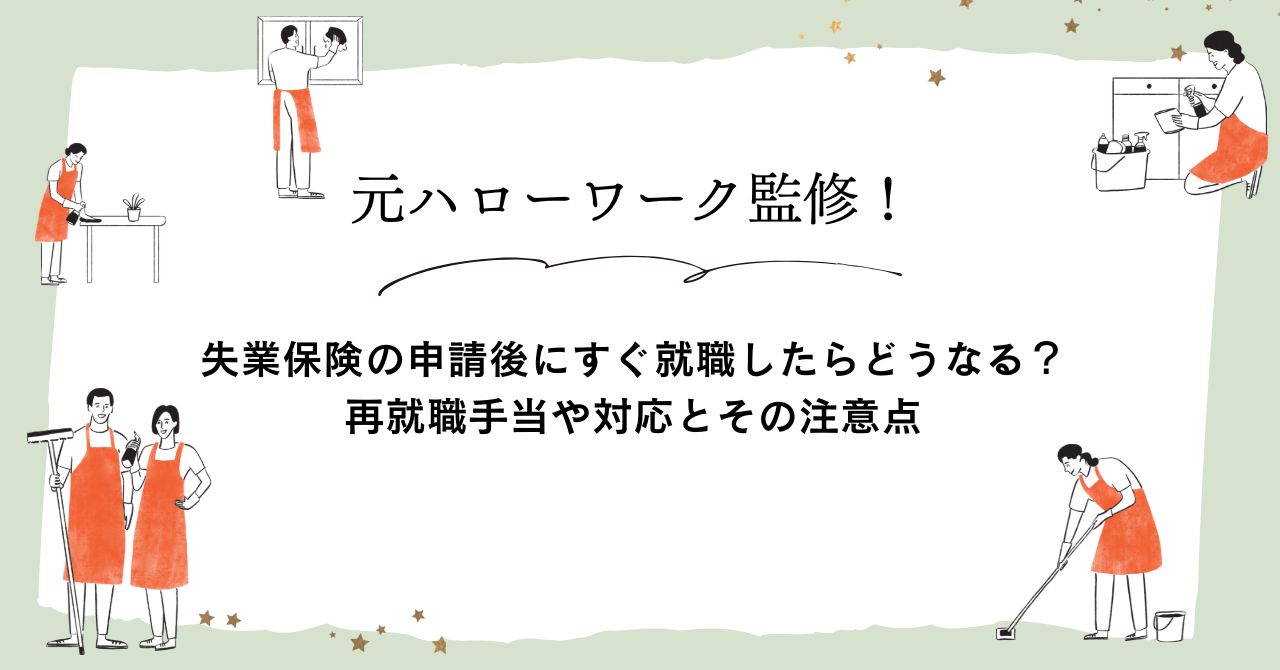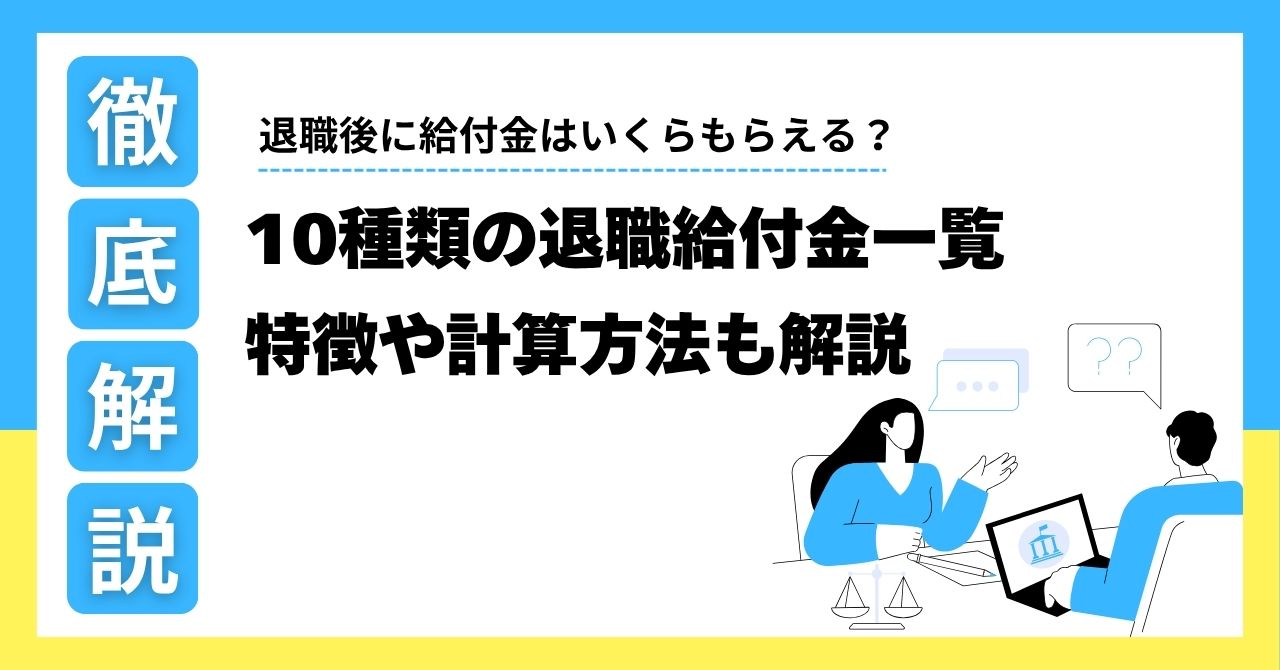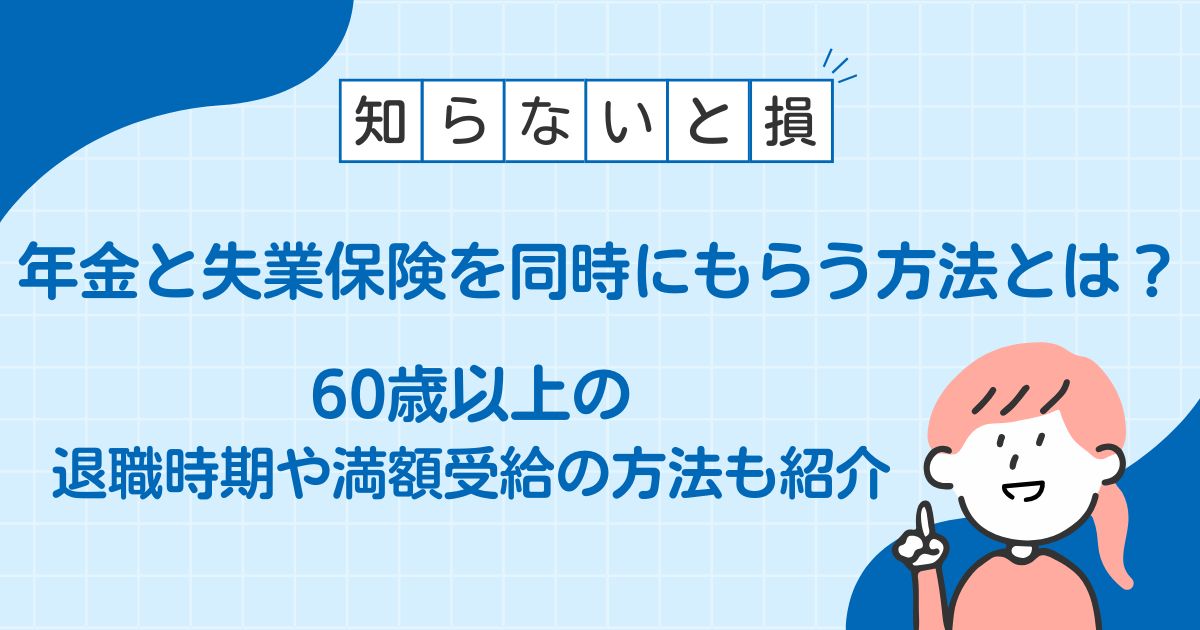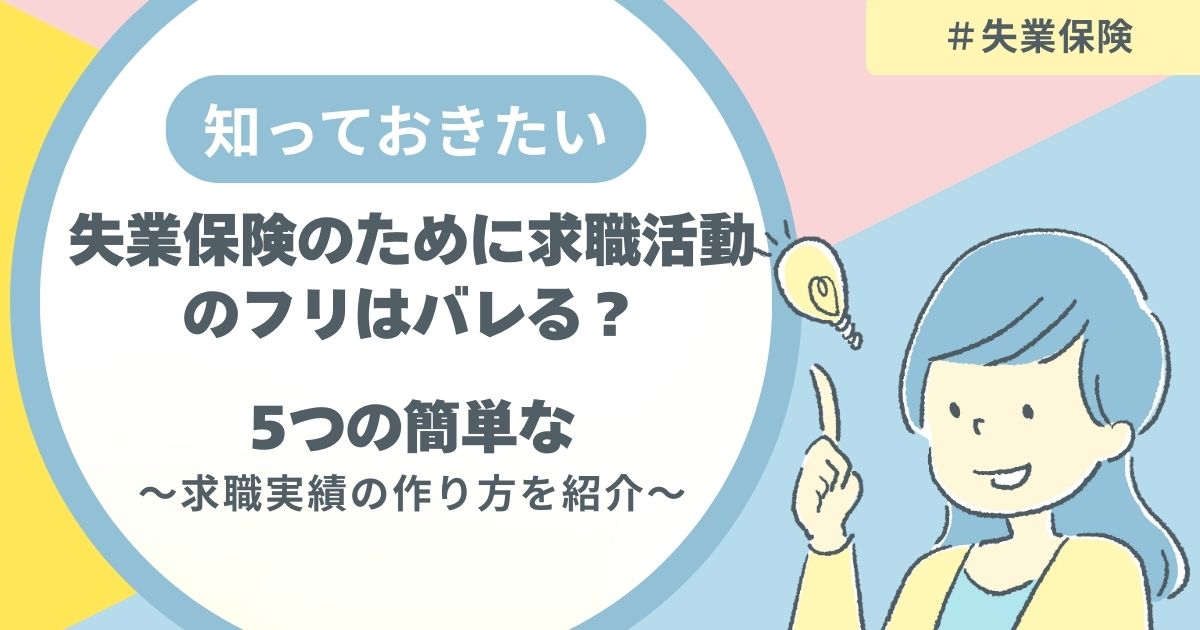元ハロワ職員<br>佐藤
元ハロワ職員<br>佐藤この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 適応障害で退職したいけど逃げなのかな…
- 適応障害で退職をすると後悔するのかな?
このようにお悩みではありませんか?
適応障害とはストレス性障害とも呼ばれるもので、不眠や意欲低下などの症状が出ている状態のことです。適応障害になると仕事に行けなくなったり、行動が億劫になったりします。退職する方もいますが、中には後悔するのではないかと不安な方もいるでしょう。
 元ハロワ職員<br>佐藤
元ハロワ職員<br>佐藤そこでこの記事では、適応障害で退職をすると後悔をするのかについて紹介します。
辞めるときの注意点も解説しているため、適応障害の方は必見の内容です。ぜひ最後までご覧ください。
今すぐ退職後の手当を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。

適応障害とは?

適応障害とは、特定の状況や出来事が原因で行動や気分に症状が現れるものです。神経が過敏になるため周囲を気にしやすくなったり、憂うつな気分になりやすくなったりします。
適応障害になると仕事に行くのが怖いと感じて、食事や睡眠が十分に取れなくなります。生活に支障が出ることもあり、仕事を辞めるケースも珍しくありません。
適応障害で退職しても後悔しない理由

適応障害によって仕事に行くのが億劫になり、退職を検討することはよくあります。適応障害で退職するのは甘えだと引き目を感じる方もいますが、適応障害による退職は逃げではありません。
退職を後悔しない理由には、以下の2つが挙げられます。
退職を後悔しない理由
- 転職をして適応障害が治る可能性があるため
- 無理して働いて適応障害を悪化させると治療に時間がかかるため
そもそも職場の人間関係が悪い、業務量が多すぎるのが原因で適応障害が発症した場合、転職をすれば治る可能性が高いです。
このようなケースは、自分の努力による改善が難しいため、転職をするのが現実的です。無理をして働けば適応障害が悪化し、治療に余計時間がかかるので、本当に無理だと感じたら辞めるのも1つの手段です。
適応障害で退職をするデメリット

適応障害による退職は逃げではないものの、以下のデメリットもあります。
適応障害で退職をするデメリット
- 必ずしも次の職場が自分に合うとは限らない
- 経済的な負担が生じる
- 次の仕事が決まるまでのブランクが生まれる
転職先で人間関係や業務量で悩む可能性がないとはいえません。そもそも自分の働いている業界が激務、上下関係が厳しい場合は、転職しても再び悩む可能性があります。
また、貯蓄がない方であれば生活が不安定になったり、次の仕事が決まるまでのブランクも生まれるため、精神的なプレッシャーが大きくなる場合もあります。
適応障害で退職を勧められたときにするべきこと

適応障害で退職を勧められた際は、以下5つのことを行うのが大切です。
- 主治医・産業医に相談をする
- 適応障害の原因や経緯などを上司に相談をする
- 担当業務の内容や量の調整に関して相談する
- 休職して体調が回復するか様子を見る
- 家族などの信頼できる相手に相談して判断する
それぞれの行動を詳しく解説します。
なお、退職前にやっておくことに関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

①主治医・産業医に相談をする
心身の不調が出ていても、自分が適応障害なのを自覚していないケースがあります。
そのため、心身の不調を感じた際は、主治医・産業医に相談をして適応障害の診断を受けるのが大切です。
産業医がいない場合は心療内科を受診し、医師のアドバイスのもと、今後の進路を決めましょう。なお、自己診断や自己流で治療をするのは症状悪化につながるため避けてください。
②上司に相談をする
適応障害の状態で今までのように働くと症状悪化につながりますが、業務量を見直すと症状は改善されるかもしれません。
また、人間関係の場合は部署異動、疲労の場合は休職など改善方法はさまざまあるため、いずれの方法を行うにも、上司への相談が必要です。適応障害との診断が降りていれば、話もスムーズに進みます。
③担当業務の内容や量の調整に関して相談する
適応障害で退職を勧められた際は、担当業務の内容や量の調整に関して上司に相談し、変更してもらえるか打診するのも大切です。業務内容が難しい場合や量が多いことが原因で適応障害が発症・悪化している場合があります。
業務内容や量を調整してもらうと、症状が緩和される可能性があるため、退職を決断する前に相談して対応してもらえるか確認してみましょう。
例えば、締切の延長や担当顧客の変更、業務の一部削減など、自分の体調に合わせた調整を提案するのがおすすめです。
休職して体調が回復するか様子を見る
適応障害で退職を勧められても、いきなり退職するのではなく、休職して体調の様子を見るのが大切です。少しの期間でも休業すると体調が回復し、その後復帰できる場合があります。
さらに、休業中に体調が回復しない場合は、退職するかどうかを時間をかけて判断できます。そのため、突発的な判断で退職した後に後悔するリスクも抑えられるでしょう。
休職期間中は、主治医の指示にしたがって療養に専念するのが大切です。
なお、休職後に復職せずに退職する方法や注意点に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

家族などの信頼できる相手に相談して判断する
適応障害で退職を勧められた際は、主治医や上司だけでなく、信頼できる家族に相談して退職を決めるのも大切です。主治医と違い、上司の中には適応障害に対する理解が低く、親身になってもらえない場合があります。
また、自分にとって親身になってくれる相手へ相談すると精神的にも楽になりやすいでしょう。
そのため、家族などの信頼できる相手に相談して、退職を検討してみるのもおすすめです。
適応障害で退職を伝えるときのポイント
適応障害で退職を伝える場合、以下のポイントを押さえておきましょう。
適応障害で退職を伝えるときのポイント
- 上司に適応障害を伝えていない場合、理由は自己都合や健康面の理由で問題ない
- なるべく早めに退職する旨を伝える
適応障害であっても、早めに退職の意向を伝えるのが大切です。意識するポイントは基本的に他の理由で辞めるときと同じです。
上司が適応障害を把握していれば話が通じやすいですが、知らない場合は自己都合や健康面の理由だと伝えたほうがスムーズなケースもあります。
適応障害で退職をするときの4つの注意点

適応障害で退職をするとき、以下の注意点があります。
適応障害で退職をするときの注意点
- 精神科・心療内科で受診を受ける
- 有給を使い切る
- すぐに辞められないときは退職代行を検討する
- 退職以外の方法も検討する
それぞれの注意点を踏まえた上で、退職を検討しましょう。
①精神科・心療内科で受診を受ける
まずは、精神科・心療内科で受診を受けましょう。今はネットで自己診断をする方法もありますが、専門医に診てもらうのが確実です。自己診断をして自己流で治療をするのは、悪化の原因につながるため止めましょう。
また、病院から診断書を貰えればスムーズに理解してくれたり、今後のサポートも受けやすくなったりします。
なお、口頭で伝えるのは、企業によっては嘘を疑われる可能性があるため、診断書の提出とセットで伝えるようにしましょう。
②有給を使い切る
有給休暇は退職した時点で消滅することから、できる限り使い切って退職するのがおすすめです。
ただし、人員調整や引き継ぎなどの関係もあり、有給は早めに申請するのが無難です。もしも有給を消化しきれない場合は、退職日をずらしたり、有給の買取などを相談してみましょう。
おすすめ:【社労士監修】退職時に有給を使い切るコツを解説│退職戦略室
③すぐに辞められないときは退職代行を検討する
勤め先がブラック企業ですぐに辞められない場合は、退職代行の利用も検討してみましょう。退職代行とは、労働者に代わって退職の意思を伝えてくれるサービスです。
退職代行サービスを使えば即日辞めることもできるため、なるべく早く・面倒なことは避けたい方におすすめです。適応障害は原因を取り除かない限り、悪化していきます。早めに治療に専念するためにも、退職代行サービスを検討してみましょう。
④退職以外の方法も検討する
年齢や状況によって退職が難しい場合は、退職以外の方法を検討しましょう。人間関係や業務量が原因で適応障害が起きている場合、部署異動や転勤で治る可能性があります。
そもそも、ストレスを感じやすい人の場合は、転職をしても再び適応障害を発症してしまう可能性があります。
したがって、まずは現在の職場で環境を変えてもらうことを考えましょう。休職をするのも効果的な方法です。適応障害の診断書が降りていれば、上司からの理解もスムーズに得られるはずです。
なお、退職日の決め方やおすすめの退職日に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
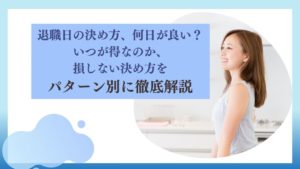
適応障害で退職した後に回復するための過ごし方

適応障害は退職をしたからといって、すぐに治るものではありません。回復するためには、以下の過ごし方を意識しましょう。
適応障害で退職後の過ごし方
- 十分な睡眠とバランスの取れた食事・運動をする
- 担当医の指示を受ける
- 段階的に社会復帰に向けた行動を取る
現在適応障害の方は、ぜひ参考にしてください。
十分な睡眠とバランスの取れた食事・運動をする
十分な睡眠とバランスの取れた食事・運動を意識しましょう。回復のためには生活リズムを一定にすることが大事です。不規則な食事や睡眠・運動不足は疲れを感じやすくさせたり、精神的に悪い影響を及ぼしたりします。
まずは、初めから100点を目指す必要はなく、自分が目標達成できそうなものから実行するのがポイントです。身体が慣れてきたら、運動する量を増やしていきましょう。
ただし、心身ともに疲労している場合は何もせず問題ありません。
担当医の指示を受ける
最後は担当医の指示を受けましょう。適応障害の治療をしていく上で、どのような過ごし方をするべきかは体調で大きく変わってきます。
休養期であれば何もしないことがポイントですが、回復に向けて徐々に動く時期も増えていきます。ただし、どの時期に何をするか素人が判断するのは難しいので、担当医の指示を受けて回復を目指していきましょう。
段階的に社会復帰に向けた行動を取る
適応障害で退職した方は、いきなり社会復帰を目指すのではなく、段階的に進めることが大切です。例えば、最初は転職ではなく、近所のサークルや趣味の集まり、ボランティア活動などなどに参加するのがおすすめです。
徐々に慣れていけば、段階的に活動を活発にし、最終的に社会復帰につながるでしょう。焦らずに自分のペースで活動の幅を広げていくようにしてみてください。
適応障害で退職した後に活用できる支援制度5選
適応障害で退職した後は、以下5つの支援制度を活用できる可能性があります。
- 傷病手当金
- 自立支援医療制度
- 障害者手帳
- 労災保険
- 生活保護
それぞれの制度に関して詳しく解説していきます。
なお、退職したらもらえるお金に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
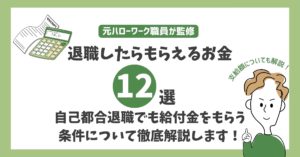
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している方を対象にもらえる支援金です。仕事以外の事由による怪我や病気によって休業している方に支給されます。
ただし、退職日の1年以上前から健康保険に加入している場合でなければ支給されません。受給期間は、初回支給日から通算1年6ヵ月間です。

なお、傷病手当金の受給条件や会社が嫌がる理由に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会(病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金))
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、適応障害などの精神疾患のある方を対象に、医療費の自己負担割合を軽減する制度です。通常の医療費が3割負担に対し、支援を受けると通院費用が1割にまで軽減されます。
ただし、入院費用は対象外になるため、入院が必要な方は注意してください。また、申請する際は、診断書や所得証明書などの書類を提出して審査を受ける必要があります。
障害者手帳
障害者手帳は、身体的・精神的に障害のある方が取得できる制度です。主に、就労支援や経済的な支援を受けられるため、フルタイムで働けない方が生活しやすくなります。
特に、税金の控除や公的機関の割引きなどを受けられるため、医療費に生活費を割きやすくなるでしょう。
ただし、認定基準は各自治体に応じて異なるため、確認しておくのがおすすめです。
労災保険
労災保険は、労働者が業務や通勤が原因で起きた傷病によって働けなくなった際に支給される手当金です。労働者であればアルバイトやパートなどの雇用形態は問わず対象になる制度です。
都道府県労働局や労働基準監督署で、仕事による適応障害だと判断してもらえると支給されます。そのため、適応障害によって退職した方は、一度問い合わせてみるのがおすすめです。
生活保護
生活保護は、適応障害などの疾患の有無に関わらず、生活困窮者を対象に受給できる制度です。適応障害が原因で働けずに生活費に困っている方も対象です。
また、通院などの医療費や世帯費用、就労のための訓練費・教育費なども支援されます。そのため、社会復帰や適応障害の治療に専念するためにも活用できるでしょう。
適応障害の退職でよくある質問

ここでは、適応障害の退職でよくある質問を3つ紹介します。
適応障害の退職でよくある質問
- 適応障害で退職をした場合、失業保険を受けられますか?
- 適応障害での退職は自己都合退職になりますか?
- 適応障害で即日退職はできますか?
それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。
適応障害で退職を検討している方は「転職×退職のサポート窓口」に相談しよう

「会社に行くのが怖い」「会社でも家でも何もやる気が起きない」などの場合は、適応障害の可能性があります。適応障害はすぐに治るものではなく、治るまでに数ヵ月かかります。
しかし、症状の改善はストレスとなる原因を取り除いたケースが多く、発症した環境を変えなければ悪化する可能性が高いです。まずは専門医に診てもらい、適応障害であるか把握しましょう。その上で上司に相談して休職をしたり、異動を希望したりしてみてください。
それでも治らない、どうしても辛いようであれば、退職をするのも1つの手段です。適応障害で辞めるのは逃げではないため、引け目を感じる必要はありません。
今すぐ退職後の手当を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。