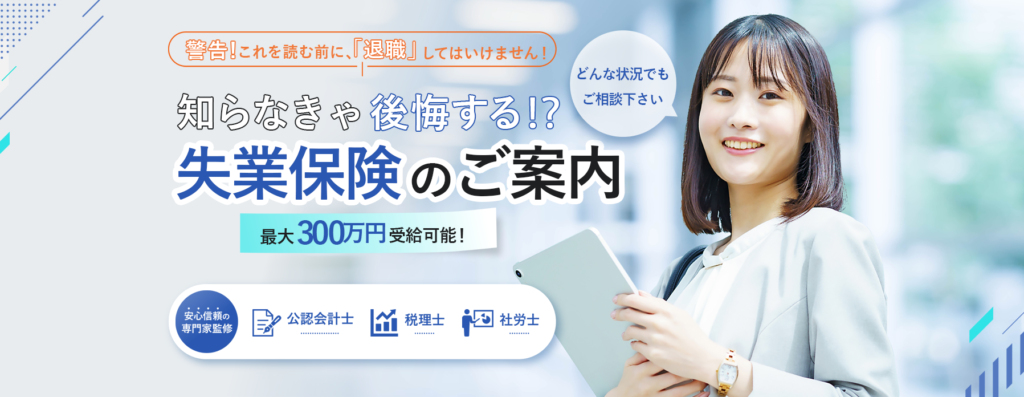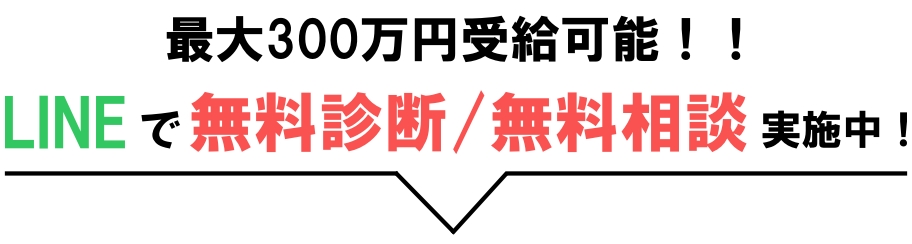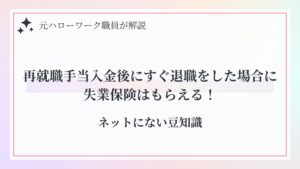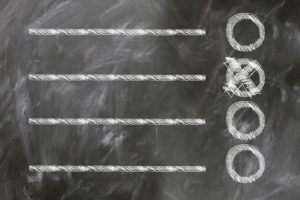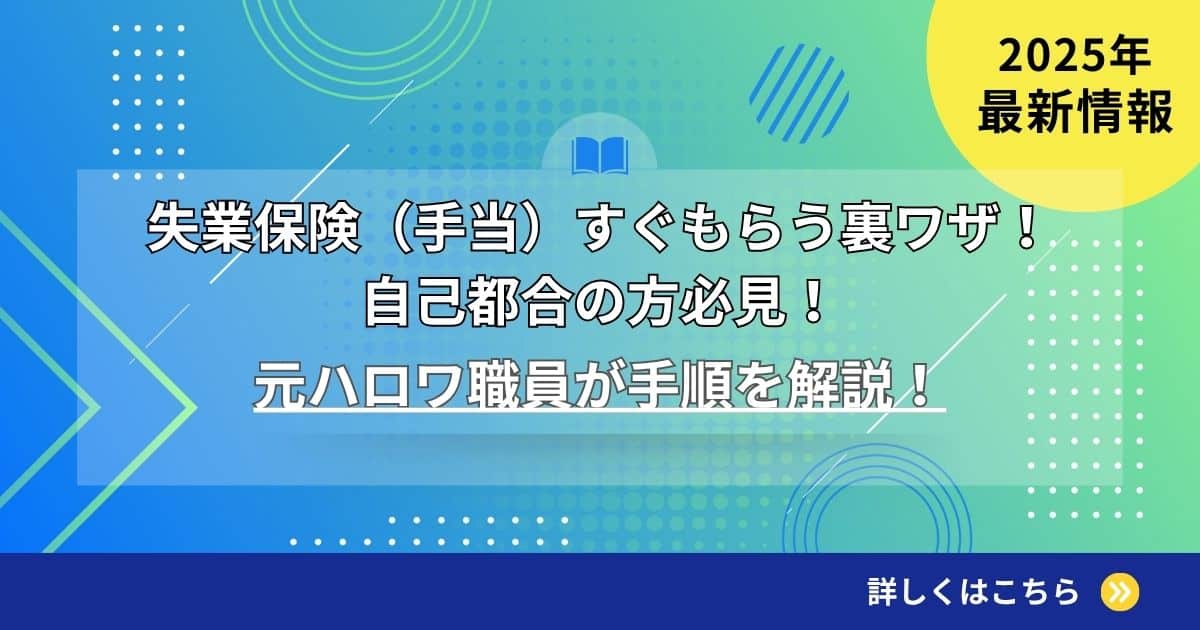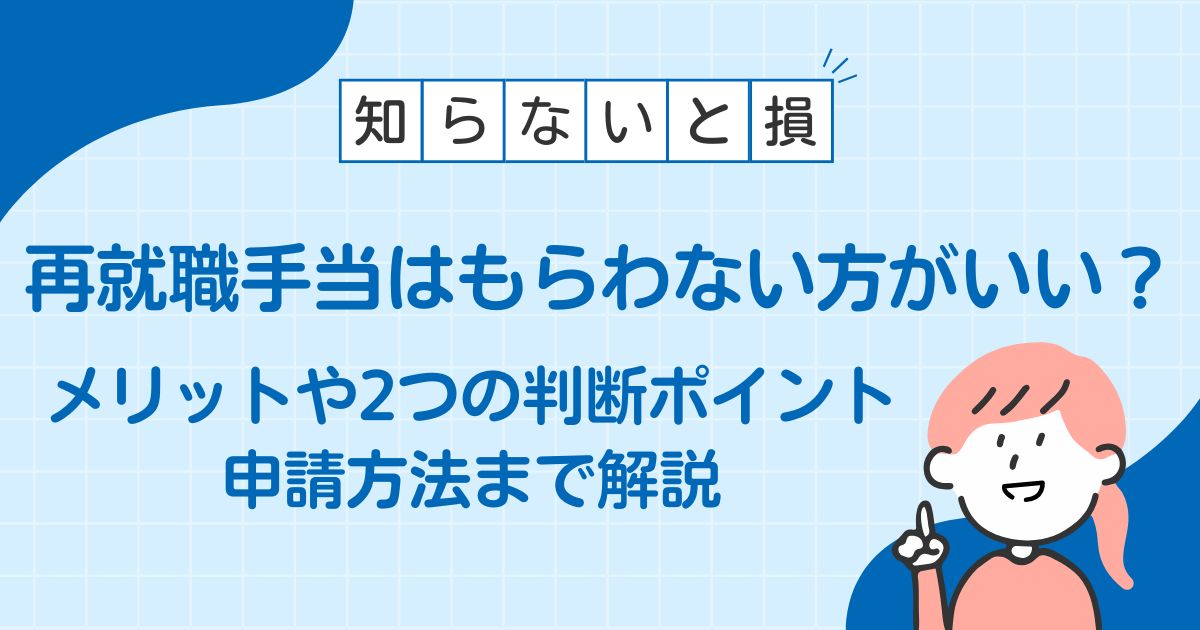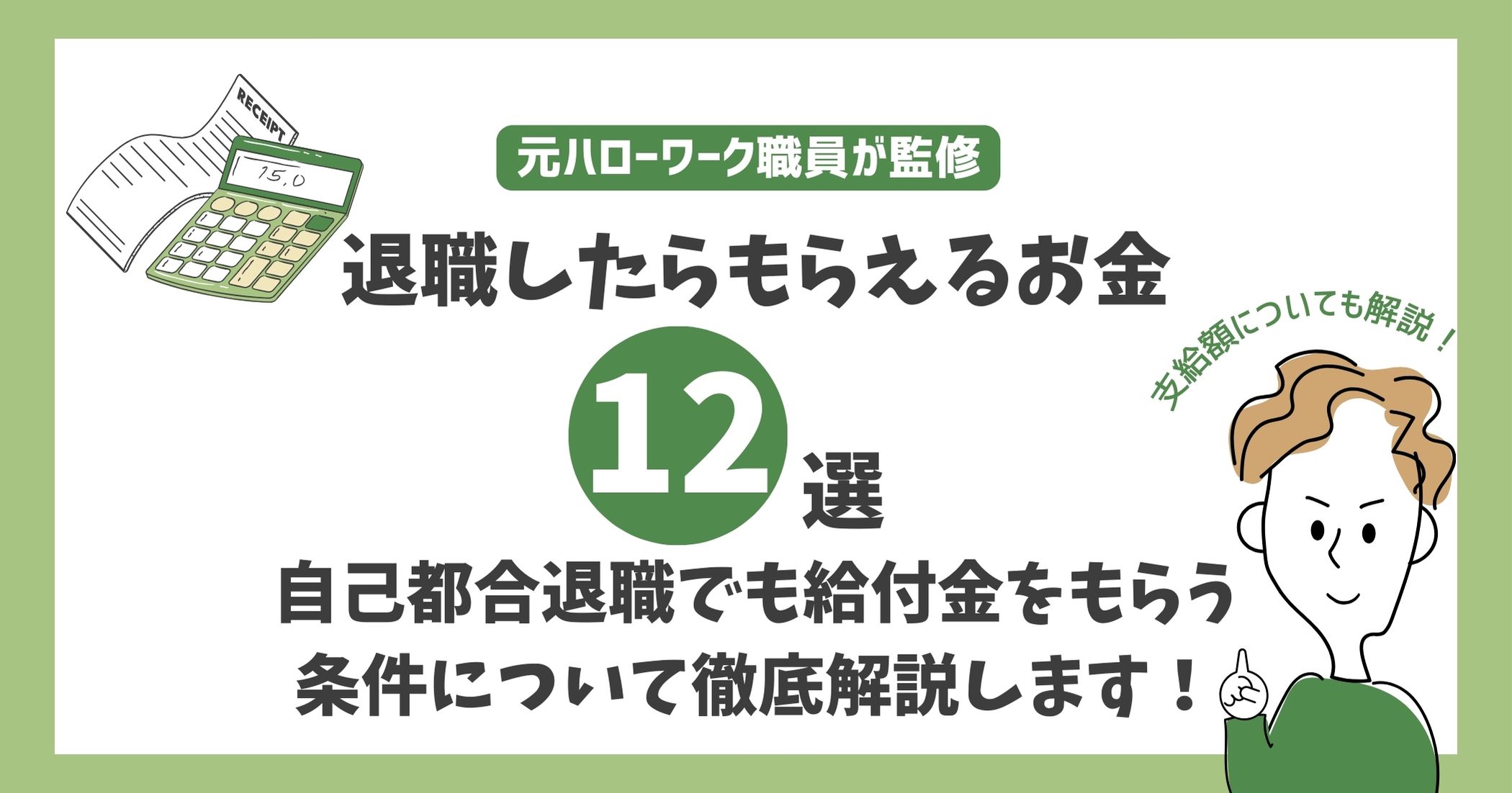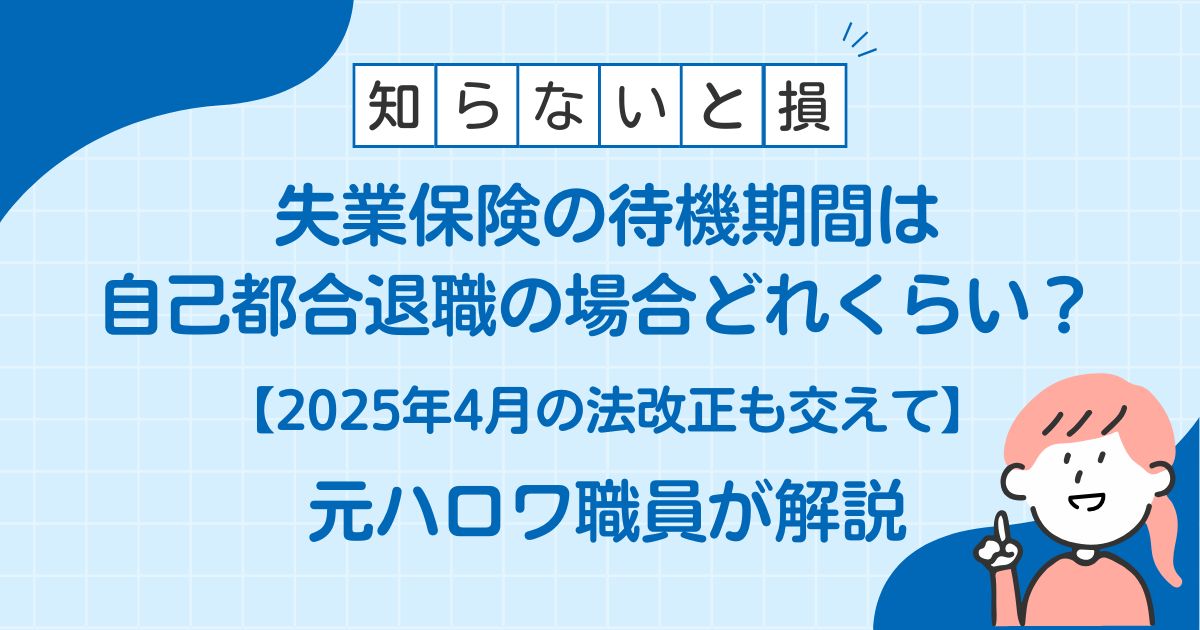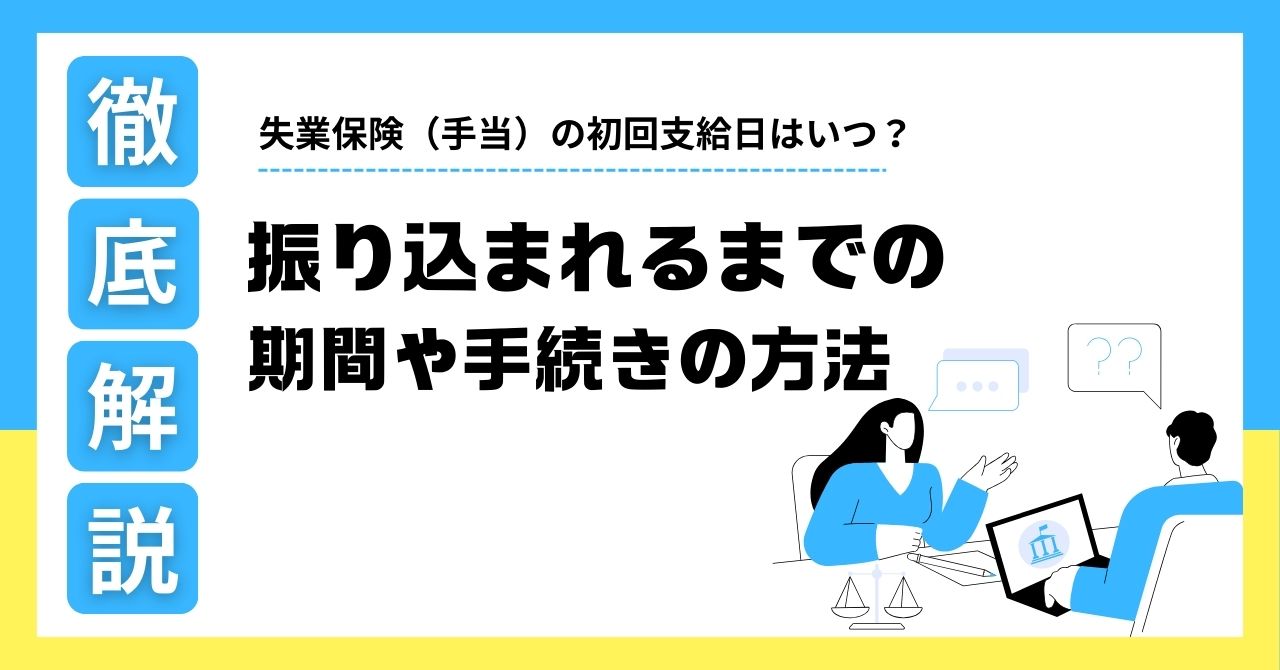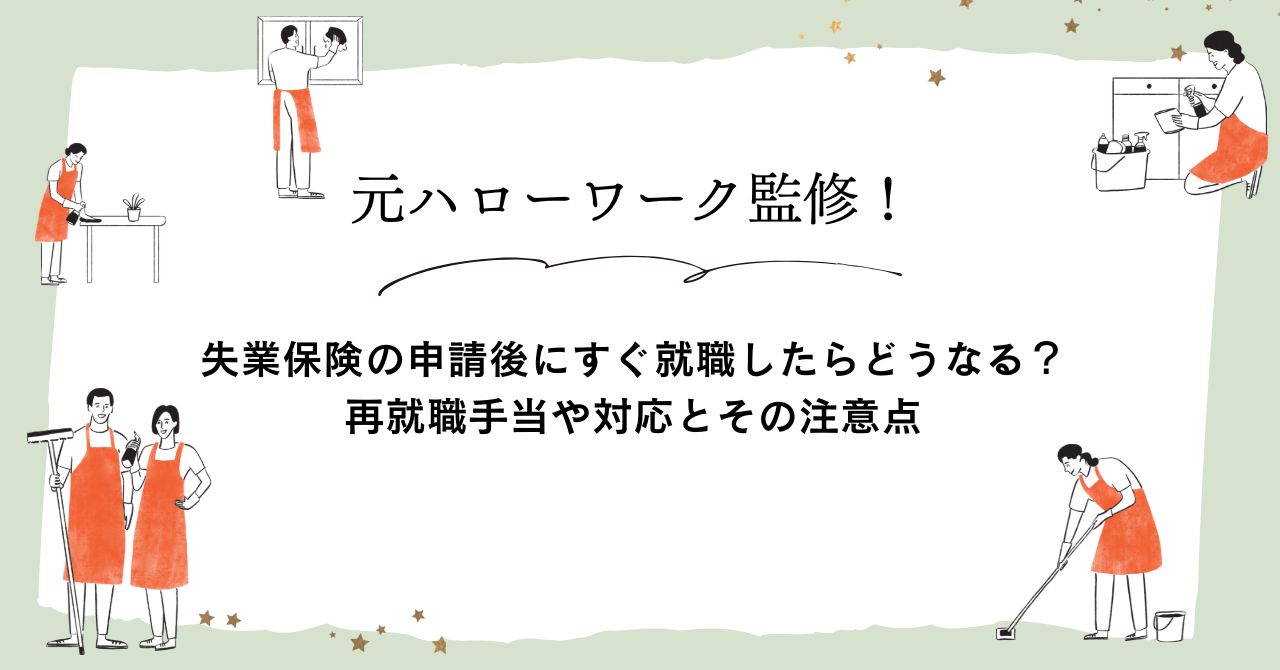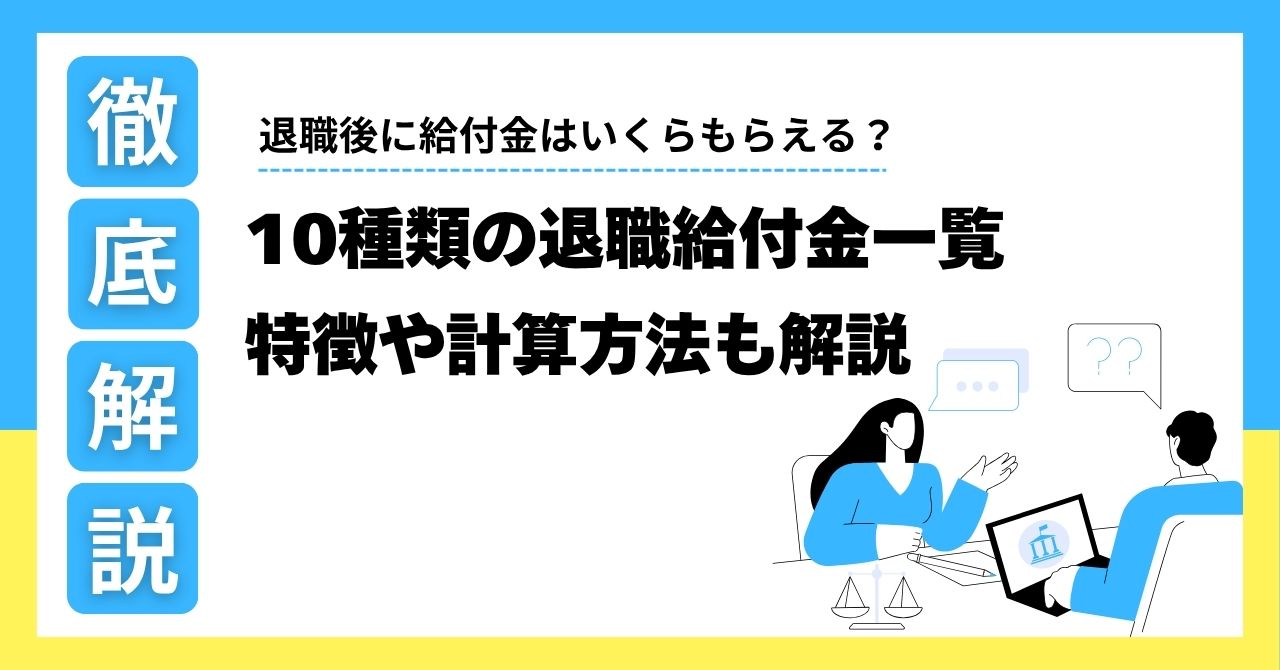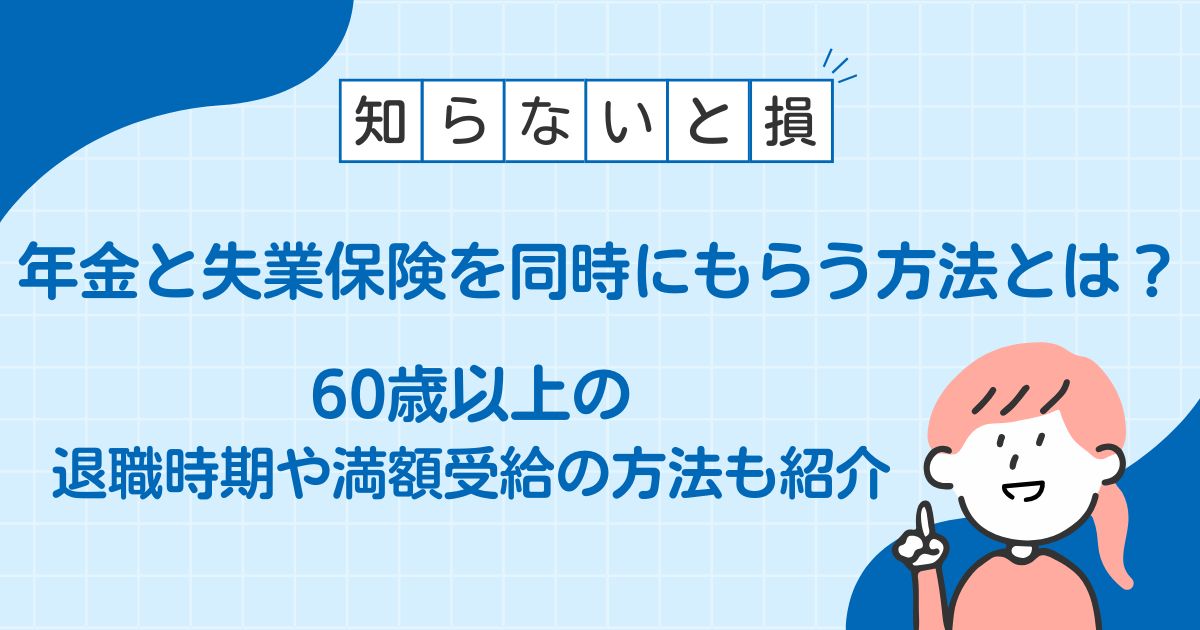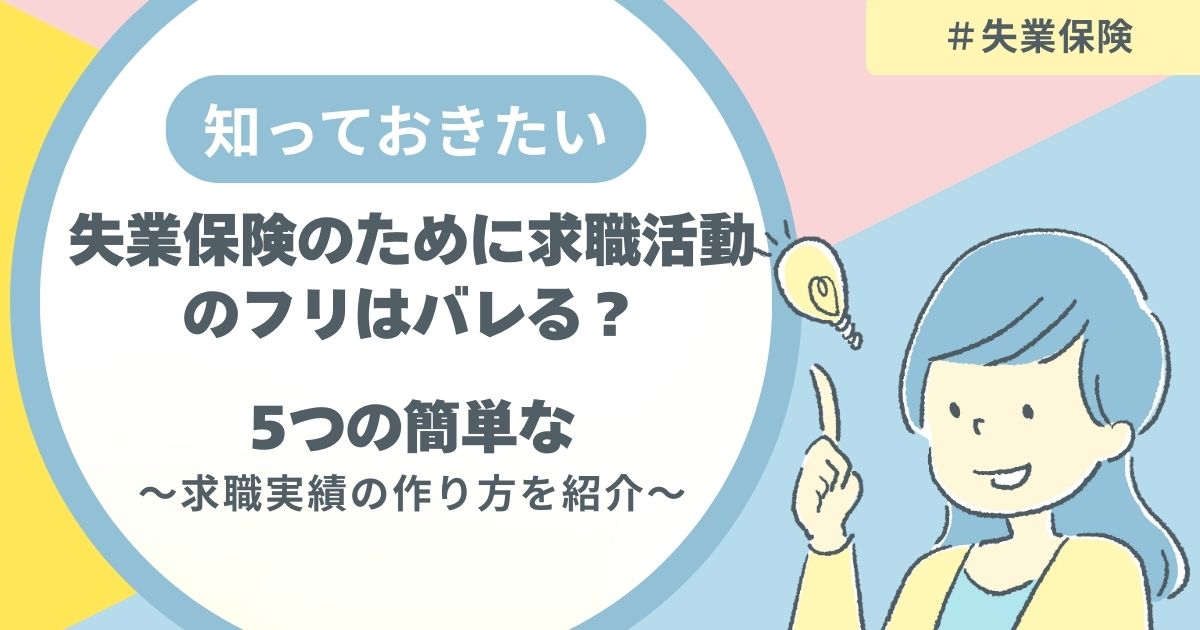元ハロワ職員<br>佐藤
元ハロワ職員<br>佐藤この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 会社を退職した!やるべきことはある?順番は?
- 会社を退職したけど、いろいろな手続きに必要な書類がわからない
- 退職後やることはどんなことがある?
このようにお悩みではありませんか?
会社を退職した後は自分でさまざまな手続きをする必要があり、期限を超過したり手続きしなかったりするとペナルティが課される場合もあります。
 元ハロワ職員<br>佐藤
元ハロワ職員<br>佐藤本記事では、会社を退職したらやるべきことを解説します。
3人の実例をもとに、退職後の流れをわかりやすく紹介しており、対象外のケースについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
また、失業保険を早くもらいたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。

退職したらやるべき5つの手続き

退職したらやるべき手続きとして、以下の5つが挙げられます。
退職したらやるべき手続き
- 健康保険を切り替える
- 年金を切り替える
- 失業保険の受給手続きをする
- 住民税の支払い方法を変更する
- 所得税の確定申告をする
それぞれの手続きを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
健康保険を切り替える
退職したらやるべき手続きとして、健康保険の切り替えがあります。
勤務している間は健康保険組合に加入できますが、退職すると資格が失われます。もし国民健康保険に加入する場合は、14日以内に手続きを済ませましょう。また、任意継続を選ぶ場合は20日以内に手続きを完了させましょう。
健康保険に加入していれば、病気や怪我の治療費の負担は3割になります。しかし、加入していない場合は全額自己負担となるため、思いがけない事態に備えて早めに手続きを行うことが大切です。
なお、退職後すぐに転職先に入社する場合は、転職先が健康保険に関する手続きを代行してくれることが多いです。
健康保険の扱いには、以下3つのパターンがあります。
- 国民健康保険に切り替える場合
- 配偶者の扶養に入る場合
- 退職前の健康保険を継続する場合
ここからは、それぞれのパターンを詳しく解説していきます。
国民健康保険に切り替える場合
家族の扶養に入らず、任意継続もしない場合は国民健康保険へ加入手続きをする必要があります。退職後の14日以内に、お住まいの地域の役所で手続きを行うことで、市町村が運営する国民健康保険に加入できます。
退職後に無職期間がある方や、自営業を始める方などが加入の対象です。
なお、国民健康保険制度を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者の扶養に入る場合は、退職後すぐに家族の扶養に入る手続きを行いましょう。家族の扶養に入ると、自分の保険料を支払う必要がなくなります。
被保険者の父母、祖父母、配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹のうち、被保険者の収入で生計を立てており、「年収が130万円未満」かつ「被保険者の収入の2分の1未満」の方は、扶養に入ることが可能です。
※被保険者と別居している場合は、年収が130万円未満でかつその金額が被保険者からの仕送りなどの援助よりも少ない方が扶養の対象となります。
扶養に入るためには、被保険者の勤務先で手続きが必要です。被保険者が加入している健康保険組合によって加入条件や必要書類が異なるため、確認しながら手続きを進めましょう。
2024年10月から、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件が変更され、従業員数が101人以上から51人以上となっています。
なお、社会保険加入のメリットや手取り額の変化を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について|厚生労働省
退職前の健康保険を継続する場合
退職前の健康保険を継続する場合は、退職から20日以内に任意継続の手続きを行ってください。任意継続をするためには、前職で2ヵ月以上健康保険に加入していたことが条件です。
前職の健康保険を継続すると、国民健康保険よりも安く抑えられる場合がある。また、退職金が多く支給された場合は、国民健康保険に切り替えると翌年の保険料が高くなることはありません。
なお、任意継続の手続きは前職の健康保険の加入先によって方法が異なります。もし前職が協会けんぽに所属している場合は、住んでいる地域の協会けんぽ支部で手続きを行ってください。健康保険組合に所属している場合は、各組合の事務所で手続きを行います。
なお、退職後の健康保険について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について|全国健康保険協会
年金を切り替える
家族の扶養に入る方や退職後すぐに次の勤務先で社会保険に加入しない方は、退職から14日以内に年金の切り替え手続きを行う必要があります。
20~60歳の会社員は、国民年金だけでなく厚生年金にも加入しています。退職すると自動的に厚生年金から抜けるため、転職しない場合は家族の扶養に入るか、国民年金に切り替える手続きを行いましょう。
なお、年金の制度や手続きを詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
国民年金に加入する場合
転職先が未定の方や個人で事業を始めようと考えている方は、国民年金第1号被保険者に切り替えましょう。
なお、加入手続きが遅れると、遅れた期間の保険料が一括で請求されることがあるため注意が必要です。また、国民年金は2年以上前の保険料を支払えないため、2年以上手続きが遅れると将来の年金額が減額されます。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者の国民年金第3号被保険者年金(被扶養配偶者)になるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 配偶者が第2号被保険者(会社員や公務員)であること
- 退職者の今後の年収が130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること
なお、配偶者の扶養に入る場合は、配偶者が所属する会社に依頼する必要があります。
失業保険の受給手続きをする
失業期間が長くなる可能性がある方は最寄りのハローワークに行き、失業保険の手続きをしましょう。退職前の2年間で12ヵ月以上雇用保険に加入している、かつ働く意思がある方は失業保険が受け取れます。
ただし、自己都合で退職した方は7日間待機期間があり、さらに2ヵ月の給付制限期間が設けられます。失業給付金を早く受け取るためにも、退職後は可能な限り早く手続きをしましょう。
なお、雇用保険の概要について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
また、以下の記事では失業保険をハローワークで受け取る手続きを解説しています。もらえる金額や条件もまとめているので、ぜひご覧ください。

失業保険を早くもらいたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
住民税の支払い方法を変更する
住民税の支払い方法を変更する場合は、退職後の翌月10日までに異動届出書を提出し、住民税の支払い方法を変更する手続きが必要です。会社員の場合、給料から住民税が天引きされていますが、退職すると支払いが停止してしまいます。
手続きを怠ると、後日徴収通知が届くことになるため、通知内容に従い支払いを行いましょう。通知の支払い期限を忘れるか、支払いが遅れた場合は未納扱いとなってしまいます。スムーズに税金の支払いを完了するためにも、事前に手続きを行っておくことをおすすめします。
住民税の支払方法変更の手続きは以下3つのように離職期間・時期によって異なります。
- 退職後1ヵ月程度で転職する場合
- 1~5月に退職して転職まで1ヵ月以上期間が空く場合
- 6~12月に退職して転職まで1ヵ月以上期間が空く場合
なお、住民税について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
退職後1ヵ月程度で転職する場合
退職後1ヵ月程度で転職する場合は、退職する前の会社に「給与所得者異動届出書」の作成を依頼し、転職先に提出してください。ただし、1ヵ月以上の間隔がある場合は、一時的に普通徴収に切り替えるか、退職前の会社に数ヵ月分の住民税をまとめて天引きしてもらうよう依頼しましょう。
なお、再就職後には、特別徴収に切り替える手続きも可能です。その場合、退職時に自動的に普通徴収に切り替えられるため、送られてきた納付書で住民税を支払う必要があるかどうかを転職先に確認してください。
1~5月に退職して転職まで1ヵ月以上期間が空く場合
一般的に退職月から5月までの住民税は一括で徴収され、最終月の給与や退職金から天引きされます。
ただし、退職月の給与や退職金と合計した額よりも多くの住民税が徴収されてしまう場合は、全額または一部(1ヵ月分など)を退職する会社に依頼し、普通徴収に変更して自分で支払うことも可能です。
6~12月に退職して転職まで1ヵ月以上期間が空く場合
退職月分は住民税が天引きされますが、残りは自分で納付する必要があります。納付方法は一括か分割かを選択でき、納付通知書は役所から送られてきます。
もし希望があれば、退職月から翌年5月までの住民税を退職月の給与や退職金から一括で支払うことも可能です。ただし、一括で支払う場合は、別途申請が必要です。
所得税の確定申告をする
退職後に転職しなかった方や自営業を始めた方は、翌年2月16日から3月15日までにお住いの地域の税務署で確定申告を行う必要があります。これは、退職後の所得税を正確に計算し、足りなかった分の所得税を納付したり払いすぎた所得税を還付してもらったりするためです。
確定申告をするためには、まず前職での給与所得がわかる源泉徴収票の原本を準備しましょう。確定申告書は税務署で受け取れるうえ、税務署の公式サイトからもダウンロードできます。
指示にしたがって必要事項を記入し、書類が完成したら税務署の窓口に提出、郵送または電子申請をしましょう。
なお、所得税の確定申告について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
また、失業保険の受給方法や条件などについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
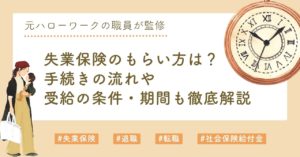
【実例】退職後にやることは人によって違う!3人のケースで具体的に解説
退職後の手続きや行う事は「全員に共通」に行う事もありますが、実際には「どのように過ごすか」「次の仕事が決まっているか」「療養が必要か」などによって、やるべきことの順番や内容は異なります。
ここでは、3人の実例をもとに、退職後の流れをわかりやすく紹介します。
ケース①:退職後すぐに転職したAさん(30代・正社員)
Aさんは、退職日の前に転職先が決まっており、退職日の翌日に新しい会社に入社しました。
- 退職日:4月30日
退職する会社に下記の書類の発行依頼をしました。
・離職票
・雇用保険被保険者資格証
・健康保険資格喪失証明書
・源泉徴収票
・年金手帳 - 5月1日:新しい会社に入社し、社会保険に自動加入
- 5月2日:前職の健康保険証を郵送で返却
※保険証の返却は、退職日前に行うケースもありますが、退職日までに病院へ行く可能性があるのであれば返却を退職日以降に郵送で行うことが望ましいです。 - 5月12日:前職に依頼した書類が届く(離職票は提出なため保管のみ)
再就職先に、雇用保険被保険者資格証、源泉徴収票、年金手帳を提出した。
転職先がすぐに決まっている場合は、失業保険の手続きや国民健康保険の切り替えなどが不要になります。
ただし、前職の健康保険証の返却や離職票の保管は忘れないようにしています。
離職票は早期での退職をすることになった場合に使用する可能性があるため保管をしています。
ケース②:失業保険を申請したBさん(40代・退職後に求職活動)
Bさんは退職後、しばらく求職活動に専念することに決めていました。そのため、失業保険の申請を行う流でした。
- 3月31日:退職日
退職する会社に下記の書類の発行依頼をしました。
・離職票
・雇用保険被保険者資格証
・源泉徴収票
・年金手帳 - 4月16日:離職票などが自宅に届く
- 4月17日:区役所で国民健康保険と年金の切り替え
離職票など退職を証明する書類が必要なため、離職票などの書類が届いてから手続きを行っております。 - 4月18日:ハローワークで求職申し込み・失業保険の手続き
- 5月16日:認定日
- 5月21日:初回の失業手当が振り込まれる
失業保険を受け取るには、ハローワークでの求職申し込みと、離職票の提出が必要です。
また、初回の受給までは少し時間がかかるため、事前にスケジュールを確認しておくことが重要です。
ケース③:療養に専念し傷病手当金を申請したCさん(20代・適応障害の診断あり)
Cさんは退職時点で体調を崩しており、主治医の診断をもとに、退職後は療養を優先することにしました。会社の健康保険制度を利用して、傷病手当金を申請しました。
- 退職日:2月28日(休職期間を経て退職)
・離職票
・雇用保険被保険者資格証
・源泉徴収票
・年金手帳
・傷病手当金の申請書 - 3月2日:医師の診断書を受け取り、傷病手当金の申請準備
- 3月5日:会社に申請書類の記入を依頼
- 3月12日:離職票など会社に依頼した書類が自宅に届く
- 3月13日:区役所で国民健康保険と年金の切り替え
- 3月14日:健康保険組合に申請書を提出
- 3月27日:初回の傷病手当金が振り込まれる
退職後でも、継続して療養が必要と認められれば、在職中の健康保険を使って傷病手当金を受け取ることができます。
ただし、会社側の証明欄が必要になるため、退職前から準備を進めておくのがベストです。
このように、「転職する」「求職活動をする」「療養に専念する」など状況によって、退職後にやるべき手続きやタイミングは変わってきます。
自分の状況に合ったスケジュールを立て、必要な書類を早めに準備しておくことが大切です。
各種給付金の手続きは複雑かもしれませんが、社会保険給付金サービスを利用することで退職前にしっかりと準備することで退職後の生活も安心できます。
社会保険給付金サポート「ヤメル君」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大1000万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
退職したら会社からもらう5つの書類

最後に、退職したら会社からもらう書類を5つ紹介します。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 健康保険資格喪失証明書
- 源泉徴収票
- 年金手帳
どれも重要な書類のため、自分がもらった書類と照らし合わせて確認してみてください。
離職票
離職票は、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、退職したことを証明する公的な書類です。離職票には以下の2種類あります。
- 雇用保険被保険者離職票-1:雇用保険の資格喪失を通知する書類
- 雇用保険被保険者離職票-2:前職の給与所得や離職理由、被保険者期間などを通知する書類
雇用保険被保険者離職票-1には、氏名や生年月日、被保険者番号や資格喪失年月日などが記載されています。
雇用保険被保険者離職票-2は、失業保険の受給手続きに必要となるため大切に保管しなければいけません。
離職票は、退職日の翌日から10日程度で会社から交付されるのが一般的です。
もし離職票が届かない場合は、会社に確認してください。また、万が一会社が対応してくれない場合は、本社の管轄にあるハローワークへ問い合わせましょう。離職票を送ってもらえないことを伝えれば、ハローワークが会社に連絡をしてくれます。
また、離職票が届くまでにできることや、届かない場合の対処法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、労働者が雇用保険に加入していたことを証明する書類です。正式名称は「雇用保険被保険者証」で、雇用保険の加入時に交付されます。
雇用保険被保険者証には以下の情報が記載されています。
- 被保険者番号
- 被保険者の氏名
- 被保険者の生年月日
- 確認(受理)通知年月日
- 資格取得年月日
- 事業所名略称
就職中は会社が管理していますが、退職時には会社から返却してもらう必要があります。
雇用保険被保険者証は、失業保険の受給手続きや再就職した際の雇用保険の適用手続きにも使用するため、大切に保管しておきましょう。
健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書は、退職などによって健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類です。正式名称は「健康保険被保険者資格喪失証明書」で、退職時に会社から交付されます。
また、健康保険資格喪失証明書には以下の情報が記載されています。
- 被保険者の氏名
- 生年月日
- 住所
- 健康保険被保険者証(記号・番号)
- 資格喪失年月日(退職日の翌日)
- 事業所の名称・所在地・代表者名・電話番号
健康保険資格喪失証明書は、退職後に国民健康保険や配偶者の健康保険に加入する際に必要です。また、国民健康保険への加入手続きの期限は、退職日の翌日から14日以内に行わねければいけません。
なお、健康保険の資格喪失証明書の詳細や、必要になるケースについては、日本年金機構の以下のページで確認できます。
国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
源泉徴収票
源泉徴収票は、1年間の給与総額や支払った税金の金額などが記載された重要な書類です。
退職時には、1月1日から退職日までの期間の給与に基づいた源泉徴収票が発行されます。
源泉徴収票には、支払金額や徴収した所得税額、控除した社会保険料などが記載されており、確定申告をする際に必要です。
また、退職後の健康保険や年金の手続きにも使用するため、受け取り後は、大切に保管しておきましょう。
年金手帳
年金手帳は、公的年金制度への加入者に交付される重要な書類です。
通常、入社後は会社に預けていますが、退職後の年金手続きに必要です。
ただし、一部の会社ではマイナンバーのみで年金を管理している場合もあるため、個人によっては自宅で保管している場合もあります。
なお、2022年4月からは年金手帳は廃止されたため、基礎年金番号通知書やマイナンバーでの手続きに移行しました。
基礎年金番号や通知書などを詳しく知りたい方は、以下の日本年金機構のページで詳しく解説しています。
また、以下の記事では、社会保険給付金の受け取りに必要な書類を紹介しています。社会保険給付金の条件や申請方法もまとめているので、ぜひご覧ください。

退職したら会社に返却するもの
会社を退職する際は、以下のような会社から貸与された物品を返却する必要があります。
- 健康保険被保険者証
- 社員証・社章
- 名刺(自分の名刺・取引先の名刺)
- 通勤定期券
- パソコン、携帯電話
- 貸与された文房具・備品・書籍
- 業務で使用した書類や制作物
- 制服や作業着、印鑑など
物品は会社の所有物であり、退職後も社員個人の手元に置いておくことは許されません。情報漏洩やトラブル防止のため、必ず返却しましょう。
ただし、会社によって返却物が異なる場合もあります。退職時に会社から案内されるリストや指示にしたがって、漏れなく返却するのが大切です。私物と混同しないよう、事前に整理しておくのもよいでしょう。
返却を怠ると、会社から連絡が来たり、トラブルに発展したりする恐れがあります。スムーズな退職手続きのためにも、返却物の確認と対応は怠りなく行いましょう。
退職後の手続きで困った場合の4つの相談先
退職後の手続きで困った場合の相談先は以下の4つです。
- 総合労働相談コーナー
- 法テラス
- 弁護士事務所
- 社会保険給付金サポートサービス
状況に応じて適切な相談先を選ぶことが、トラブルの解決につながります。それぞれ詳しく解説していきます。
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、退職後の手続きや労働問題に関するあらゆる相談を無料・予約不要で受け付けている公的な相談窓口です。
都道府県労働局が設置しており、解雇や退職、賃金、労働条件など幅広い労働問題を対象に、専門の相談員が面談や電話で対応しています。プライバシーにも配慮され、助言・指導やあっせんなどの解決方法も案内してもらえます。
退職後のトラブルで困ったら、まずは総合労働相談コーナーに相談するのがおすすめです。労働問題のプロが親身になって対応してくれるため、一人で悩む必要はありません。
法テラス
国が設立した法テラスは、日本司法支援センターと呼ばれる総合案内所です。労働問題を含むさまざまな法的トラブルに対して、電話や面談で解決に役立つ法制度や相談先を無料で案内しています。
また一定の収入・資産要件を満たせば、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えも利用できるため、経済的な不安がある場合でも安心して相談可能です。
法的な観点からのアドバイスが必要な場合は、法テラスを訪れてみるとよいでしょう。退職後の手続きや労働問題に詳しい専門家が、解決への道筋を示してくれます。
弁護士事務所
退職後の手続きで困った場合、弁護士事務所に相談すると、退職手続きや未払い賃金・退職金の請求、会社との交渉などを法的にサポートしてもらえます。
弁護士は法律の専門家であり、退職に関するトラブルや複雑な手続きを代理して対応できます。例えば、会社が退職を認めない場合や未払い賃金・退職金の請求、損害賠償請求など個人では対応が難しい問題も弁護士が法的根拠に基づいて交渉・解決してくれるため、安心して手続きを進められるでしょう。
法律の専門家の助言を受けることで、自分の権利を守りつつ、円滑に問題を解決できるでしょう。
ただし弁護士への相談は有料です。事前に料金体系を確認し、費用対効果を見極めたうえで利用しましょう。
社会保険給付金サポートサービス
社会保険給付金サポートサービスは、退職後に受給できる失業保険や傷病手当金などの申請手続きを専門家がサポートしてくれる有料サービスです。
社会保険給付金の申請は手続きが複雑で、受給条件の確認や必要書類の準備、申請書の記入などで多くの人が戸惑ってしまいます。サポートサービスを利用すると、専門家が受給資格の事前確認から書類作成、申請まで丁寧に支援してくれます。手続きミスや受給漏れを防ぎ、安心して給付金を受け取りたい方におすすめのサービスです。
給付金の申請手続きで不安を感じたら、社会保険給付金サポートサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。専門家のサポートを受けられるため、円滑に給付金を受給できるはずです。
ただし有料サービスであるため、料金体系を十分に確認し、メリットとデメリットを比較検討したうえで利用を決めましょう。なお、自治体によっては、同様の支援を無料で行っている場合もあります。
未払い給与の有無を確認する方法
未払い給与の有無を確認するには、給与明細や雇用契約書、銀行通帳などの支払い記録をもとに、支払日を過ぎても給与が振り込まれていないかを確認し、証拠を集めることが必要です。
給与の未払いがあるかどうかを明確にするには、実際に支払われるべき金額や支払日を示す契約書類や明細、振込記録などの客観的な証拠が不可欠です。
例えば、以下のような資料を確認しましょう。
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 給与明細(紙またはWeb)
- 出勤簿やタイムカード
- 銀行通帳や振込明細
- メールや電話での支払い約束の記録
証拠を集めることで、客観的に未払いの事実を立証でき、会社への請求や労働基準監督署への申告時にもスムーズに対応できます。
ただし証拠が不十分だと、会社から支払い義務を否定されるリスクもあります。できるだけ多くの証拠を集め、第三者が見ても未払いと判断できる状態にしておくことが大切です。
もし証拠集めで困ったら、労働基準監督署や弁護士に相談するのも一つの手です。未払い給与の請求は、証拠の有無が勝敗を分けると言っても過言ではありません。入念に証拠を固めましょう。
未払い給与があった場合の3つの請求方法
未払い給与があった場合の請求方法は以下の3つです。
- 会社への請求・交渉をする
- 労働基準監督署への申告をする
- 労働審判や訴訟などの法的手続きを検討する
状況に応じて適切な請求方法の選択が、未払い給与の回収につながるでしょう。それぞれ詳しく解説していきます。
会社への請求・交渉をする
未払い給与があった場合、まず証拠を集めたうえで会社に直接支払いを請求し、必要に応じて内容証明郵便などで正式に請求・交渉する必要があります。
具体的には、以下のようなステップで請求・交渉を進めていきましょう。
- 未払い給与の証拠(給与明細、雇用契約書、出勤記録など)を集める
- 会社の経理担当者や上司に、口頭または文書で支払いを請求する
- 会社が応じない場合は、内容証明郵便で正式に請求する
- 会社と粘り強く交渉を続ける(必要に応じて社会保険労務士や弁護士に相談)
証拠をもとに会社と交渉し管理ミスが原因であれば、速やかに解決する場合が多いです。また交渉の事実自体が、後の法的手続きでも有効な証拠となります。
ただし、交渉の過程で感情的になったり、脅迫めいた言動を取ったりするのは厳禁です。あくまで冷静に、証拠に基づいた請求が大切です。うまくいかない場合は、専門家に相談して適切な対処法を探りましょう。
特に内容証明郵便を利用して請求すると、請求の事実を客観的に証明でき、時効の完成を一時的に止める効果もあります。
労働基準監督署への申告をする
未払い給与があった場合、証拠を揃えて労働基準監督署へ申告すると、監督署が調査・指導を行い、会社への是正勧告が可能です。
労働基準監督署は労働基準法違反の疑いがある場合、労働者からの申告を受けて事実関係を調査します。未払いが認められれば、会社に対し支払いなどを指導します。
申告に必要な証拠書類は、以下の通りです。
- 雇用契約書
- 給与明細
- 出勤簿やタイムカード
- 銀行通帳の写しなど
行政の介入によって会社に支払いを促すことができるため、会社との交渉で解決しない場合は有効な方法です。
ただし、申告から是正勧告、実際の支払いまでにはある程度の時間を要します。速やかな解決を望む場合は、他の方法と併用しましょう。
労働審判や訴訟などの法的手続きを検討する
労働審判や訴訟は、裁判所の関与のもと、会社に支払い義務の履行を強制できる法的手続きです。
会社との交渉や労働基準監督署への申告で未払い給与問題が解決しない場合は、証拠を揃えて労働審判や訴訟などの法的手続きを利用すれば、強制力をもって給与の支払いを請求できます。
任意の支払いに応じない会社に対し、最終的な解決を図る手段です。
労働審判は、裁判所の調停と裁判の中間的な手続きで、原則3回以内の期日で迅速な解決を目指します。一方、訴訟は正式な裁判であり、判決によって権利義務関係を確定させます。
どちらの手続きでも、主張を裏付ける証拠が重要です。給与の未払いを立証できる客観的な資料を可能な限り集めましょう。
また、手続きの専門性から弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。法的な観点から適切な主張・立証を行い、会社との交渉も代理人として行ってもらえるため、手続きを有利に進められます。
ただし、弁護士費用や手続きにかかる時間・労力を考えると、少額の未払い給与の場合は割に合わないこともあります。他の解決手段での妥協も視野に入れつつ、慎重に検討する必要があるでしょう。
退職後にやることに関するよくある質問
退職後にやることに関してよくある質問は、次の3つです。
- 任意継続と国民健康保険はどちらがお得ですか?
- 健康保険の切り替えを忘れた場合どうなりますか?
- 退職後に転職先が決まっている場合はどのような手続きが必要ですか?
退職後にやることを具体的に知りたい場合は、ぜひ参考にしてください。
失業保険を早くもらいたい方は「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめ!

本記事では、退職したらやることを順番に紹介しました。退職したらやるべき手続きとして、以下の5つが挙げられます。
- 健康保険を切り替える
- 年金を切り替える
- 失業保険の受給手続きをする
- 住民税の支払い方法を変更する
- 所得税の確定申告をする
必ずしも上から順番にやる必要はありませんが、どれも期限が設定されていたり早い方が有益だったりするため、可能な限り早めに対応しましょう。
失業保険を早くもらいたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。