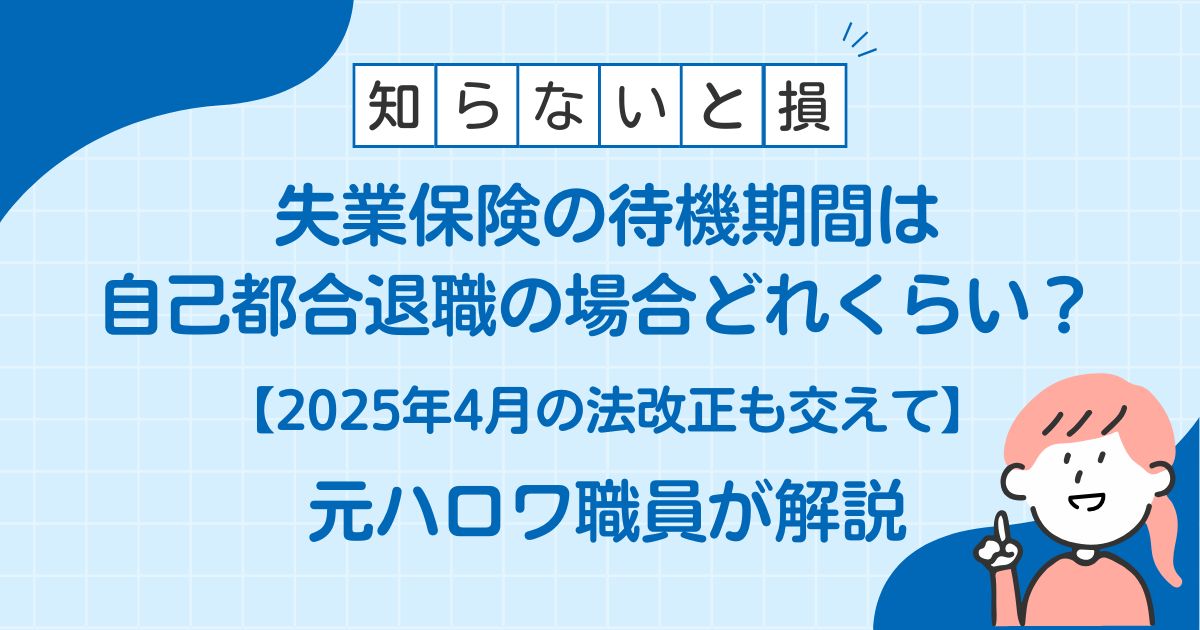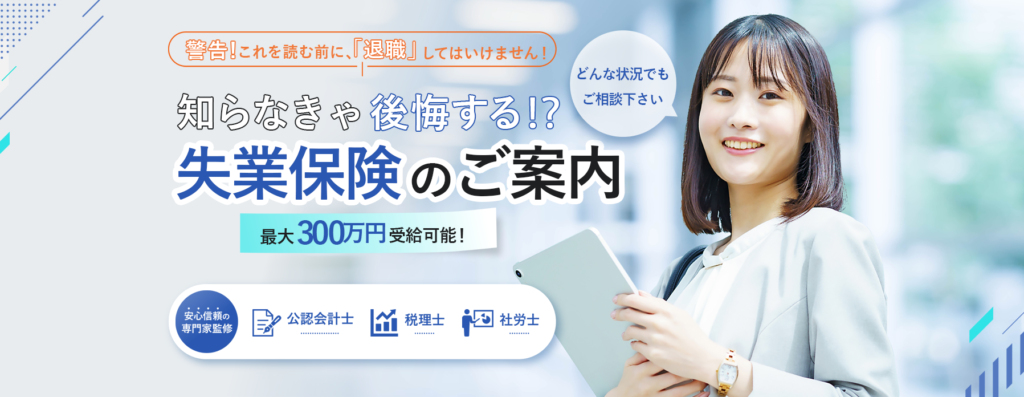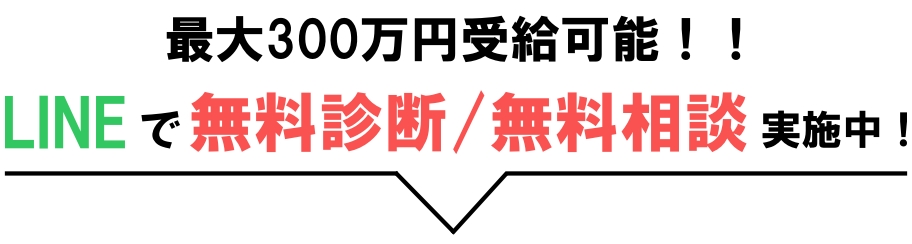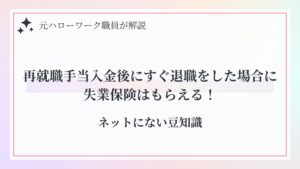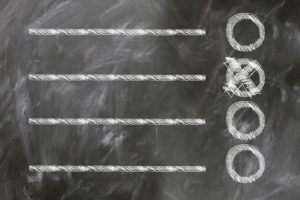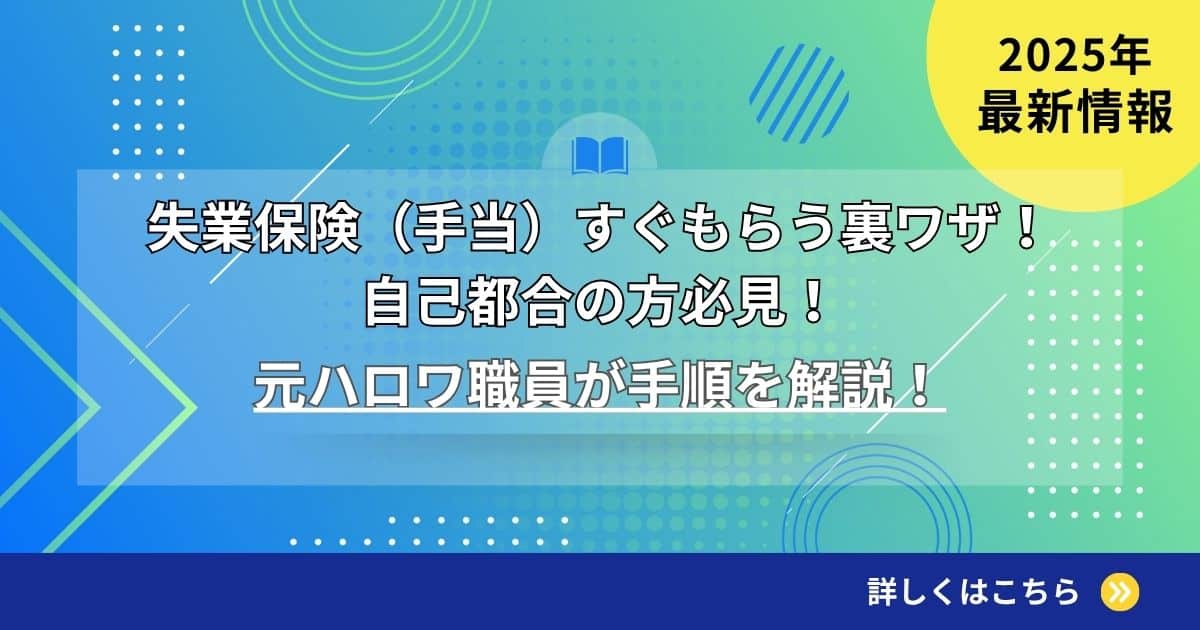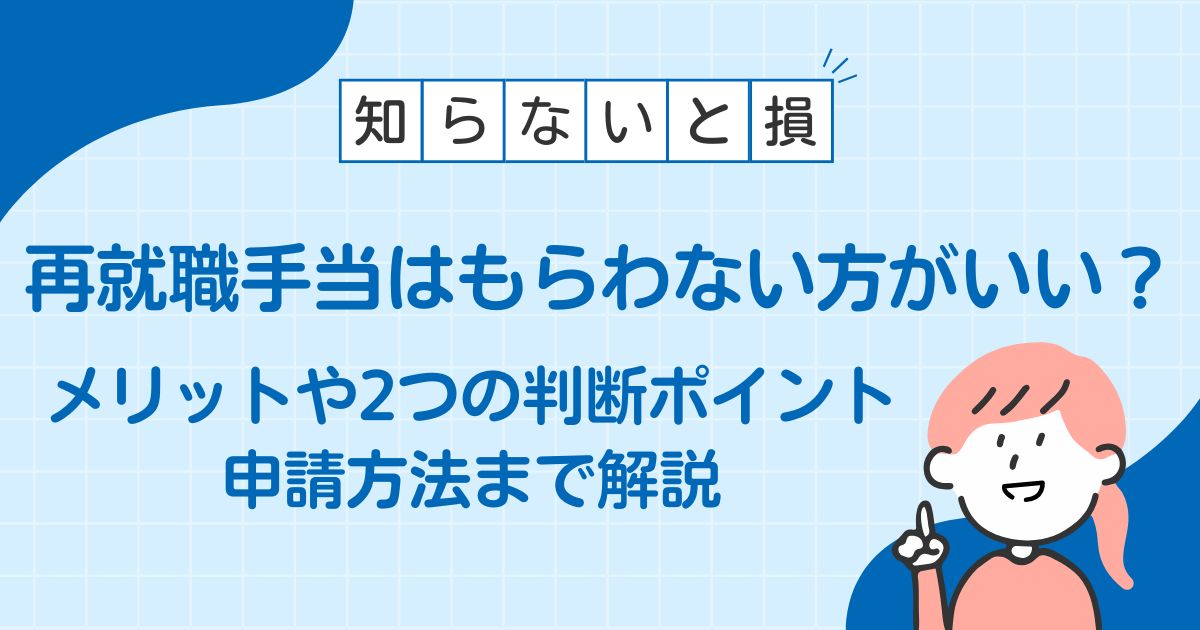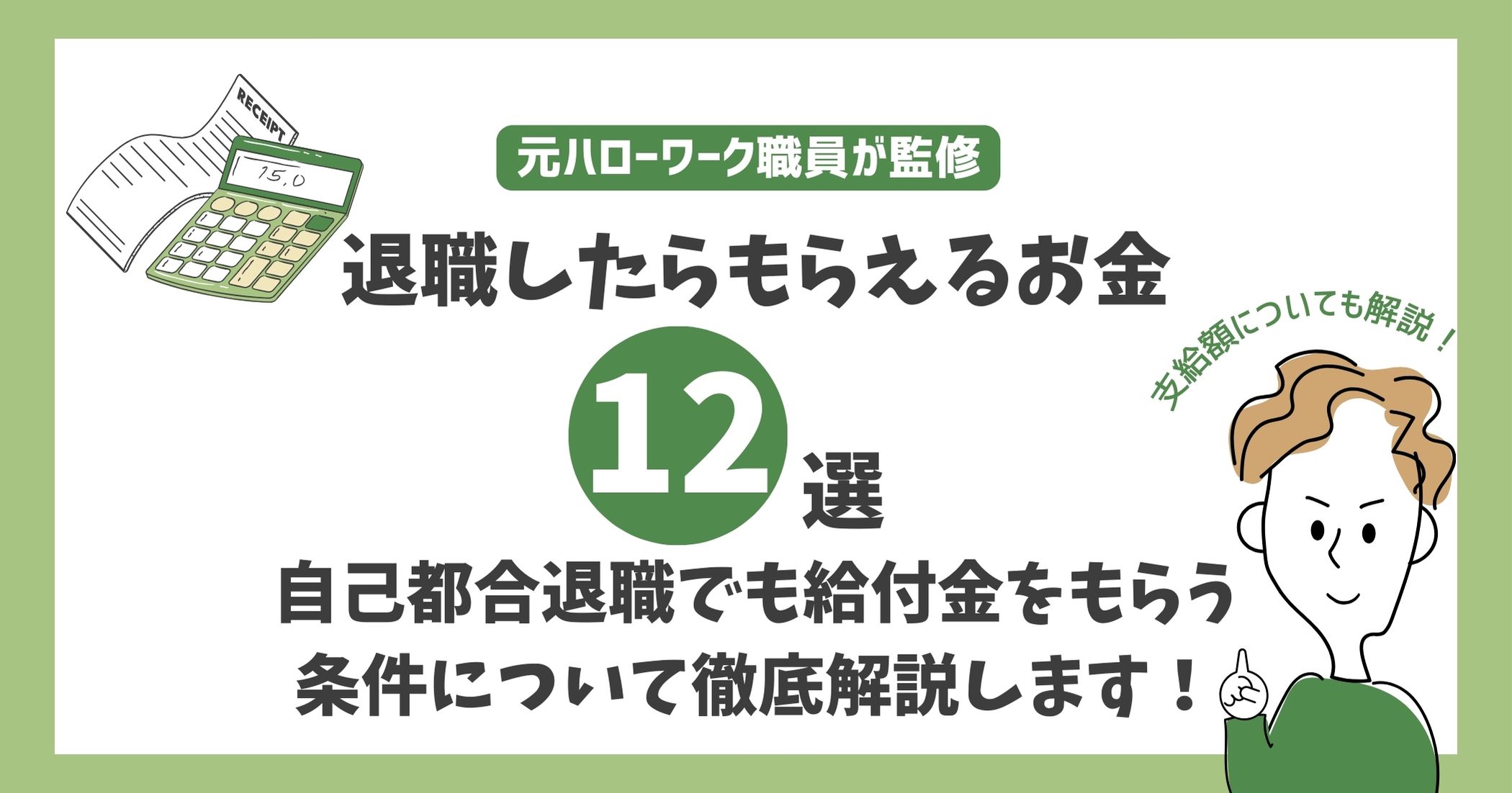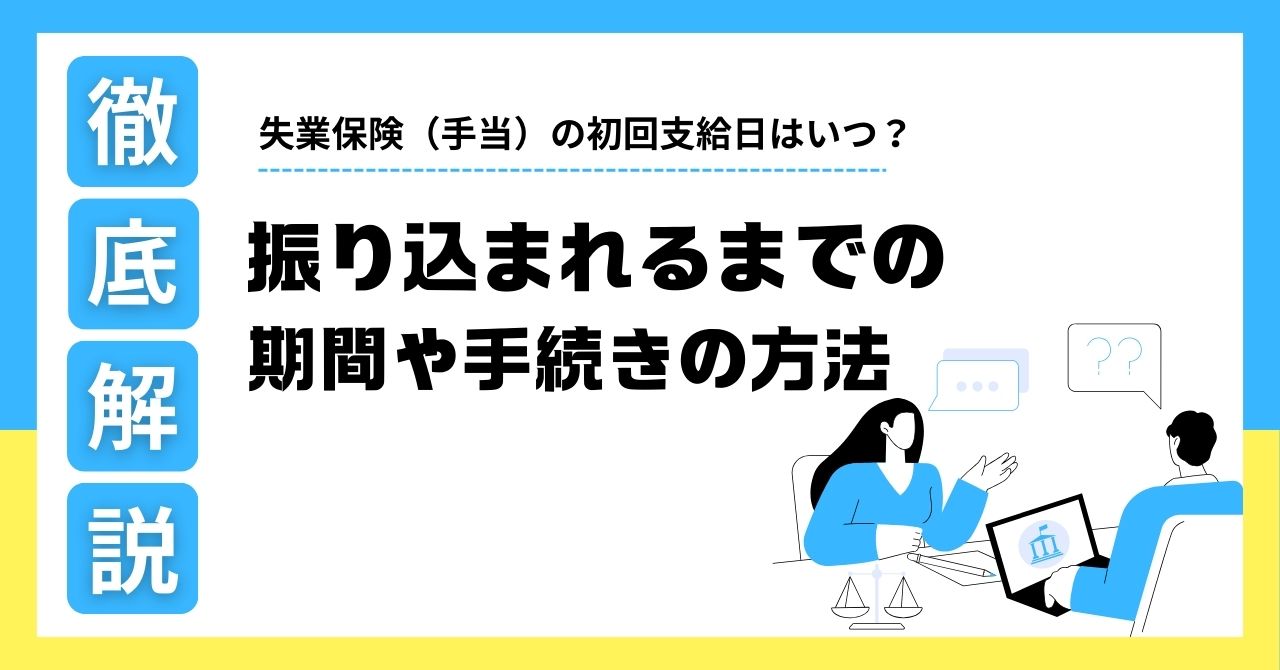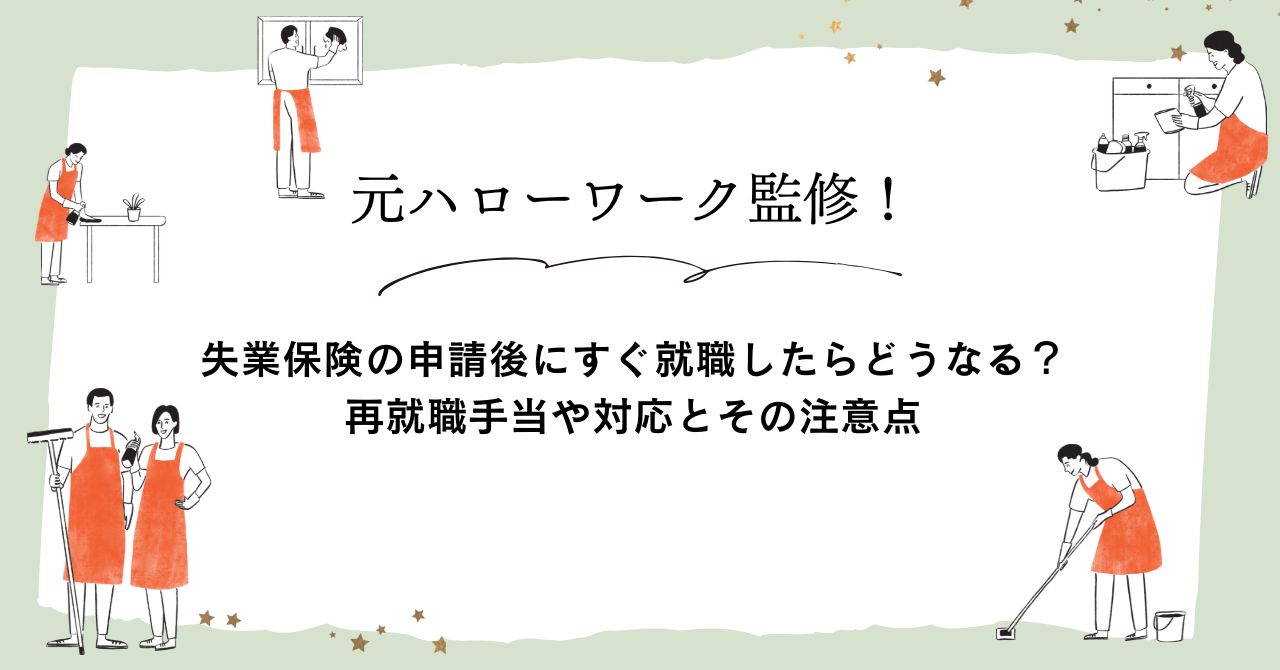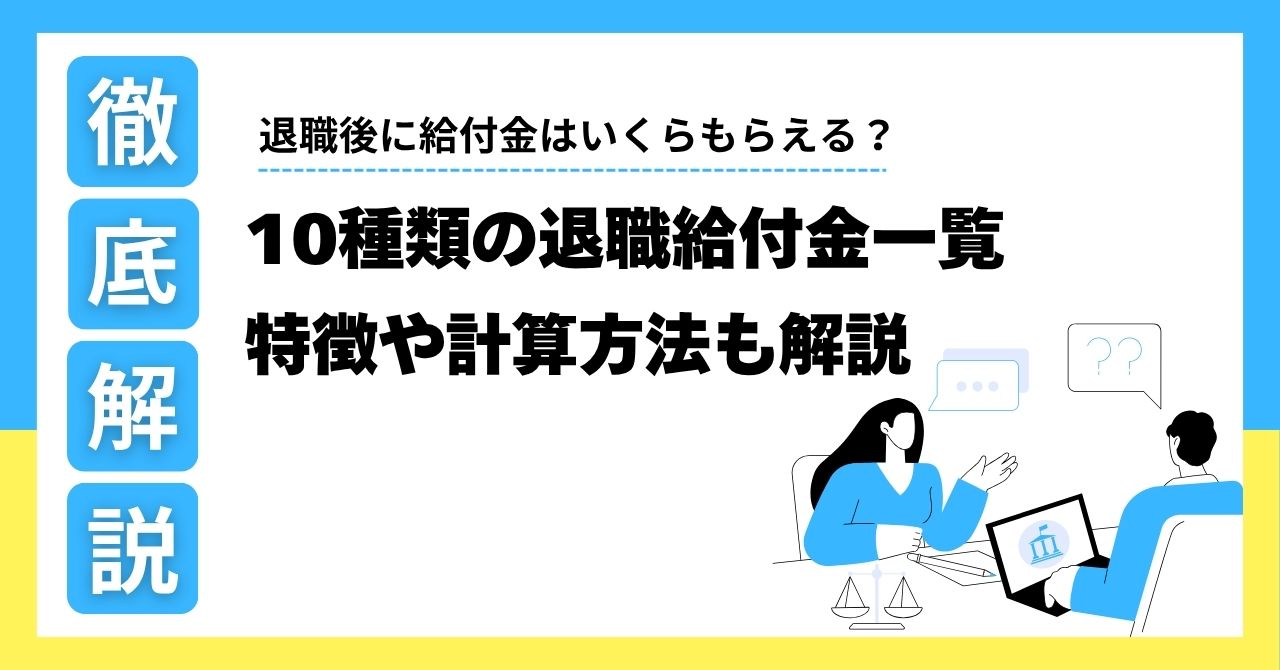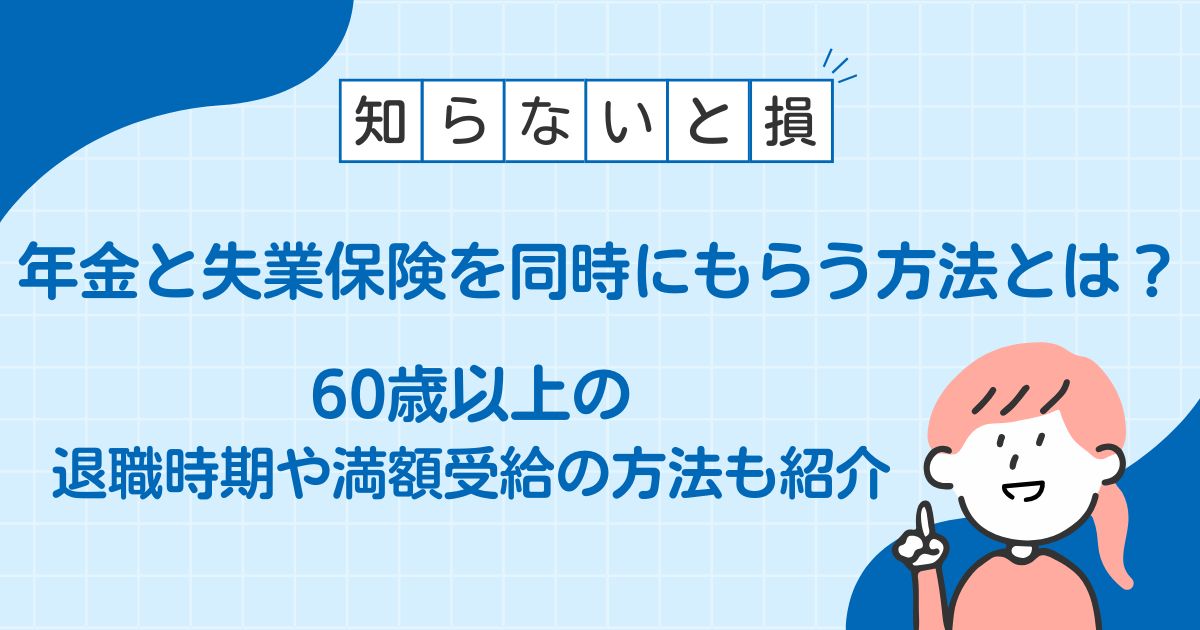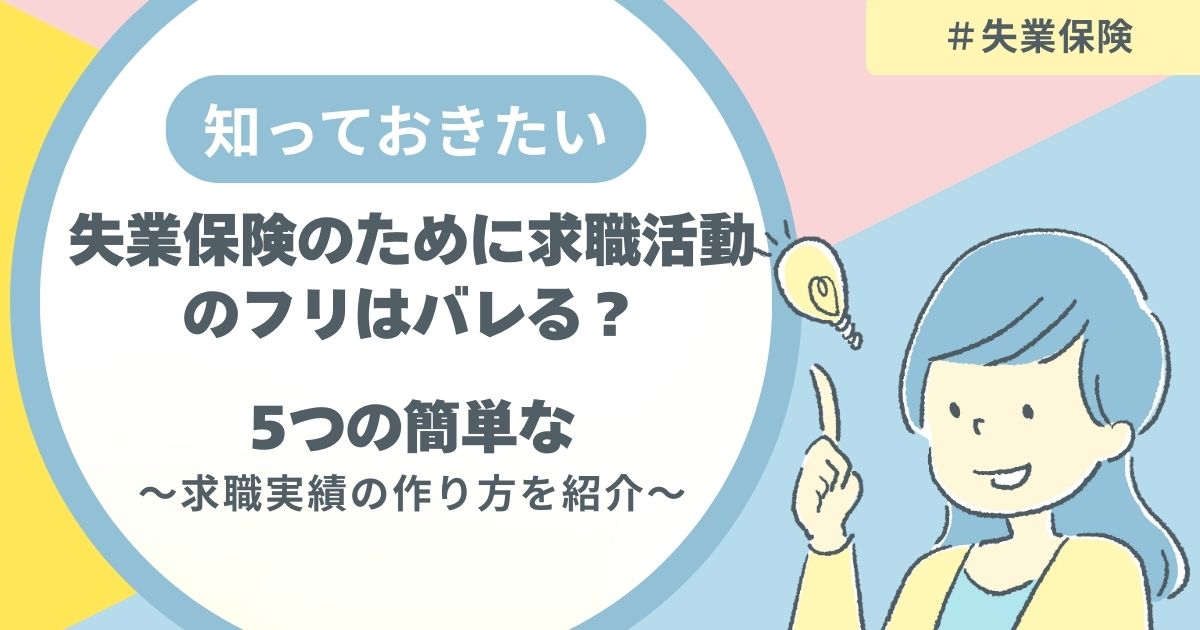「失業保険の受給開始時期を知りたい」
「待機期間や給付制限期間中のルールを理解したい」
自己都合退職を決めた方で、上記のような疑問はありませんか?
自己都合で退職した場合、失業保険の受給開始時期は、会社都合退職の場合と異なるルールが適用されます。
特に「待機期間」と「給付制限期間」は、きちんと理解しておかなければ、生活設計に大きな影響を与える可能性があります。
また、2025年4月から自己都合退職の給付制限期間は改正により1ヶ月に短縮されました。
これは離職日を基準としていますので、離職日が2025年4月1日以降である必要があります。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部本記事では、自己都合退職後の失業保険の待機期間に関して、概要や受給までの流れなどを詳しく解説しているので、自己都合退職を予定されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
なお、本記事は、厚生労働省発表のリーフレットを参考に記事を分かりやすく解説しております。
参考:「給付制限期間」が1か月に短縮されます(厚生労働省)
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、失業保険受給に関するご相談や受給額の診断までサポートしています。
失業保険に関する些細なお悩みでも丁寧に対応させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
本コンテンツ(退職の手引き)は、読者に価値のある情報を提供することを目的として独自の基準に基づき制作しています。≫コンテンツ制作・運営ポリシー

【自己都合退職の場合】失業保険の待機期間に関する概要
自己都合退職の失業保険の待機期間に関して、以下3つの項目に分けて概要を解説します。
- 失業保険の待機期間は7日間
- 【自己都合退職の場合】7日間の待機期間に加えて2ヵ月間の給付制限期間が発生
- 2025年4月からは給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮
上記の項目が頭に入っていれば、自己都合退職での失業保険受給のイメージがつきやすくなります。
では、それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。
失業保険の待機期間は7日間
失業保険の待機期間は、自己都合退職、会社都合退職に関わらず、7日間です。待機期間は失業状態であることを確認するために設けられています。
また、待機期間中は失業手当は支給されません。なお、待期期間は雇用保険法で定められており、すべての人に一律で適用されます。
自己都合退職か会社都合退職かに関わらず、基本的に失業保険の受給資格決定後に7日間の待期期間が発生します。
失業保険の待機期間に関してより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

【自己都合退職の場合】7日間の待機期間に加えて2ヵ月間の給付制限期間が発生
自己都合退職すると、7日間の待機期間と2ヵ月間の給付制限期間が設けられます。
給付制限期間は、自己都合退職者がすぐに失業手当を受け取るのを防ぎ、求職活動をうながすための期間です。
例えば、10月1日に自己都合で退職し、同日に離職票を提出して求職申し込みを行った場合、10月1日から7日間(10月7日まで)が待機期間です。
その後、10月8日から2ヵ月間(12月7日まで)が給付制限期間となり、この間は失業手当は支給されません。
しかし、2025年4月1日から法改定により、給付制限が期間が変わりました。
2025年4月からは給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮
2025年4月からは、早期の再就職支援や生活支援を強化するべく、自己都合退職の失業保険給付制限期間が、2ヵ月から1ヵ月に短縮されます。
例えば、2025年4月1日に自己都合で退職し、同日に離職票を提出して求職申し込みを行った場合、4月1日から7日間(4月7日まで)が待機期間です。
その後の給付制限期間は1ヵ月間(5月7日まで)となり、5月8日から失業手当の支給が始まります。
給付制限期間が1ヵ月短縮されたことで、転職活動時の経済的負担を軽減しやすくなりました。
2025年3月31日が退職日の場合は、適用されませんので給付制限の1ヶ月にしたい場合は、2025年4月1日以降に退職をする必要があります。
失業保険をさらにもっと早く(給付制限を無くして)受け取りたい方は下記の記事を参考にしてください。
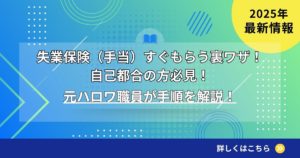
給付制限が1ヶ月にならないケース
自己都合の給付制限は原則1ヵ月に短縮されましたが、すべてのケースが一律で「1ヵ月」になるわけではありません。離職日・過去5年の離職履歴・離職理由の区分・教育訓練の有無の4点で、1ヵ月以外(長くなる/付かない)に振り分けられます。
離職日で給付制限が1ヶ月にならない
給付制限が長くなるケースの1つ目は改正前の離職した場合です。
離職日が2025年3月31日以前(3月31日も含む離職日)の自己都合退職は、従来ルールで原則2ヵ月の給付制限が適用されます。
現在では離職日が2025年3月31日以前であることが少ないため、離職日が原因で給付制限が長くなることは稀です。
2つ目のケースは起こりえます。
短期離職を繰り返した時
2つ目に短期離職の繰り返しです。
直近の退職日から5年以内に「正当な理由のない自己都合退職」で受給資格決定を2回以上受けている場合は、給付制限が3ヵ月に延びます。
ここは誤解が多いポイントなので、離職日とカレンダーを見て過去5年の離職歴を必ず確認してください。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部このケースは、2ヶ月ではなく、3ヶ月になってしまうので気をつけてください!
「正当な理由のない自己都合退職」とは通常の自己都合退職が該当します。
注意点:この「5年以内に2回以上」というカウントには、特定受給資格者や特定理由離職者として認められた離職(例:会社都合ややむを得ない家庭・健康・通勤事情など)は含まれません。
つまり、過去に病気・介護・結婚など正当な理由で退職していた場合、それは「繰り返しの自己都合退職」とはみなされず、3ヶ月の給付制限にはつながらないということです。
制度上ここを混同する方が多いため、離職票の「離職理由コード」を必ず確認し、ハローワークで説明を受けるようにしましょう!
さらに、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇も給付制限が3ヵ月になります。
会社都合でない解雇だから失業保険はもらえない──そう思っていませんか?
実は「懲戒解雇」でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給できる可能性があります。
ただし、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が適用されると、給付制限が3ヶ月になるケース、
そもそも会社都合退職になり給付制限が無く失業保険を有利にもらえる事もあります。
懲戒解雇でも給付を受け取れるかどうかを元ハローワーク職員の視点で、最新制度を交えて徹底解説します。
⇒懲戒解雇でも失業保険はもらえる?詳しくはこちら
逆に給付制限が1日もないケース
給付制限が付かない(0ヵ月になる)ケースもあります。
会社都合の離職(特定受給資格者)や、やむを得ない事情による特定理由離職者に該当すれば、待期期間満了後に給付制限なしで基本手当の対象へ進みます。
離職票には自己都合退職と記載されていても該当の可否はハローワークが個別事実で判断するため、離職票の区分や診断書・転居等の証明ができる証拠を用意して早めに相談しましょう。
また、2025年4月以降は学び直しの促進策として、教育訓練等(厚生労働大臣指定の教育訓練・公共職業訓練・短期訓練受講費の対象訓練等)を離職前1年以内または離職後に受けた(受けている)場合、自己都合でも給付制限が解除されます。受講の種類や開始時期で取扱いが変わるため、受講前に適用可否を確認しておくと安全です。
そしてこの判断の起点は「離職日」です。例えば、3月31日離職は旧ルール、4月1日離職は新ルールの適用が基本です。給付制限の長短は受給手続の時期ではなく離職日で決まる点を押さえておくと、手戻りが防げます。迷ったら離職票の理由区分と離職日、過去5年の離職歴、教育訓練の受講有無を先に整理し、ハローワークで照会しましょう。
特に「失業保険をすぐにもらえるのか?」という点が気になる方は、失業保険はいつからもらえるのか?元ハロワ職員が徹底解説したこちらの記事も参考になります。制度の適用タイミングを具体例で確認しておくと、給付制限期間の考え方がより明確になります。
自己都合退職の場合でも失業保険をすぐもらえる3つのケース
自己都合退職になっても、特定の条件を満たせば、待機期間終了後すぐに失業保険を受け取れる可能性があります。
待機期間終了後すぐに失業保険を受け取れるケースは以下の3つです。
- 特定理由離職者に該当する場合
- 職業訓練を受講する場合
- 【2025年4月以降】教育訓練給付金対象講座を受講した場合
上記のケースに該当する方は、早めに失業保険を受け取れる可能性があるため、手続きするのがおすすめです。
では、上記3つのケースを詳しく見ていきましょう。
特定理由離職者に該当する場合
自己都合退職でも「特定理由離職者」に該当すると、通常の給付制限期間の免除が受けられ、失業保険を早急に受け取れるかもしれません。
特定理由離職者とは、自己都合退職であっても、やむを得ない事情が認められる場合に該当します。
特定理由離職者に該当する主なケースを以下の表にまとめました。
| 該当するケース | 詳細 |
|---|---|
| 健康上の理由 | 病気や心身の障害で働けなくなった場合(診断書が必要) |
| 家庭の事情 | 妊娠、出産、育児、親族の介護や看病など |
| 通勤困難 | 配偶者の転勤や結婚などでの引越しで通勤が困難になった場合 |
| 契約更新拒否 | 有期契約社員が契約更新を希望しても拒否された場合 |
| ハラスメント等 | 職場でのパワハラやセクハラなどが原因で退職した場合(証拠が必要) |
上記に該当する場合、特定理由離職者に認定され、早めに失業保険を受け取れる可能性があります。
参考:特定理由離職者になるにはどうすればいい?失業理由を証明する方法を徹底解説!
職業訓練を受講する場合
自己都合退職でも、公共職業訓練を受講する場合は、通常の給付制限期間の免除が受けられ、失業保険をすぐに受給できるかもしれません。
公共職業訓練は、再就職に必要なスキルや知識を習得するための制度で、受講者には早期の経済的支援が必要と判断されるため、早めの受給を目指せます。
公共職業訓練には、以下のようなプログラムがあります。
| 公共職業訓練の種類 | 詳細 |
| IT分野の職業訓練 | プログラミングやデータ分析など、IT分野での再就職を目指すコース |
| 介護職員初任者研修 | 介護分野での就職を目指すための資格取得コース |
なお、自己都合退職でも失業保険をすぐに受給する方法に関してさらに詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
職業訓練・教育訓練やその他での方法も記載!!
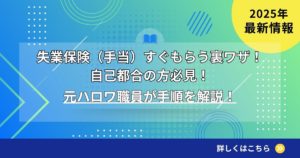
【2025年4月以降】教育訓練給付金対象講座を受講した場合
2025年4月施行の雇用保険法改正で、通常の給付制限期間がなくなります。雇用保険法改正は、スキルアップやキャリア形成の促進を目的に施行が決まりました。
離職後に厚生労働省が指定する教育訓練を自主的に受講した場合、または離職前1年以内の場合は再就職支援の一環として給付制限が撤廃されます。
2025年4月以降、自己都合退職者が教育訓練給付金対象講座を受講し、7日間の待機期間終了後すぐの失業保険受給が可能です。
失業保険の待機期間中に注意したい2つのポイント
失業保険の待機期間では、特に以下2つのポイントに注意しましょう。
- アルバイトや収入をともなう活動は控える
- 生活費の確保を計画する
失業保険にプラスしてお金を得る活動をすると、不正受給につながる恐れがあるため、意識しなければなりません。
では、それぞれの注意ポイントを詳しく解説します。
アルバイトや収入をともなう活動は控える
失業保険の待機期間中は、アルバイトや収入をともなう活動は控える必要があります。
待機期間は、完全に失業状態にあることを確認するための期間です。待機期間中に収入を得る活動を行うと、「完全な失業状態」とみなされず、待機期間が延長される可能性があります。
待期期間が延長してしまうと、失業保険の受給が遅れてしまうため、経済的な負担が大きくなりかねないため、収入を得るための活動は控えてください。
また、働いた事実を申告しなかった場合、不正受給と見なされる可能性もあるため、注意しましょう。
生活費の確保を計画する
失業保険の待機期間中は失業手当が支給されないため、生活費の確保を事前に計画しておきましょう。
計画を立てずに過ごすと、生活費が不足したり、再就職活動に支障が出る可能性があります。具体的には、以下のような計画を立てるのがおすすめです。
- 家計の見直し
- 就職活動の計画
- スキルアップ
待機期間中は収入がないため、家計を見直し、無駄な支出を削減しましょう。また、いつまでにどのような仕事を探すか、具体的な計画を立てておくと、生活費の管理がしやすくなります。
待機期間中は資格の勉強など、スキルアップに時間を充てるのもおすすめです。
計画的に行動できれば、スムーズな求職活動やスキルアップにつながり、再就職の成功率を高められます。
関連記事:失業保険の待期期間とは?アルバイトの可否や給付制限がなくなるケースを解説
関連:自己都合の場合の失業保険!基本的なしくみから具体的な流れまで解説 | 人材スカウト
【自己都合退職の場合】待機期間終了後の失業保険受給までの流れ 4STEP
自己都合退職の場合、待機期間終了後、失業保険を受給するためには、いくつかの手続きが必要です。
待機期間を終えた後の失業保険の手続きを、以下の4つのステップに分けて解説します。
- 雇用保険受給者説明会の受講
- 初回の失業認定日
- 2回目の失業認定日
- 失業手当の受給
では、それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
1.雇用保険受給者説明会の受講
雇用保険受給者説明会は、失業保険を受給するために必須の手続きで、待機期間終了後に指定された日時・場所で参加する必要があります。
説明会で扱われる主な内容は下記の通りです。
- 失業認定日の確認方法や必要書類の記入方法
- 求職活動実績として認められる活動内容(ハローワークでの職業相談や求人応募など)
- 失業保険を受け取る際の注意点(不正受給の禁止やアルバイト報告義務)
また、説明会では、失業保険を受け取るために必要な「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
雇用保険受給資格者証がなければ失業保険受給の手続きが進められないため、必ず説明会に参加しましょう。
2.最初の失業認定日
初回の失業認定日は、失業保険を受け取るためにハローワークで求職活動の成果を報告する日です。
失業認定日には、「失業認定申告書」に求職活動の内容(例:求人応募や面接、ハローワークでの相談など)を記入し、提出する必要があります。
失業保険の支給には「積極的に求職活動を行っている」ことが条件に含まれるため、失業認定日に自身が行った求職活動を申告する必要があります。
ただし、求職活動の実績報告を行わないと、失業保険は受け取れないため注意しましょう。
3.2回目の失業認定日
自己都合で退職した際、待機期間終了後に設定される2回目の失業認定日は、給付制限期間を終えたタイミングで行われます。
自己都合退職では、7日間の待機期間と原則2ヵ月の給付制限期間(2025年4月以降は1ヵ月)が設けられています。
そのため、初回認定日ではまだ失業保険は支給されず、給付制限期間終了後の2回目の失業認定日に求職活動実績を報告すると支給が開始される仕組みです。
4.失業手当の受給
失業手当は、失業認定日に求職活動実績が認められた場合、通常、失業認定日から2~3営業日以内に銀行口座に振り込まれます。
支給額や期間は、雇用保険の加入期間や離職理由など、個々の条件で異なります。
不正受給や報告漏れがあると支給が停止される場合があるため、手続きは正確に行うことを意識するようにしてください。
なお、失業手当の振込時期に関して詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

失業保険の受給に関して相談するなら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
自己都合退職の場合、失業保険の待機期間は7日間設けられており、待機期間中は失業手当は支給されません。
さらに、7日間の待機期間終了後には2ヵ月間の給付制限期間があり、制限期間中も手当は受け取れないため、注意しましょう。
ただし、2025年4月以降は給付制限期間が1ヵ月に短縮されるため、自己都合退職者も早期に手当を受け取れます。
自己都合退職で失業保険の受け取りを検討している方は、本記事を参考に計画的な転職活動を意識していきましょう。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、失業保険の受け取りに関するご相談や受給額の診断までサポートしています。
失業保険に関する些細なお悩みでも丁寧に対応させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。