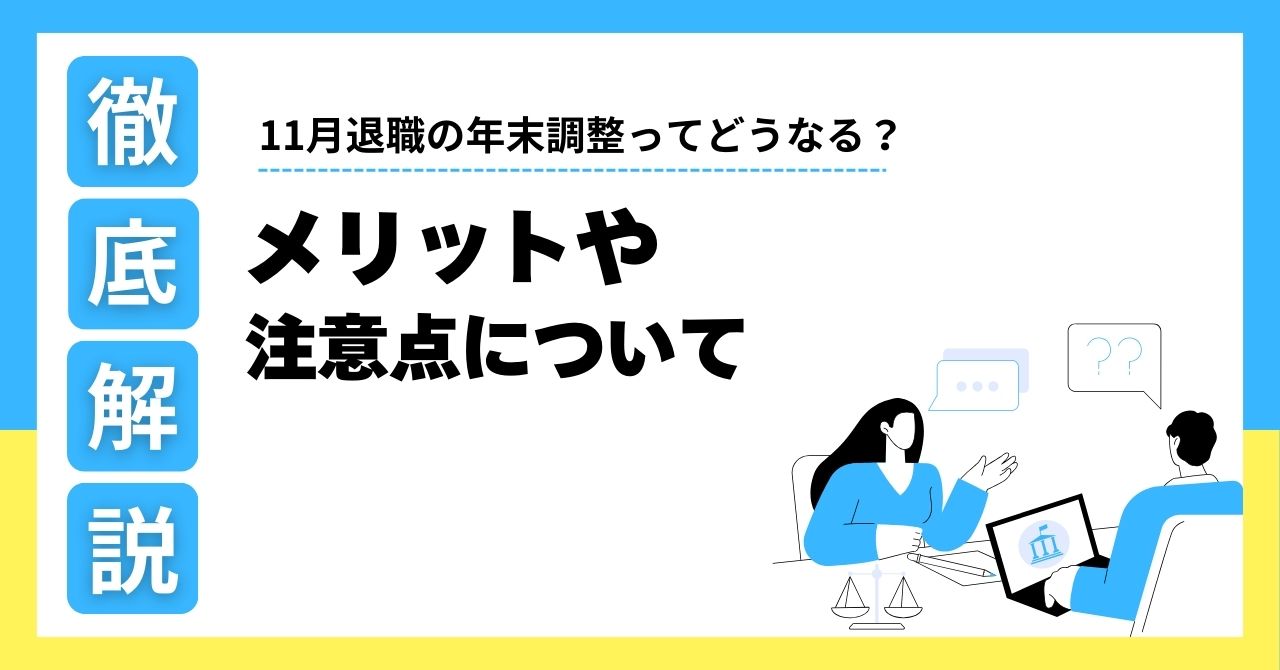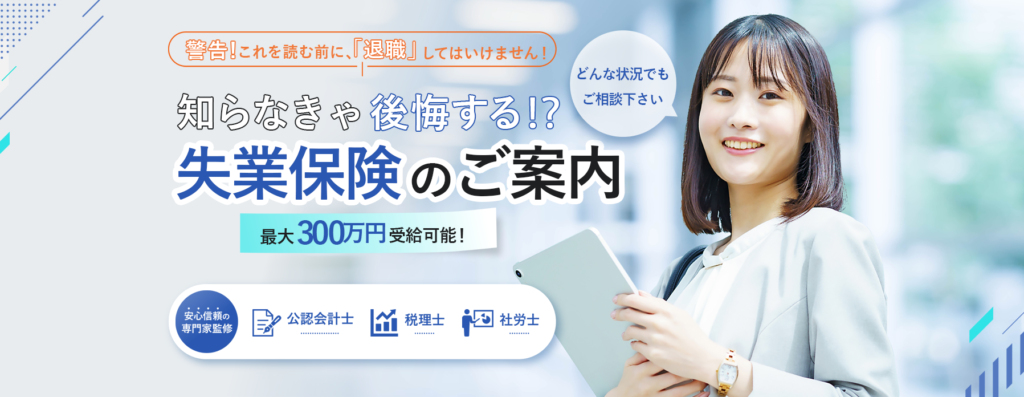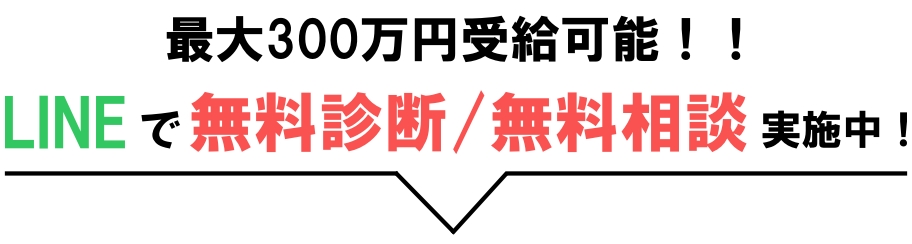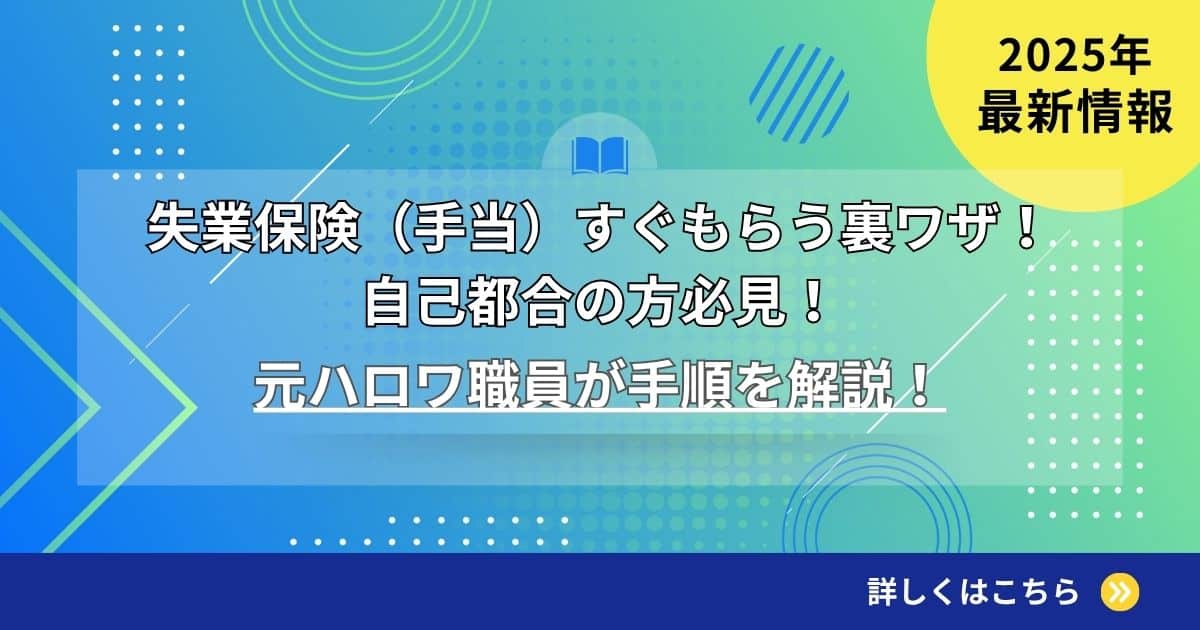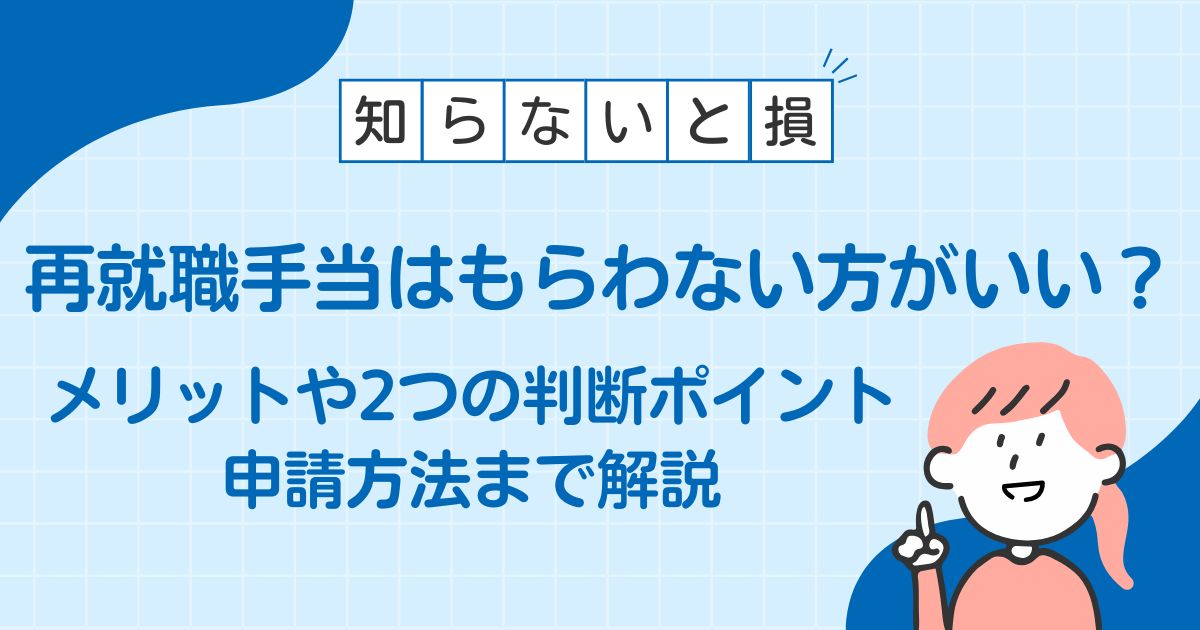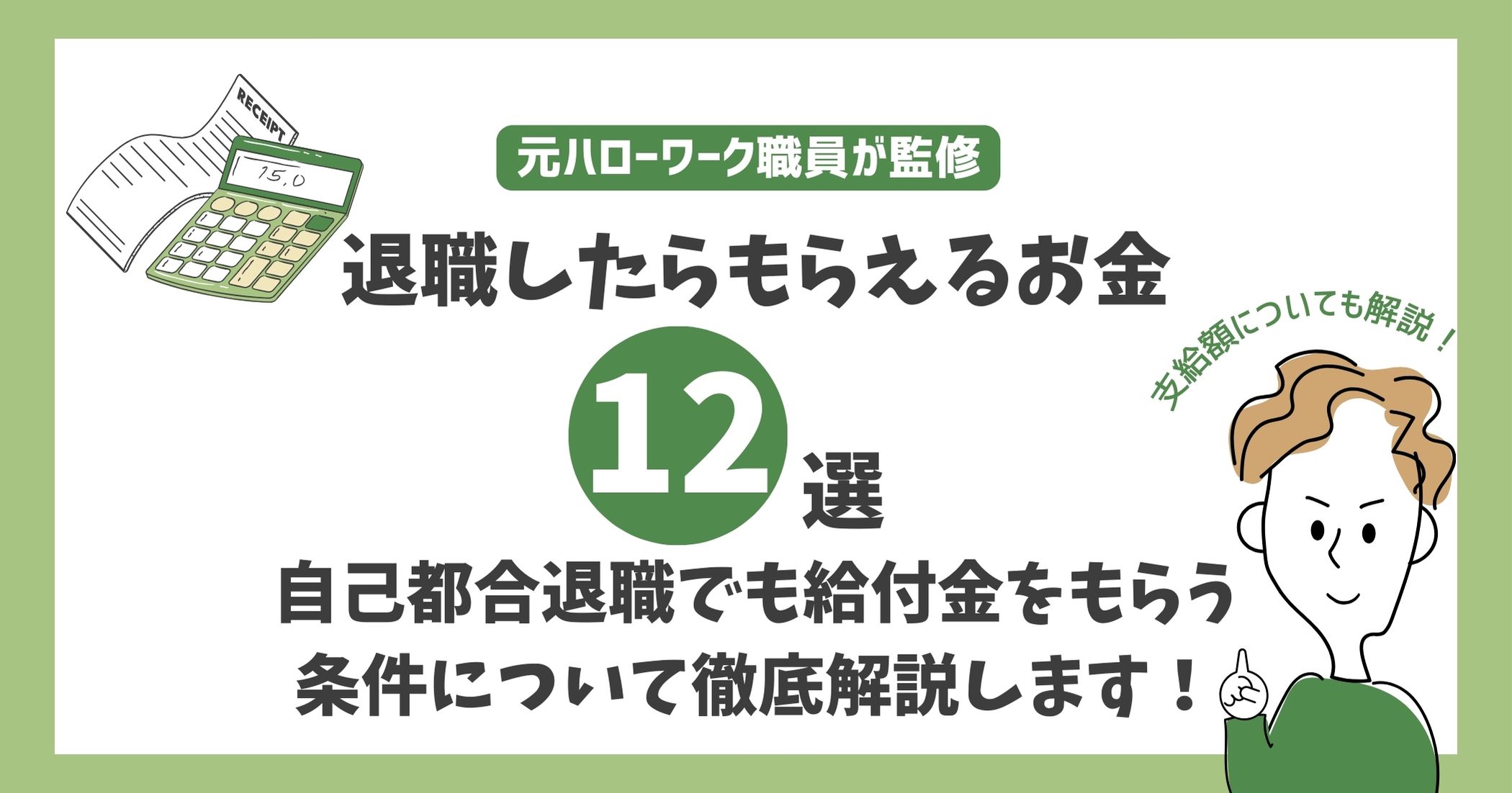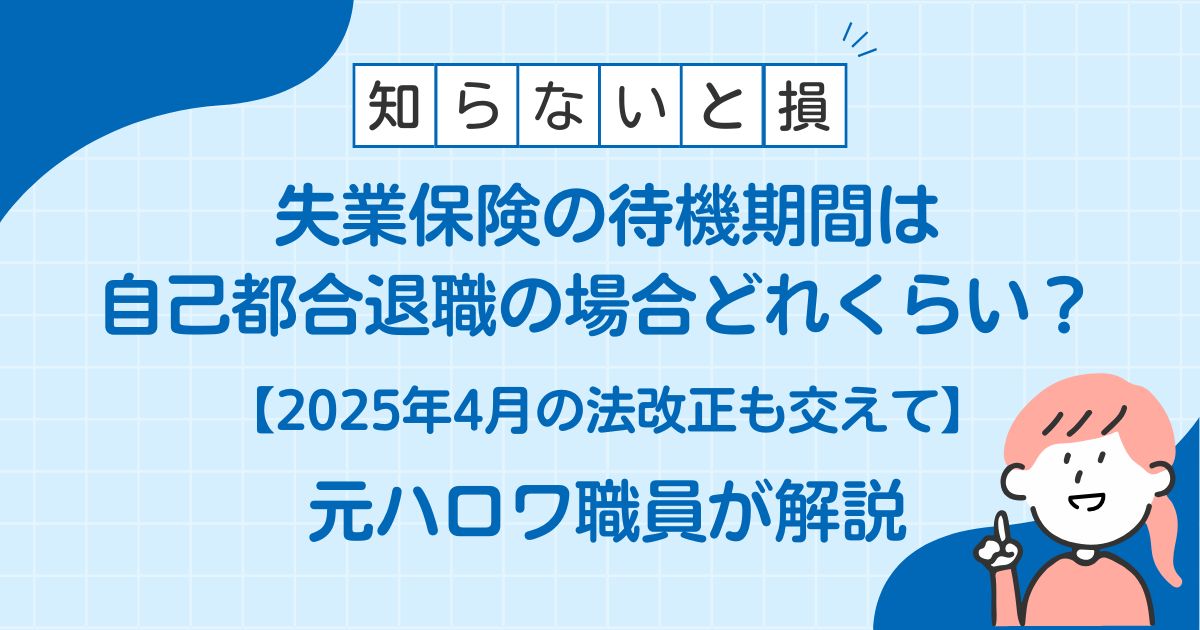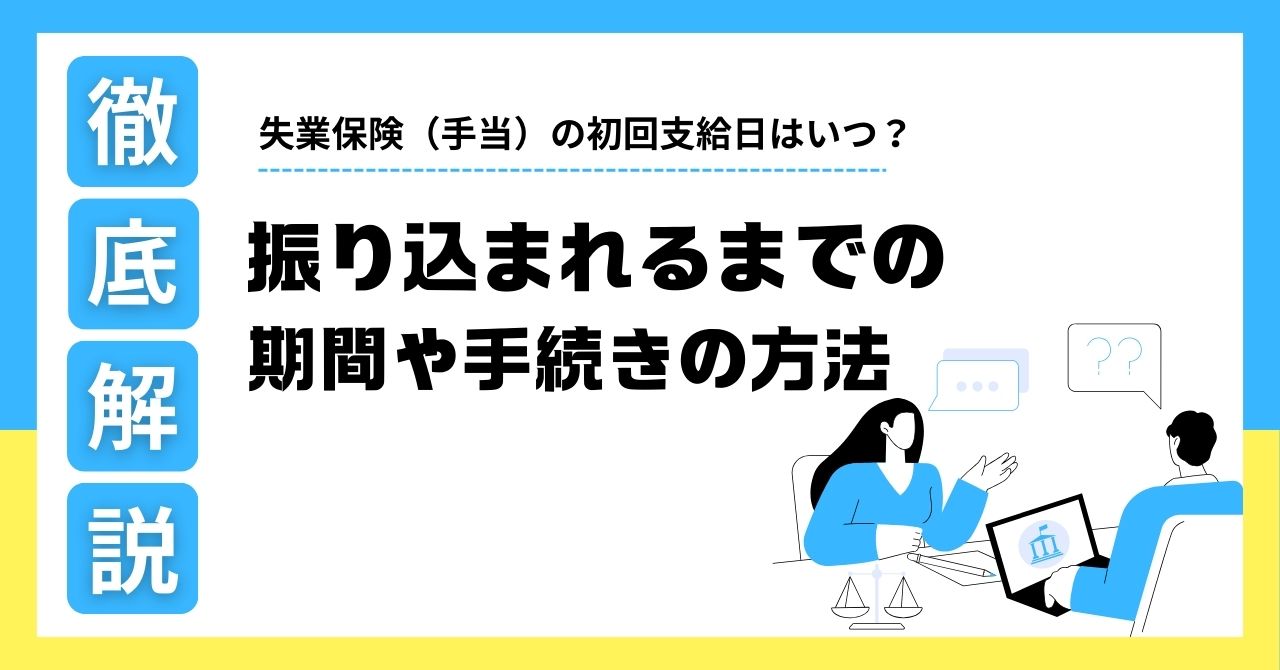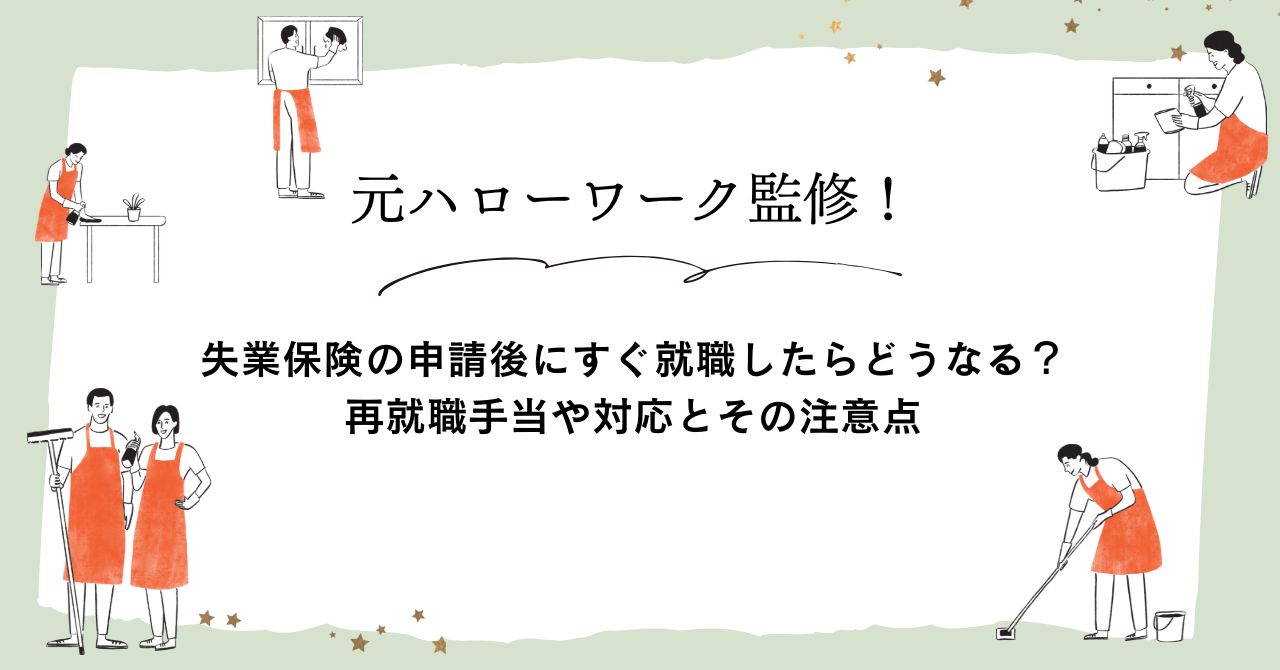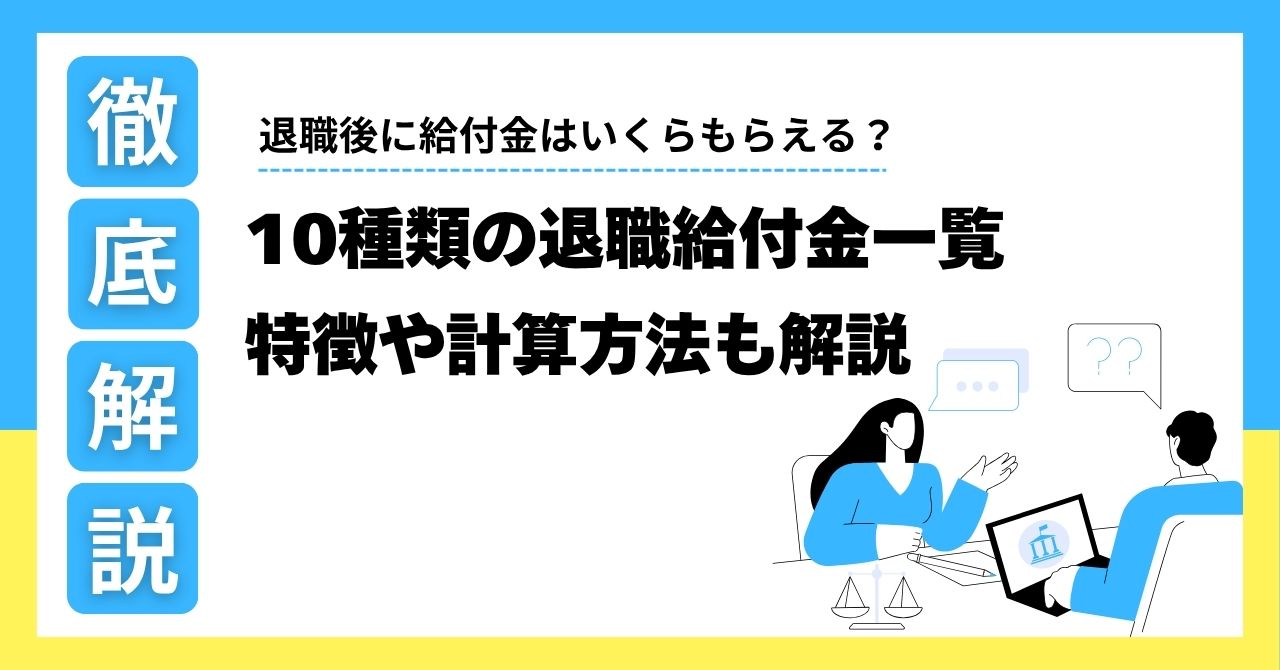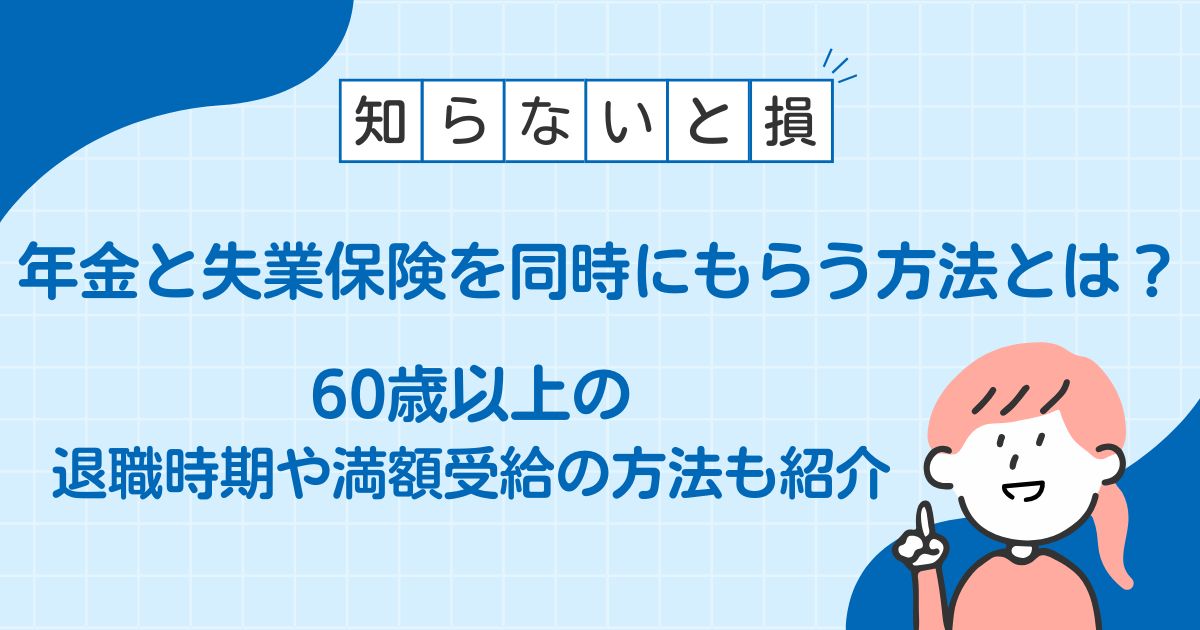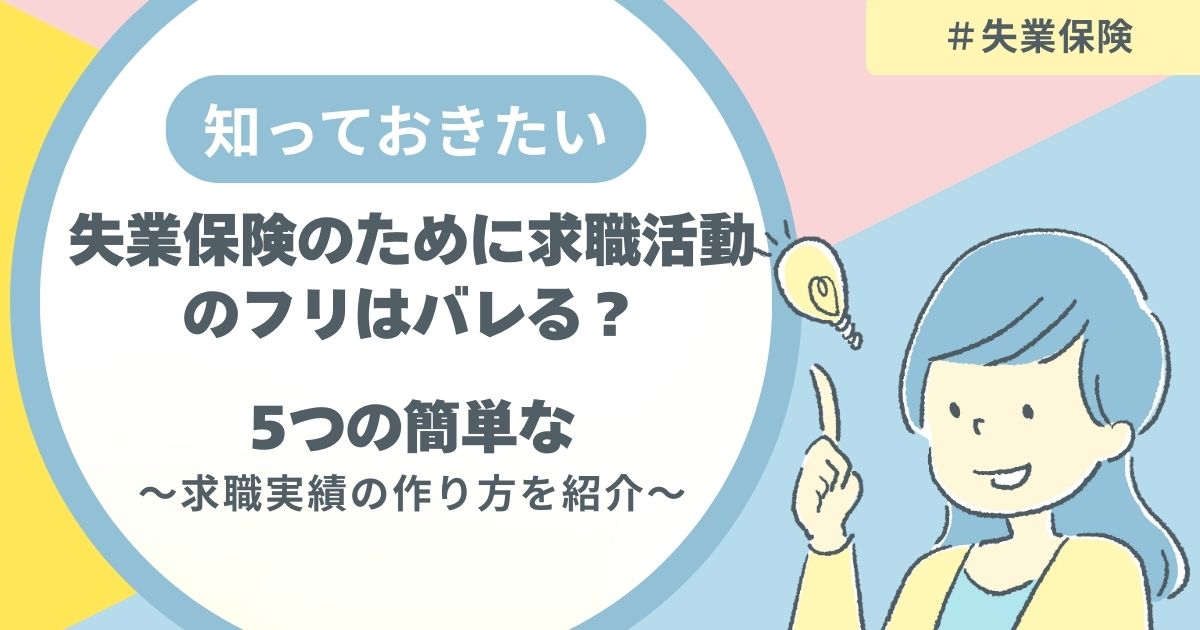11月に退職を考えている方で、以下のようなお悩みはありませんか?
「11月に退職したいけど、年末調整はどうすればいいのだろう?」
「年末が近い時期に辞めるメリットや注意点があれば知りたい」
「ボーナスや転職活動への影響も気になる…」
本記事では、11月に退職した場合の年末調整の扱いから、退職後に必要な手続きまでを詳しく解説します。本記事を読めば、11月退職に関する疑問が解消され、安心して次のステップに進めます。
11月の退職を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
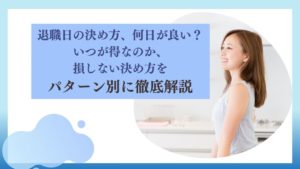
本コンテンツ(退職の手引き)は、読者に価値のある情報を提供することを目的として独自の基準に基づき制作しています。≫コンテンツ制作・運営ポリシー
退職に関する些細なお悩みでも丁寧に対応させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、退職に関するご相談を受け付けています。


11月に退職したら年末調整はどうなる?
ここでは、転職先がすぐに決まっている場合と、そうでない場合に分けて、それぞれの手続きを解説します。
- 退職後すぐに転職先が決まっている場合
- 転職が翌年1月以降になる場合
ご自身の状況に合わせて、必要な手続きを確認しましょう。
退職後すぐに転職先が決まっている場合
退職後、年内に新しい会社へ入社する場合は、転職先で年末調整を受けられます。
年末調整は、退職年の12月31日時点で在籍している会社が行う手続きだからです。退職した会社から源泉徴収票を受け取り、新しい会社の担当部署に提出しましょう。前職分の給与と合算して年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする手間はかかりません。
年末調整を自分で行いたくない方は、転職先を決めてから11月に退職し、年内に再就職するのがおすすめです。
転職が翌年1月以降になる場合
11月に退職した後、年内に再就職しない場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。会社での年末調整を受けられないため、1年間の所得を計算し、納めすぎた所得税の還付や不足分の納税手続きを自分で行わなくてはなりません。
確定申告では、退職した会社から受け取る源泉徴収票のほかに、生命保険料控除証明書など、各種控除に必要な書類を揃えて税務署に申告します。
手続きに手間はかかりますが、払いすぎた税金が戻ってくる可能性が高くなります。初めてで不安な方は、税務署の相談窓口などを活用しましょう。
11月に退職する4つのメリット
ここでは、11月に退職すると得られる4つのメリットを解説します。
- 年末にリフレッシュした状態で新年を迎えられる
- ボーナス前で引き止められにくい
- 年末の繁忙期を避けて退職できる
- 転職活動で有利になる場合がある
上記のメリットを理解し、ご自身の退職計画に役立ててください。
年末にリフレッシュした状態で新年を迎えられる
11月に退職するメリットは、年末年始を心身ともにリフレッシュした状態で迎えられる点です。
多くの企業では年末が多忙を極めますが、11月に退職すれば、慌ただしい時期を避け、自分の時間をゆっくりと確保できます。退職後の手続きや転職活動の準備をしつつ、心と身体を休ませる貴重な時間を持てるでしょう。
これまで仕事で溜まった疲れを癒し、新たな気持ちで新年をスタートさせたい方にとって、11月の退職はよい選択肢になります。
ボーナス前で引き止められにくい
多くの企業では、ボーナスは夏(6月下旬〜7月上旬)と冬(12月)の年2回支給されるのが一般的です。11月に退職する場合、ちょうど冬のボーナス支給前となるため、会社側もボーナス支給後の退職を避けたい事情があります。
支給前のタイミングで退職を申し出れば、引き止めにあいにくく、スムーズに話が進む可能性が高まります。今すぐにでも会社を辞めたいと考えている方には、11月の退職が現実的な選択肢になるでしょう。
年末の繁忙期を避けて退職できる
11月は、年末の本格的な繁忙期に入る前に退職できるメリットがあります。
12月に入ると、多くの企業では年末調整や年末商戦などで全社的に業務が忙しくなります。12月に退職を申し出ると、引き継ぎが困難になったり、職場に大きな負担をかけたりして、退職時期の調整を求められることも少なくありません。
比較的落ち着いている11月であれば、退職の申し出や業務の引き継ぎもスムーズに進めやすいでしょう。
転職活動で有利になる場合がある
11月の退職は、転職活動で有利に働く場合があります。年末は退職者が出やすく、一方で新年から新しい人材を確保したいと考える企業も多いため、求人が増える傾向にあるからです。
11月に退職すれば、ライバルがまだ本格的に動き出す前に、余裕を持って企業研究や応募準備を進められます。また、企業側も採用活動に時間をかけやすくなり、じっくりと面接に臨める可能性も高まります。
新年からのスタートを目指して転職活動を考えている方にとって、11月の退職はよいタイミングです。
11月に退職する際の3つの注意点
11月の退職にはメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。
- 年末のボーナスがもらえない場合がある
- 会社に年末調整をしてもらえない
- 社会保険の切り替えに手間や時間がかかる
上記の注意点を踏まえた上で、ご自身の状況に合った最適な判断をしてください。
年末のボーナスがもらえない場合がある
11月に退職する場合の注意点は冬のボーナスを受け取れない可能性が高い点です。
多くの企業では、ボーナスの支給条件として「支給日に在籍していること」を就業規則で定めています。冬のボーナスは12月に支給されることが多いため、11月末で退職すると、在籍条件を満たせません。
引き止められにくいメリットがある反面、ボーナスを期待している場合は収入減となります。ご自身の会社の就業規則を確認し、ボーナスの支給条件を把握した上で退職時期を慎重に検討しましょう。
会社に年末調整をしてもらえない
11月に退職し、年内に再就職しない場合、会社で年末調整をしてもらえません。
年末調整は、在籍年の12月31日時点で会社に在籍している従業員が対象だからです。11月末で退職した場合は対象外となり、自分で確定申告をして所得税の過不足を精算する必要があります。
確定申告には、源泉徴収票や各種控除証明書などを揃え、税務署で手続きを行う手間がかかるため、考慮しておきましょう。
社会保険の切り替えに手間や時間がかかる
11月に退職する際は、社会保険の切り替えに関する手続きにも注意が必要です。退職後すぐに再就職しない場合は、国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要になります。
初めて手続きを行う方には、必要書類の準備や申請の流れが複雑に感じられ、想定以上に時間がかかることもあります。
また、社会保険から国民保険に切り替えると、保険料の負担が増えるケースもあるため、事前に保険料の金額を市役所で確認しておくと安心です。
年末調整の対象者にならない4つのケース
ここでは、年末調整を受けられない主な4つのケースを簡潔に解説します。
- 給与の総額が2,000万円以上
- 中途採用者で前職分の源泉徴収票がない
- 災害減免法の規定で所得税の軽減免除を受けた
- 2つ以上から給与の支払いを受けている
上記のケースに該当する場合は、自分で確定申告が必要です。
給与の総額が2,000万円以上
年間の給与収入の総額が2,000万円を超える方は、年末調整の対象になりません。高額所得者は給与以外の所得があるケースも多く、年末調整では対応できないためです。
上記の場合は、会社から交付される源泉徴収票をもとに、自分で確定申告を行う必要があります。
また、源泉徴収票には、主に以下の記載が必要です。
- 支払いを受ける者の住所または居所、氏名およびマイナンバー
- 種別や支払い金額、源泉徴収税額
- 中途就・退職
- 生年月日
- 支払い者の住所(居所)または所在地、氏名または名称、電話番号およびマイナンバーまたは法人番号
- 摘要 など
上記の情報は年末調整や確定申告に必要となるため、内容に誤りがないか必ず確認しておきましょう。
中途採用者で前職分の源泉徴収票がない
中途採用者で前職の源泉徴収票が提出されていない場合、年末調整の対象外となるケースがあります。前職の所得情報が確認できないと、正確な所得税額が算出できず、年末調整が実施できないためです。
また、年間の給与が250万円を超える場合は、源泉徴収票を税務署へ提出する義務が生じることもあります。
上記の場合は、自分で確定申告を行い、所得税の過不足を精算する必要があり、手続きの手間が増える点にも注意が必要です。
災害減免法の規定で所得税の軽減免除を受けた
災害減免法の適用を受けて所得税の軽減や免除を受けた方は、年末調整の対象から外れることになります。
上記の制度は、自然災害などによって住宅や家財に甚大な被害を受けた場合に適用されます。条件は以下の通りです。
- 被害額が住宅や家財の時価の2分の1以上であること
- 所得金額の合計が1,000万円以下であること
- 雑損控除の適用を受けていないこと
所得金額が500万円以下の方は、所得税が全額軽減または免除されるケースもあります。年末調整では特例が反映されないため、該当する方は確定申告が必要です。
2つ以上から給与の支払いを受けている
複数の事業所から給与を受け取っている場合も、年末調整の対象外となります。源泉徴収の方法が「主たる給与」と「従たる給与」で異なるためです。
主たる給与とは、扶養控除等申告書を提出している勤務先からの給与を指し、税額表の「甲欄」に基づいて源泉徴収が行われます。一方で、勤務先から支払われる従たる給与は、「乙欄」に基づいて税額が決まります。
自分が受け取っている給与が主たるものか従たるものかを把握しておきましょう。給与の種類によって扱いが異なるため、年末調整の対象となるかどうかにも影響します。
11月で退職に関するよくある質問
ここでは、11月に退職する際によく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 11月までに消化できなかった有給はどうなりますか?
- 退職後に必要な手続きは何がありますか?
- 退職する際はどのような手順で進めればいいですか?
11月に退職を検討している方が事前に疑問を解消しておくと、スムーズに退職準備を進められます。
- 11月までに消化できなかった有給はどうなりますか?
-
11月までに使い切れなかった有給休暇は、退職日や退職日の前後の状況によって対応が異なります。年末の繁忙期が近づいている時期には、有給を消化する時間が取れず、最終的に会社側がまとめて買い取るケースも少なくありません。
一方で、退職までにある程度の余裕がある場合には、会社から有給の消化を促されることもあります。退職日までのスケジュールを踏まえて、計画的に有給を使っておくのが望ましいでしょう。
- 退職後に必要な手続きは何がありますか?
-
転職先が決まっていない場合に必要となる主な手続きは、以下の通りです。
- 年金(国民年金への切り替え)
- 健康保険(国民健康保険への加入など)
- 税金(住民税の支払い)
- 雇用保険(失業手当の受給手続き)
期限が定められているものも多いため、計画的に進めましょう。
失業保険のもらい方に関して詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
あわせて読みたい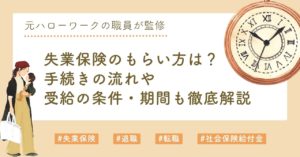 失業保険のもらい方は?手続きの流れや受給の条件・期間も徹底解説 失業保険とは、職を失った個人が経済的な安定を保ちつつ次の職に就けるようサポートするための給付金です。失業保険をもらうためには、勤務先から必要書類を受け取り、最寄りのハローワークで手続きを進める必要があります。この記事では、失業保険のもらい方について手続きの流れや条件を詳しく解説しています。給付額の計算方法や不正受給とみなされるケースも紹介しているので、ぜひご覧ください。
失業保険のもらい方は?手続きの流れや受給の条件・期間も徹底解説 失業保険とは、職を失った個人が経済的な安定を保ちつつ次の職に就けるようサポートするための給付金です。失業保険をもらうためには、勤務先から必要書類を受け取り、最寄りのハローワークで手続きを進める必要があります。この記事では、失業保険のもらい方について手続きの流れや条件を詳しく解説しています。給付額の計算方法や不正受給とみなされるケースも紹介しているので、ぜひご覧ください。 - 退職する際はどのような手順で進めればいいですか?
-
一般的な退職手続きは、以下の流れで進みます。
- 上司への意思表明
- 退職届の提出
- 業務の引き継ぎ
- 最終出社
法律上、退職の申し出は2週間前までとされていますが、円満退職のためには、就業規則に従い1~2ヵ月前には伝えるのがマナーです。11月は年末が近いため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
11月に退職する際の手続きでお悩みなら「転職×退職のサポート窓口」へ相談しよう!
11月の退職は、年末の繁忙期やボーナス支給のタイミングを避けやすく、比較的スムーズに手続きが進められる一方で、社会保険の切り替えや年末調整が受けられないなどの注意点もあります。
退職後の手続きや年末調整の対象可否、確定申告の必要性などを事前に理解しておくと、安心して次のステップに進めるでしょう。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、退職に関するご相談を受け付けています。
退職に関する些細なお悩みでも丁寧に対応させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。