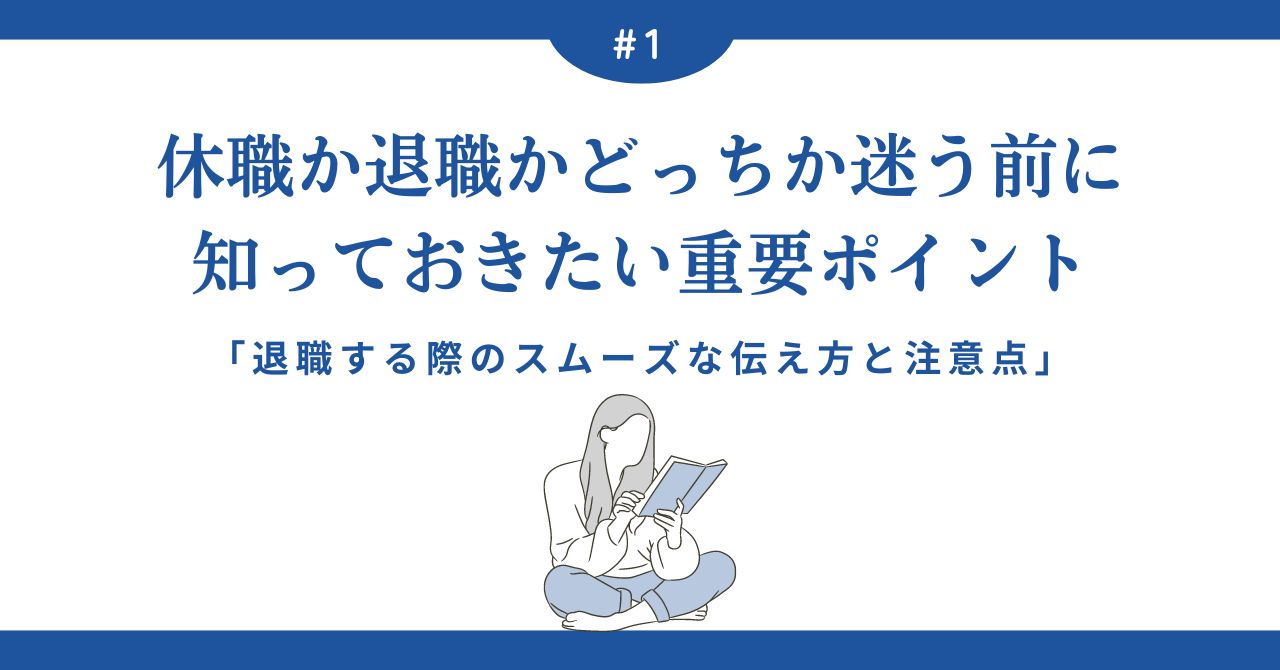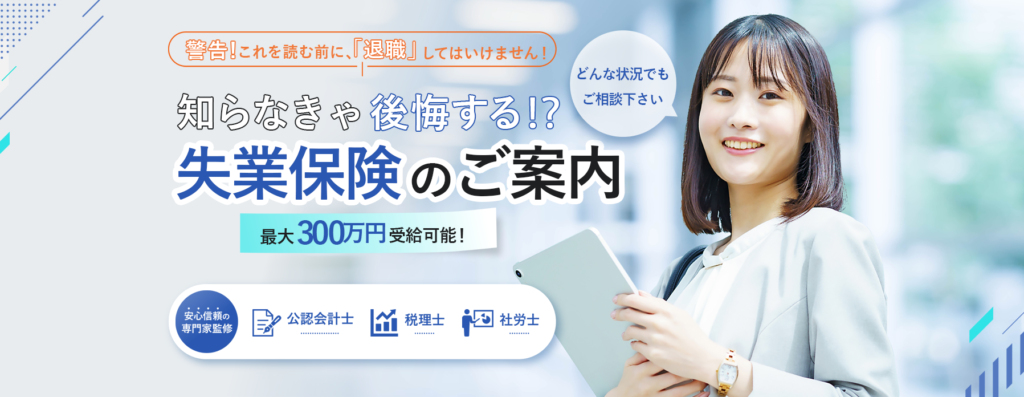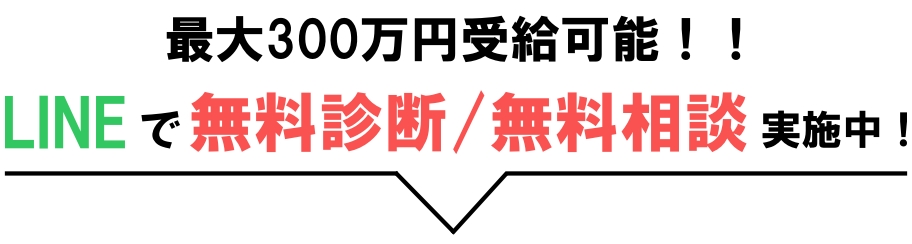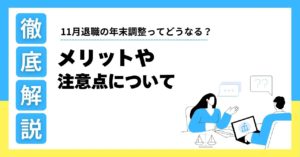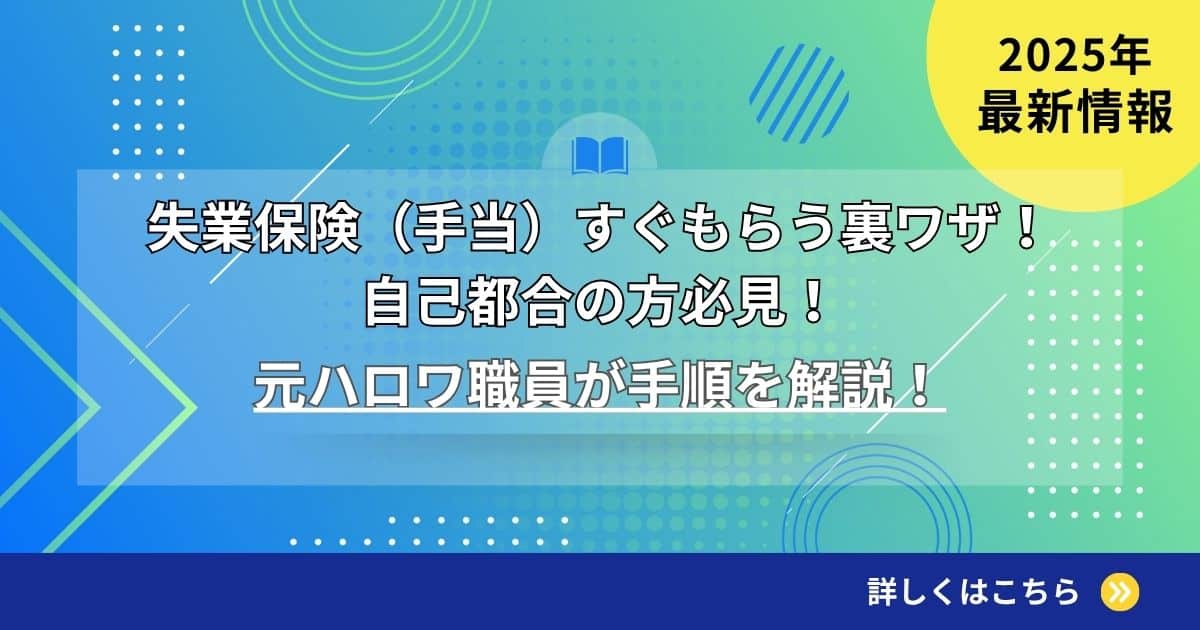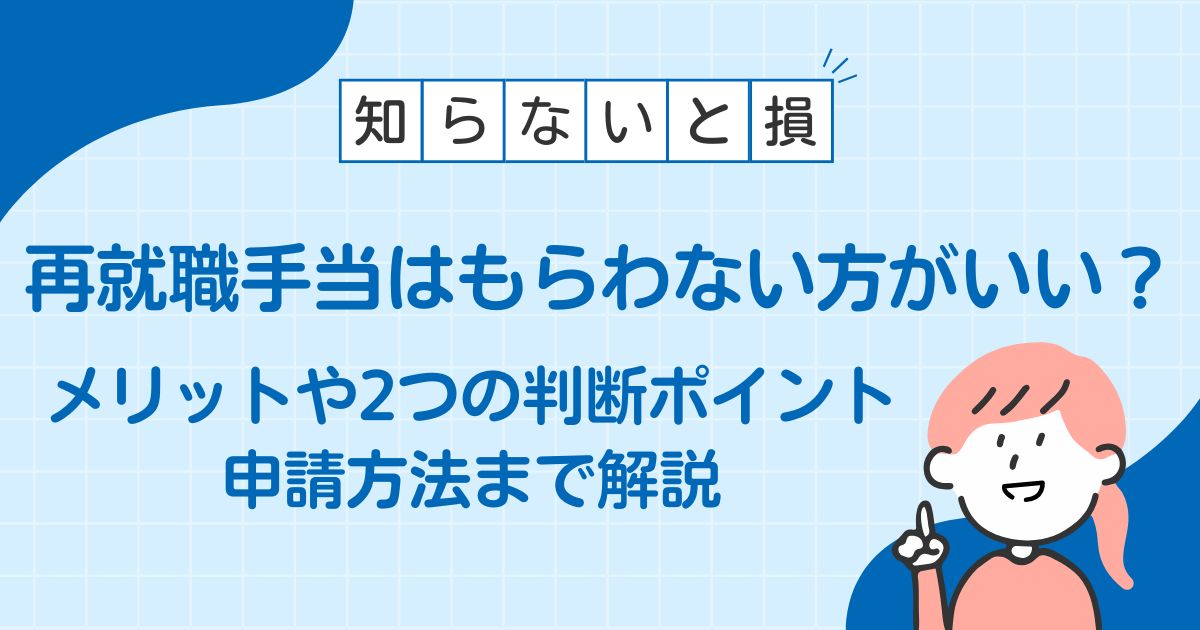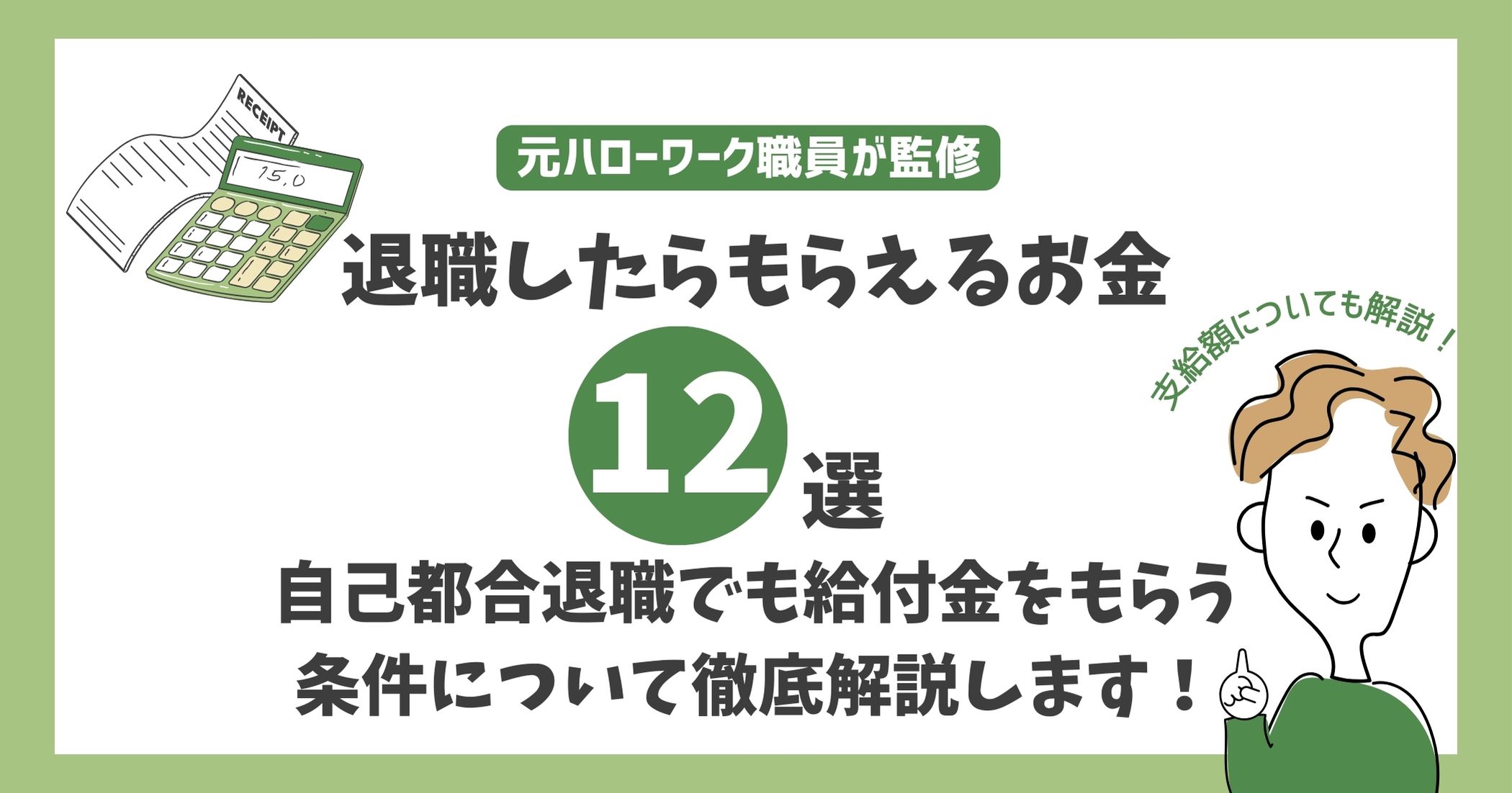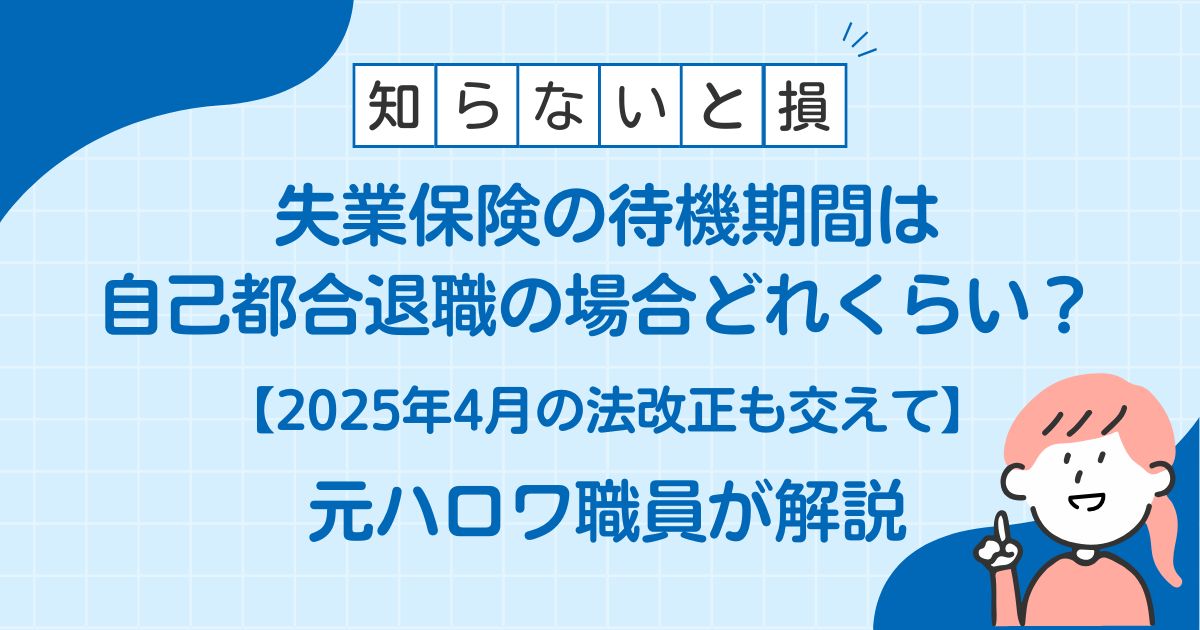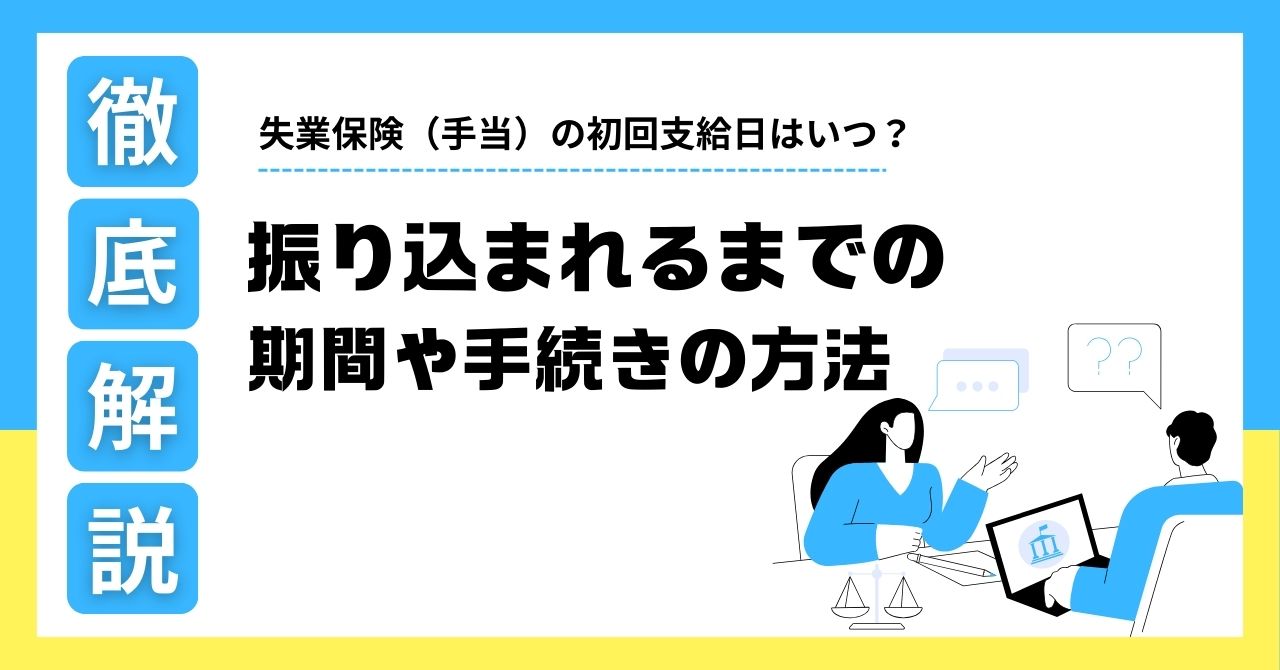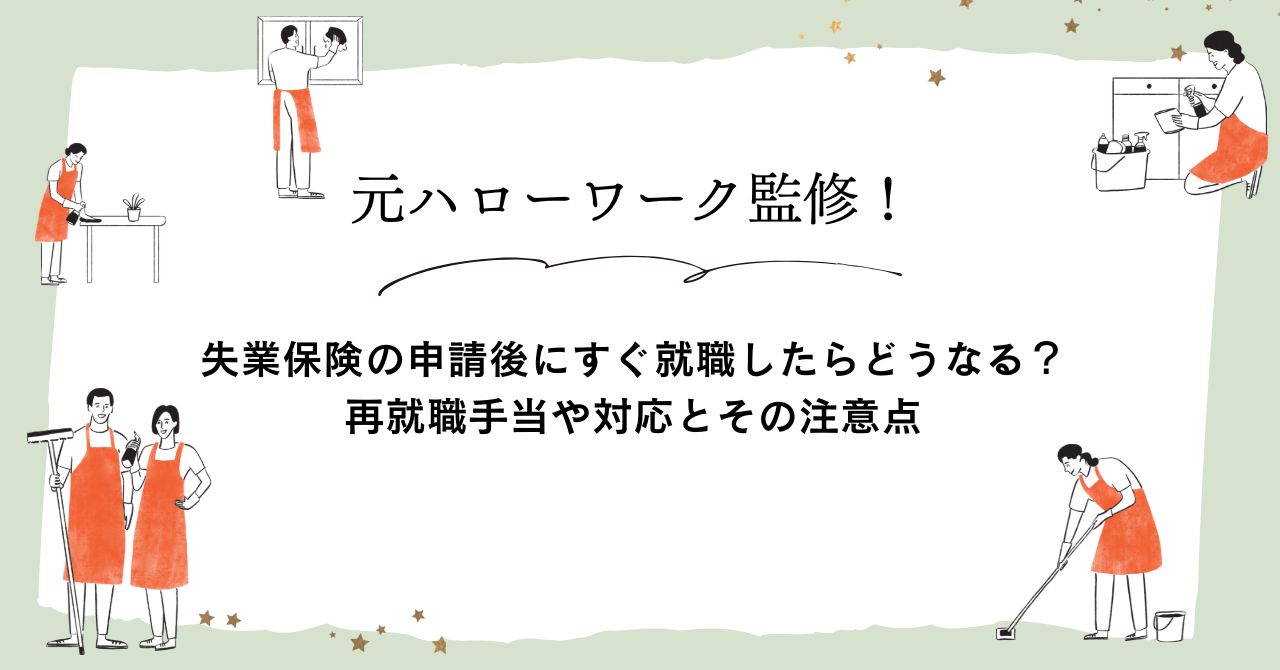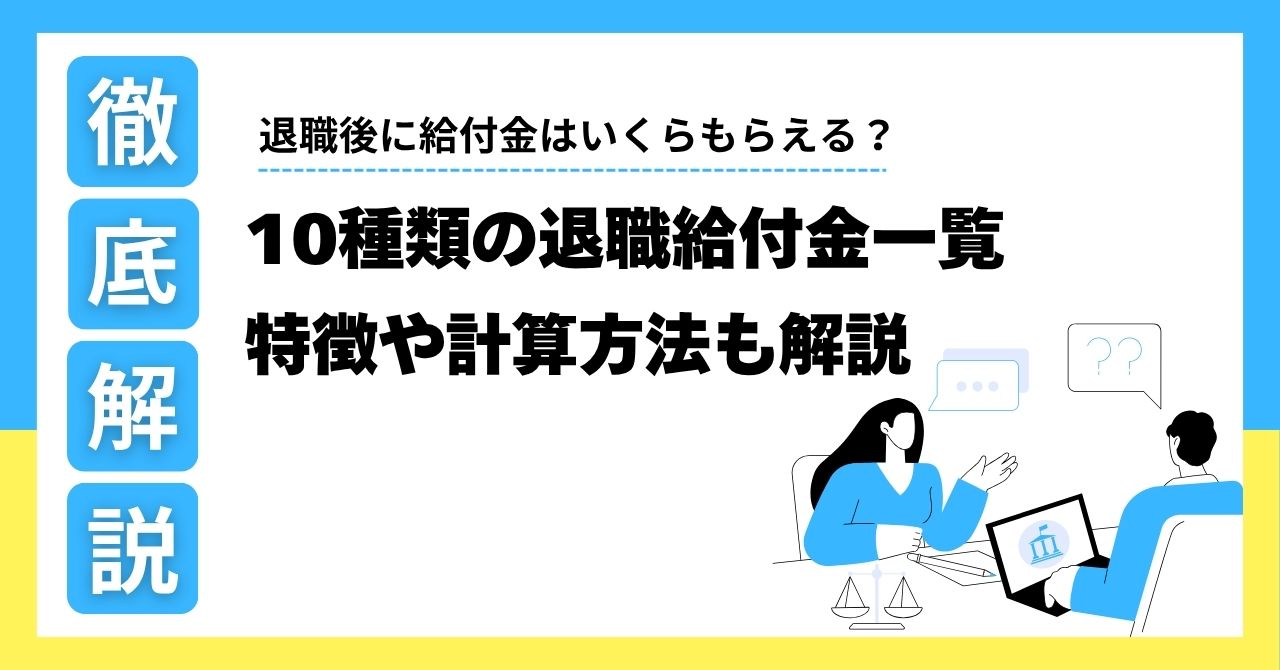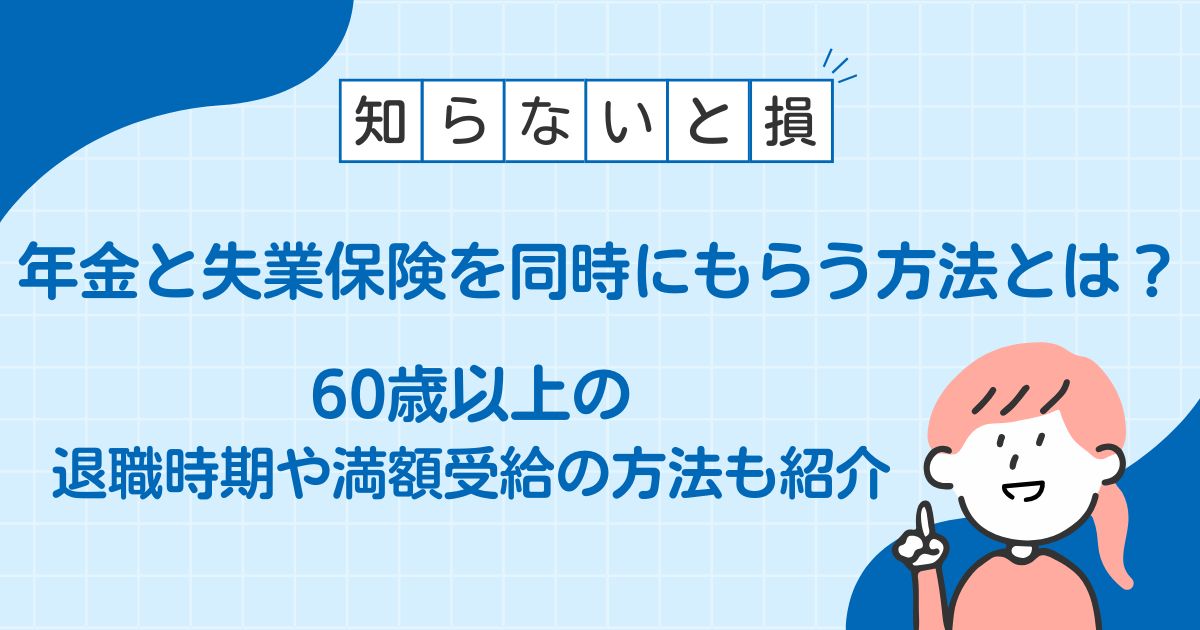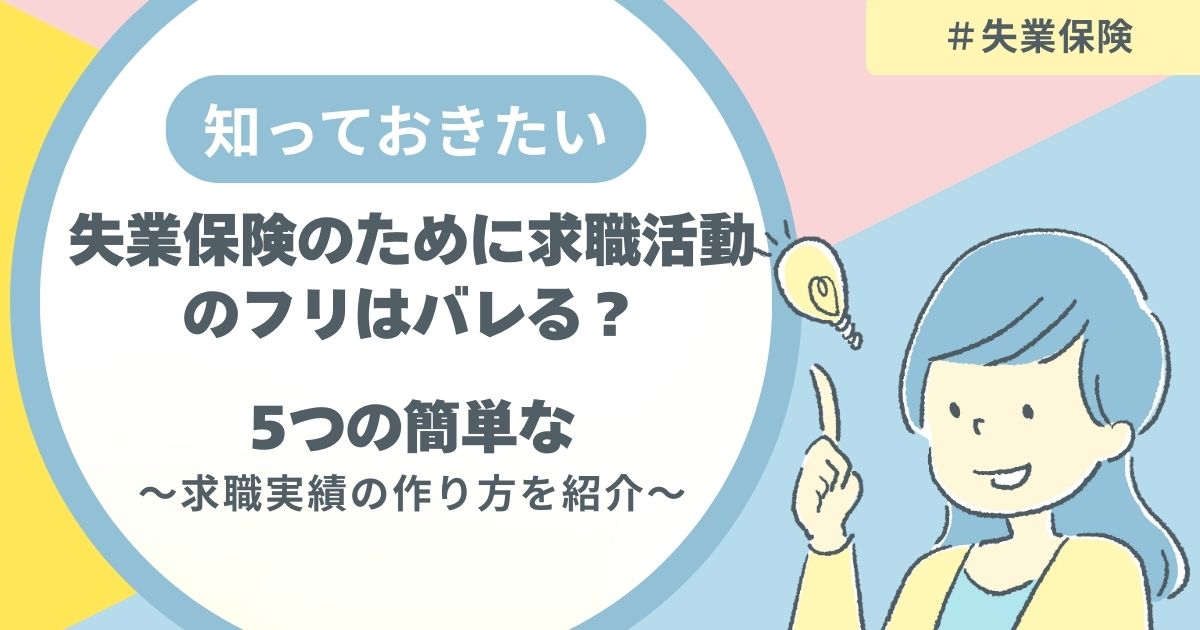元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員が解説いたします!
仕事の中でストレスやプレッシャーが増し、休職か退職かで迷う瞬間は誰にでも訪れます。
このような重要な決断を前に、どちらの選択が自分にとって最適かを慎重に判断することが求められます。
この記事は、こんな人にオススメです!
- 休職か退職をするのか迷っている。
- 休職をしたらどんなデメリットがあるのか?
- 休職して復職も考えているが正解がわからない。
- 休職後に退職をするがどのように伝えればよいのか?
- 休職や退職の注意点を知りたい。
結論から申し上げると、休職か退職どっちを選ぶべきかは、人それぞれの状況によって異なります。
現在の職場に対する不満やストレスが一時的なものであり、将来的に環境の改善が期待できる場合は、休職を選ぶのが適しているでしょう。
しかし、健康やメンタルが回復しても職場復帰が難しいと感じる場合は、退職を検討するのがよいでしょう。
本記事では、休職と退職のそれぞれのメリット・デメリットを整理し、皆さんの決断をサポートするための情報を提供します。
健康やキャリア、生活面での影響を考慮し、最適な選択を見つけましょう。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部休職を考えているということは、心身ともに疲れている可能性があります。無理をしてしまい、更に悪化する事は状況的によくありません。
この記事の内容を参考して、周りの人に助けを求めることが大切です。

「休職するなら退職しろ」と上司に言われた際の3つの対処法
休職を申し出た際、上司から「休職するなら退職しろ」と言われてしまった場合の対処法は以下の3つです。
- 人事部や頼れる上司と話し合う
- 労働組合に相談する
- 弁護士に法律相談をする
退職をすすめられても、上記の方法を活用すれば休職する方法を見つけられます。
では、それぞれの対処法を詳しく見ていきましょう。
人事部や頼れる上司と話し合う
休職に関して正当な理由がある場合、人事部や信頼できる上司に相談し、適切な対応を求めるのがおすすめです。医師の診断書や法的な主張を示しながら、冷静に状況を説明するよう心がけましょう。
会社側も、従業員の健康管理には一定の責任を負っているので、休職の必要性を理解してもらえるよう粘り強く交渉を続けてください。
なお、上司の一存で休職を拒否するのは適切な対応とは言えません。人事部や他の管理職の協力を得ながら、問題を解決していきましょう。
労働組合に相談する
休職を巡る上司とのトラブルに関して、労働組合に相談するのもおすすめです。労働組合は、従業員の権利を守るために活動しています。
組合員であれば、上司からのパワハラや不当な扱いに関して、組合を通じて会社に是正を求められます。休職や退職に関する適切なアドバイスも得られるでしょう。
また、労働組合が介入すると、会社側も従業員の立場に立った対応を迫られます。そのため、労働組合との連携を密にし、問題解決に向けて行動するのが大切です。
弁護士に法律相談をする
休職を巡るトラブルが深刻な場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。弁護士は、労働問題に関する法的な知識を持っているので、適切なアドバイスやサポートが受けられるでしょう。
また、弁護士事務所や労働組合、法テラスなどに相談すれば、労働問題に詳しい弁護士を探してもらえます。
なお、インターネット上でも労働問題に関する無料相談を受け付けている弁護士事務所もあります。気軽に相談できるため、トラブルの初期段階から弁護士に相談するのがおすすめです。
休職か退職かで迷う背景とその要因
休職と退職の間で迷う方が多いのには、以下のような要因があります。
- 職場環境や人間関係の問題が要因
- 精神的・身体的な健康問題が要因
- キャリアや将来への不安が要因
人間関係や健康、キャリアなどさまざまな要因が絡んでいます。
では、それぞれの要因を詳しく見ていきましょう。
職場環境や人間関係の問題が原因
職場での人間関係や環境の悪さがストレスの原因になることは少なくありません。
上司との関係が悪化している、同僚とのコミュニケーションがうまくいかない、あるいは過重な業務が続いているといった状況では、心身の負担が大きくなります。
このような場合、休職を通じて一時的に職場から離れることで解決を図ることができますが、根本的な改善が期待できない場合は退職を検討する必要があるでしょう。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部退職や休職を検討している人でもっとも多い要因です。
自分自身の体調が悪化してしまう前に対策を講じる必要があります。
精神的・身体的な健康問題が理由
精神的なストレスや身体的な健康問題が原因で、仕事を続けることが難しくなるケースも多くあります。
うつ病や適応障害など、深刻なメンタルヘルスの問題がある場合は、休職して治療に専念することが勧められます。
一方で、健康が回復しても職場復帰が難しいと感じるならば、退職を選ぶことも一つの選択肢です。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部復帰をしなければいけないという思いが強すぎても休職期間だけでは、体調が回復しないことが多いため休職せずに退職をするのも一つの選択肢だと思います。
なお、以下の記事では、仕事のストレスが限界の状態で現れるサインに関して詳しく解説しています。仕事のストレスでお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

キャリアや将来への不安があるため
自分のキャリアや将来に対する不安も、休職か退職かで迷う大きな要因です。
現在の職場で将来の見通しが立たない、スキルアップの機会が乏しい、昇進や転職が難しいと感じる場合、今の仕事を続けるべきか転職を視野に入れるべきか悩むことになります。
休職によって一時的に時間を確保し、キャリアの見直しを行うのも一つの方法です。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部ふとした瞬間に自分のキャリアについて悩むこともあると思います。
このままこの会社にいて自分のためになるのか?将来的に自分の収入を上げられるのか?
そんな時は一度休職をして、考える時間も必要です。
休職か退職かを決める際に考慮すべき4つのポイント
休職と退職のどちらを選ぶべきか迷った時は、以下の4つのポイントを考慮しましょう。
- 職場環境が改善される可能性があるか
- 休職中の生活費の見通しは問題ないか
- 退職後の転職計画は立てられているか
- 信頼できる人に相談し冷静に決断する
上記のポイントを意識すると、休職か退職かが選びやすくなります。
では、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
職場環境が改善される可能性があるか
職場環境の問題が原因で、休職や退職を検討しているケースは少なくありません。上司とのコミュニケーションの改善や、業務内容の見直しなど、職場環境が改善される見込みがあれば、休職を選びやすくなるでしょう。
一方、根本的な問題解決が難しいと判断されるケースでは、退職を選ぶことも視野に入れる必要があります。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部自分の健康とキャリアを守るためにも、職場環境の改善可能性は慎重に見極めるようにしてください。
休職中の生活費の見通しは問題ないか
休職中は、会社から休職手当が支給されるため、一定の収入は得られます。ただし、通常の給与よりも支給額が減るケースが多いため、生活が苦しくなる可能性もあります。
休職を検討する際は、手当の支給額を確認し、生活費を賄えるかどうか判断しましょう。貯蓄の状況や家族の協力体制なども考慮に入れ、休職中の生活設計をしっかりと立てておくと、経済的なストレスも軽減します。
また、経済的な不安が大きい場合は、転職も検討すべきです。
各種給付金の手続きは複雑かもしれませんが、社会保険給付金サービスを利用することで退職前にしっかりと準備することで退職後の生活も安心できます。
社会保険給付金サポート「ヤメル君」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大1000万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
退職後の転職計画は立てられているか
退職を選択した場合、次の仕事を見つけるまでの間は収入が途絶えてしまいます。特に、貯蓄が十分でない場合は、生活に大きな影響が出る可能性があります。
また、失業期間が長引くと、キャリアへの影響も無視できません。ブランクがあると、再就職が難しくなるケースもあるでしょう。
そのため、退職を選ぶ際は、事前に転職活動の計画を立てておくことが大切です。自分の強みを生かせる職種や業界を選定し、効率的に求人を探せる体制を整えましょう。
信頼できる人に相談し冷静に決断する
休職か退職を選択する際は、一人で悩まず、信頼できる友人や家族、同僚に相談するのも大切です。
客観的な意見をもらえば、自分の状況を冷静に分析しやすくなるので、最善の決断につなげられます。
ただし、最終的な判断は自分自身で行わなければなりません。周囲の意見を参考にしつつも、自分の人生に責任を持つことが大切です。
じっくりと考え抜いた上で、自信を持って決断を下してください。
「ゼロワンキャリア」では、数多くの転職実績を持つプロが一人ひとりに最適な求人選定や面接指導などキャリア形成をトータルサポートしています。
自分がどんな仕事に向いているのか?MBTIを用いた正確な適職診断ができます。
また、無料で相談できるので、今後のキャリアに少しでも不安がある方は問い合わせてみるのがおすすめです。
たったの30秒!
\自分に合った仕事がすぐわかる/
⇒無料適職診断はこちら
休職する3つのメリット
休職を選択した場合のメリットは、以下の3つが挙げられます。
- 治療に集中できる
- 会社に属している安心感がある
- 復職と退職の検討ができる
休職期間中は、疾患の治療や自分を見つめなおすのに最適な期間です。うまく活用できれば、キャリアを好転させるきっかけを作れるかもしれません。
では、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
治療に集中できる
休職の最大のメリットは、治療やリハビリに集中できる点です。仕事から一時的に離れることで、心身の回復に専念でき、無理なく治療を続けられます。
また、職場のストレス要因から距離を置くことで、心の健康を取り戻せます。
会社に属している安心感がある
休職中は、退職とは異なり、会社に所属している状態が維持されます。そのため、従業員としての地位は保持されるため、キャリアの継続性に関する安心感を得られるでしょう。
また、企業によっては、休職期間中も一定の給与が支給されるケースがあります。生活面での不安を軽減できる点は、大きなメリットです。
休職を検討中の方は、まずは会社にどのような休職制度があるかを確認してみましょう。休職のメリットを最大限に活用し、心身の回復に専念できる環境を整えることが大切です。
復職と退職の検討ができる
休職期間中は、職場から離れた環境で自分自身と向き合う時間が取れます。心身の回復を図りながら、復職に向けた準備を進められるでしょう。
また、体調面の改善が見られた場合は、復職の選択肢も見えてきます。休職前と違う部署など、異なる環境で働けば、新たなモチベーションを得られるかもしれません。
一方、休職中の生活を通じて、根本的な課題の解決が難しいと感じた場合は、退職を視野に入れることもできます。キャリアの方向性を見直し、転職を選択肢に入れるのも一つの方法です。
おすすめ:【具体例あり】採用基準とは?設定手順やポイント、テンプレートを紹介 | ピタリク
休職する3つのデメリット
一方で、休職には以下3つのようなデメリットも存在します。
- 収入減少のリスクがある
- キャリアに空白が生じる可能性がある
- 復職への不安感が強くなる
デメリットも理解した上で休職できれば、休職期間中の不安も軽減できます。
では、それぞれのデメリットを詳しく見ていきましょう。
収入減少のリスクがある
一方で、収入が減少するリスクがあります。病気休暇や労災保険の支給がある場合でも、通常の給与よりも少なくなることが多いです。
特に長期の休職では経済的な負担が大きくなる可能性があるため、事前にしっかりと見通しを立てておくことが重要です。
休職中は会社から給与が出ないことがほとんどですが、以下の支援制度を活用できます。
✅ 利用できる制度
- 傷病手当金(最大1年6か月、給与の約3分の2が支給)
- 障害年金(長期療養が必要な場合、該当する可能性あり)
👉 事前に手続きを確認し、収入の確保を計画しましょう。
キャリアに空白が生じる可能性がある
休職中は職歴に空白が生じるため、将来のキャリアに影響を及ぼす可能性があります。
転職活動を再開する際、休職期間が長かった場合、採用担当者からその理由を問われることも考えられます。
そのため、休職中もできる限りスキルアップや学びを続けることが推奨されます。
さらに会社からの印象が悪くなってしまうリスクもありますので、どのようにたいおうすればよいのか?を下記の記事を参考にしてください。
また、休職の話をすると休職するなら退職をしろと言われてしまうケースもあります。
実際にそうなった際にはどのように対応したらよいのか?などについて下記の記事を参考にしてください。
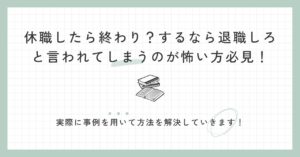
復職への不安感が強くなる
休職から復職するプロセスでは、さまざまな不安が頭をよぎるものです。特に、休職前と同じ職場に戻る場合、上司や同僚との関係性の変化が気がかりになるケースも多いでしょう。
休職期間が長引くほど、復職へのハードルは高くなっていきます。会社を離れている間に、業務の内容や職場の雰囲気が変化しているかもしれません。
そのため、休職中は復職に向けた準備を怠らないことが大切です。体調管理に努めながら、職場と積極的にコミュニケーションを取るようにしてください。
退職する3つのメリット
退職を選択した場合のメリットは、以下の3つが挙げられます。
- ストレスから完全に解放される
- 転職によるキャリアアップが期待できる
- 新しい人間関係を作れる
退職したからといってキャリアに大きく影響が出ることはありません。むしろ、キャリアチェンジでよい方向に進む可能性もあります。
では、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
ストレスからの完全に解放される
退職の最大のメリットは、職場のストレスから完全に解放されることです。
職場の問題が解決困難な場合、退職を選ぶことで心身の負担を減らし、新たなキャリアや自己実現の機会を得られます。
転職によるキャリアアップが期待できる
退職を機に、新たなキャリアを築くチャンスが広がります。特に、長時間労働や休日出勤が常態化している職場では、自分の時間を確保するのが難しいものです。
退職後は、自分のペースで転職活動に取り組めます。これまでの経験を生かしつつ、新たなスキルを身につける時間も作れるでしょう。
また、業界や職種を変えると、キャリアの幅を広げられる可能性もあります。さまざまな選択肢を検討しながら、自分に合った働き方を見つけていくことが大切です。
新しい人間関係を作れる
転職すると、新しい職場で一から人間関係を築いていくことになります。職場の人間関係に悩んでいた方にとっては、新たな出会いが刺激になるはずです。
また、新天地で上司や同僚と良好なコミュニケーションを取れれば、仕事のパフォーマンスも向上していくでしょう。ストレスを感じることなく働ける環境が整えば、モチベーションも自然と上がります。
さらに、新しい人間関係の構築は自分自身の成長にもつながり、多様な価値観や経験を持つ人と交流すると視野も広げられます。
退職する3つのデメリット
退職を選択した場合のデメリットは、以下の3つです。
- 収入が途絶える場合がある
- 保険や年金の手続きが必要になる
- 失業期間が長くなると転職に不利になる
退職するデメリットを踏まえておけば、退職後の負担も軽減できます。
では、それぞれのデメリットを詳しく見ていきましょう。
収入が途絶える場合がある
退職後は収入が途絶えるため、次の仕事がすぐに見つからない場合、経済的な不安が増します。
特に家族を養っている場合、生活費の確保が重要です。
そのため、退職を決断する際には、退職後の生活費の計画を事前に立てておく必要があります。
各種給付金の手続きは複雑かもしれませんが、社会保険給付金サービスを利用することで退職前にしっかりと準備することで退職後の生活も安心できます。
社会保険給付金サポート「ヤメル君」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大1000万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
保険や年金の手続きが必要になる
退職後は、健康保険や年金の手続きを自分で行う必要があります。これらの手続きは時間と労力を要するため、退職後のスムーズな手続きを考慮し、事前に準備しておくことが大切です。
特に健康保険については、国民健康保険や任意継続の手続きが必要になることが多いため、注意が必要です。
失業期間が長くなると転職に不利になる
退職後、再就職までに時間がかかると、転職活動で不利になるケースがあります。一般的に、離職期間が3ヵ月以上に及ぶと、企業側から何らかの問題があると見なされるかもしれません。
また、長期の失業期間は、スキルのブランク化や社会性の低下を招くリスクもあります。転職市場での価値が下がってしまえば、希望する条件での再就職が難しくなるでしょう。
そのため、退職を選択する際は、できるだけ失業期間を短くする工夫が必要です。事前に転職活動の準備を進め、スムーズに再就職できる体制を整えてください。
休職か退職かを決めるためのポイント
休職か退職かを決める際には、以下のチェックリストを参考にすることで、自分に最適な選択を見つけやすくなります。
これらの項目を冷静に検討し、自分に合った道を選びましょう。
職場復帰の可能性
まず、職場に復帰できる可能 性があるかどうかを考えてみましょう。
職場環境が改善され、問題が解決する見込みがあるならば、休職を選ぶことが適しているかもしれません。
しかし、改善の見込みが薄い場合や、再び同じストレスを感じる可能性が高い場合は、退職を検討する必要があります。
休職したら復職しにくくなる?と思われる方もいると思います。
実際には、会社の体制によりますが、復職後に不利になる可能性があるのは事実です。
復職しやすくするための対策として、
- 定期的に会社と連絡を取る(復職の意志を示す)
- リワークプログラム(職場復帰支援)を活用する
- 時短勤務などの選択肢を確認しておく
👉 会社側も復職した社員を活用したいと考えています。事前準備をしておけば、スムーズに戻ることが可能です。
休職期間中の生活の安定
次に、休職期間中に生活が安定するかどうかを考えましょう。
収入が減少するリスクがあるため、生活費の見通しを立てることが重要です。
また、家族やパートナーからのサポートが得られるかどうかも、休職を決める際に重要な要素となります。
退職後の新たな職場を見つけられるか
退職を決断する前に、次の職場を見つけられるかどうかを考えましょう。
転職市場の動向や自分のスキルに合った仕事があるかを確認することで、退職後の不安を軽減できます。
転職エージェントを利用して、転職活動をスムーズに進めることも有効です。
退職をスムーズに伝える3つの方法とは?
退職を決意した際、円滑に退職手続きを進めるための方法は以下の3つです。
- 事前に上司へ相談し準備する
- 退職理由を明確に伝える
- 退職の時期を早めに報告する
上記の方法を頭に入れておくと、退職の旨を伝えやすくなります。
では、それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。
なお、以下の記事では、適応障害の方向けに、退職に関する注意点などを詳しく解説しています。適応障害に該当する方は、ぜひ参考にしてみてください。

事前に上司へ相談し準備する
退職を決意したら、まずは上司に事前に相談し、準備を進めましょう。
突然の退職表明はトラブルを招く可能性があるため、できるだけ早めにメールやLINEではなく対面またはオンラインで上司に話し、退職の意向を伝えることが重要です。
また、退職の理由や時期についても、事前に整理しておくとスムーズに話が進みます。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部事前に相談しておくことは、もめ事を起こさないために重要な部分です。
しかし、ここで重要なことは「録音」など証拠の残る形をとる事です。
パワハラ上司などにあたってしまうと面倒になるため録音を取っておくと万が一の時に役立ちます。
※録音をとることは盗聴にならないので、訴えられるなどはないので問題ございません。
退職理由を明確に伝える
退職の際には、理由を明確に伝えることが重要です。
個人的な事情やキャリアの方向性を丁寧に説明することで、上司や同僚にも理解してもらいやすくなります。
可能であれば、退職の意向を伝える際に建設的に退職したい理由を伝えて、職場の改善に貢献することもできます。
トラブルに発展する可能性もあるためネガティブな理由は避けるようにしてください。
退職の時期を早めに報告する
退職の時期はできるだけ早めに報告しましょう。
会社側も後任の採用や引き継ぎの準備が必要なため、余裕を持って退職の時期を伝えることで、円満な退職が可能となります。
一般的には、退職の意向は少なくとも1ヶ月前に報告することが推奨されます。
「お世話になりました。」「感謝しています。」など、を伝えるようにして、円満退職を意識しましょう。
退職する際の3つの注意点とトラブル防止策
退職の意思を伝える際は、トラブルを避けるために以下の3つの点に注意が必要です。
- 退職日を事前に確定させる
- 退職時の書類手続きを確認する
- 会社への返却物を整理しておく
上記の注意点を踏まえておくと、退職時のトラブルを未然に防げます。
では、それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。
なお、以下の記事では退職後にやるべきことに関して詳しく解説しています。適切な退職の流れも分かるので、ぜひご覧ください。

退職日を事前に確定させる
退職日を事前に確定させることは、トラブルを防ぐために非常に重要です。退職日が不明確だと、会社側も準備が進まず、後任者の引き継ぎが滞る可能性があります。
退職日が決まったら、書面で確認を行い、トラブルを未然に防ぎましょう。
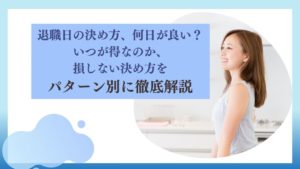
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部退職の意思が固い場合は、退職届の提出を行ってください。
退職時の書類手続きを確認する
退職時には、さまざまな書類手続きが必要になります。
退職届や離職票、社会保険や年金の手続きなど、必要な手続きを事前に確認しておくことで、スムーズに退職を進めることができます。
これらの手続きが遅れると、後でトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。
会社への返却物を整理しておく
退職時には、会社から借りていた物品や資料を整理して返却することも忘れずに行いましょう。
パソコンや社用携帯、名刺など返却が必要な物をリストアップし、早めに整理することで、退職後のトラブルを防ぐことができます。
休職や退職に関するよくある質問
休職や退職に関しては、多くの方が疑問や不安を抱えるものです。ここでは、以下のよくある質問を取り上げます。
- 休職中に転職活動をしても問題ありませんか?
- 休職中でも給与は支給されますか?
- 退職後の失業保険はいつから受け取ることができますか?
- 退職時に退職金は必ず受け取ることができますか?
- 休職を経ずにすぐに退職した方が良い場合もありますか?
それぞれの質問と回答を詳しくみていきましょう。
休職中に転職活動をしても問題ありませんか?
休職中に転職活動を行うことは可能ですが、会社の就業規則や労働契約に違反しないよう注意が必要です。
また、休職理由が病気や怪我である場合は、体調が回復してから転職活動を始めることが望ましいです。
休職中でも給与は支給されますか?
休職中の給与支給は、会社の規定や休職理由によって異なります。
一般的に、病気休暇や育児休暇の場合は一定期間給与が支給されることがありますが、その後は無給となることが多いです。
また、労災保険が適用される場合、一定の補償を受けられる場合もあります。
退職後の失業保険はいつから受け取ることができますか?
退職後の失業保険は、退職理由や前職での勤務期間により受給開始時期が異なります。
一般的には、退職後7日間の待機期間を経て、失業保険の受給が開始されます。
失業保険の受け取りができるタイミングは退職の理由によって異なるため注意が必要です。
✅ 自己都合退職の場合
- 2か月の待機期間の後に支給開始
- 受給期間:90日~150日(年齢・勤務年数による)
✅ 会社都合退職の場合
- 7日後から支給開始
- 受給期間:90日~330日(条件により異なる)
👉 「自己都合退職」でも、ハラスメントなどの理由があれば「会社都合退職」と認められる場合があります。ハローワークに相談しましょう。
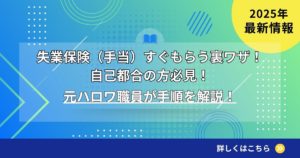
退職時に退職金は必ず受け取ることができますか?
退職金が支給されるかどうかは、会社の退職金規定や就業規則によります。
退職金制度がある会社では、一定の条件を満たせば退職金を受け取ることができますが、制度がない場合は退職金が支給されないこともあります。
休職を経ずにすぐに退職した方が良いもありますか?
休職を経ずにすぐに退職した方が良い場合もあります。
例えば、職場環境が非常に悪化していて改善の見込みがない場合や、深刻なハラスメントを受けている場合は、早急に退職を検討するのが適切です。
また、自分の健康状態が悪化している場合や、他に緊急の理由がある場合も、すぐに退職を選ぶ必要があります。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部休職をすると会社からの印象は悪くなるため、攻撃的な言葉や態度をあからさまに出してくる上司もいるでしょう。
そうならないためにも、休職せずに退職をする選択がよいでしょう。
職を決めた場合、退職届と退職願の違いは?
- 退職願 → 撤回可能(会社に承認される前なら取り消せる)
- 退職届 → 撤回不可(一度提出すると基本的に辞めるしかない)
✅ 退職する際は、まず退職願を提出し、退職日が確定したら退職届を出すのが一般的です。
退職後の給付金について相談するなら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
体調不良や精神的な悩みを抱えて、仕事の継続が難しくなっているケースは少なくありません。しかし、休職と退職のどちらを選ぶべきか、なかなか決断できずに悩んでいる方も多いのが実情です。
休職と退職の選択に迷った時は、それぞれのメリットとデメリットを整理し、自分のキャリアプランに照らし合わせて判断することが大切です。
また、短期的な視点だけでなく、長期的な人生設計も視野に入れながら、慎重に検討を重ねる必要があるでしょう。
休職をお考えの方は、ぜひ本記事を参考に、退職をうながされたときの対処法としてお役立てください。