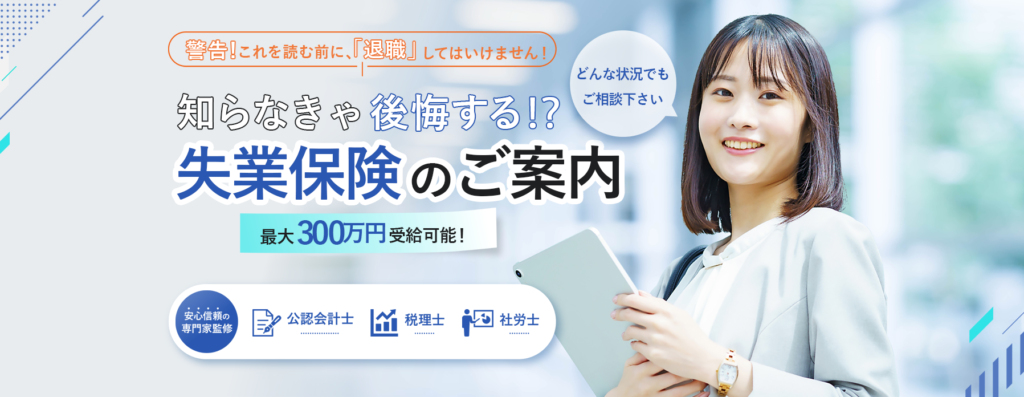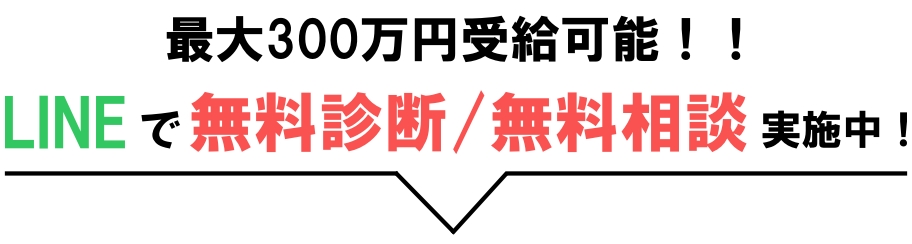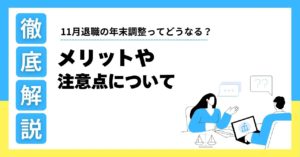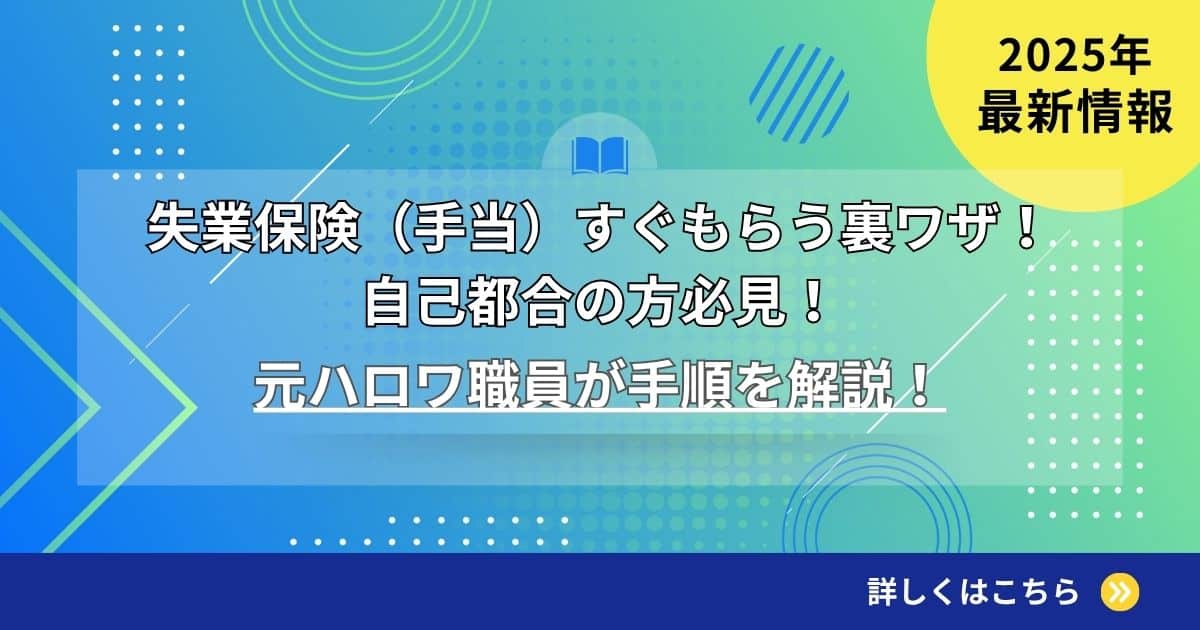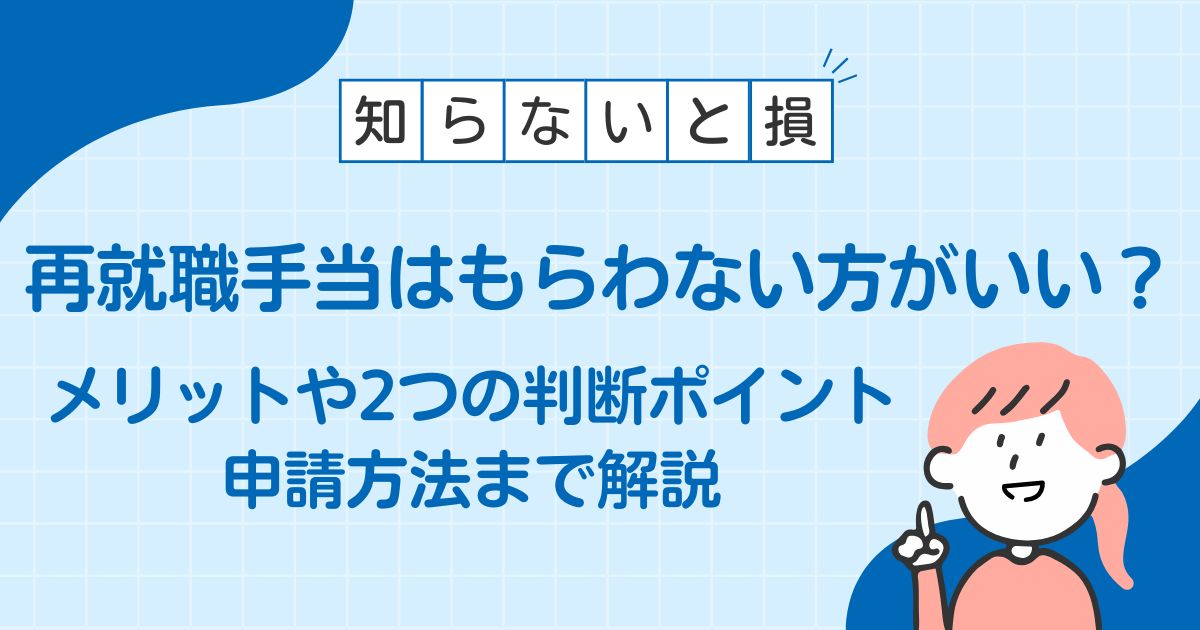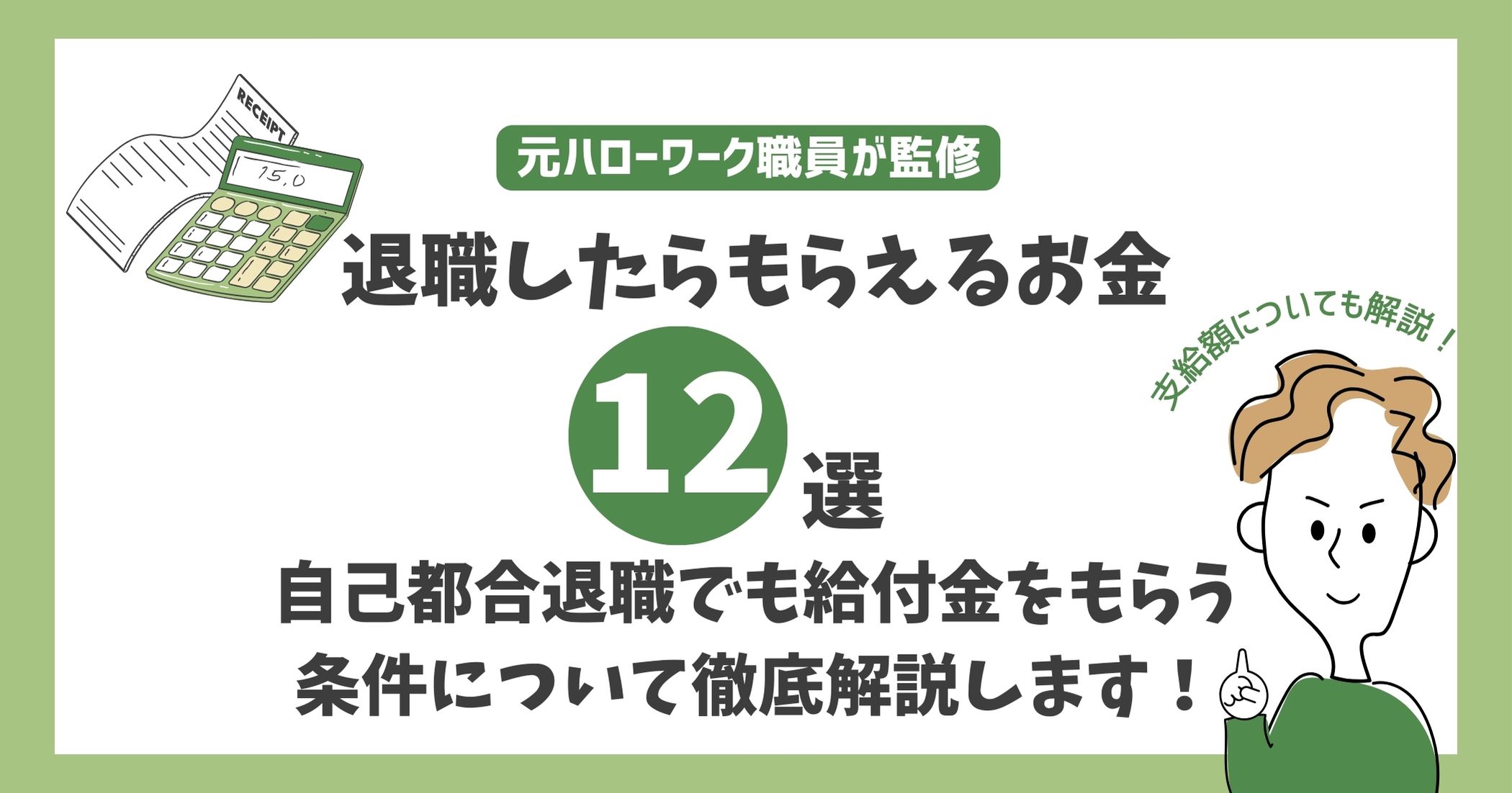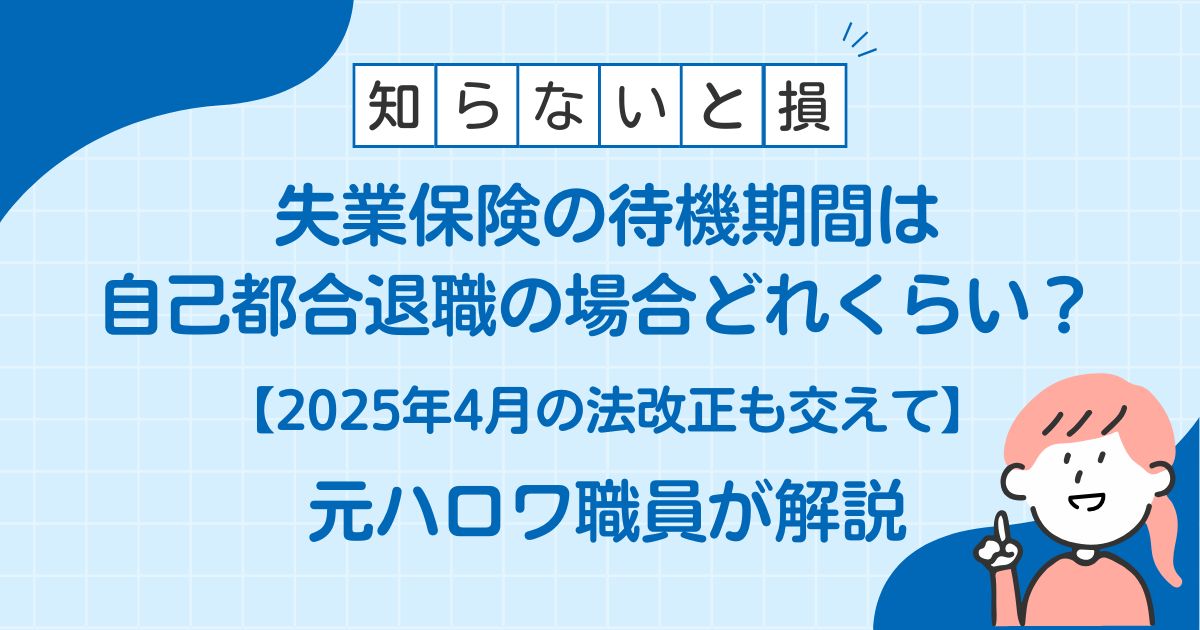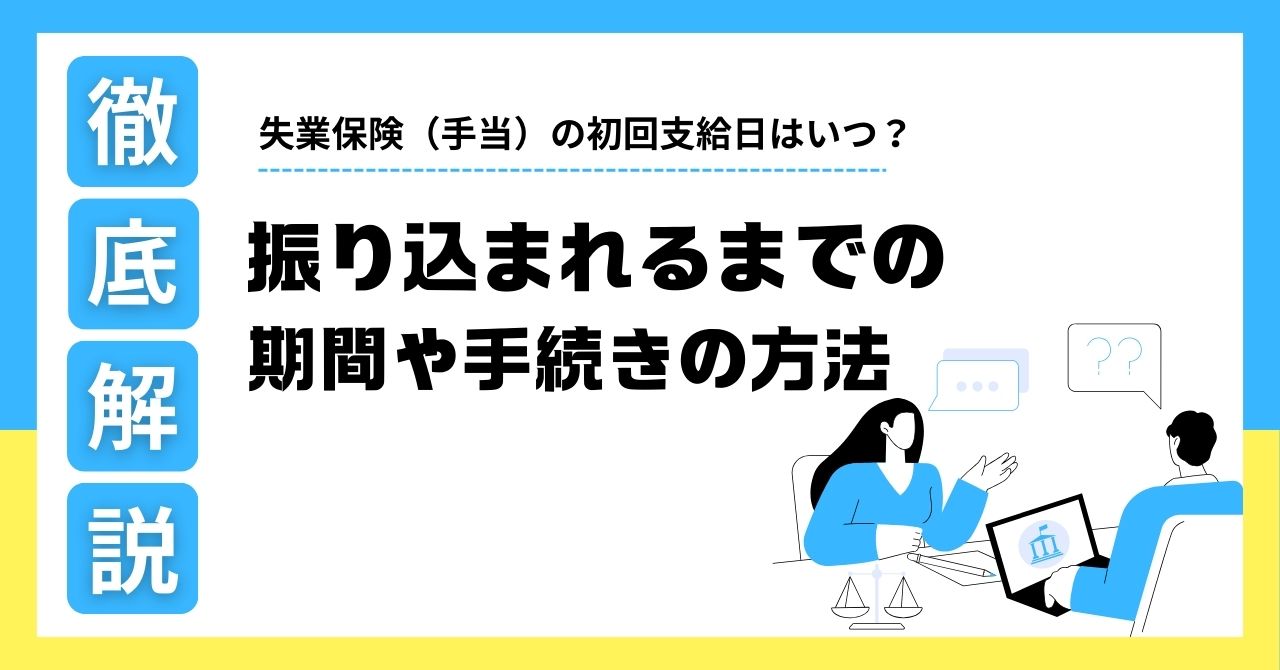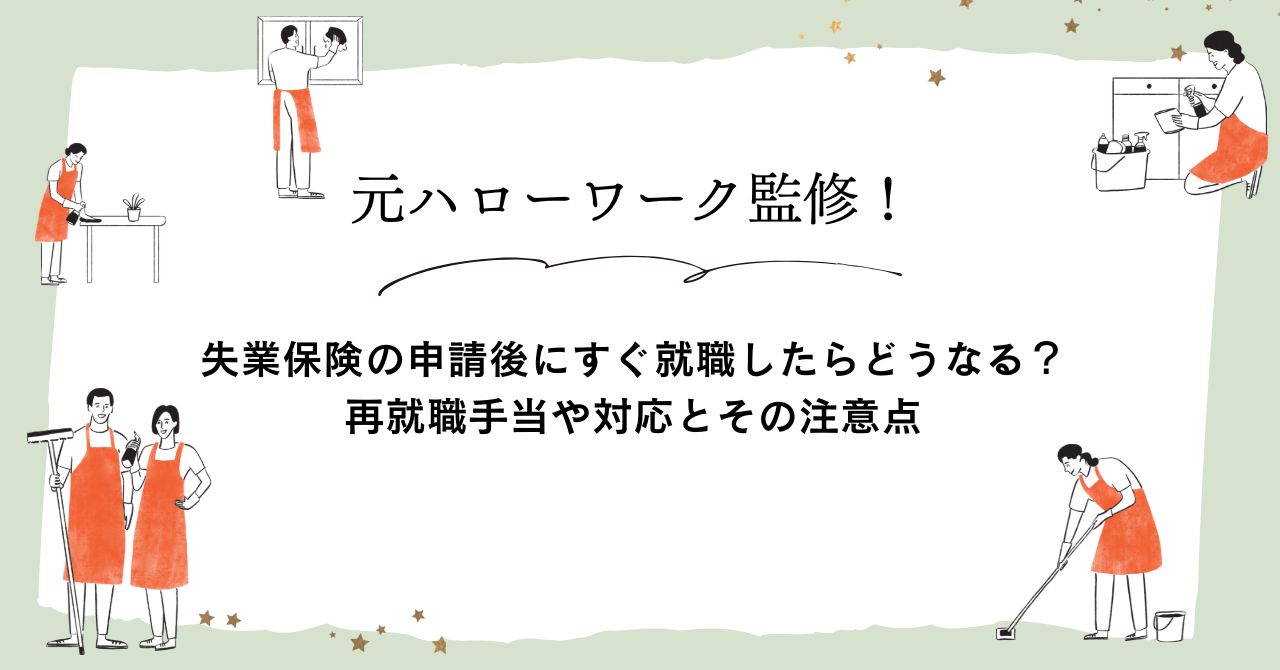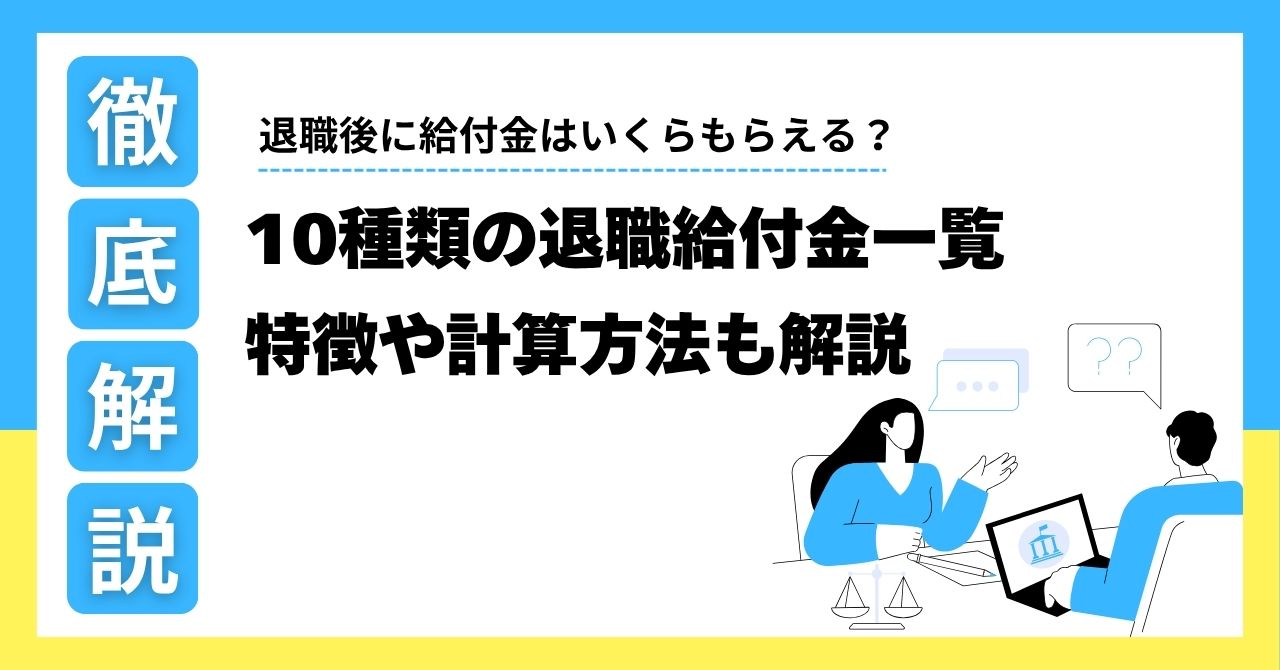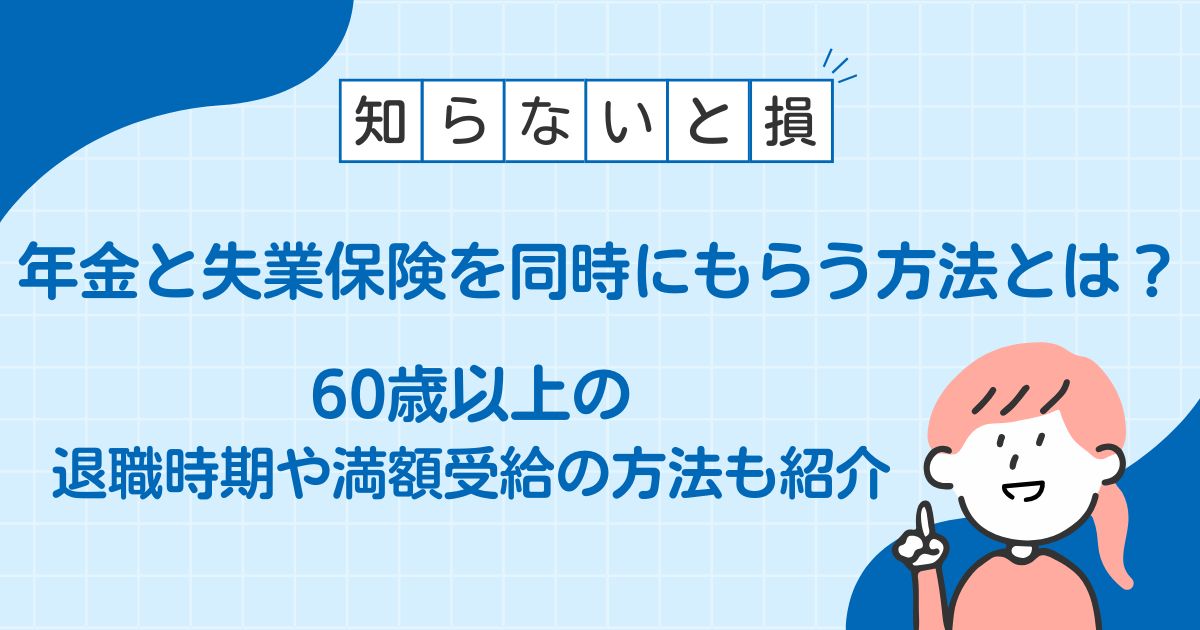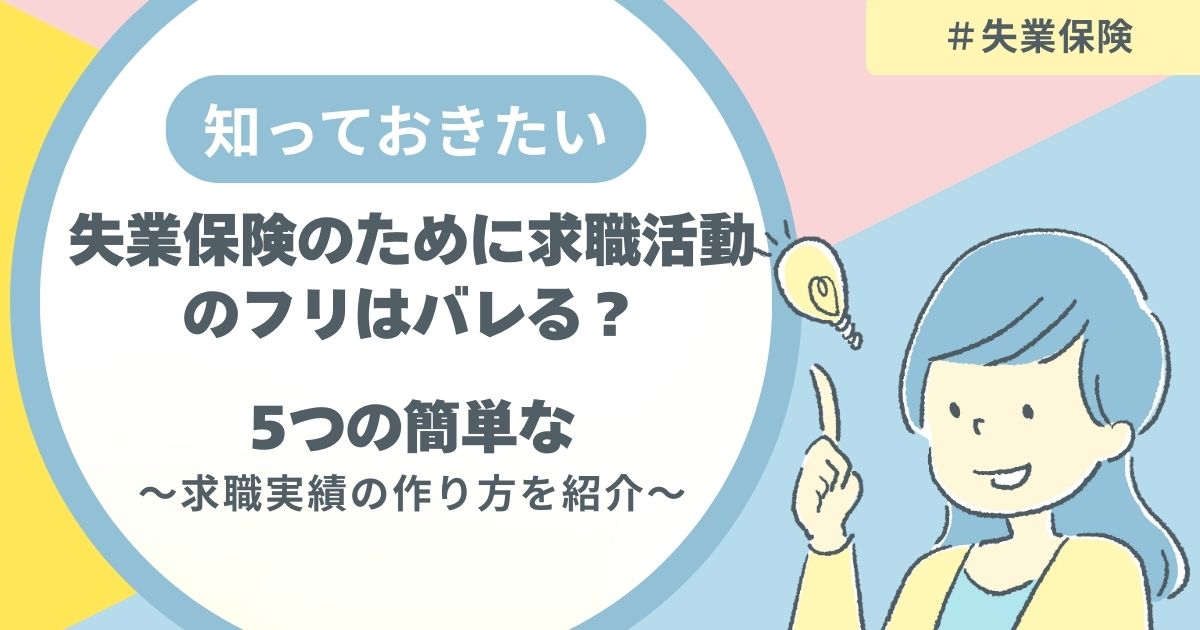退職に関して以下のお悩みはありませんか?
「10月に退職するメリットとデメリットは?」
「10月に会社を辞める場合、何を気をつけるべき?」
退職は人生の大きな節目であり、タイミングによって得られるものや注意すべき点が異なります。
本記事では、10月に退職をするメリット・デメリットや退職時期の決め方、円満退職のための注意点などを詳しく解説します。10月に退職をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、退職に関するご相談を受け付けています。
退職に関する些細なお悩みでも丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

10月に退職する2つのデメリット
ここでは、10月に退職する2つのデメリットを解説します。
- 冬のボーナスを受け取れない
- 年末調整を受けられない
上記のデメリットを事前に把握し、しっかり対策を検討していきましょう。
冬のボーナスを受け取れない
多くの企業では冬のボーナスを12月に支給するため、10月に退職すると、一般的に冬のボーナス支給前に会社を去ることになります。ボーナス支給に関して、支給日に会社に在籍しているのを条件とする企業は少なくありません。
10月は上半期の区切りであり、夏のボーナス支給後であるため、9月末で退職する方が比較的多い傾向です。もし冬のボーナスを確実に受け取りたい場合は、退職時期の再検討が必要になるかもしれません。
年末調整を受けられない
10月に退職し、その年の内に再就職しない場合、会社での年末調整を受けられません。
年末調整は、毎月の給与から天引きされた所得税の過不足を精算する重要な手続きです。会社で年末調整を受けられない場合は、翌年の2月中旬から3月中旬頃に自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、払いすぎた税金が戻ってくる可能性もあるため、忘れずに行いましょう。
ただし、年内に新しい会社に転職し、12月末時点で在籍していれば、転職先の会社で年末調整を受けられます。
10月に退職する2つのメリット
ここでは、10月に退職する2つのメリットを解説します。
- 夏のボーナスを受け取ってから退職できる
- 有効求人倍率が高くなる時期に転職活動を進められる
上記のメリットを自身の状況と照らし合わせて、退職のタイミングを検討しましょう。
夏のボーナスを受け取ってから退職できる
多くの企業では夏のボーナスを6月から7月頃に支給します。そのため、10月に退職する場合、夏のボーナスを受け取った後に退職が可能です。
ボーナスはまとまった金額になる場合が多く、退職後の生活費や転職活動中の資金として活用できるでしょう。
ただし、ボーナスの支給時期や条件は企業によって異なります。支給日より前に退職すると夏のボーナスも受け取れない可能性があるため、事前に自社の就業規則や賃金規程を確認しておくのが大切です。
有効求人倍率が高くなる時期に転職活動を進められる
一般的に、10月頃は有効求人倍率が高まる傾向です。実際に2024年10月の有効求人倍率は1.27倍と同年4月から9月までの水準よりも高くなっています。有効求人倍率が高いと、求職者1人あたり複数の求人があり、就職しやすい状況です。
10月に退職する場合、求人が比較的多い時期に転職活動を進められるため、より多くの選択肢の中から自分に合った仕事を見つけやすいでしょう。
参考:一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について
退職日を決める際に重要な5つのポイント
退職日をいつにするかは、その後の生活やキャリアに大きく影響するため慎重な判断が必要です。
退職日決定の際に考慮すべき5つの重要なポイントは以下の通りです。
- 社会保険料(健康保険、厚生年金)を考えて決める
- 現職の引継ぎの時間を考慮する
- 賞与(ボーナス)・退職金をもらってから辞める
- 次の職場の入社日を考えて決める
- 退職後に活用できる退職金を考慮する
特に社会保険料や賞与、退職金などの金銭面は、退職日によって受け取れる金額が変わる可能性があるため、慎重な検討が求められます。
退職日の決め方に関してより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
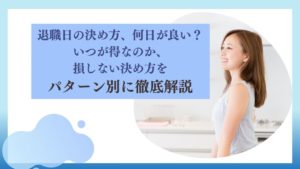
退職の意思を職場に伝える際の3つの注意点
退職の意思を職場に伝える際には、円満な退職とスムーズな手続きのために、以下3点に注意しましょう。
- 退職の1ヵ月前には意思を伝える
- 原則として会社の就業規則に従う
- できるだけ繁忙期を避ける
上記の点に配慮すると、上司や同僚との良好な関係を保ちながら退職準備を進められるため、ぜひ参考にしてみてください。
退職の1ヵ月前には意思を伝える
退職の意思は、遅くとも退職希望日の1ヵ月前までには直属の上司に伝えるのが望ましいです。
法律上は、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し入れから2週間で退職できるとされています(民法第627条第1項)。
しかし、業務の引き継ぎや後任者の選定には時間が必要です。多くの会社の就業規則では、退職の申し出時期を「1ヵ月前まで」などと定めています。
円満に退職するためには、就業規則に従い、余裕をもって意思を伝えましょう。
参考:民法
原則として会社の就業規則に従う
退職日を決める際や退職の意思を伝える時期は、原則として自社の就業規則に従いましょう。就業規則には、退職に関する手続きや申し出の期限などが具体的に記載されています。就業規則に従えば、会社側も退職手続きをスムーズに進めやすくなります。
また、会社の状況によっては退職を引き止められる可能性も考えられるので、就業規則に従って退職の旨を伝えれば、「非常識」「急な申し出」と受け取られるリスクを避けられるでしょう。
できるだけ繁忙期を避ける
就業規則を守って退職の意思を伝えても、できる限り会社の繁忙期を避けて退職日を設定するのが望ましいです。
繁忙期に退職すると、上司や同僚に負担をかけてしまったり、引き継ぎ業務も十分に行えないまま退職日を迎えることにもなりかねません。
業種や企業によって繁忙期は異なりますが、自社の業務サイクルを考慮し、比較的落ち着いている時期に退職日を設定すると、円満な退職につながります。
10月に円満退職するための流れ【6STEP】
ここでは、10月に円満退職を実現するための具体的な流れを6つのステップで解説します。
- 退職目的に応じて計画を立てる
- 転職先を決定する
- 退職の旨を上司に相談する
- 退職届を提出する
- 引き継ぎを行う
- 退職手続きを行う
上記のステップを一つひとつ丁寧に進めれば、スムーズな退職につなげられるので、ぜひ参考にしてみてください。
1.退職目的に応じて計画を立てる
まず、退職の目的に応じて具体的な退職計画を立てましょう。キャリアアップのための転職か、家庭の事情での退職かなど、目的によって退職する時期や退職後のプランが明確にできます。
また、退職後の収入源や必要な生活費、社会保険の手続きなどを事前に洗い出し計画を立てると、生活費の見直しや貯蓄なども計画的に進められます。
2.転職先を決定する
退職計画を立てたら、転職先を決定します。在職中に転職活動を行い、次の職場が決まってから退職の意思を伝えるのが、収入面や精神的な安定を考えると理想的です。
転職先を選ぶ際は、自身の経験やスキルを活かせるか、企業の将来性、労働条件などを総合的に判断しましょう。
もし現在の職場でのミスマッチや人間関係、労働条件などが退職理由に含まれる場合は、同じ過ちを繰り返さないよう十分に考慮して転職先を検討するのが大切です。
3.退職の旨を上司に相談する
転職先が決定し退職希望日が固まったら、直属の上司に退職の意思を伝えます。原則、会社の就業規則に従い、退職希望日の1ヵ月以上前に相談するのが一般的です。
退職理由を聞かれるケースも多いため、退職理由を明確にし、強い意思を持って伝えるのが大切です。
曖昧な伝え方をすると引き止めにあう可能性もあるため、感謝の気持ちとともに、退職の意思が固い旨をはっきりと伝えましょう。
4.退職届を提出する
上司に退職の意思を伝え、退職日や最終出社日が正式に確定したら、会社に退職届を提出します。提出タイミングは、原則として就業規則の規定に従いましょう。
退職届は、会社に退職の意思を正式に表明する重要な書類なので、直属の上司に手渡しで提出するのがマナーです。
5.引き継ぎを行う
退職日までに、後任者や関係部署へ担当業務の引き継ぎを行いましょう。引き継ぎのスケジュールを作成し、必要な資料やマニュアルを準備するなど、計画的に進めるのが重要です。
また、自身の残務整理もきちんと行い、退職後に迷惑がかからないようにするのが大切です。
加えて、有給休暇が残っている場合は、業務の進捗や引き継ぎ状況とのバランスを見ながら、計画的に消化するようにしましょう。
6.退職手続きを行う
最終出社日には、会社から貸与されていた健康保険証や社員証、制服などを返却します。また、会社からは離職票や雇用保険被保険者証、源泉徴収票など、退職後の手続きに必要な書類を受け取ります。
上記の書類は、失業保険の申請や確定申告などで必要なため、必ず受け取り大切に保管しましょう。
なお、お世話になった上司や同僚、取引先などへ挨拶しておくと、良好な関係を維持したまま退職できます。
退職時は失業保険や傷病手当などのお金を受け取れる場合がある
退職時には、失業保険(基本手当)や傷病手当金、就職促進給付、求職者支援制度などの給付金を受け取れる可能性があります。
上記の制度は、転職先が決まらないまま退職した場合や、病気や怪我ですぐに働けない場合など、生活費の不安を和らげるのに役立ちます。
ただし、いずれの給付金も受給するには一定の条件を満たす必要があり、自動的に受け取れるわけではありません。
そのため、自身がどの制度の対象になるのか、どのような手続きが必要なのかを事前に確認し、適切に申請するのが大切です。
なお、退職後にもらえるお金に関して詳しく知りたい方は、以下の記事で自己都合退職でも給付金をもらう条件などを解説しているので、参考にしてください。
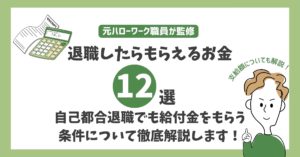
10月に損せずに退職したいなら「転職×退職サポート窓口」に相談しよう
10月に退職する場合、冬のボーナスを受け取れない、年末調整ができず、年内に転職しなかった場合は自身で確定申告を行う必要があるなどのデメリットがあります。
一方、10月の退職は夏のボーナスを受け取ってから退職できることや、有効求人倍率が高くなるタイミングで転職活動を進められるなどのメリットもあります。
退職時期を決定する際には、ご自身の退職目的や、ボーナス・退職金などの金銭的な状況を総合的に考慮し、計画的に進めるのが大切です。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、退職に関するご相談を受け付けています。
退職に関する些細なお悩みでも丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。