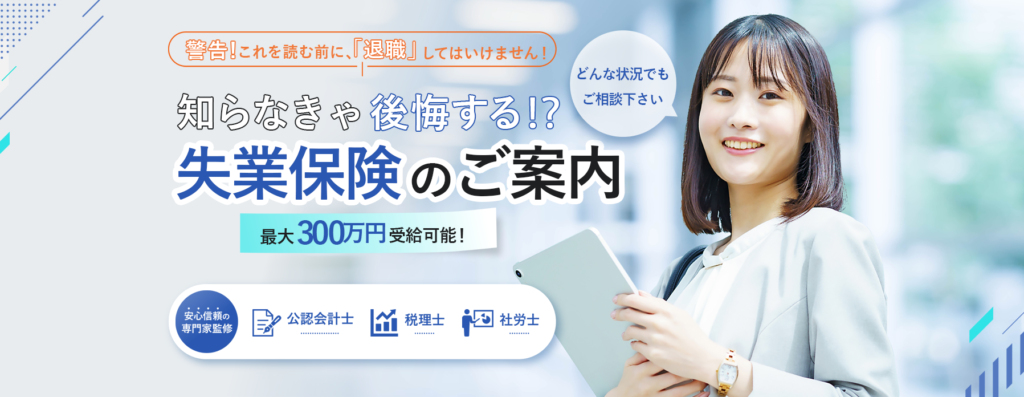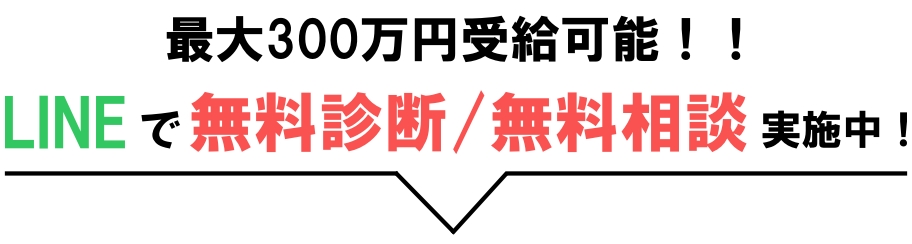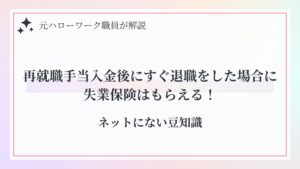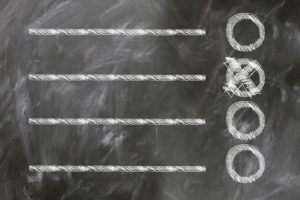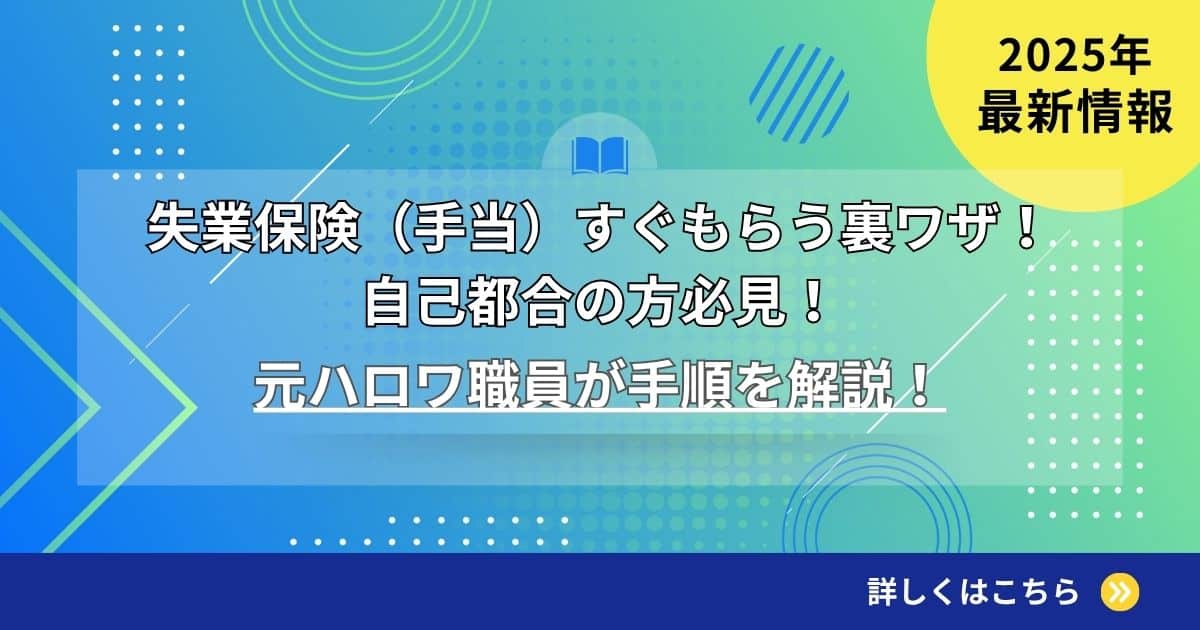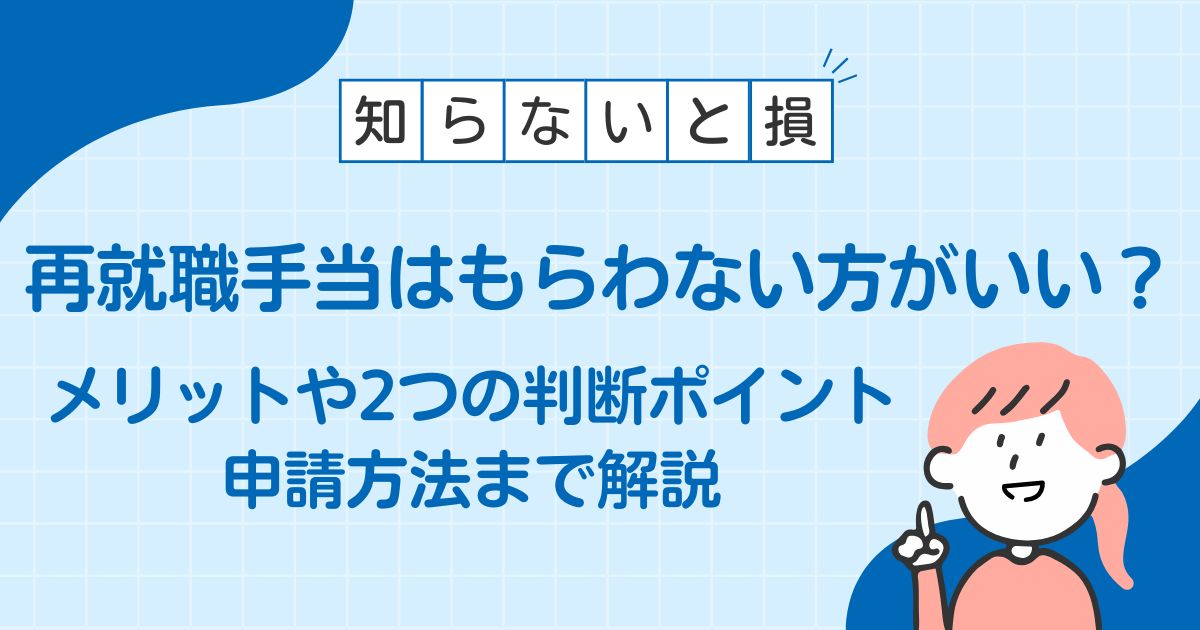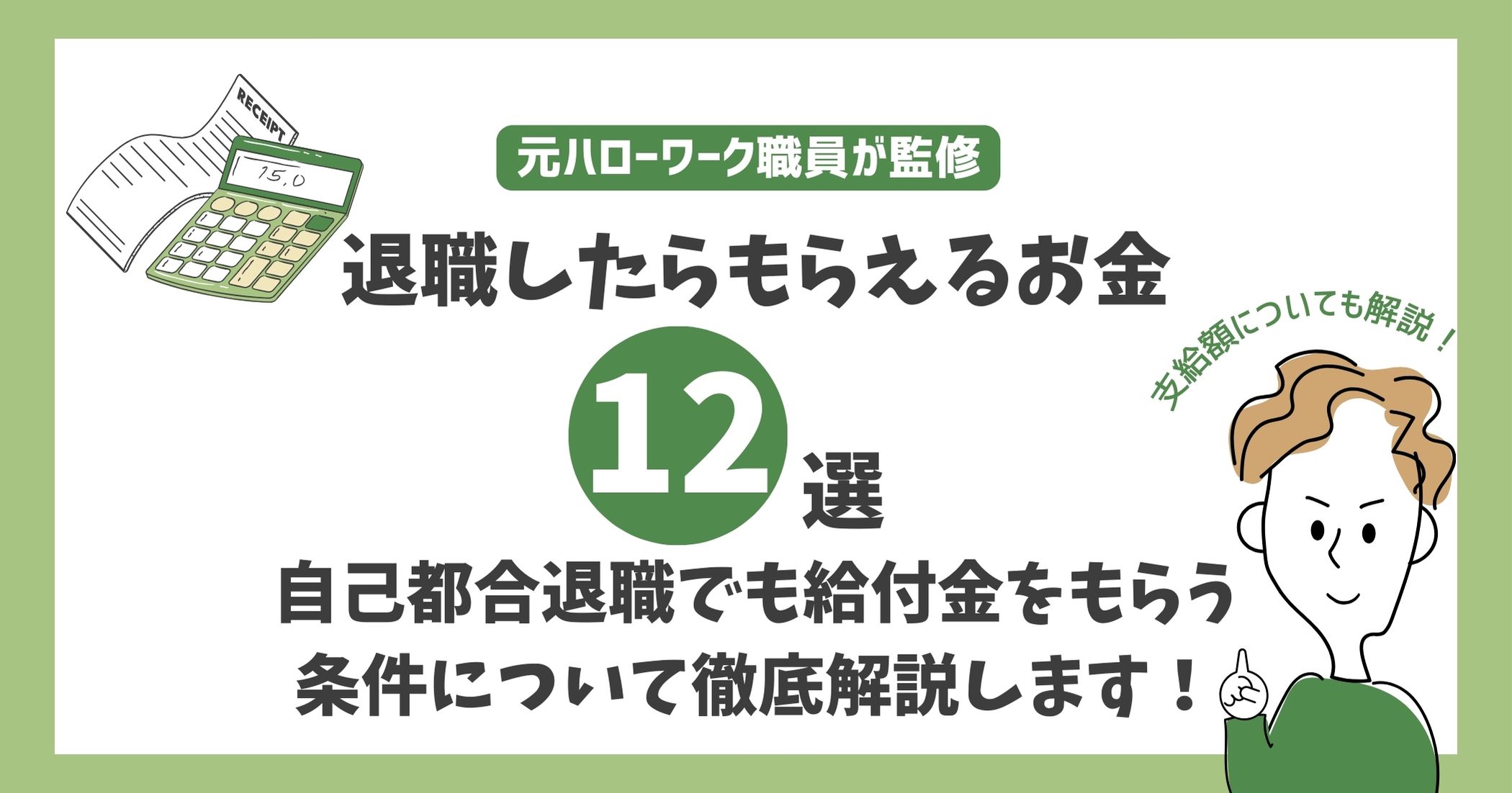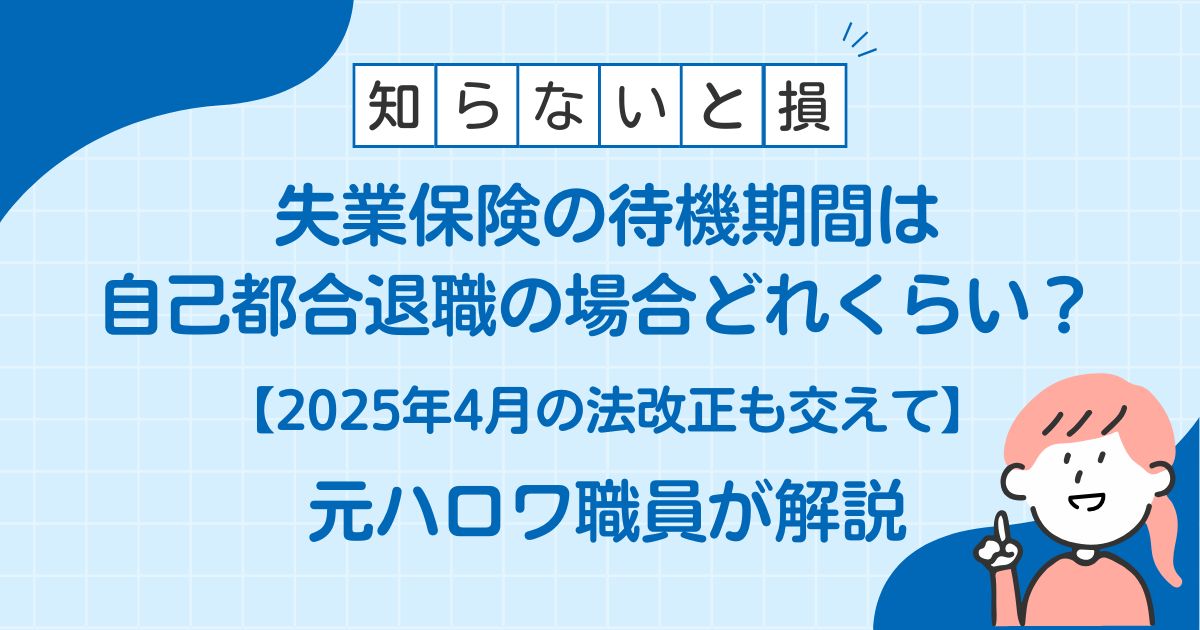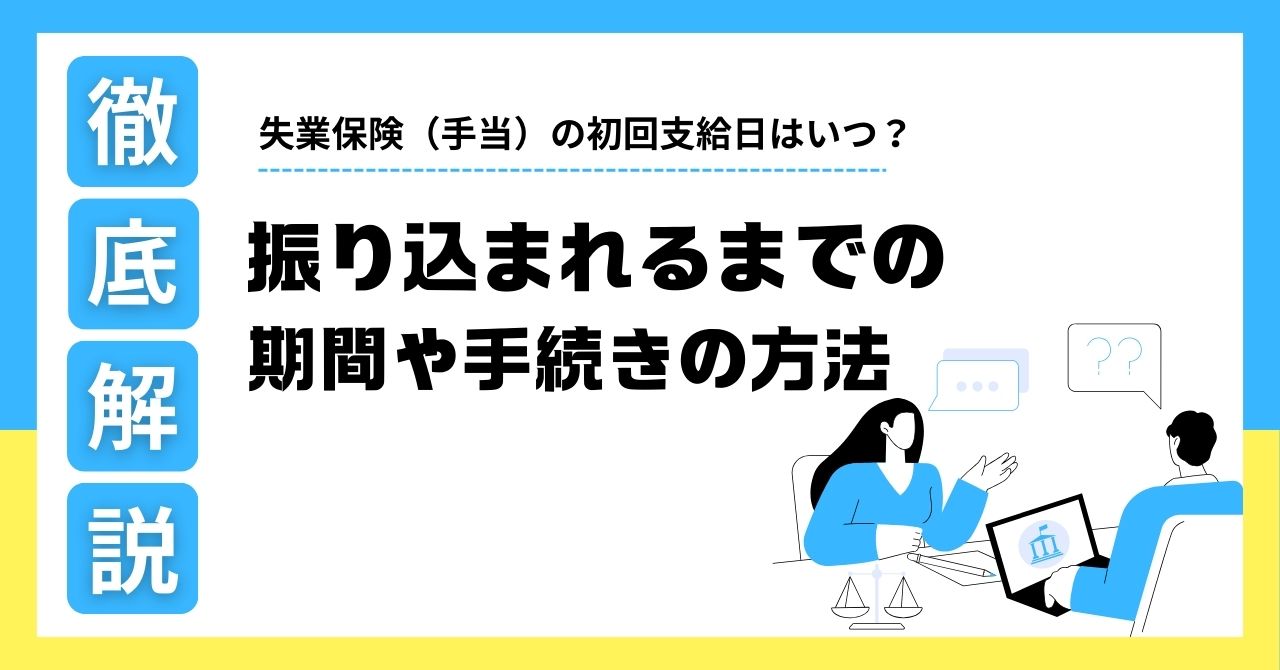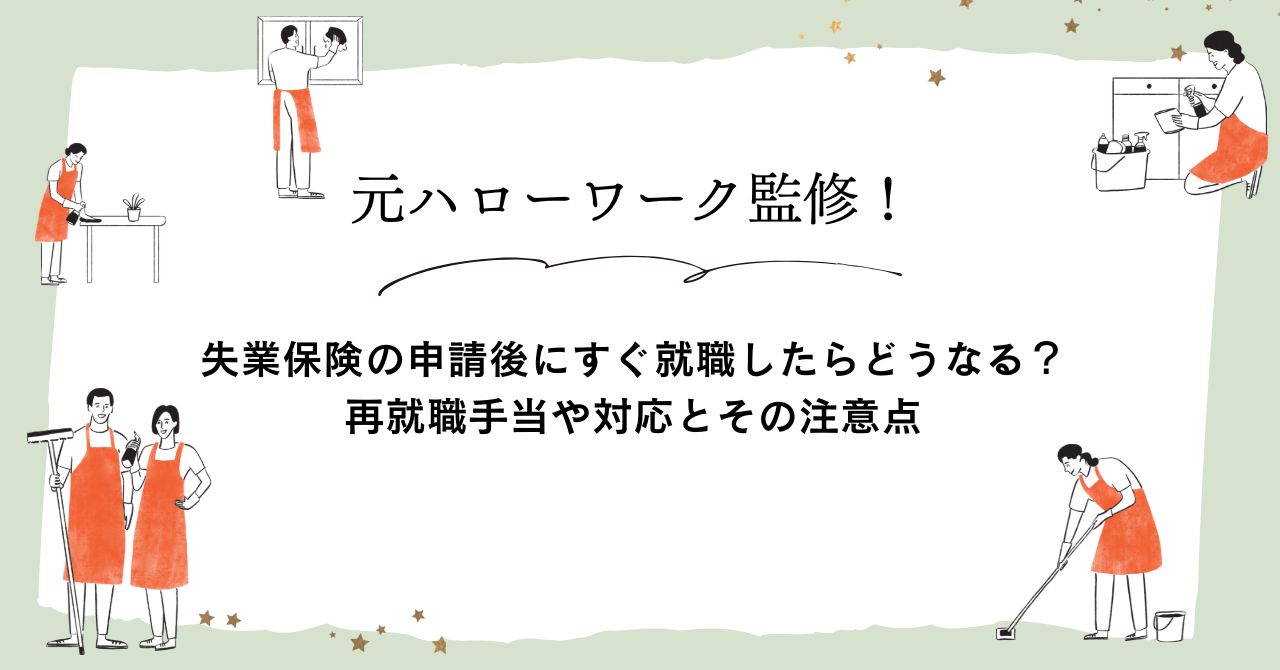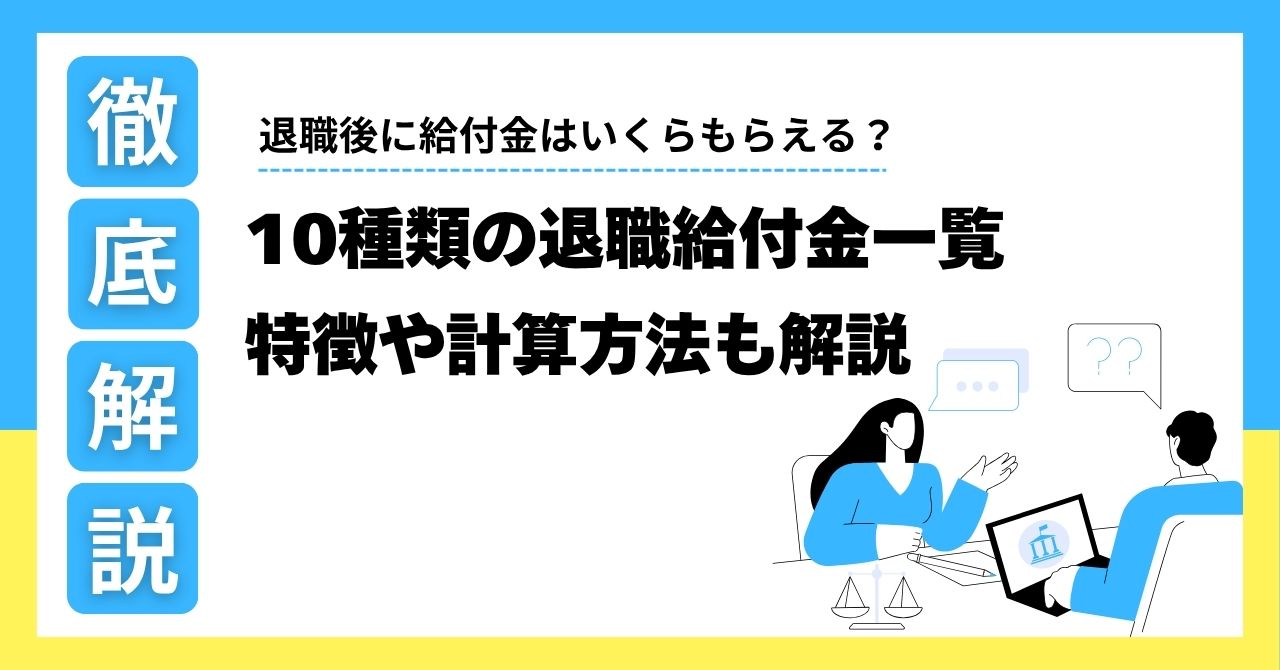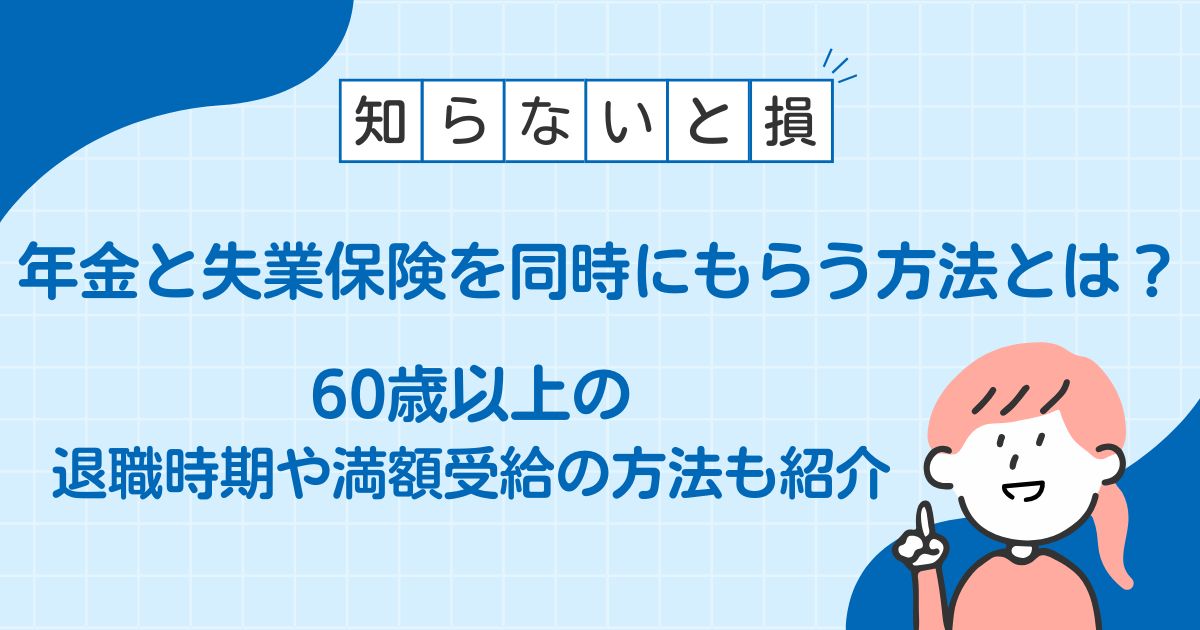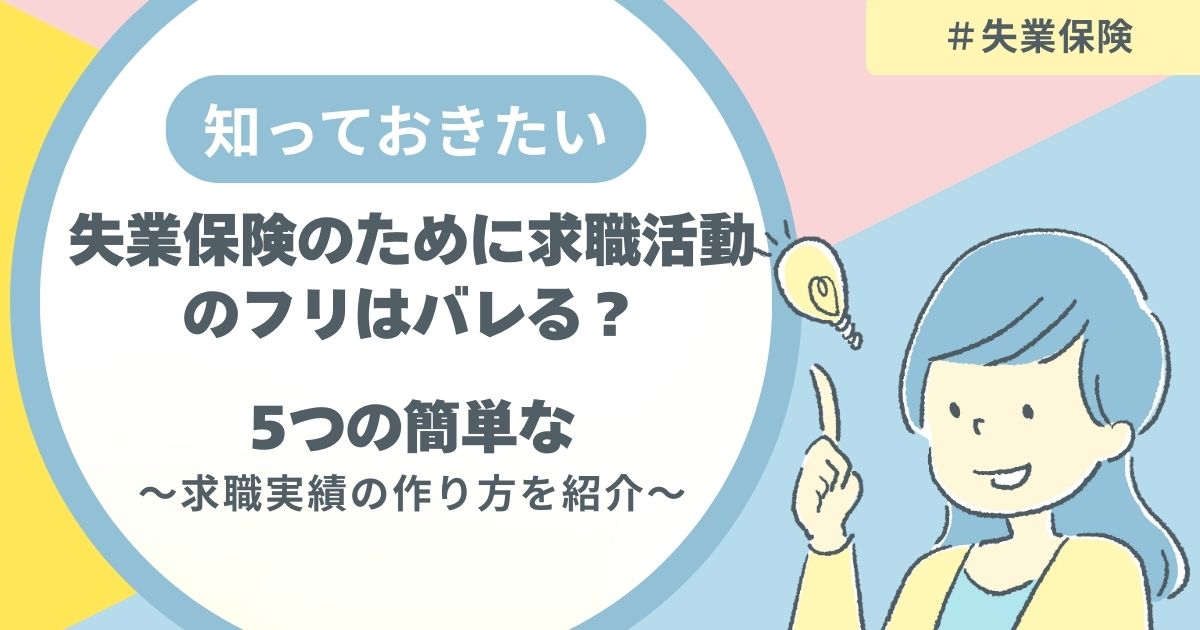元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員の私が監修を行います!
病気が原因で仕事を辞めざるを得ない状況に直面することは、誰にでも起こり得ることです。
このような場合、失業保険が生活の助けになることがありますが、その受給には特定の条件と手続きが必要です。
病気で退職した場合の給付日数、給付期間が気になる。
失業保険はいつからもらえるのか?
病気退職での待機期間は?
傷病手当金の申請の方がいい?
退職後の生活が不安で悩んでいる。
結論から申し上げると、病気で退職をしても要件を満たせば、失業保険の申請が可能です!
待機期間は通常通り7日間ありますが、給付制限(1ヶ月手当が支給されない期間)を無くせる可能性があります。
給付期間(給付日数)は通常の失業保険と同じ日数です。
本記事では、病気で退職した場合に失業保険を受け取るための条件や手続きの流れ、給付制限(1ヶ月手当が支給されない期間)を無くすために必要な事や注意点について詳しく解説します。
困難な状況において正しい情報を得ることで、次のステップへの準備が行いやすくなります!
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部退職後の不安を無くすためにもこの記事を参考にしてください!

特定理由離職者は失業保険の受け取る際に診断書はいらない?
特定理由離職者が失業保険を受け取る際、診断書が必要かどうかは、ハローワークが判断を行います。病気や怪我などにより離職した場合は、医師の診断書が証明として必要になるケースが多いです。
病気や怪我などにより離職した場合、診断書をハローワークに持参する必要があるため、医師の診断書は場合によって必要になります。
特定理由離職者の条件を満たしているかどうか、不安な方は、事前にハローワークに相談してみるのがおすすめです。必要な書類や手続きに関して、アドバイスをもらえるでしょう。
特定理由離職者とは?
特定理由離職者とは、やむを得ない事情で退職した人です。雇用契約の更新がなされなかった場合や、病気、怪我など、正当な理由で離職した方が該当します。一方、解雇や企業の倒産による離職は、特定受給資格者に該当します。
特定理由離職者になるためには、離職理由を証明する書類の提出が必要です。病気や怪我の場合は診断書、雇い止めの場合は雇用契約書などが求められます。
特定理由離職者になるための具体的な方法や、必要な証明書類に関しては以下の記事を参考にしてください。

特定理由離職者と判断される5つの基準
特定理由離職者と判断される主な基準は、以下の5つです。
- 雇い止めでの離職
- 健康上の理由での離職
- 妊娠・出産・育児を理由とした離職
- 通勤が困難あるいは不可能な場合の離職
- 家族の介護や看護を理由とした離職
上記に当てはまるかどうかを把握しておくと、失業給付の申請時にスムーズに手続きが進められます。では、それぞれの内容を詳しく解説していきます。
雇い止めでの離職
雇用期間が定められている際、労働契約の更新や延長がされずに離職が必要になる場合は、特定理由離職者と判断される可能性があります。
ただし、特定理由離職者と判断されるためには、「期間の定め」や「更新や延長の可能性」が明示された労働契約で、雇用契約期間の満了が条件です。
また、雇用契約期間の満了日以前に、本人から更新または延長の希望を申し出ている必要があります。
雇い止めの場合、労働契約所や雇入通知書などの書類を証拠として提出します。雇用契約の内容を確認し、必要な書類を揃えておきましょう。
健康上の理由での離職
健康上の理由、病気や心身の障害など、従業員本人の健康状態が理由で離職した場合、特定理由離職者に該当します。健康状態に配慮し、別業務を割り振られたものの、業務遂行が難しく離職した場合も同様です。
健康上の理由により離職した場合、ハローワークに医師の診断書をはじめ指定された書類の提出が必要になる場合があります。
診断書の取得には時間とコストがかかるため、早めに準備を始めるのがおすすめです。
妊娠・出産・育児を理由とした離職
妊娠・出産・育児などで離職した場合、雇用保険受給期間の延長が適用される場合があります。離職日翌日から30日以上働けない場合、受給期間延長措置の対象になります。
受給期間延長措置を受けたうえで、特定理由離職者として申請する場合、受給期間延長通知書の提出が必要です。
そのため、ハローワークに、妊娠・出産・育児が離職理由であることを証明する必要があります。母子手帳の写しなど、妊娠・出産・育児の状況を示す書類を用意しておきましょう。
通勤が困難あるいは不可能な場合の離職
生活環境の変化で、通勤が不可能または困難になって離職した場合も、特定理由離職者に該当します。通勤不可能または困難の理由として、結婚による住所変更や子どもの保育所や保育施設が遠方になったなどが挙げられます。
失業保険の受給申請時は、住民票の写しや転勤辞令など、離職理由に応じた書類の提出が必要です。
家族の介護や看護を理由とした離職
父母の死亡や親族の病気、怪我など家庭の事情で離職した場合、特定理由離職者に該当します。退職を申し出た時点で、介護や看護が30日を超える日数になると見込まれることが条件です。
また、家族の介護や看護による離職で特定理由離職者と判断されるためには、扶養控除等申告書や健康保険証、介護・看護を必要とする家族の診断書などの提出が必要です。
なお、ハローワークへ相談すると、必要な手続きや注意点に関してアドバイスをもらえるでしょう。
失業保険における特定理由離職者の3つのメリット
特定理由離職者として失業保険を受給するメリットは、以下の3つです。
- 受給資格が緩和される
- 給付制限期間がなく失業手当の支給が早くなる
- 所定給付日数が長くなる場合がある
上記のメリットを理解しておくことで、離職後の生活設計にも余裕が生まれます。
受給資格が緩和される
特定理由離職者として受給する場合、離職日以前の1年間で被保険者期間6ヵ月以上であることが条件です。一方、一般受給資格者が失業保険を受給する場合、離職日以前の2年間で雇用保険の被保険者期間が12ヵ月以上必要です。
特定理由離職者は仕事を継続する意思があったものの、やむを得ない事情で退職を余儀なくされた事情を汲んでいます。
ただし、雇用保険の加入期間が短いと、受給できる失業手当の日数も少なくなります。離職前の就労状況を確認し、受給額と期間を把握しておきましょう。
給付制限期間がなく失業手当の支給が早くなる
特定理由離職者として失業保険を受ける場合は、給付制限期間がなく、7日間の待機期間後に失業手当を受け取れます。給付制限期間とは、7日間の待機期間後から支給認定が開始されるまでの期間で、通常は1ヵ月です。
給付制限がある一般受給資格者よりも、早い段階で手当を受け取れます。
ただし、特定理由離職者でも、正当な理由なく再就職を拒否した場合などは、給付制限を受ける可能性があります。失業保険を受給しながら、積極的に再就職活動を行いましょう。
参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
所定給付日数が長くなる場合がある
失業保険の受給期間を所定給付日数と呼び、年齢や雇用保険の被保険者期間によって規定が異なります。
雇止めで離職した場合、所定給付日数が長くなる場合があります。また、更新・延長されなかった場合の所定給付日数は最大330日と、一般受給資格者と比較すると長期間にわたり受給可能です。
ただし、所定給付日数が長いからと言って、安易に失業状態を続けるのは避けましょう。再就職が遅れるほど、雇用のチャンスを逃す恐れがあります。
失業保険における特定理由離職者のデメリット
特定理由求職者として手当を受給する際、書類集めや手続きに時間と労力がかかるのがデメリットです。書類に不備があると受理されないため、必要書類を揃えなければいけません。
また、不正受給を実施した場合は厳しく罰せられるため、注意が必要です。虚偽の申告や必要書類の改ざんなど、不正な手段で失業保険を受給するのは避けましょう。
病気で退職した場合でも失業保険を受け取れる3つの条件
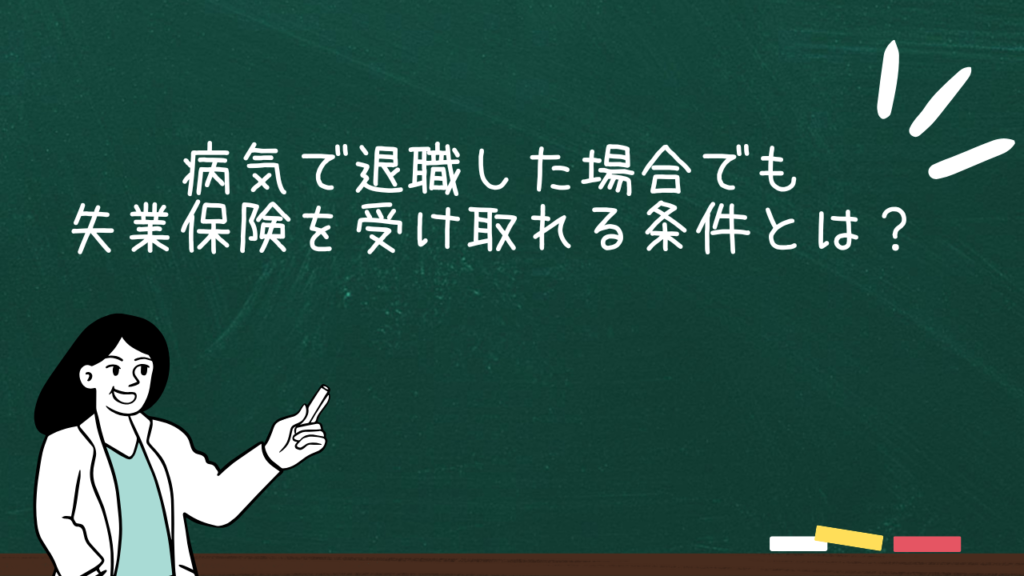
病気で退職した場合でも、失業保険を受け取るには以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 特定理由離職者に該当する
- 医師の診断書など証明書を提出している
- 雇用保険の加入期間の条件を満たしている
上記を満たしていれば、病気が理由でも失業手当を受け取れる可能性があります。では、それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
特定理由離職者に該当する
病気で退職した場合、「特定理由離職者」に該当するかどうかが重要です。
特定理由離職者とは、病気やケガ、家族の介護などのやむを得ない理由で退職した人を指します。
この条件に該当すれば、一般的な自己都合退職者よりも有利な条件で失業保険を受け取ることができます。
具体的には、給付制限期間(1ヶ月手当が支給されない期間)が免除される可能性があるため、より早く失業保険を受給可能です。
特定理由離職者の判定は、ハローワークでの申告内容や医師の診断などの証明書類に基づいて行われます。
医師の診断書など証明書を提出している
病気を理由に退職した場合、医師の診断書や通院記録などの証明書を提出する必要があります。
診断書には病気の内容や治療の必要性、労働継続が困難である旨が記載されているため、退職理由が「病気」であることを証明し、特定理由離職者として認定を受けることが可能です。
上記の書類を事前に準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
また、地域のハローワークによっても申請の流れや必要書類が異なります。
専門家に相談して不備の無いように進めることが大切です。
雇用保険の加入期間が条件を満たしている
失業保険を受け取るためには、退職前の雇用保険の加入期間が一定条件を満たしている必要があります。
具体的には、退職前の2年間で12か月以上雇用保険に加入していることが条件となります。
ただし、特定理由離職者の場合、条件が緩和される場合もありますので、加入期間が不安な場合は専門家などへ確認してみましょう。
「転職×退職のサポート窓口」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。
評判も良く、利用者数1万人越えのサービスなので信頼性も高いです。
もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大300万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
病気で退職後に失業保険を申請するまでの流れ【3STEP】
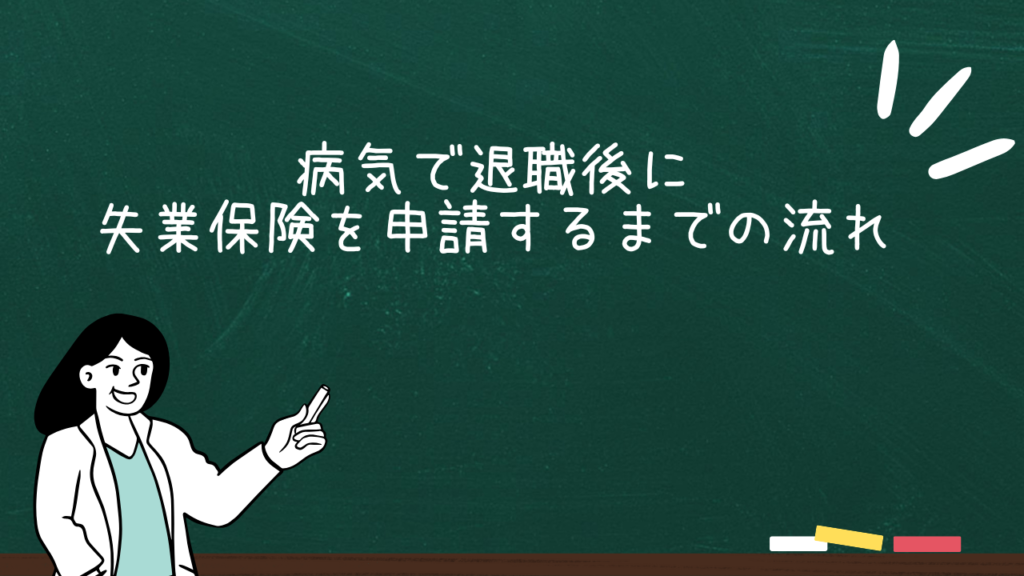
病気で退職後に失業保険を申請するまでの流れは、以下の3つのステップに分かれます。
- 離職票と医師の診断書を準備する
- ハローワークで離職理由を申告する
- 受給資格の確認後、求職活動を開始する
あらかじめ流れを把握しておけば、スムーズに手続きを進められます。では、それぞれのステップを順番に確認していきましょう。
1.離職票と医師の診断書を準備する
退職後にまず行うべきことは、会社から離職票を受け取ることです。
この離職票がなければ、失業保険の申請ができません。
また、医師の診断書も忘れずに用意しましょう。
これにより、退職理由が「病気」であることを証明できます。
離職票の受け取りには時間がかかることもあるため、会社に早めに依頼することが大切です。
診断書の取得についても、医療機関での手続きに時間がかかる場合がありますので、計画的に進めましょう。
2.ハローワークで離職理由を申告する
離職票と診断書を準備したら、最寄りのハローワークで離職理由を申告します。
この際、離職理由が「病気」であることを正確に伝えることが重要です。
特定理由離職者として認定されるための審査が行われます。
申告の際には、診断書や離職票をもとに、具体的な病状や退職に至った経緯を説明する必要があります。
不明点があれば、その場でハローワークの担当者に質問しましょう。
3.受給資格の確認後、求職活動を開始する
ハローワークで離職理由が確認され、受給資格が認定されると、失業保険を受け取るための求職活動がスタートします。
特定理由離職者の場合、給付制限期間がない場合が多いため、早期に失業保険を受け取れる可能性があります。
求職活動の実績は、失業保険を受給するための重要な条件となります。
ハローワークが指定する活動内容をしっかり把握し、計画的に進めましょう。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部特定理由離職者として申請をすることによって、国民健康保険料の軽減申請も可能になります。
少し聞きなれない言葉ですが、離職コードが33番となり、軽減申請が可能です。
病気で退職した場合の「給付制限期間」とは?
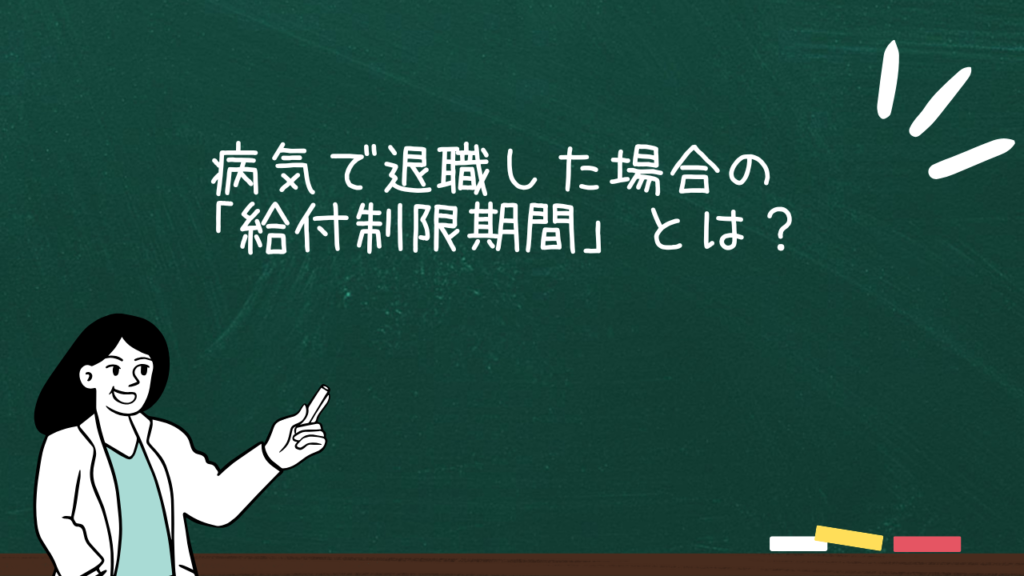
病気で退職した場合の「給付制限期間」を、以下の3つの観点から解説します。
- 給付制限期間とは自己都合退職に適用される期間
- 特定理由離職者は給付制限期間が免除されるケースが多い
- 給付制限期間中の生活の注意点
上記を理解しておけば、退職後の金銭的な不安を軽減できます。では、各ポイントを詳しく見ていきましょう。
給付制限期間とは自己都合退職に適用される期間
一般的に、自己都合で退職した場合、失業保険の受給開始までに1か月間の「給付制限期間」が設けられます。
この期間中は失業保険を受け取ることができません。
一方で、特定理由離職者や会社都合退職者の場合は、この給付制限期間が免除される場合があります。
病気退職の場合は特定理由離職者に該当する可能性があるため、早めに受給できる場合が多いです。
特定理由離職者は給付制限期間が免除されるケースが多い
病気やケガなどのやむを得ない理由で退職した場合、特定理由離職者として認定されることで、給付制限期間が免除される可能性があります。
ただし、この認定を受けるためには、診断書や証明書の提出が必要です。
ハローワークでの認定手続きは慎重に進める必要があります。
不備があると認定がされなかったり、遅れることもあるため、記入された書類の内容や提出期限に注意しましょう。
給付制限期間中の生活の注意点
万が一、特定理由離職者として認定されなかった場合、給付制限期間中の生活費をどのように確保するかが重要です。退職金や貯金を活用するほか、家族や自治体のサポート制度を利用することも検討しましょう。
また、給付制限期間中でも、求職活動は始めることが可能です。
積極的に求人情報をチェックし、次の職場を探す努力を続けることが重要です。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部失業保険の申請で難しいのが、不備の書類を提出後に、訂正をさせてもらえずに特定理由離職者として申請が可能な人でも認定を受けれなくなってしまうこともあります。
提出前に、問題ないのかを専門家に確認してもらうことも大切です。
病気で退職した場合に受け取れる失業保険の金額と給付期間
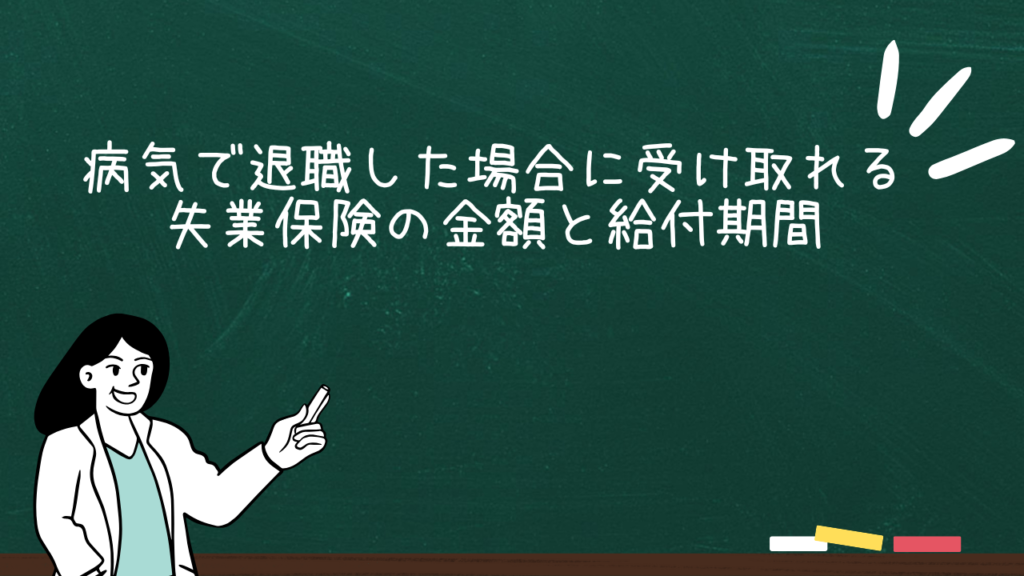
病気で退職した場合に受け取れる失業保険の金額と給付期間を、以下の3つの観点から解説します。
- 基本手当日額の算出方法
- 特定理由離職者と一般退職者の給付期間の違い
- 雇用保険の加入期間が給付期間に与える影響
上記を把握しておけば、自分がどれくらい受け取れるのか、どのくらいの期間支給されるのかを事前にイメージできます。では、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
基本手当日額の算出方法
失業保険の基本手当日額は、退職前の給与額に基づいて算出されます。具体的には、退職前6か月間の総賃金を180で割り、その金額に一定の給付率を掛けた金額が基本手当日額です。
給付率は年齢や賃金の水準によって異なりますが、おおむね50%~80%となっています。詳細はハローワークで確認することが推奨されます。
特定理由離職者と一般退職者の給付期間の違い
特定理由離職者は、一般退職者に比べて有利な条件で失業保険を受け取れることはありません。特定理由離職者の中でも契約社員の方が契約を更新できずに離職になった状況であれば会社都合退職と同じ扱いとなり失業保険の給付期間を長くなることはあります。ただ、病気での退職のみでは給付期間は自己都合退職と変わりません。
給付期間は雇用保険の加入期間や年齢によって異なります。自身の条件に合った給付期間を事前に確認しておきましょう。
雇用保険の加入期間が給付期間に与える影響
雇用保険の加入期間が長いほど、失業保険の給付期間も長くなります。
たとえば、加入期間が10年以上の場合、最大330日間の給付を受けることができる場合があります。
逆に、加入期間が短いと給付期間も短くなるため、退職前の加入期間をしっかり把握しておくことが大切です。
参考:失業保険が受給できる期間は?退職理由ごとに受給できる期間や条件を紹介【社会保険労務士監修】
病気で退職後に失業保険を受け取る際の3つの注意点
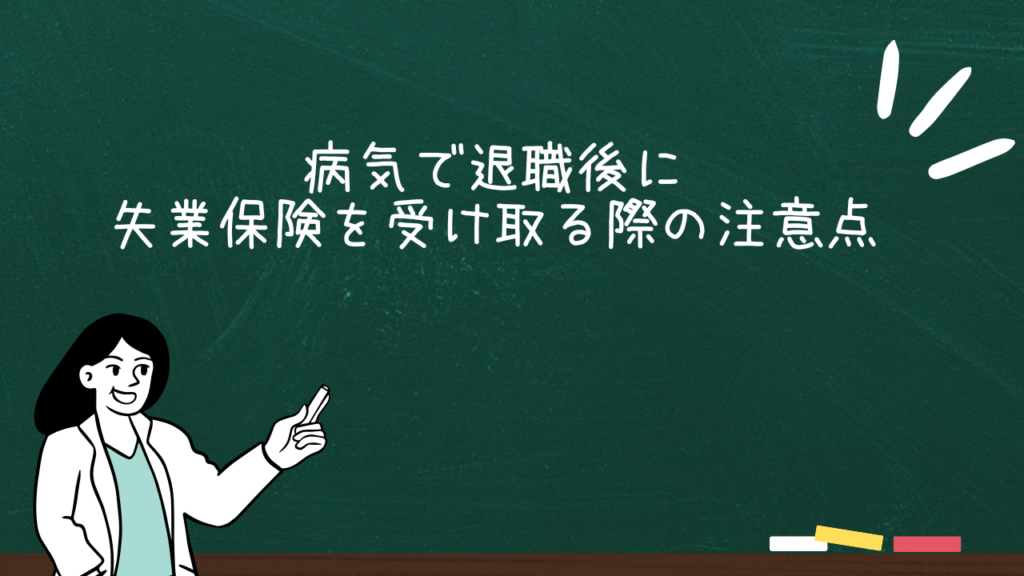
病気で退職後に失業保険を受け取る際は、以下の3つの注意点を押さえておく必要があります。
- 申請期限を守る
- 受給期間の申請期限延長は早めに準備して申請する
- 健康状態が悪化した場合は傷病手当への変更も検討する
上記を事前に押さえておくことで、想定外のトラブルや手続きの遅れを防ぎやすくなります。では、それぞれの注意点を詳しく確認していきましょう。
申請期限を守る
失業保険の申請には期限があります。通常、離職後1年以内に申請を行う必要がありますが、病気などで申請が遅れる場合は、延長申請を行うことが可能です。
期限を過ぎてしまうと、失業保険を受け取れなくなる可能性があるため、早めの行動をしましょう。
受給期間の申請期限延長は早めに準備して申請する
病気やケガで長期間療養が必要な場合、失業保険の受給期間を延長することができます。申請期限延長申請には、医師の診断書や延長を必要とする理由を記載した書類が必要です。
受給期間の申請期限延長を希望する場合は、ハローワークで詳細な手続きを確認し、早めに準備を進めましょう。
健康状態が悪化した場合は傷病手当への変更も検討する
受給期間中に健康状態が悪化し、求職活動が困難になった場合、「傷病手当」への切り替えを検討することも可能です。傷病手当は、失業保険の受給中に病気やケガが悪化した場合に支給されます。
上記の場合も、医師の診断書が必要となるため、必要書類を早めに準備しておきましょう。
「転職×退職のサポート窓口」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。
評判も良く、利用者数1万人越えのサービスなので信頼性も高いです。
もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大300万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
病気で退職した場合の失業保険と「傷病手当」の違いとは?
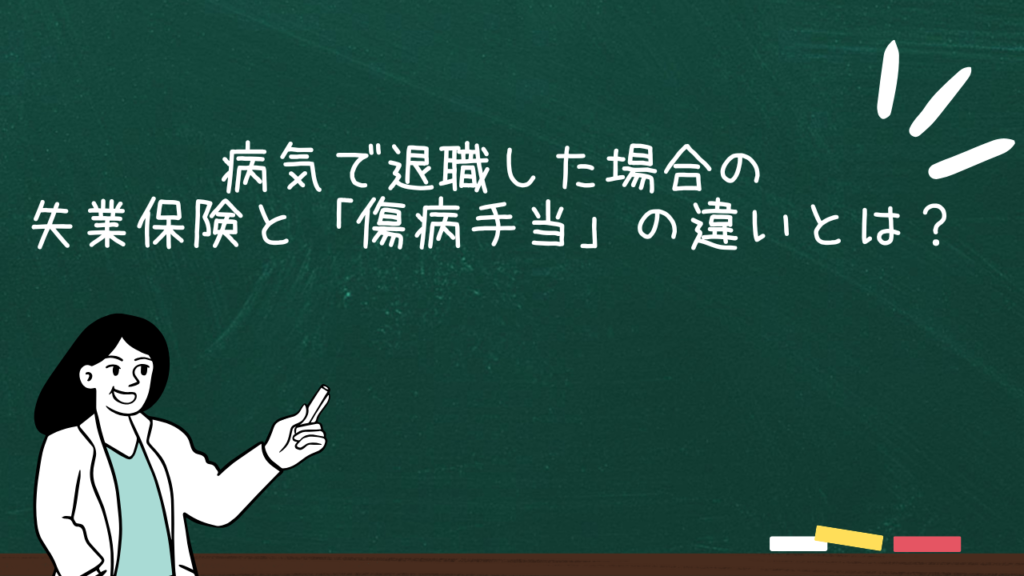
病気で退職した場合の失業保険と「傷病手当」の違いを、以下の3つの観点から解説します。
- 失業保険と傷病手当の支給条件の違い
- 受給可能な期間と金額の差異
- どちらか一方しか受け取れないルール
上記の違いを理解しておくと、自分の体調や状況に応じて、どちらを優先すべきか判断しやすくなります。では、それぞれのポイントを順に見ていきましょう。
失業保険と傷病手当の支給条件の違い
失業保険は、求職活動を行う意思と能力がある場合に支給されます。一方、傷病手当は、病気やケガにより労働が困難な場合に支給されます。
そのため、現在の健康状態や就職活動の状況に応じて、どちらを選ぶべきか判断が必要です。
受給可能な期間と金額の差異
失業保険と傷病手当では、受給可能な期間や金額に違いがあります。失業保険は、雇用保険の加入期間や年齢によって給付期間が決まりますが、傷病手当は最長で1年6か月間支給されます。
金額についても異なるため、事前に具体的な条件をハローワークで確認しておきましょう。
どちらか一方しか受け取れないルール
失業保険と傷病手当は、同時に受け取ることができません。どちらか一方を選ぶ必要があります。そのため、自分にとってどちらが適しているかを慎重に検討しましょう。
医師やハローワークの担当者に相談しながら、適切な選択をしましょう。
また、雇用保険の傷病手当を受け取るのであれば、健康保険の傷病手当金を受け取れるように準備をした方が良いです。
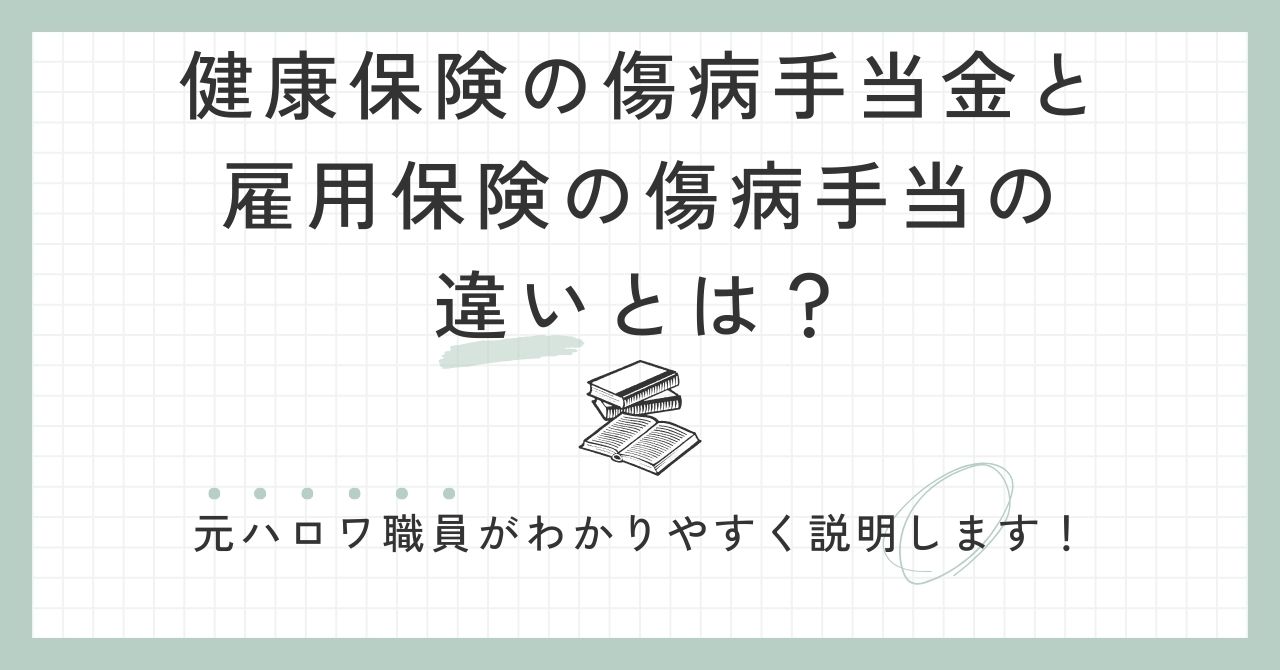
失業保険の手続きをスムーズに進めるための元ハロワ職員の2つのアドバイス

失業保険の手続きをスムーズに進めるための、元ハロワ職員の2つのアドバイスを紹介します。
- 事前に必要書類を揃える
- 早めの来所で待ち時間を短縮する
上記を意識すれば、手続きの流れがぐっとスムーズになります。では、それぞれのポイントを具体的に見ていきましょう。
事前に必要書類を揃える
失業保険の申請には、離職票や診断書、本人確認書類などが必要です。
これらの書類を事前に揃えておくことで、手続きがスムーズに進みます。
特に離職票は、会社からの発行に時間がかかることがあるため、早めの依頼をおすすめします。
早めの来所で待ち時間を短縮する
ハローワークは混雑することが多いため、早めに来所することで待ち時間を短縮できます。また、手続きがスムーズに進むよう、必要書類を事前に確認しておくことも大切です。
事前に予約が必要な場合もあるため、事前にハローワークのウェブサイトや電話で確認しておきましょう。
病気で退職した場合の失業保険に関するよくある4つの質問

ここでは、病気で退職した場合の失業保険に関するよくある質問とその回答をまとめます。
「転職×退職のサポート窓口」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。
評判も良く、利用者数1万人越えのサービスなので信頼性も高いです。
もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大300万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
退職後の給付金に関する相談は「転職×退職サポート窓口」にご相談ください
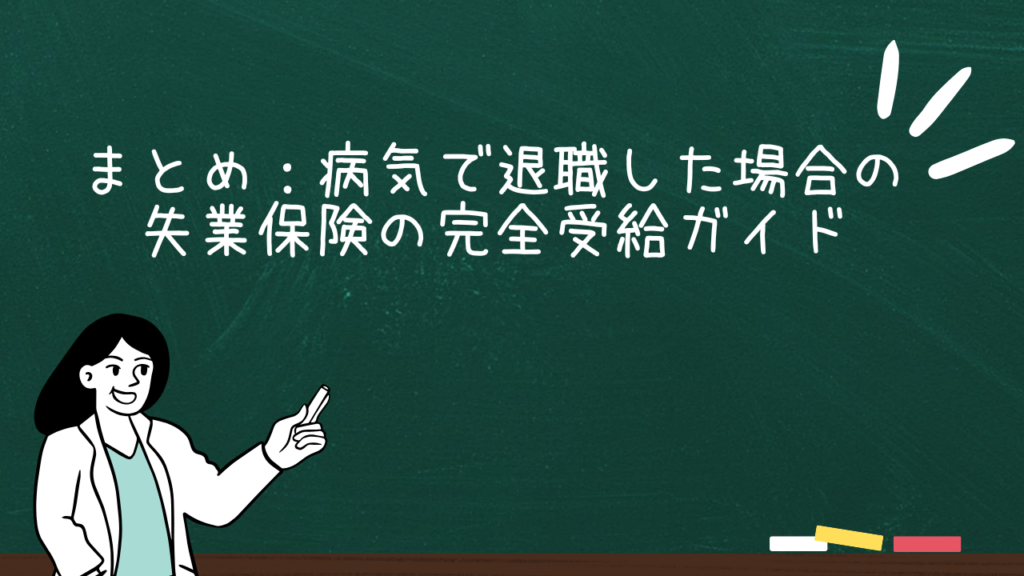
病気で退職した場合でも、失業保険を受け取ることは可能です。ただし、そのためには特定の条件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。
特定理由離職者として認定を受けることで、給付制限期間の免除や有利な条件での受給が可能になります。
失業保険の申請や受給には、離職票や診断書などの準備が欠かせません。
さらに、申請期限を守り、ハローワークでの手続きをスムーズに進めることが重要です。
本記事の情報を参考にしながら、必要な準備を進め、安心して次のステップへ進んでください。