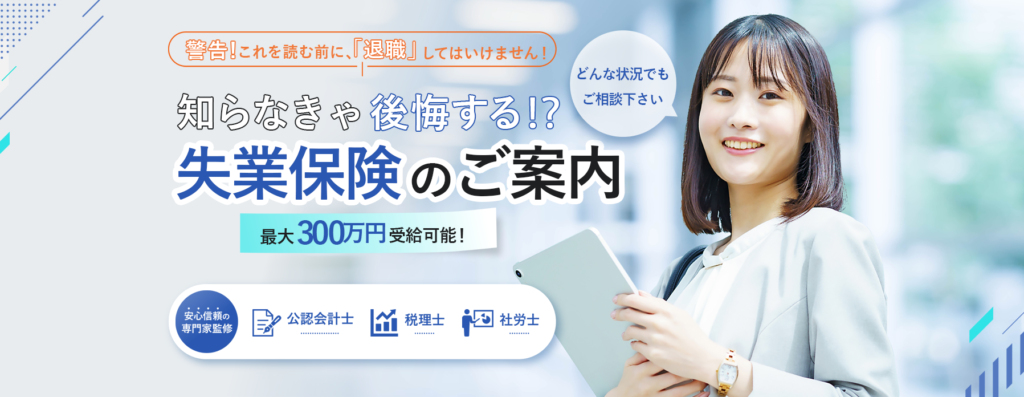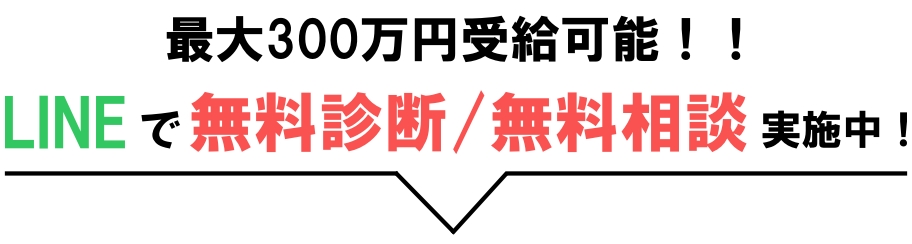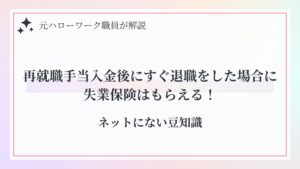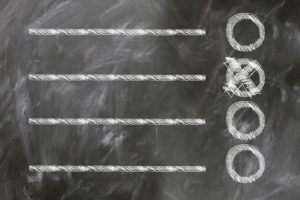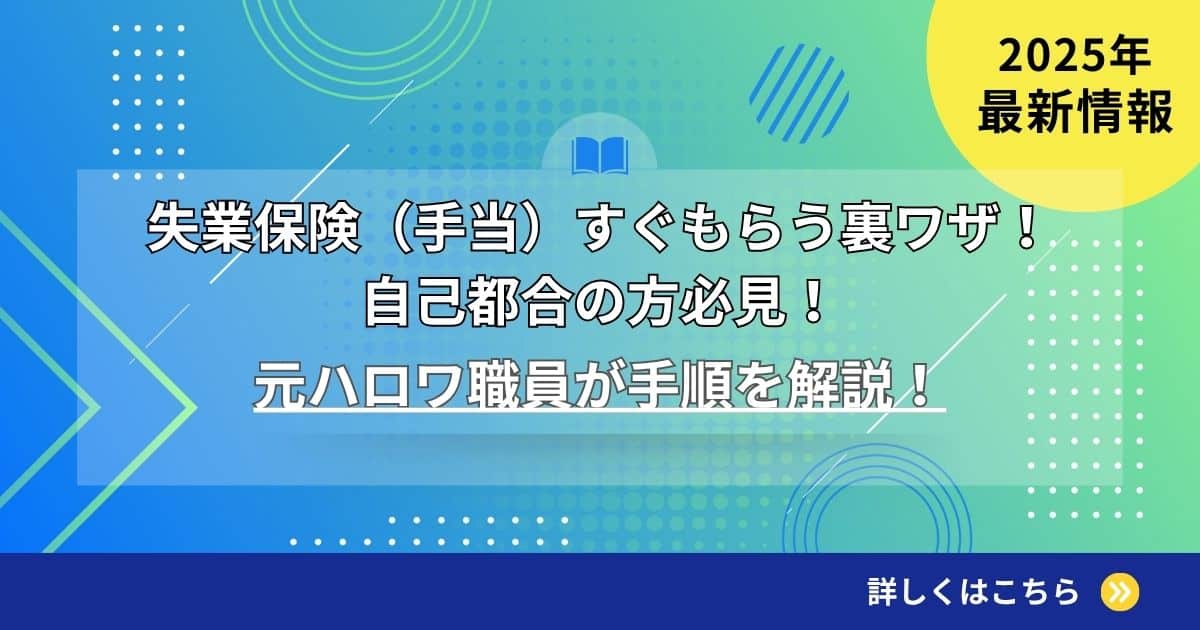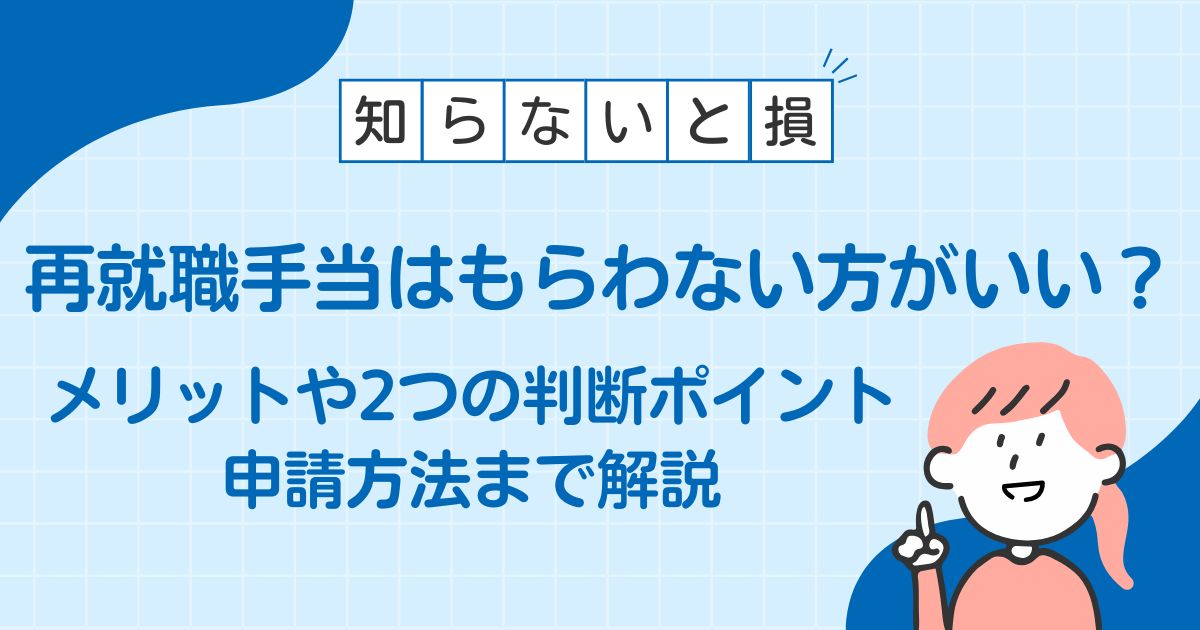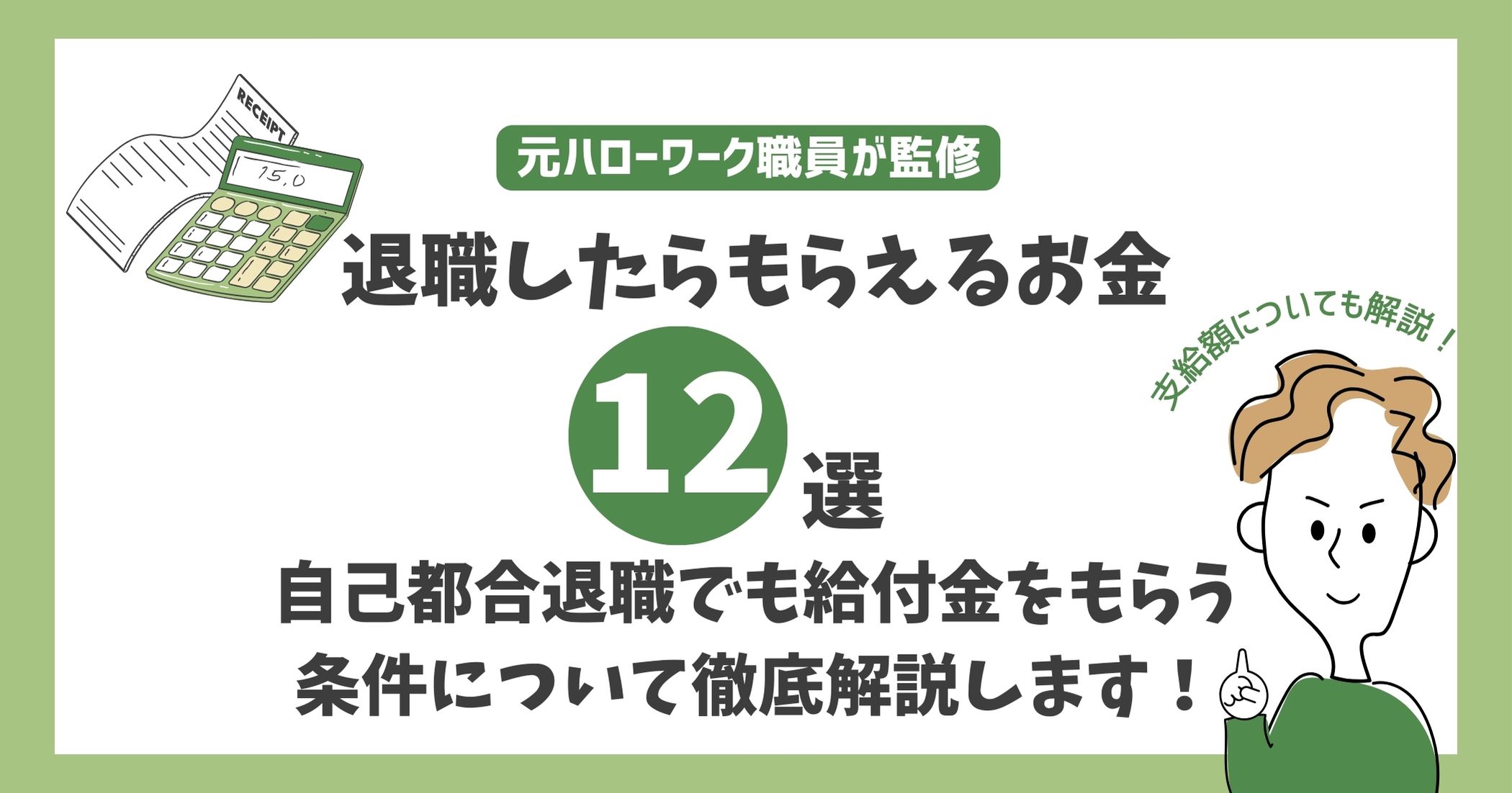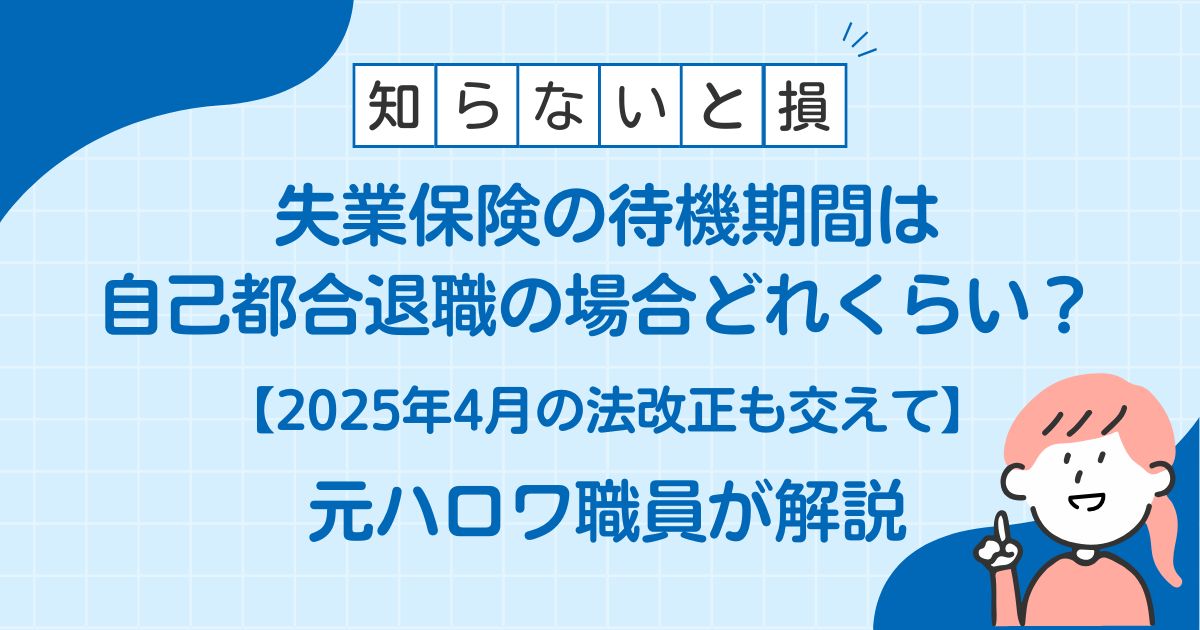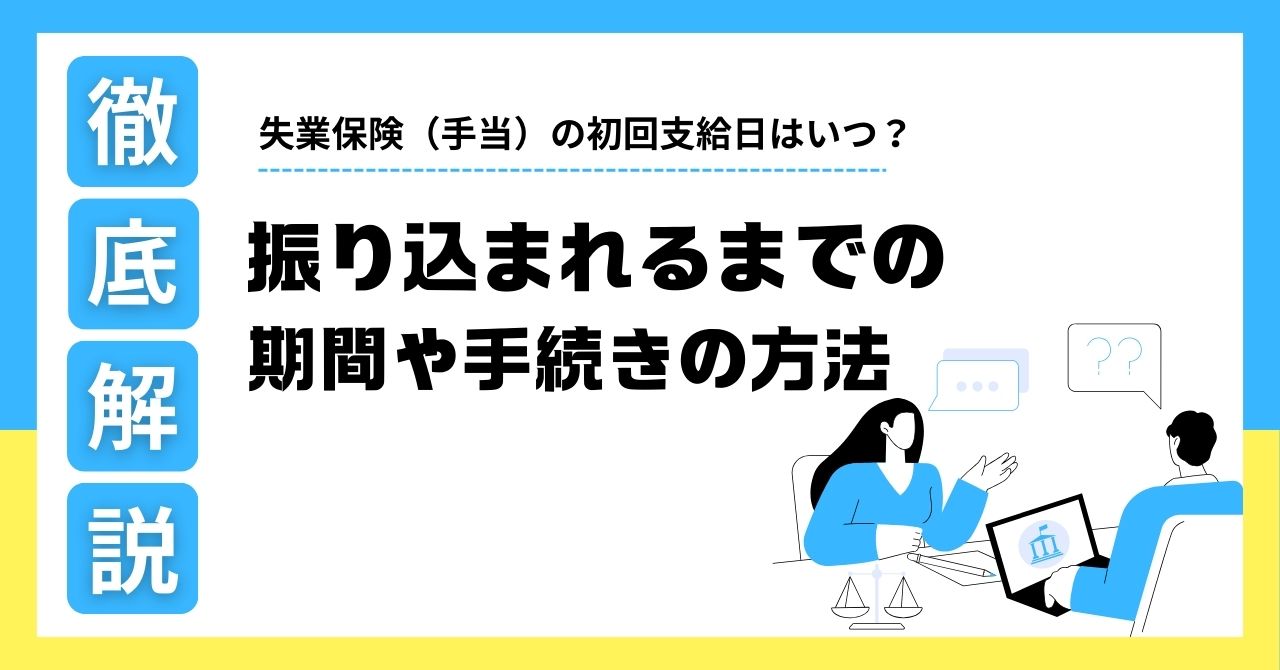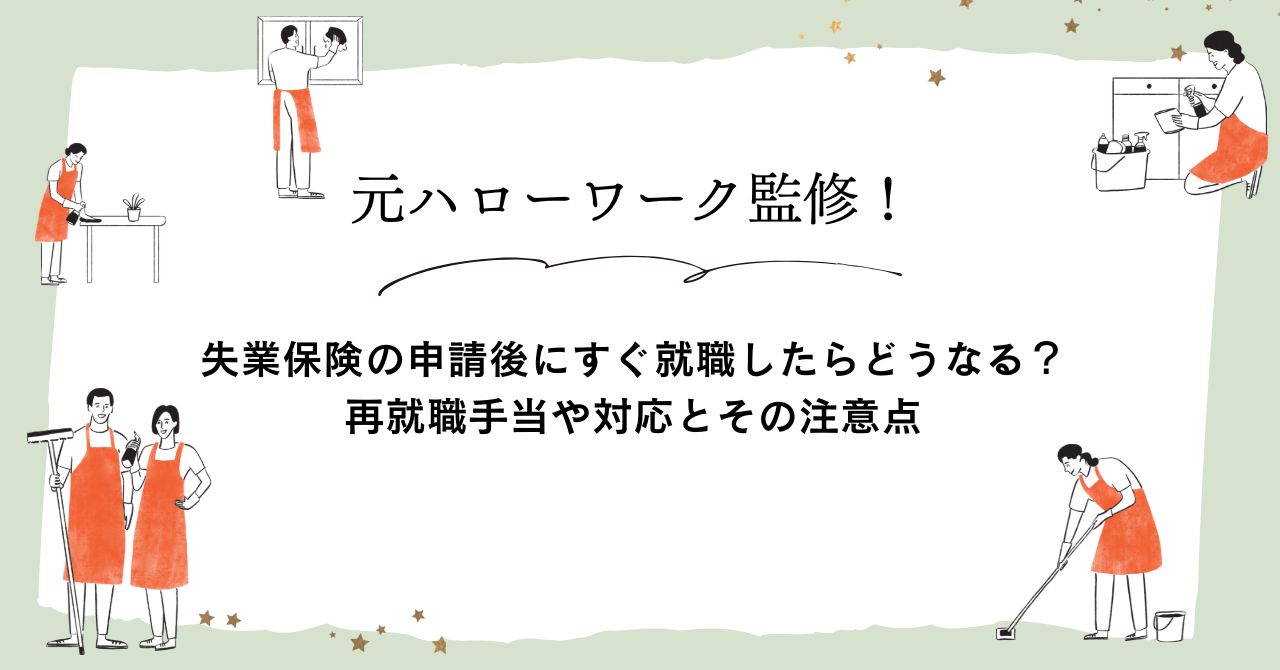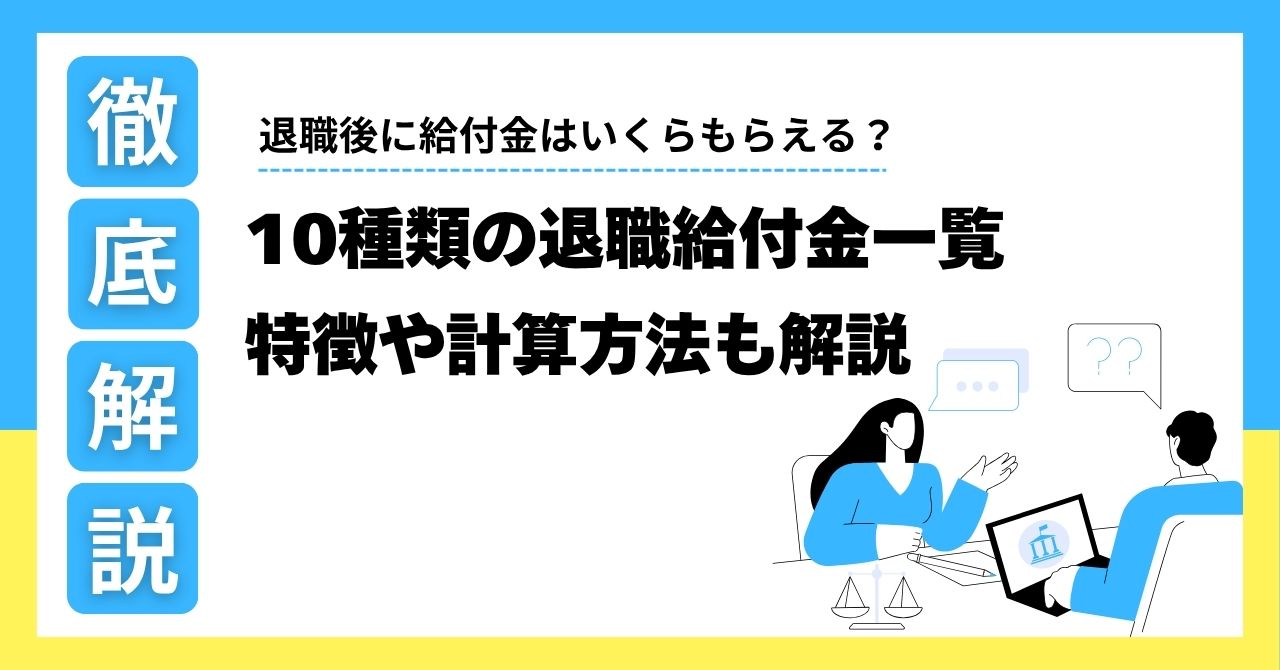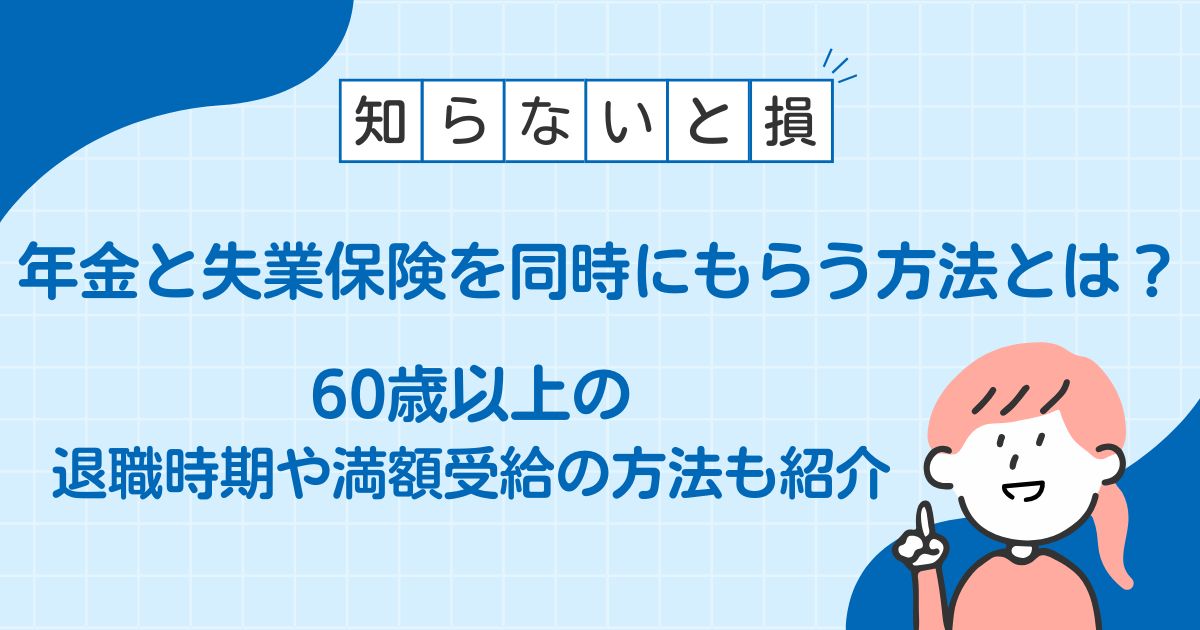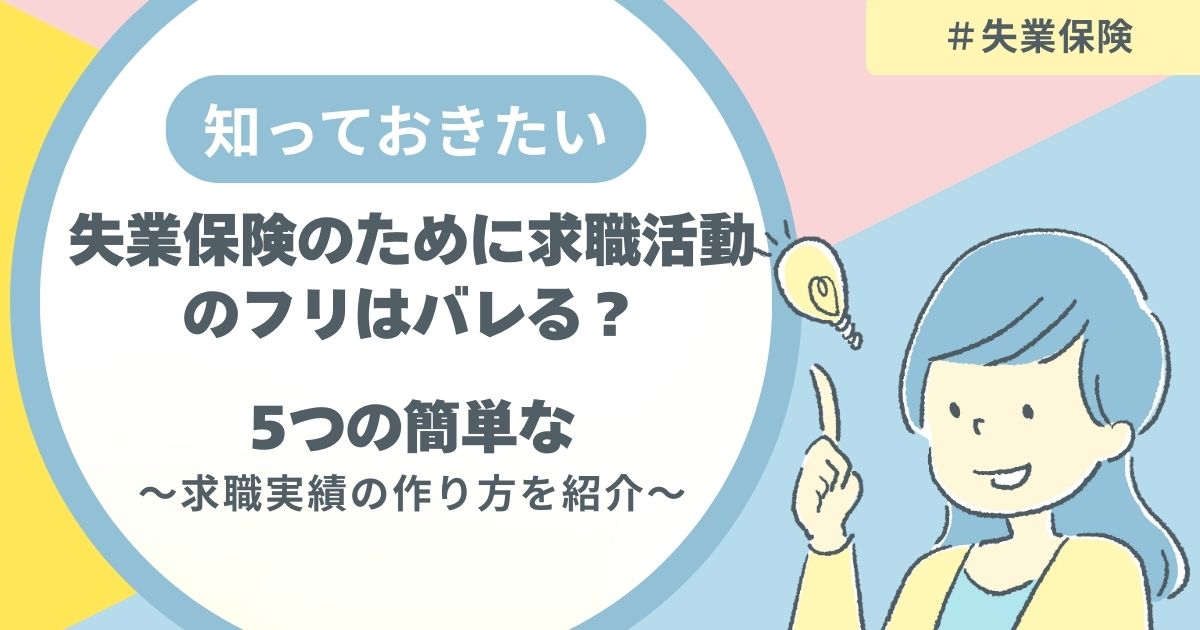- うつ病での休職や退職はずるいと思われる?
- うつ病での休職や退職する前にやるべきことは?
うつ病での休職や退職を検討している方は、このようにお悩みではありませんか?
うつ病での休職や退職をずるいと感じる人のほとんどは、病気に対する理解の浅さや給付金に関する羨ましさが原因です。仮にずるいと思われても、うつ病を発症しているなら、休職や退職も視野に入れて今後を考えるべきでしょう。
 元ハロワ職員<br>佐藤
元ハロワ職員<br>佐藤この記事ではうつ病での休職や退職をずるいと感じる理由や退職する前にすべき5つのことを解説します。
サポートしてくれる就労サービスや休職・退職するメリットも解説するので、ぜひご覧ください。
今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。

うつ病での休職や退職をずるいと感じさせてしまう3つの理由

うつ病での休職や退職をずるいと感じさせてしまう理由は、以下の3つが挙げられます。
- うつ病に対する理解が浅く偏見や誤解がある
- 業務の負担が増えることに抵抗がある
- 傷病手当金の受給に対するやっかみがある
それぞれの理由を詳しく解説します。
うつ病に対する理解が浅く偏見や誤解がある
うつ病での休職を「ずるい」と感じる人が多いのは、うつ病への理解が十分に広まっていないことが原因です。
うつ病は目に見えない病気であるため、深刻さや症状の重さが周囲の人々に正しく理解されにくいです。
うつ病を単なる気分の落ち込みや怠けと考えている人は多く、治療と休養が必要な病気の認識が広まっていません。また、外見からは症状が分かりにくいため、休職や退職を単なる怠けと誤解されがちです。
周りからは「気分で休んでいる」ように見えることも、誤解を招く原因となっています。中には、うつ病を「甘え」や「わがまま」と誤解し、休職や退職の必要性を理解できない人もいるでしょう。
このような誤解や偏見を解消するためには、うつ病に関する正しい知識を広めていくのが重要です。
うつ病は誰でも経験する可能性がある病気であり、症状の改善には適切な治療と休養が欠かせません。周りの理解と支援が回復への一歩となります。
業務の負担が増えることに抵抗がある
うつ病で誰かが休職すると、残された社員の仕事が増えるのは避けられません。引き継ぎが不十分なまま業務量が増え、残業が増えたり、休暇が取りづらくなったりします。
こうした状況が続くと、「なぜ頑張っている側だけが大変な思いをするのか」などの不満が募ります。
職場の雰囲気が悪くなり、休職している人への批判的な声も出てきがちです。
ただ、うつ病は本人も予期せず発症する病気です。会社側は人員配置を見直したり、業務を適切に分散したりして、職場全体の負担を減らす対策をする必要があります。
傷病手当金の受給に対するやっかみがある
うつ病での休職や退職をずるいと感じる理由の1つに、傷病手当金の受給に対するやっかみがあります。
傷病手当金は、働いていないにも関わらず一定の収入が得られる制度であるため、働き続けている人々から不公平感を抱かれやすいです。
また、うつ病は外見からは症状が分かりにくいため、周りから誤解をされる原因にもなっています。
傷病手当金は給与の3分の2ほどが支給されるため、「働かずに給料をもらっている」などの批判を受けます。最長1年6ヵ月も受給できることへの不満の声も多いです。
うつ病の症状が目に見えないため、「本当に働けないのか」などの疑念が生まれやすいです。
しかし、傷病手当金は病気や怪我で働けない人を経済的に支える重要な制度になります。受給には医師の診断書が必要であり、単なる怠けや甘えではないことを理解してもらう必要があります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
うつ病での休職や退職に関するトラブルを回避する4つの方法

うつ病での休職や退職に関するトラブルを未然に防ぐには、以下の4つの方法が有効です。
- 専門医の診断を受けうつ病であることを正式に確認する
- 上司や人事部門に早めに状況を説明し相談する
- できる限り丁寧に業務の引き継ぎを行う
- 休職中はSNSへの投稿を控える
それぞれの方法を、詳しく解説していきましょう。
専門医の診断を受けうつ病であることを正式に確認する
うつ病での休職や退職をスムーズに進めるには、まず精神科や心療内科で専門医の診断を受けるのが大切です。
医師の正式な診断があれば、会社への診断書の提出もスムーズになり、休職や退職の手続きも進めやすくなります。
医師との診察では、自分の症状や日々の生活状況を丁寧に説明しましょう。
医師は問診を通じて総合的に判断し、必要な診断書を発行してくれます。
体調の悪化を感じたら、自己判断せずに早めに医療機関を受診するのがおすすめです。
上司や人事部門に早めに状況を説明し相談する
体調の変化を感じたら、上司や人事部門へ相談をしましょう。
早い段階で会社に伝えれば、業務調整や休職の準備がスムーズに進みます。
まずは直属の上司に状況を話し、仕事量の調整を相談するのがおすすめです。
加えて、人事部にも相談すれば、休職制度や傷病手当金の詳しい情報が得られます。
もし産業医や社内カウンセラーがいる場合は、専門的なアドバイスをもらうのも有効です。
自分の状態や治療の必要性は正直に伝えましょう。
無理に働き続けるのではなく、できる範囲で仕事をしながら、休職の準備を進めていくのがよいでしょう。
できる限り丁寧に業務の引き継ぎを行う
休職や退職の際は、業務の引き継ぎを丁寧におこなえば、後々のトラブルを防げます。
引き継ぎでは、書類やデータの保存場所、仕事の進み具合、今後の予定、気をつけるべき点などを文書にまとめます。
引き継ぎ先となる同僚には、必要に応じて直接説明をおこなうのがよいです。
体調が悪い中での作業は大変ですが、自分のペースで着実に進めるのが大切です。
無理せず、できる範囲で誠実に対応しましょう。
休職中はSNSへの投稿を控える
うつ病での休職中は、SNSへの投稿は控えめにしましょう。安易に投稿すると、同僚や会社関係者から「本当に休職や退職する必要があったのか」と疑念を持たれる可能性が高くなります。
特に問題なのが、休職中の平日や勤務時間帯に、旅行や遊びに行った写真をアップすることです。こうした行為は「病気のふりをしてサボっているのでは」「ずるい」などの印象を周囲に与えかねません。
もちろん、うつ病で療養中の行動を制限する必要はありません。気分転換に旅行や遊びに行くことは、心身の回復のためにも大切です。
しかし、休職・退職者への風当たりが厳しい日本の現状を考えると、SNSでそうした情報を発信するのはリスクが大きいと考えられます。休職中はSNSの使用は最小限にとどめ、ストレスを感じない穏やかな環境で過ごすことを心がけましょう。
うつ病で休職や退職する前にやるべき5つのこと

うつ病で休職や退職する前にやるべきこととして以下の5つが挙げられます。
うつ病で休職や退職する前にやるべきこと
- 医師へ相談する
- 身近な人に相談する
- 家計の状況を把握する
- 仕事が原因のうつ病なのか考える
- 休職・退職以外の方法を考える
それぞれの行動を詳しく解説します。
医師へ相談する
うつ病で休職や退職を考える前にやるべきことの1つ目は医師へ相談することです。うつ病は専門的な診断と治療が必要な病気であり、自己判断で休職や退職を決めることはリスクがともないます。まずは信頼できる医師に状況を詳しく伝え、適切な診断を受けましょう。
医師は現在の症状に対して最適な治療方法を提案し、必要に応じて休職や退職のタイミングなどもアドバイスしてくれます。医師への相談が、今後の対応を決める上での重要な第一歩となるでしょう。
身近な人に相談する
うつ病で休職や退職を考える前にやるべきことの2つ目は身近な人に相談することです。家族や友人、信頼できる同僚に自身の状況や悩みを打ち明けることで精神的なサポートを得られます。
また、客観的な視点から助言を受けることで、休職や退職に向けた判断がより慎重に行えるようになるでしょう。支えとなる身近な人とのコミュニケーションは、うつ病の回復にも大きく寄与します。
もし身近な人に相談するのが難しければ、適切な機関にカウンセリングをお願いしてもよいでしょう。
家計の状況を把握する
うつ病で休職や退職を考える前にやるべきことの3つ目は家計の状況をしっかりと把握しましょう。収入が減少する可能性があるため、現在の収支バランスや貯蓄額、支出の見直しが必要です。特に、生活費やローンの支払いなど毎月の固定費を確認し、休養に必要な期間の資金が確保できるかどうかを検討するのが重要です。
収入が減少しても生活を維持できるかを見極めることで、安心して休職や退職の判断ができます。家計の状況を冷静に把握すると、将来的な不安を軽減する助けになるでしょう。
以下の記事では、休職・退職時に受け取れる失業保険と傷病手当金を詳しく解説しています。どちらの制度が自分に合っているのか、給付金額はいくらになりそうかをしっかりチェックしておきましょう。

仕事が原因のうつ病なのか考える
うつ病で休職や退職を考える前にやるべきことの4つ目は本当に仕事が原因でうつ病が発症しているかをじっくり考えることです。仕事が原因だと思われる場合、職場環境や業務内容の改善が必要であり、休職や退職が本当に最善の選択かを見極めるために、まずは原因を特定しなければなりません。
仕事以外の要因が影響している場合もあるため、生活環境や人間関係、家庭の状況も含めて総合的に考慮する必要があります。原因を明確にすると適切な対策が立てられ、無理のない休職や退職の判断が可能となります。
以下の記事では、仕事が原因のうつ病で退職した際の失業保険に関して詳しく解説しています。うつ病で再就職が難しい場合、失業保険を最大300日受給できる条件なども確認できるので、ぜひチェックしてみてください。

休職・退職以外の方法を考える
うつ病で休職や退職を考える前にやるべきことの4つ目は休職や退職以外の他の方法がないか検討することです。休職や退職は最後の手段として考えるべきであり、職場での配置転換や勤務時間の短縮、リモートワークの導入など、働き方の見直しが可能かを上司や人事部門と相談するのが重要です。
また、心療内科やカウンセリングを活用して仕事と生活のバランスを改善する方法を探ることも有効です。休職や退職以外の選択肢を模索することで、心身ともに負担を軽減しながら働き続けられます。
以下の記事では、うつ病であっても休職・退職せずに働き続ける方法を具体的な事例を交えて解説しています。 会社と話し合って業務内容の見直しや配置転換をしてもらうなど、前向きな解決策を見出すヒントが得られるでしょう。
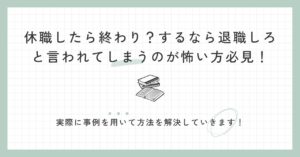
うつ病で休職や退職するときに活用できる8つのサービス

うつ病で休職や退職を検討している人におすすめなのが、以下の8つの支援サービスです。
- ハローワーク
- 転職エージェント
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援事業所
- 地域障害者職業センター
それぞれのサービスの特徴を紹介します。
ハローワーク
うつ病で休職や退職するときに活用できる就労サービスとしてハローワークが挙げられます。ハローワークでは就職相談や求人情報の提供だけでなく、職業訓練や再就職支援プログラムなども利用できます。うつ病を抱えた状態での転職活動は大きな負担になるため、ハローワークの専門スタッフが提供するサポートが重要です。さらに、障害者手帳を持つ場合は、障害者向けの特別な就職支援サービスも利用可能です。
ハローワークを利用すれば自分に合った職場を見つけるためのサポートを受けられ、安心して次のステップに進めるでしょう。
以下の記事では、ハローワークに行くのが怖いと感じる理由と、その不安を和らげる方法を解説しています。実際にハローワークを利用した人の感想もあるので、参考にしてみてください。

なお、「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
転職エージェント
うつ病で休職や退職するときに活用できる就労サービスとして転職エージェントも挙げられます。転職エージェントは、個々のスキルや経験に基づいて最適な職場を紹介し、面接対策や履歴書の添削などのサポートを提供してくれる民間のサービスです。
特に、うつ病を抱える方にとっては精神的な負担を軽減しながら転職活動を進めることが重要であり、転職エージェントのアドバイスは大いに役立ちます。
また、転職エージェントは非公開求人にもアクセスできるため、よりよい条件の職場を見つけるチャンスが広がります。
障害者就業・生活支援センター
うつ病で休職や退職するときに活用できる就労サービスとして障害者就業・生活支援センターも挙げられます。障害者就業・生活支援センターは障害者が就業や生活の支援を受けながら社会復帰を目指すための専門機関です。
うつ病を抱える方に対して職場復帰や新たな職探しのサポートを提供し、就業に関するアドバイスやカウンセリングを行います。また、生活面でのサポートも行い、仕事と生活のバランスを取り戻すための支援を受けることも可能です。
就労移行支援事業所
うつ病で休職や退職するときに活用できる就労サービスとして就労移行支援事業所も挙げられます。就労移行支援事業所は、障害や病気を抱える人々が社会復帰を目指すためのトレーニングやサポートを提供する施設です。
うつ病を抱える方が、再び職場に戻る自信をつけるために、職業訓練や実習を通じてスキルを磨きながら、個別のサポートを受けられます。また、事業所では、適切な職場を見つけるためのアドバイスや求人情報の提供も行われています。就労移行支援事業所を利用すれば、無理なく社会復帰を目指すための準備が進められるでしょう。
地域障害者職業センター
うつ病で休職や退職するときに活用できる就労サービスとして地域障害者職業センターも挙げられます。地域障害者職業センターは障害を持つ人々が適切な職場を見つけ、職業生活を安定させるための支援を行う専門機関です。
うつ病を抱える人に対しても、個別の職業相談や職場での支援策の提案を行い、就労継続や職場復帰をサポートします。また、企業との連携を通じて障害者雇用の場を広げる取り組みも行われており、安心して働ける環境の提供が期待できるでしょう。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働条件や職場環境の改善に関して相談できる公的機関です。 退職や休職に関するトラブルにも対応してくれるので、会社との交渉がうまくいかない場合は相談するのがおすすめです。
特に、うつ病の原因が長時間労働やパワハラなど、職場の問題に起因している場合は、労働基準監督署に事情を説明すれば、是正を求める指導をしてもらえる可能性があります。
職場のハラスメントや違法な扱いでうつ病を発症したケースは、労働基準監督署への相談を検討してみてください。
こころの耳
「こころの耳」は厚生労働省が開設している、悩み相談窓口です。 仕事のストレスや心の不調で困っている労働者とその家族のために、電話とメールでの相談を無料で行っています。
プライバシーが守られた環境で、うつ病の辛さを吐き出せる貴重な窓口です。 専門のカウンセラーが親身になって話を聞いてくれるため、誰にも言えない悩みを打ち明けられます。
メンタルヘルスの改善に向けたアドバイスはもちろん、うつ病の休職に必要な手続きなどの情報も教えてもらえます。 ストレスや抑うつ状態に悩んでいる人は、一度利用を検討してみてください。
参考:こころの耳
退職代行サービス
うつ病の症状が辛く、会社に退職の意思を直接伝えるのが難しいケースも少なくありません。 このようなときに有効なのが、「退職代行サービス」の利用です。
退職代行サービスでは、本人に代わって会社へ退職の意思を正式に伝えてくれます。本人が直接会社と会話しなくてよいため、精神的な負担を大幅に減らせるのが大きなメリットです。
退職後の生活設計や再就職に向けたキャリア相談にも乗ってくれるので、退職後の不安も軽減できる可能性があります。うつ病で自力での退職が難しい方は、退職までの流れをプロに任せ、ひとまず会社と距離を置くことに専念するのもよいでしょう。
うつ病で休職や退職する3つのメリット

うつ病で休職や退職する主なメリットには以下の3つがあります。
- うつ病の原因となるストレスから解放される
- うつ病の治療や休養に専念できる
- 新しいことにチャレンジできる機会が得られる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
うつ病の原因となるストレスから解放される
うつ病で休職や退職を決断するメリットとして、うつ病の原因となるストレスから解放されることが挙げられます。職場環境や業務内容が原因でうつ病を発症した場合、ストレスが続くことで症状が悪化する恐れがあります。
休職や退職をすると、ストレスの源から距離を置き、心身を休める時間を確保できるようになります。ストレスが減少することで治療に専念でき、回復にも近付けるでしょう。
うつ病の治療や休養に専念できる
治療や休養に専念できることもメリットの1つです。仕事を続けながらうつ病の治療を行うことは、心身に大きな負担をかけることがあります。
休職や退職をすると仕事から解放され、医師の指導のもとで適切な治療を受ける時間と環境を確保できます。また、十分な休養を取ることで、心身の回復が促進され、再び社会に戻る準備を整えることが可能になるでしょう。
新しいことにチャレンジできる機会が得られる
うつ病で休職や退職を決断するメリットとして、新しいことにチャレンジできる機会が得られることが挙げられます。仕事を離れることでこれまでの環境やルーティンから解放され、自分自身を見つめ直す時間が生まれます。この時間を利用して新たなスキルを学んだり新しい趣味や興味を見つけたりするできるでしょう。
また、今まで考えていなかったキャリアチェンジや、より自分に合った職場を探すきっかけにもなります。新しいことに挑戦すると、うつ病の回復だけでなく、より豊かな人生を築くチャンスを手に入れられるでしょう。
以下の記事では、休職するなら退職しろと言われたときの対処法を解説しています。休職と退職のメリット・デメリットにも触れているので、あわせて参考にしてください。
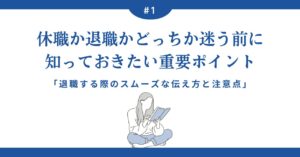
うつ病で休職や退職するデメリット

うつ病で休職や退職するデメリットは、以下の3つです。
- 経済的な問題
- 再就職の困難さ
- 心理的な負担
休職や退職によって収入が減少または無くなると、生活に支障をきたす可能性があります。
うつ病の治療には時間がかかるため、長期的な収入の減少は大きな負担となるでしょう。また、うつ病の治療中や回復途中では、就職活動自体が難しいです。
うつ病の経歴を理由に採用を躊躇する企業もあり、再就職のハードルが高くなります。
心理的な負担は、周囲の理解不足や偏見、自己肯定感の低下などで起こるものです。休職や退職で周囲の反応に傷ついたり、自分の価値を見失ったりすると、うつ病が悪化してしまう可能性もあります。
ただ、デメリットを恐れるあまり、必要な休養や治療を先延ばしにするのは避けましょう。
早めの対応が、結果的に早い回復につながります。
うつ病で休職した後に復帰する際の2つの注意点

うつ病で休職した後、職場に復帰する際は以下の2点に気をつけましょう。
- 同僚に感謝の気持ちを伝える
- 積極的な職場でのコミュニケーションを意識する
それぞれ詳しく解説していきます。
同僚に感謝の気持ちを伝える
うつ病休職から復帰した際は、休んでいる間仕事を助けてくれた同僚に、まず感謝の気持ちを伝えましょう。休職中は申し訳ない気持ちでいっぱいになりがちですが、素直に感謝を言葉にすることが大切です。
「休んでいる間、仕事を代わりにしてくれてありがとう」「おかげさまで休養できました。感謝しています」などの感謝の言葉を口にすることで、お互いに前向きな気持ちになれるでしょう。
一方で、休職したことを必要以上に申し訳なく思うのは禁物です。同僚との上下関係を意識しすぎて、萎縮した態度を取り続けると、かえって居心地の悪さを感じることになります。
その結果、また新たなストレスを抱え込んでしまう危険性もあります。
うつ病を発症したことは何ら恥ずかしいことではありません。感謝の気持ちは伝えつつ、同僚とはフラットな関係を築くことを心がけましょう。
積極的な職場でのコミュニケーションを意識する
休職中に職場との接点が絶たれていたために、人間関係に不安を覚えるケースも少なくありません。
そのようなときは、自分から同僚に話しかけてみるのがおすすめです。休み明けの挨拶はもちろん、休憩中などにも気軽に会話を交わしてみてください。
最初は緊張してうまく話せない可能性もあります。それでも、明るく振る舞うように心がければ、徐々に同僚との距離も縮まっていくでしょう。
積極的にコミュニケーションを取ることで、安心して働ける職場環境を取り戻せます。
うつ病での休職や退職に関する相談なら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
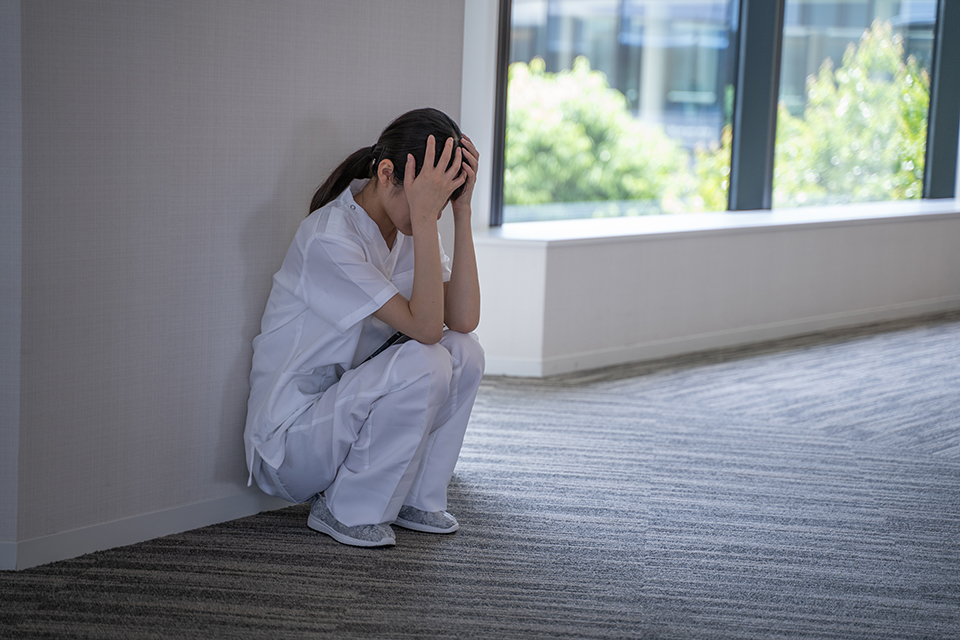
うつ病での休職や退職をずるいと感じる人も少なからずいますが、そういった声を気にして無理してしまっては、より体調が悪くなる危険性があります。
うつ病だと感じたら医師に相談し、身近な人からのアドバイスや家計の状況なども考えながら休職や退職も考えましょう。
あなたの心を守れるのはあなただけしかいません。
これ以上仕事を続けるのは辛いと感じたら、思い切って辞めてしまうのもよいでしょう。
今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。