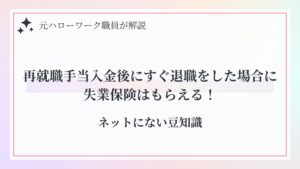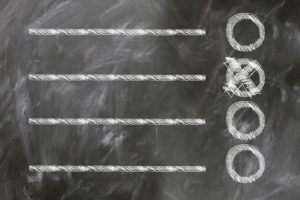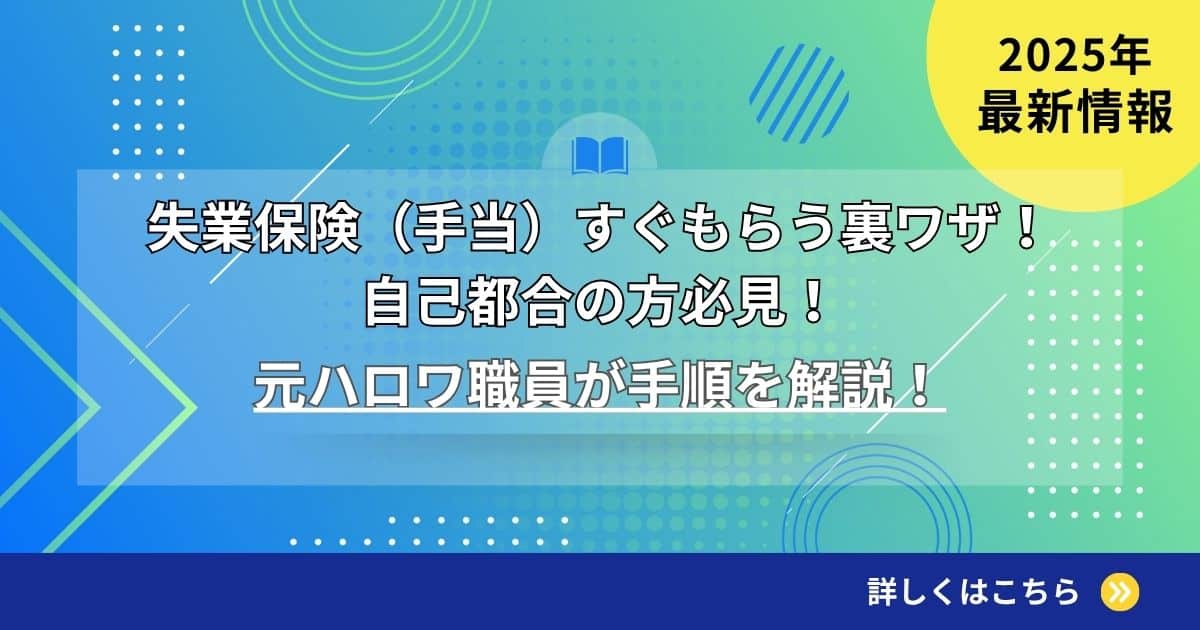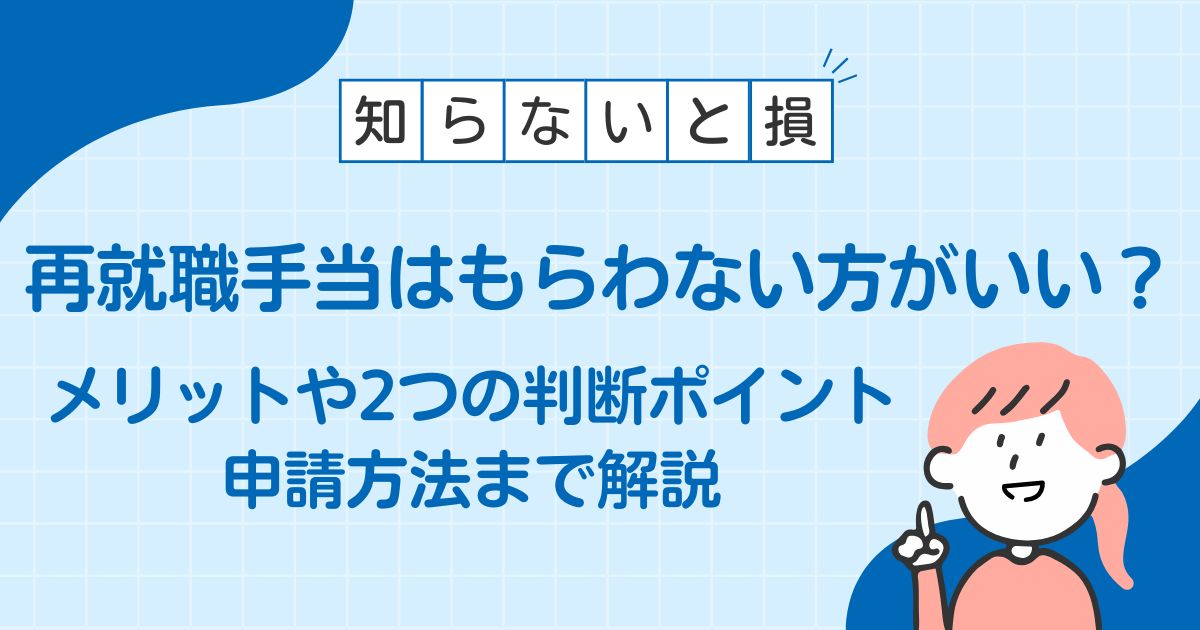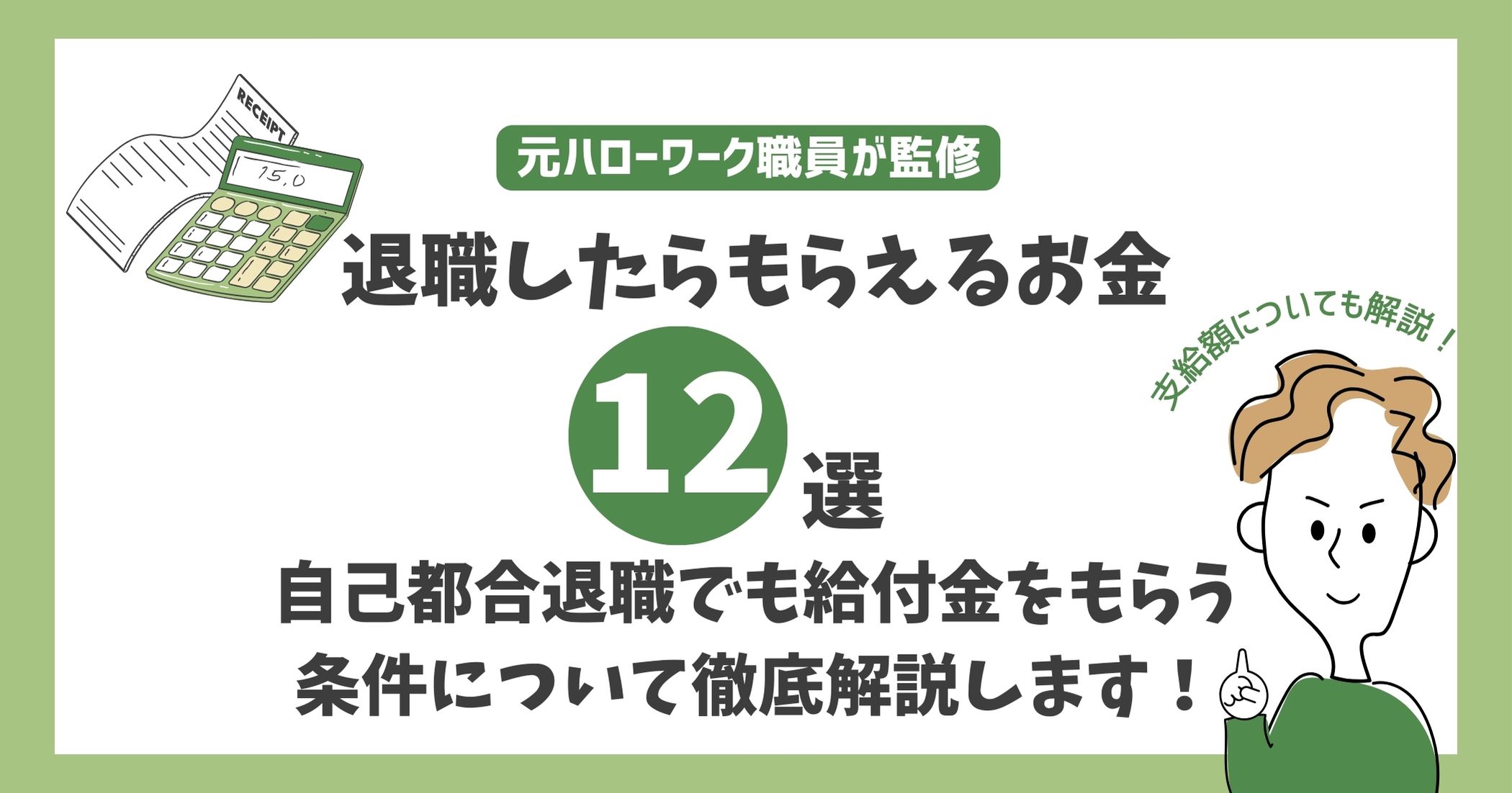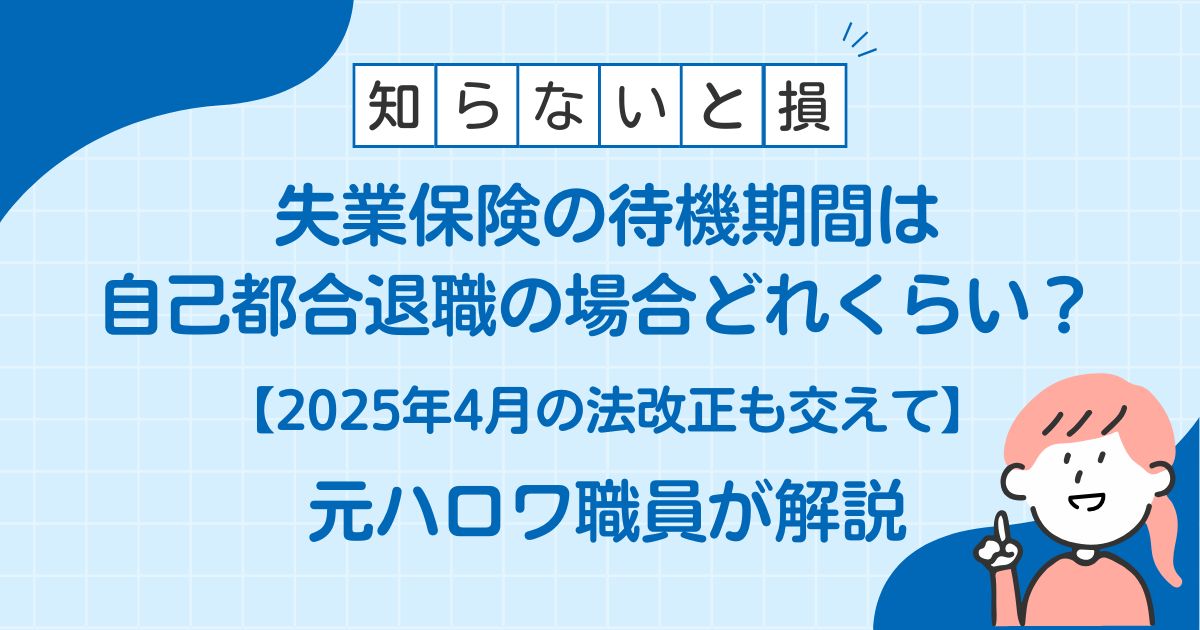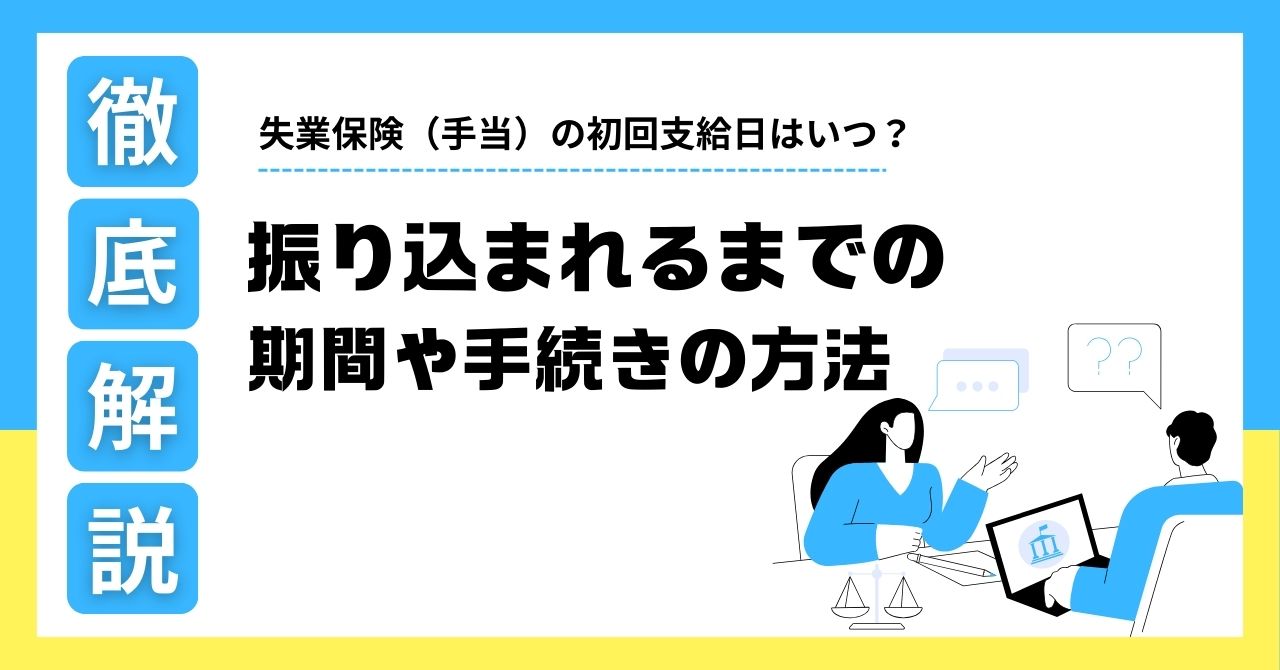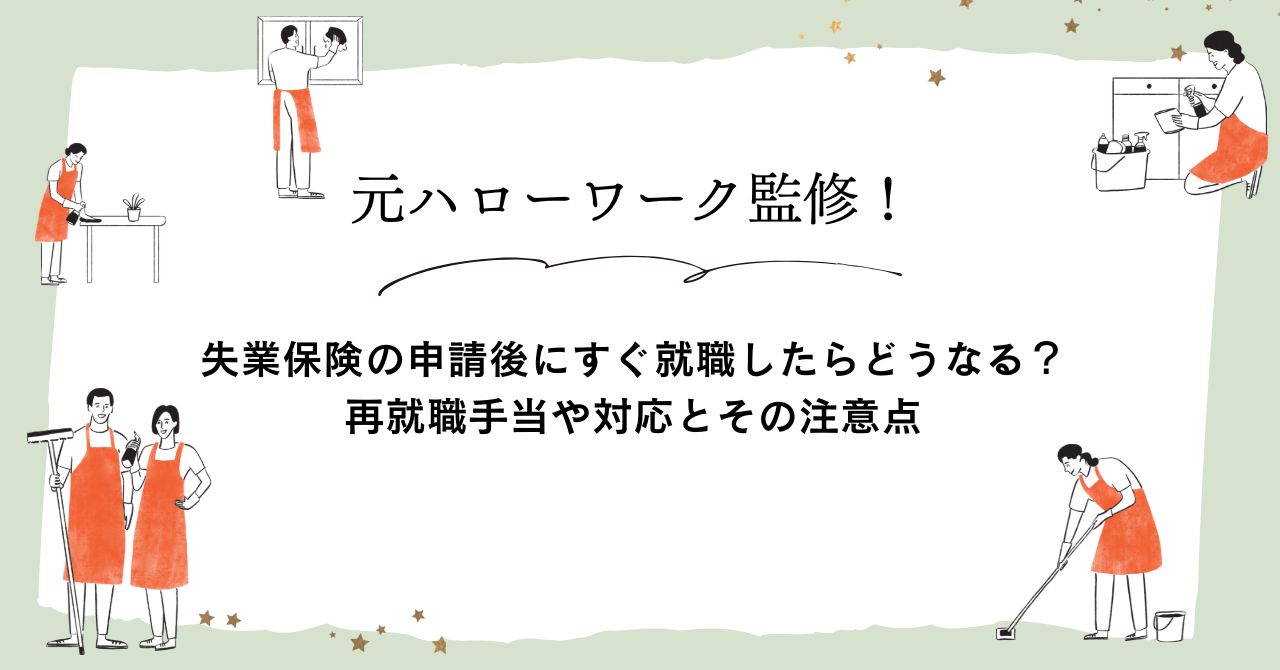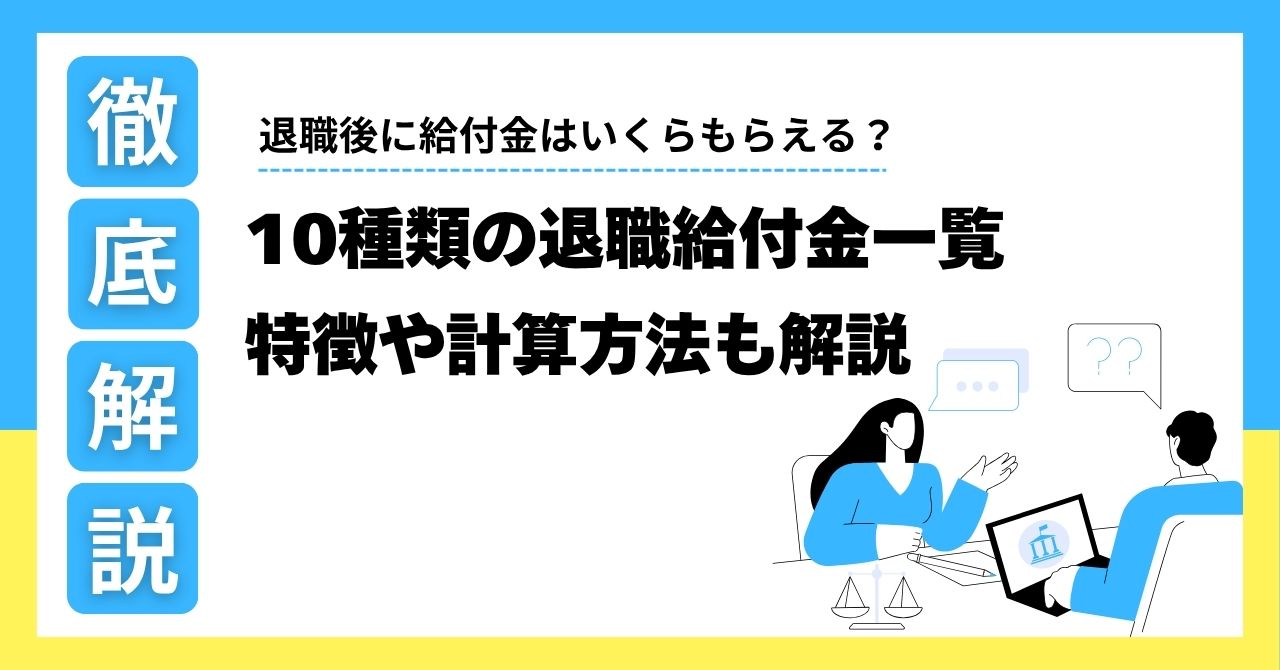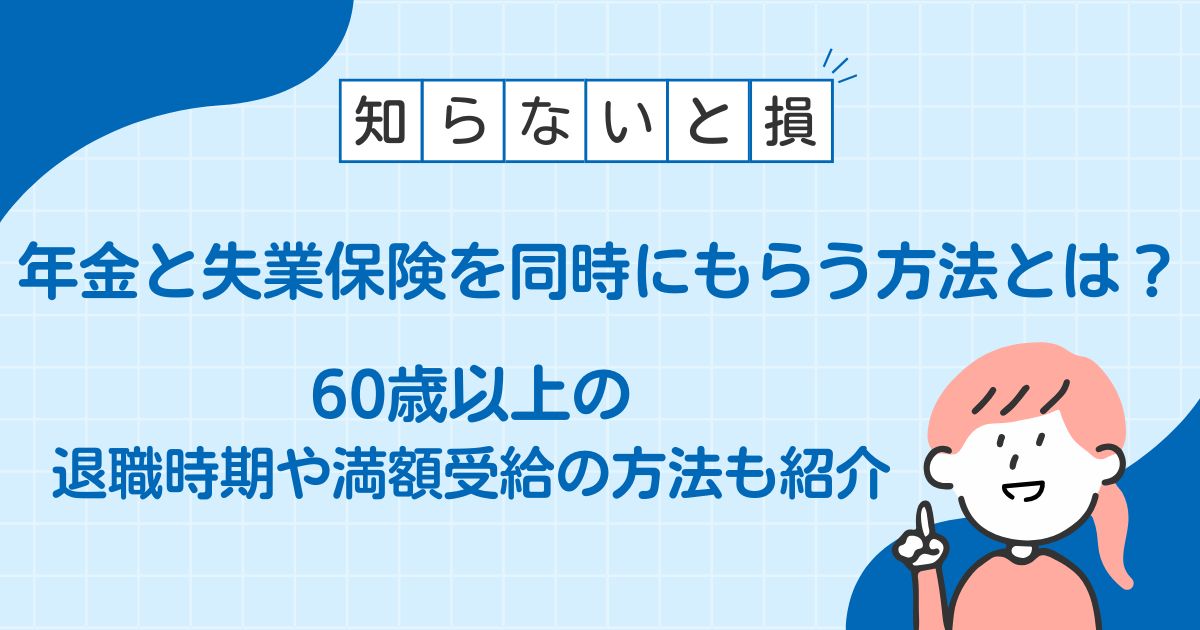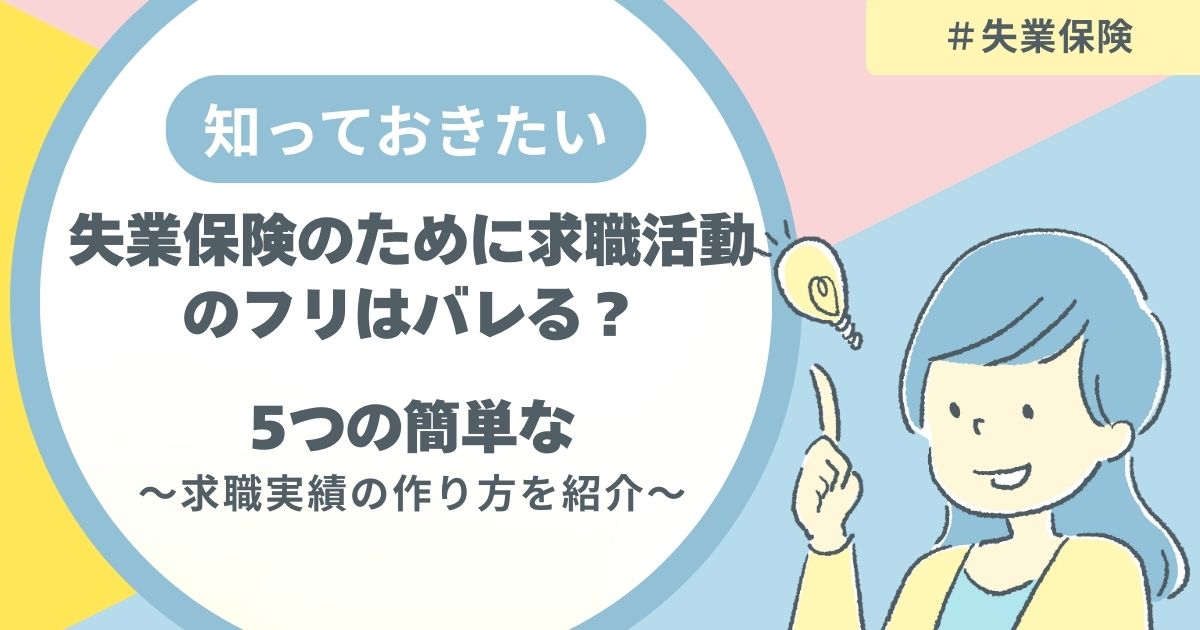- 公務員は失業保険を受け取れないと聞いたが、本当なのか知りたい
- 失業保険の代わりに受け取れる退職手当について詳しく知りたい
- 退職手当の金額が失業保険より少ない場合の対処法が知りたい
公務員を退職しようと検討している方で、上記のように悩んでいませんか?
公務員は基本的に失業保険を受け取れませんが、退職手当であれば受け取れます。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部本記事では、公務員が失業保険を受け取れない理由や、代わりに受給できる退職手当などを詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
また、今すぐ退職手当以外に受け取れる給付金について詳しく知りたい方は、「ヤメル君」に相談するのがおすすめです。
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「ヤメル君」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大1000万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!

【結論】公務員は退職後に失業保険を受け取れない
公務員は「雇用保険法第6条」に基づき、雇用保険の適用対象外とされているため、退職後に失業保険を受け取れません。
失業保険は、雇用保険に加入する一般労働者のための給付金であり、急な失業のリスクが低い公務員には適用されません。
公務員は、失業保険が適用されない代わりに、退職手当が支給されます。
そのため、基本的に公務員は失業保険の対象外と理解しておきましょう。
公務員が例外的に失業保険を受給できる3つのケース

公務員が例外的に失業保険を受給できる3つのケースは、以下のとおりです。
- 期間雇用の公務員の場合
- 準公務員として働いていた場合
- 退職手当が失業保険に満たない場合
原則として公務員は失業保険を受給できませんが、上記3つのケースに当てはまる場合は例外的に失業手当を受け取ることが可能です。それぞれのケースを詳しく確認してみましょう。
期間雇用の公務員の場合
期間雇用の公務員は、雇用保険に加入している場合、退職後に失業保険を受給することが可能です。
通常、公務員は雇用保険法第6条に基づき雇用保険は適用されません。しかし、期間雇用の公務員は非正規雇用として扱われるため、雇用保険の対象です。
ただし、勤続期間が半年以上になると正規雇用とみなされ、失業保険の対象外となるため注意しましょう。
期間雇用の公務員が失業手当を受け取れるのは、あくまで短期間の雇用契約の場合に限られます。
参考:雇用保険法第6条
準公務員として働いていた場合
準公務員として働いていた場合も、雇用保険に加入していれば、退職後に失業保険を受給することが可能です。
具体的には、国立大学法人の職員や日本郵政株式会社の職員などが該当します。
準公務員は雇用保険法の適用事業所で勤務しながら雇用保険料を支払っているため、退職後に雇用保険の失業給付を受け取る権利が発生します。
公務員に準ずる立場でありながら、民間企業の労働者と同様の失業保険制度の恩恵を受けられるのが準公務員の特徴です。
参考:雇用保険法
退職手当が失業保険に満たない場合
公務員が退職時に受け取った退職手当の額が失業保険相当額に満たない場合、「失業者の退職手当」として差額分を受給することが可能です。
通常、公務員は雇用保険の適用対象外ですが、退職手当制度により、失業保険相当額との差額を補填する仕組みが設けられています。
退職手当制度は、公務員が退職後に求職活動を行う際の経済的に支援するのが目的です。ただし、受給には勤続期間や失業状態であることなど、特定の条件を満たす必要があります。
公務員が失業保険を受け取れない理由
公務員が失業保険を受け取れない主な理由は、公務員が労働者ではなく「官公庁の職員」に該当するためです。
失業保険は、急な解雇や倒産のリスクがある労働者の生活を支援する制度で、雇用が安定している公務員は対象外です。
公務員は、原則として終身雇用制が適用され、解雇されるリスクが極めて低いと考えられています。
また、退職後も再就職先が見つかりやすいため、民間労働者向けの失業保険の意義と一致しないと考えられています。
公務員には安定した雇用環境が保障されているため、民間労働者とは異なる支援制度が適用されているのだと理解しておきましょう。
公務員が失業保険の代わりに受け取れる退職手当とは
公務員に失業保険は適用されませんが、退職後には「退職手当」が支給されます。
退職手当は、公務員が一定の条件を満たして退職した際に支給され、失業保険と同様に退職後の生活支援が目的です。
ここでは、退職手当の支給条件と申請方法を詳しく解説します。
公務員の方で退職を検討しているかたは、それぞれ理解しておきましょう。
支給条件
公務員が退職手当を受け取るためには、以下4つの条件を満たす必要があります。
- 勤続期間が原則12ヵ月以上であること
- 退職手当の支給額が失業保険相当額に満たない場合
- 退職日の翌日から1年以内に失業していること
- 求職活動を行っているが、待機日数を超えても再就職が決まらない場合
退職手当は、一定の勤続年数を積み重ねた公務員に対して、退職後の生活を支援する制度です。
退職手当の支給額が失業保険相当額に満たない場合に支給されます。
さらに、退職日の翌日から1年以内に失業していると、退職手当と失業保険相当額の差額を受け取れる場合もあります。
ただし、退職後に再就職が決まっていたり、求職活動を行っていなかったりする場合は、支給対象外となるため注意が必要です。
支給額は、退職時の給与や年齢、退職理由などによって変動します。国家公務員の場合は内閣官房を基準に、地方公務員の場合は各自治体の条例に基づいて、支給額が決定されます。
そのため、退職手当の受け取りを検討している方は、上記の条件を満たしているのか確認しましょう。
参考:内閣人事局|失業者の退職手当の支給要件及び支給額算定基準
申請方法
退職手当を受け取るための申請方法は以下のとおりです。
- 所属していた組織から退職票を取得する
- ハローワークで退職表を提出し、求職の申込みを行う
- 退職手当受給資格証を受け取る
- ハローワークで失業中と認められる
- 退職手当が支給される
上記の方法で退職手当を申請できますが、請求には期限があるため注意が必要です。
支給時期は、通常は申請から1ヵ月程度での振り込みが多い傾向です。
しかし、基本的に退職してから1年以内に申請しなければ、退職手当の受給が難しくなってしまいます。
そのため、提出書類の不備や期限の徒過には十分に注意し、退職手当を受給できるよう、余裕をもって手続きを進めましょう。
参考:内閣人事局|勤続期間が12月以上で国家公務員を退職し失業している方へ
公務員が受け取れる退職手当の金額
公務員が受け取れる退職手当の金額は、以下のように退職した場面により異なります。
- 自己都合退職の場合
- 定年退職の場合
それぞれどのように異なるのか理解していきましょう。
自己都合退職の場合
自己都合退職とは、本人の意思により退職する場合を指し、結婚や育児、介護などの理由も含まれます。
支給率の算定は、「国家公務員退職手当支給率早見表」により決まり、勤続年数が影響します。
例えば、勤続5年の支給率は『2.511』ですが、勤続10年の場合は『5.022』と、支給率は約2倍以上です。
実際の支給額は「退職時の俸給月額×支給率」で求められるため、勤続年数が長いほど、支給される退職手当の額も大きくなります。
ただし、地方公務員の場合は、各自治体の条例によって支給率が異なるため注意しましょう。
定年退職の場合
国家公務員の定年は原則60歳とされ、地方公務員の場合も60歳で定年でしたが、近年では定年の年齢が引き上げられました。
公務員の定年退職の支給率も、「国家公務員退職手当支給率早見表」により勤続年数に応じて設定されています。
勤続35年以上の場合、最高支給率である『47.709』に達し、自己都合退職と同様に勤続年数が長いほど退職手当の額も大きくなります。
実際の支給額は「(退職時の俸給月額×支給率)+調整額」で計算可能です。
そのため、月給50万円の公務員が、35年以上勤務した後に定年退職する場合の退職手当は以下のように求められます。
(月給50万円 × 47.709 ) +調整額 ≒ 約2,385万円
ただし、地方公務員の場合は各自治体の規定に基づいて支給率が設定されるため、上記とは異なります。
なお、定年退職の場合、雇用保険の失業給付は支給されませんが、退職手当の方が大きな金額になります。
公務員の退職手当が失業保険よりも少ない時の対処手順【3STEP】
公務員の退職手当が失業保険よりも少ない時の対処手順は以下のとおりです。
- 差額を受け取れるか確認する
- ハローワークで求職の申し込みを行う
- 退職時の給付金をサポートしてくれる窓口に相談する
退職後の生活を支えるためにも、退職手当の方が少なりそうな方はそれぞれ理解していきましょう。
1.差額を受け取れるか確認する
退職手当の支給額が失業保険相当額を下回るかどうかは、ハローワークで確認できます。
確認する際には、給与や勤続年数、退職理由や失業状況など、詳細な情報が必要です。
そのため、事前に関連書類を準備しておくとスムーズに手続きを進められます。
また、教員などの地方公務員の場合は、勤務先の教育委員会に問い合わせても確認できます。
ただし、差額支給の手続きは、基本的に退職日から1年以内に申請を行わなければ、受給できなくなるため注意しましょう。
2.ハローワークで求職の申し込みを行う
公務員の退職手当が失業保険相当額よりも少ない場合、差額を受け取るためには、ハローワークでの求職申込みが必要です。
申請するためには、ハローワークで「求職申込み証明書」と「失業証明書」の取得が必要です。
また、継続的な就職活動を行い、活動記録を提出しなければ受給できません。
ただし、教員の場合、ハローワークでの申請に加えて、教育委員会での手続きも必要です。
なお、申請するために訪れるハローワークはお住まいの地域により異なるため、事前に調べておきましょう。
失業保険の申請手続きについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

3.退職時の給付金をサポートしてくれる窓口に相談する
公務員の退職手当や失業保険に関する手続きは、複雑な部分も多く、初めて経験する方にとっては戸惑う場合もあると思います。
そのような場合、退職時の給付金に詳しいサポート窓口に相談するのがおすすめです。
サポート窓口では、経験豊富なスタッフが、退職手当や失業保険に関する質問や相談に丁寧に対応してくれます。
また、申請書類のチェックや提出代行など、手続きをスムーズに進めるための支援も行っています。
支援サービスは全国対応しており、勤務先の地域に関わらず相談可能です。
退職時の給付金に関して、少しでも不安や疑問があれば、早めにサポート窓口に相談してみましょう。
なお、公務員の退職時の給付金に関して、専門家のサポートを受けたい方は、ぜひ「ヤメル君」をご利用ください。
\退職後に最大1000万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
公務員が転職活動で利用できる4つの制度

公務員の転職活動を支援する制度は、以下の4つが代表的です。
- 官民人材交流センターによる再就職支援
- 国家戦略特区の退職特例制度
- 求職者支援制度
- 再任用制度
それぞれの制度の特徴を、詳しく見ていきましょう。
官民人材交流センターによる再就職支援
官民人材交流センターによる再就職支援は、国家公務員の早期退職者や分限免職者を対象に、民間の再就職支援会社を活用して再就職活動をサポートする制度です。
官民人材交流センターは、国家公務員法改正に基づき設立され、公務員の再就職支援を一元的に行う機関です。
従来の各省庁による斡旋を廃止し、民間の専門的な再就職支援会社と連携することで、幅広い業種や地域への転職を支援しています。
国家戦略特区の退職特例制度
国家戦略特区の退職特例制度は、国家公務員が設立から5年未満のスタートアップ企業に転職し、3年以内に再び国家公務員に復職した場合、退職前後の勤続年数を通算して退職手当を算定する制度です。
同制度は、スタートアップ企業が成長初期に直面する「質の高い人材確保」の課題を解決するとともに、官民間の人材流動性を高めることを目的としています。
また、公務員が持つ高度な知見や経験をスタートアップで活用できるよう、再び公務員に戻る際の経済的リスクを軽減する狙いもあります。
求職者支援制度
求職者支援制度は、公務員を退職した後に失業保険を受給できない場合でも、無料で職業訓練を受講しながら、一定の条件を満たせば月10万円の職業訓練受講給付金を受け取れる制度です。
求職者支援制度を利用すれば、再就職や新たなキャリア形成に必要なスキルを習得しながら、生活費の一部を確保できます。
例えば、公務員として働いていた方が退職後にIT関連のスキルを身につけたい場合、求職者支援制度を利用してプログラミングやデータ分析などの訓練コースを無料で受講できます。
再任用制度
再任用制度は、公務員が定年退職後も希望すれば再び公務に従事できる制度です。
同制度は高齢化社会に対応し、公務員として培った知識や経験を引き続き活用することを目的としています。
また、公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられたことにともない、退職後の生活基盤を安定させるためにも導入された背景も存在します。
なお、再任用制度ではフルタイム勤務や短時間勤務など、任意の雇用形態を選択することが可能です。
参考:公務への再任用
公務員の受け取れる給付金が気になる方は「ヤメル君」がおすすめ
公務員は労働者ではなく「官公庁の職員」とされ、雇用保険の対象者に該当しないため失業保険を受給できません。
ただし、公務員であっても、国立大学法人や日本郵政株式会社などの準公務員として雇用保険適用事業所で勤務していた場合は、退職後に失業保険を受け取れます。
そのため、公務員が退職する際は退職手当を受け取るのが一般的です。
退職手当の支給額は、自己都合退職と定年退職、勤続年数や退職時の給与などにより変動します。
また、退職手当が失業保険よりも支給額が少ない場合には、以下3つの方法で対処します。
- 差額を受け取れるか確認する
- ハローワークで求職の申し込みを行う
- 退職時の給付金をサポートしてくれる窓口に相談する
サポート窓口は全国対応し、お住まいの地域に関係なく相談できます。
また、今すぐ退職手当以外に受け取れる給付金について詳しく知りたい方は、「ヤメル君」に相談するのがおすすめです。
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「ヤメル君」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大1000万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!