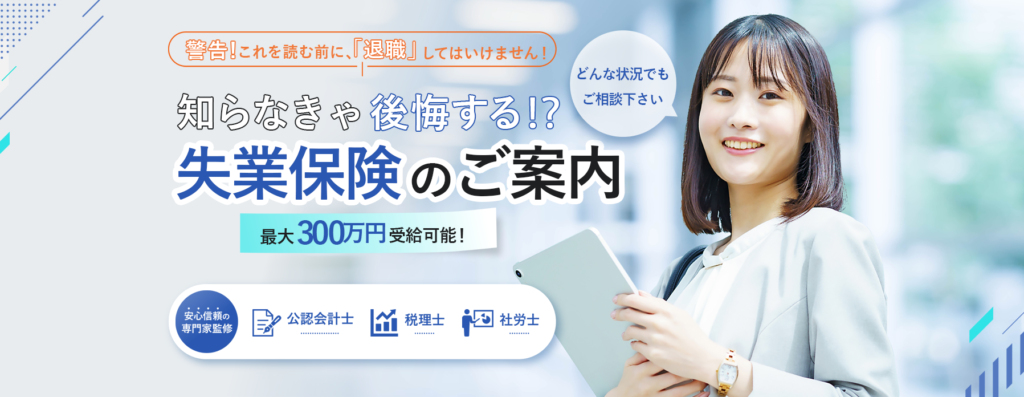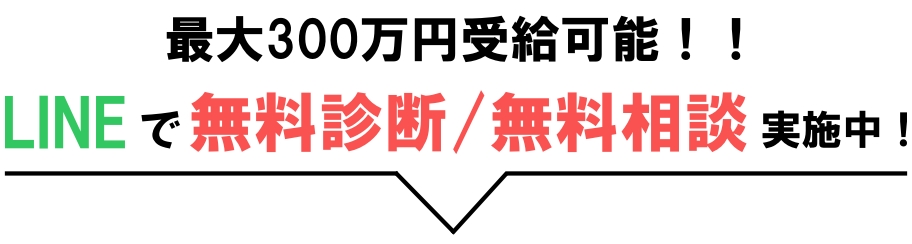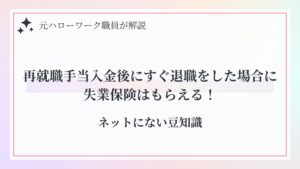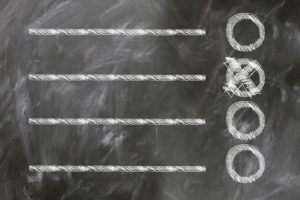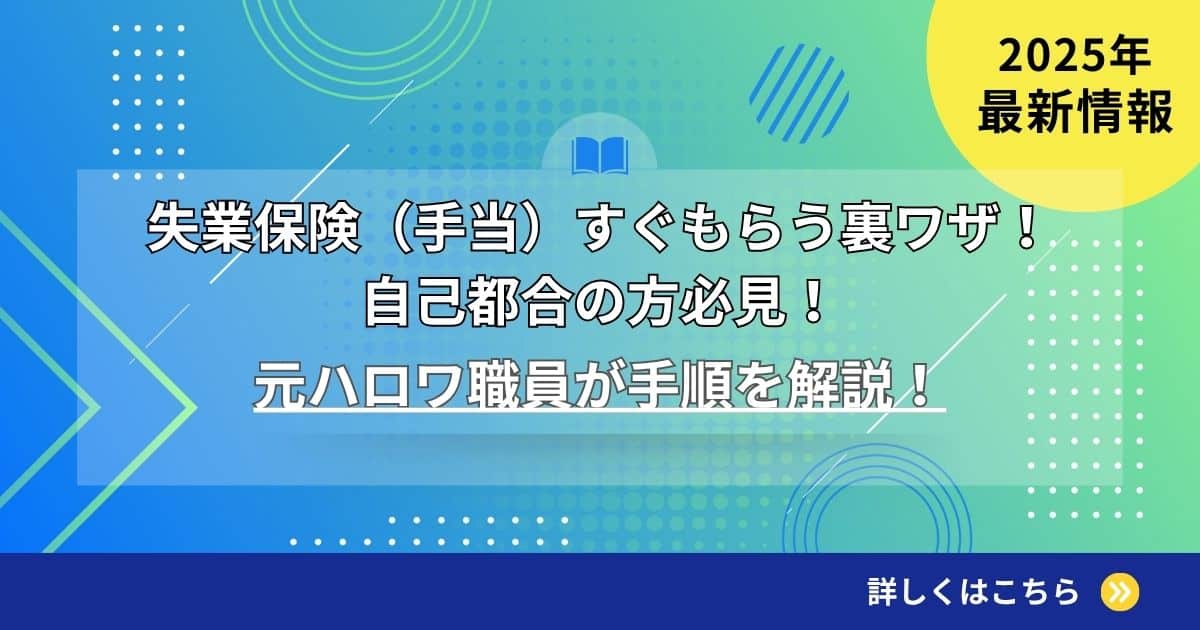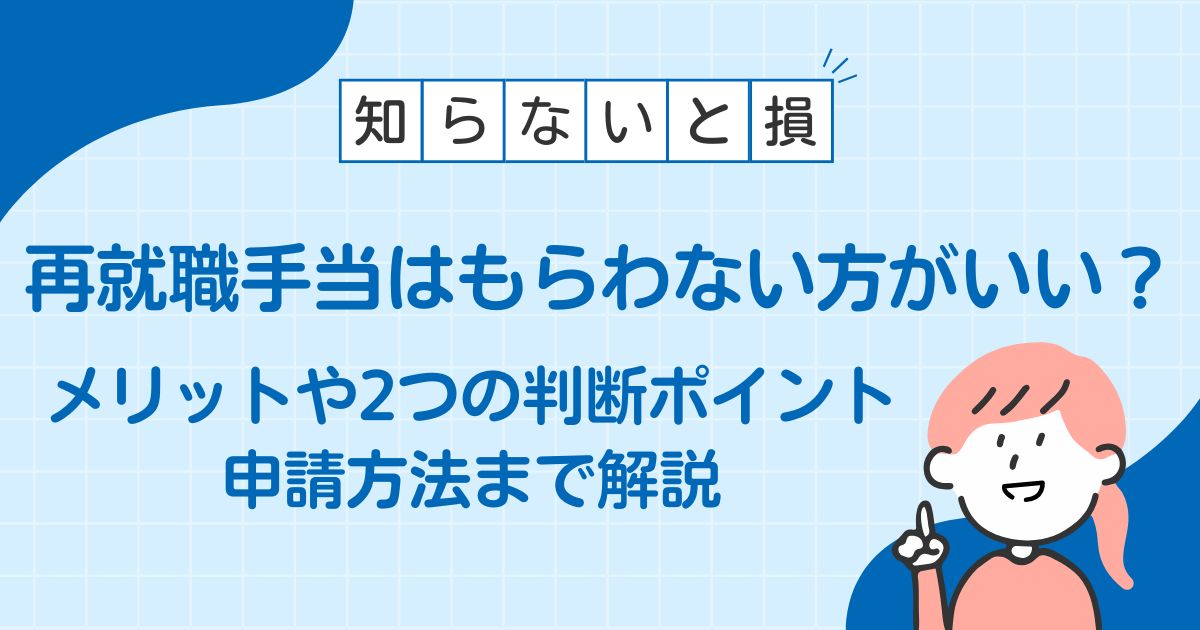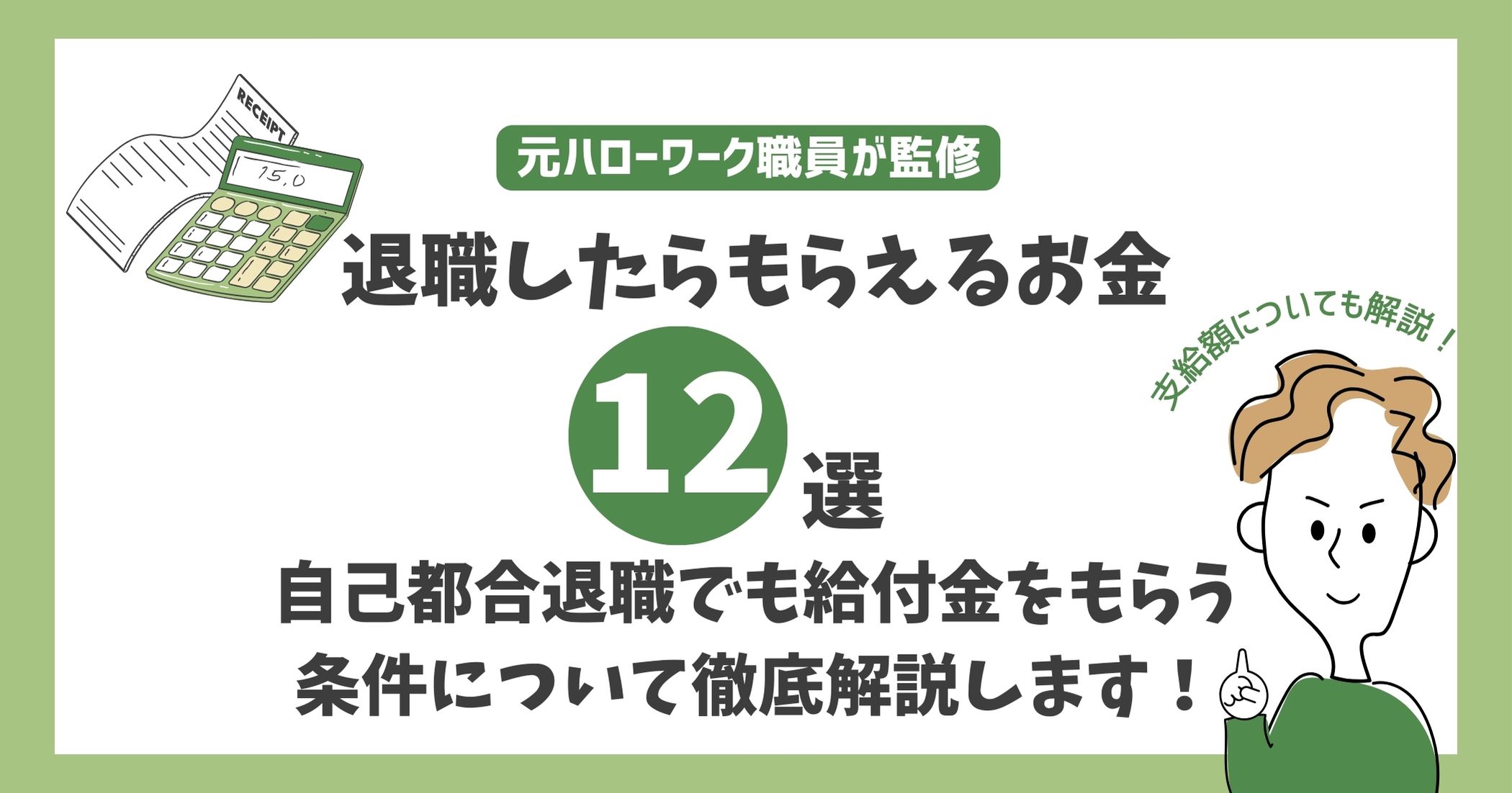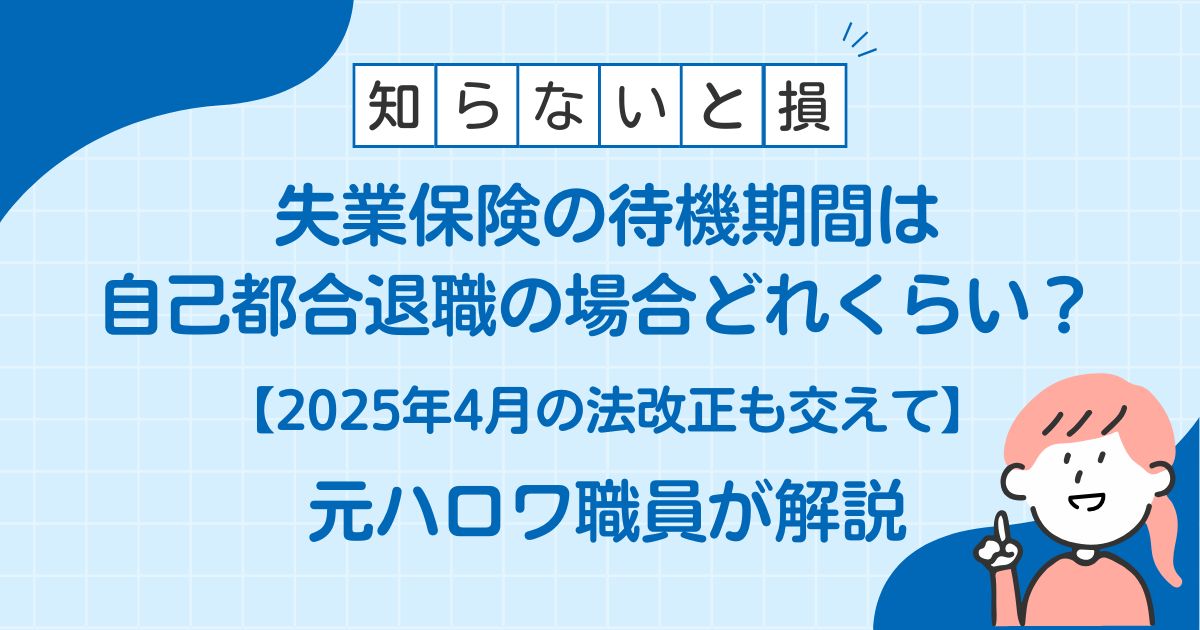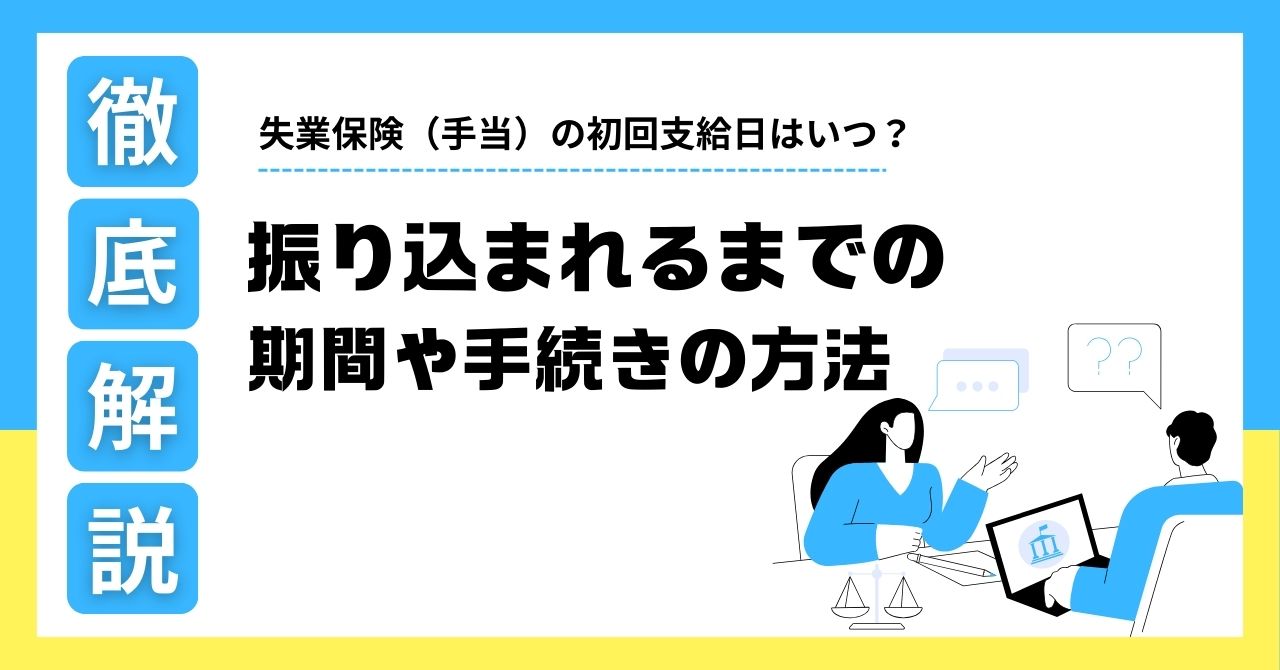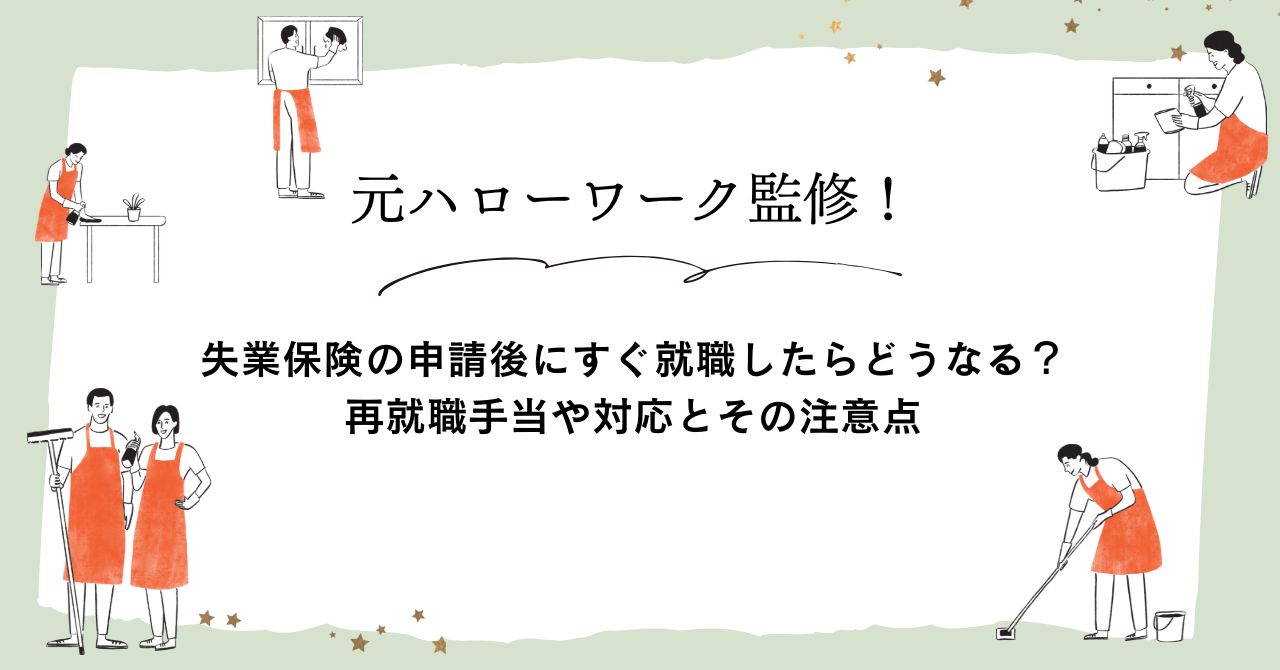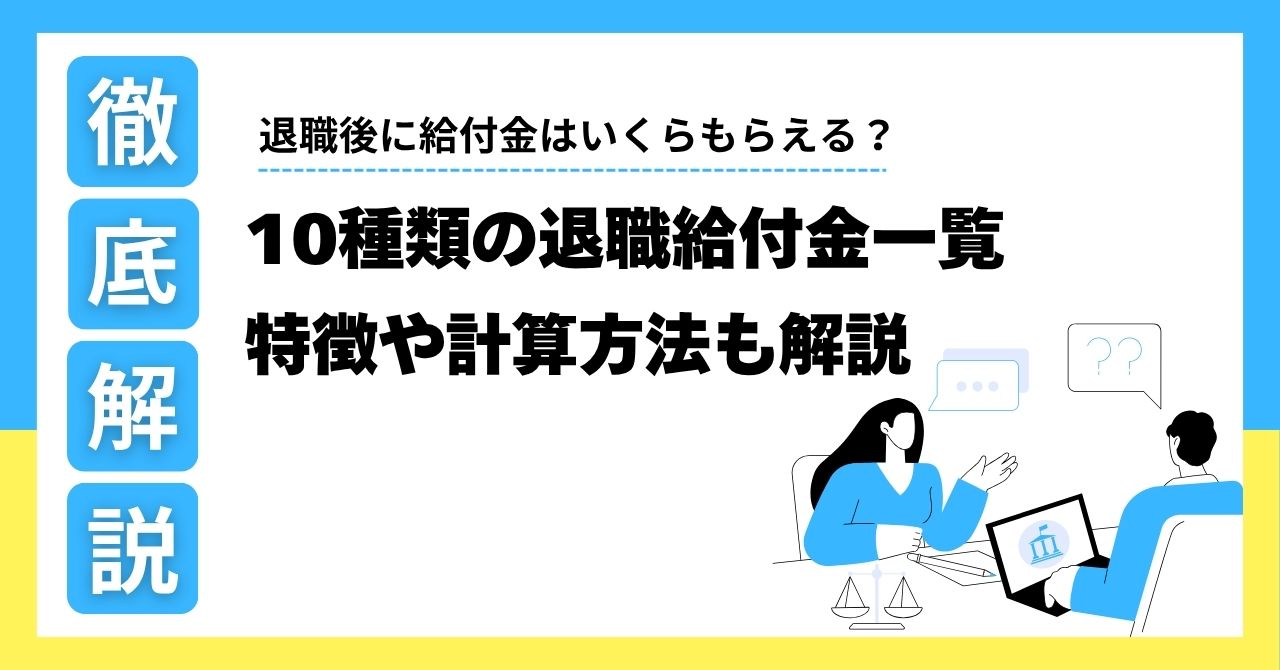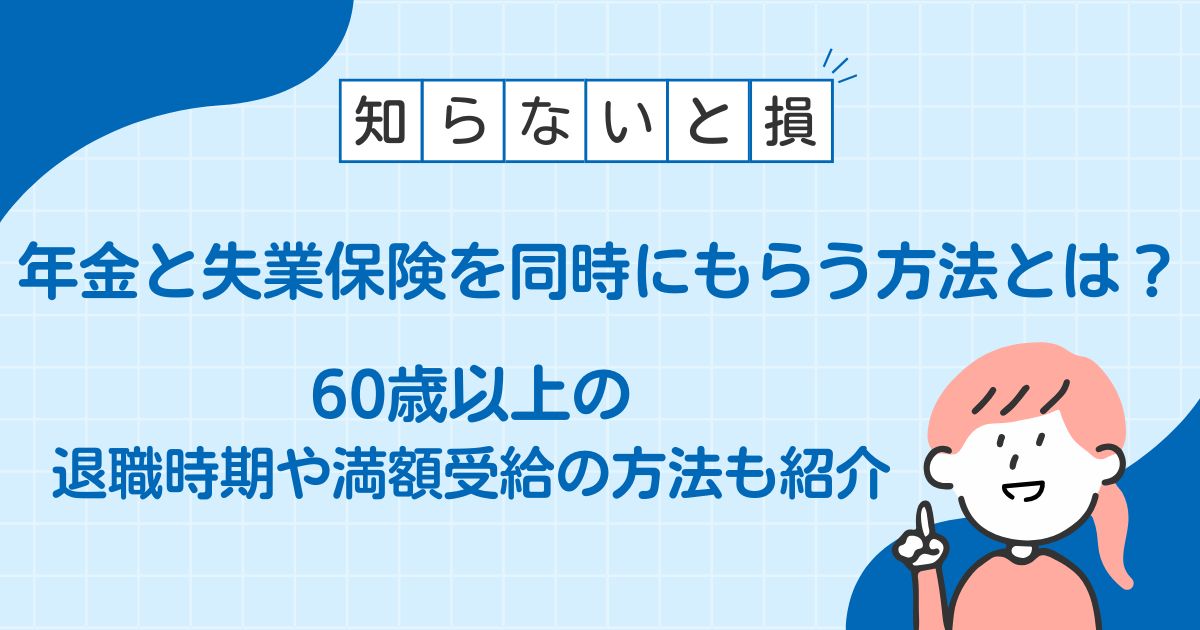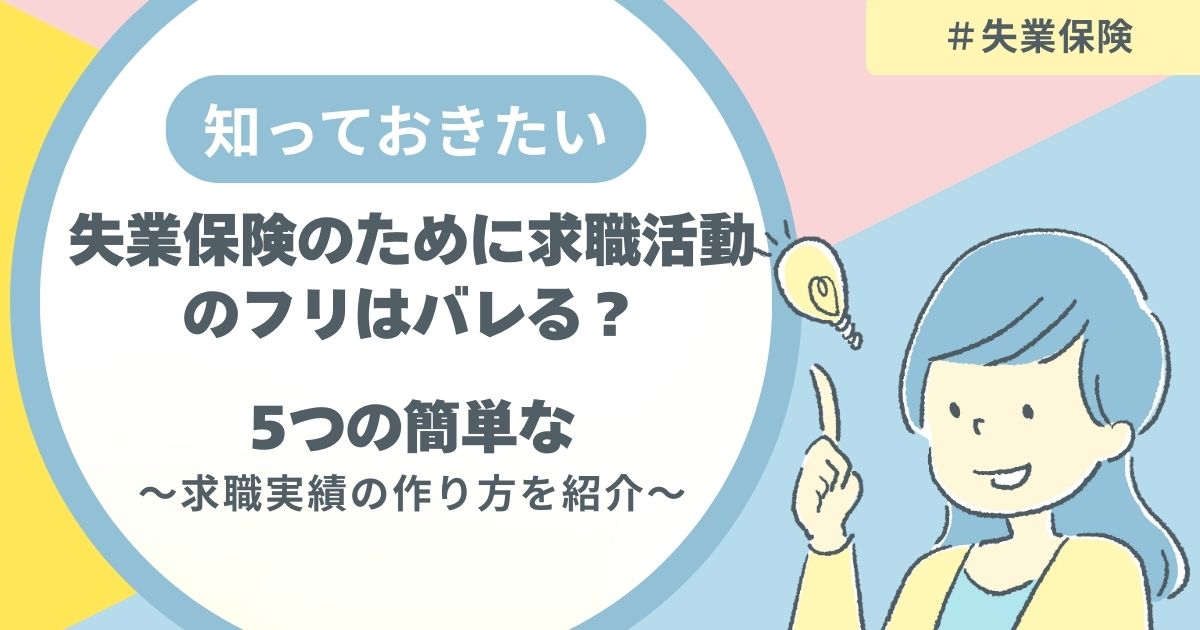失業保険を受け取る際に以下のようにお悩みではありませんか。
「失業保険の求職活動実績は、ハローワークの職業相談だけでも大丈夫?」
「相談する時に気をつけるべきことはあるの?」
本記事では、失業保険の求職活動実績での職業相談の位置づけや、相談可能な内容を詳しく解説します。
本記事を読むことで、求職活動実績を作る方法と職業相談の活用法が分かります。これから求職活動実績を作ろうと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、退職に関するご相談を受け付けています。
退職に関する些細なお悩みでも丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

失業保険は職業相談だけでも実績を作れる?
失業保険を受け取るには、ハローワークで「求職活動実績」を作る必要があります。実績は、職業相談を受けると、簡単に作成が可能です。
実際、失業認定期間中に複数回の職業相談を活用し、じっくり就職先を探す人もいます。職業相談のみで実績を作っても、就職意欲が疑われる心配はほとんどありません。
確実に求職活動を進めたい方は、ハローワークの職業相談を積極的に利用し、実績をしっかり積み重ねていくのがおすすめです。
失業保険の受給条件とは?
失業保険を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職する前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上あること(倒産や解雇など特定の理由で退職した場合は、1年間で6ヵ月以上あれば対象)
- 働く意欲と能力があり、積極的に仕事を探しているのに就職できていない状態であること
- 積極的に就職活動を続けているにも関わらず、就職にいたっていない状況であること
上記の条件を満たしていても、以下のような状態では原則として受給できません。
- 病気や怪我で、すぐには働けない状態にある
- 妊娠・出産・育児のため、すぐに働き始めることが難しい
- 定年退職後で、しばらく休養したいと考えている
- 結婚を機に家事に専念し、当面は働く予定がない
受給を考えている方は、以下から詳細を確認できます。
参考:基本手当について
失業保険の受給条件に関して、具体的に知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

求職活動実績として認定されない3つのケース
ここでは、求職活動実績として認定されにくい主な3つのケースを解説します。
- インターネット上で求人検索・求人サイト登録を行った
- 派遣会社への登録を行った
- 友人・知人に仕事の紹介をしてもらった
上記の活動がなぜ実績として認められにくいのか、詳しく見ていきましょう。
インターネット上で求人検索・求人サイト登録を行った
求人サイトで情報を見たり、サイトへ登録したりしただけでは、基本的に求職活動実績として認められません。
ハローワークが認めている民間の職業紹介サービスや派遣会社を利用した場合も同じです。実績として扱われるには、単なる情報収集ではなく、就職相談や求人への応募など、実際の行動が必要です。
ただし、ハローワークの施設内で求人検索を行い、窓口で相談をした場合は、実績として認められる場合があります。
派遣会社への登録を行った
派遣会社に登録しただけでは、求職活動実績にはなりません。
登録だけではなく、派遣会社の担当者と具体的な仕事内容に関して相談したり、仕事の紹介を受けたりする行動が必要です。
派遣会社への登録は、求人サイトへの登録と同じ扱いになる場合が多く、実績として認められるには、担当者とのやり取りのような具体的な活動を示す必要があります。
実際に仕事の紹介や面接への進展があれば、求職活動実績として扱われる場合があります。
友人・知人に仕事の紹介をしてもらった
友人や知人から仕事を紹介された場合でも、事実を客観的に証明するのは難しいため、通常は求職活動実績にはなりません。
厚生労働省の基準では、「客観的に確認できる求職活動が必要」とされており、誰が見ても明らかに仕事を探しているとわかる行動が求められます。
ただし、紹介をきっかけにして実際に企業の面接を受けた場合は、具体的な行動があるため、求職活動実績として認められる場合があります。
求職活動実績として認められる活動の詳細は、以下のサイトをご覧ください。
参考:求職活動実績とは
ハローワークの職業相談で相談できること
ここではハローワークの職業相談で、相談できる3つの項目を解説します。
- 求職活動の進め方や適職の見つけ方に関する相談
- 応募書類の書き方や面接対策に関する相談
- 職業訓練に関する相談
上記の相談を活用し、より自分に合った仕事探しや効果的な選考対策を進めましょう。
求職活動の進め方や適職の見つけ方に関する相談
職業相談では、求職活動の進め方や、自分に合った仕事の探し方を相談できます。初めての就職活動や久しぶりに再就職を目指す方にとって、何から始めればよいのか不安に感じることは少なくありません。
また、自分一人で適職を判断するのは難しい場合があります。ハローワークの職員は、これまでの職歴やスキルなどをもとに、一人ひとりの状況に合わせたキャリア相談を行ってくれます。
相談を通じて、自分では気付かなかった新しい仕事の可能性に出会える可能性もあります。
応募書類の書き方や面接対策に関する相談
職業相談では、応募書類の作り方や面接対策の相談も可能です。再就職するためには、これまでのスキルや経験だけでなく、応募書類の内容や面接での受け答えも合否を左右する要素です。
職業相談では、履歴書や職務経歴書の書き方を教えてもらえるほか、添削もお願いできます。模擬面接を通じて面接練習のサポートも受けられるので、安心して面接に挑めるでしょう。
職業訓練に関する相談
新しいスキルを身につけて別の職種に挑戦したい方や、ブランクがあって復職に不安を感じている方にとって、職業訓練は役立つ制度です。
求職活動には、求人への応募や面接だけでなく、就職に必要なスキルを学ぶことも含まれます。職業相談を利用すれば、どのような職業訓練コースがあるのか、希望する仕事に活かせるスキルや資格が学べるコースは何かなどの情報も教えてもらえます。
相談では、職員が希望や状況を確認し、条件に合う訓練コースを案内してくれます。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、退職に関するご相談を受け付けています。
退職に関する些細なお悩みでも丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ハローワークで職業相談をする際の流れ【3STEP】
職業相談を利用する際の手順を、3つのステップで解説します。
- 求職者登録をしてハローワークカードを受け取る
- 相談窓口に行き担当者に相談する
- 雇用保険受給資格者証にハンコをもらう
上記の流れを事前に把握しておけば、当日の手続きが円滑に進みます。
1.求職者登録をしてハローワークカードを受け取る
初めて職業相談をする場合、まず求職者登録を行い「ハローワークカード」を受け取ります。カードがあれば、次回以降、受付で提示するだけで相談窓口や求人情報検索端末をスムーズに利用可能です。
なお、求職者登録時には、職務経歴や希望条件などを記入する求職申込書を作成します。
2.相談窓口に行き担当者に相談する
ハローワークカードを受け取ったら、相談窓口へ向かいましょう。
総合受付などで職業相談をしたい旨を伝えると、番号札を渡されるか、直接相談ブースへ案内されます。順番が来たら指定された窓口で相談を開始し、仕事探しの悩みや応募書類の添削依頼など、具体的な内容を伝えます。
雇用保険を受給中または手続き中の場合は、「雇用保険受給資格者証」を持参し、相談前に担当者に提示しましょう。
3.雇用保険受給資格者証にハンコをもらう
職業相談が終了したら、最後に「雇用保険受給資格者証」に確認のハンコを押してもらいます。ハンコが、職業相談を行った求職活動実績の証明となります。
ハンコをもらい忘れると、実績として認められない可能性があるため、必ず確認しましょう。
なお、1日に複数回相談しても、ハンコは1回分にしかならないため、複数の実績が必要な場合は、日をあらためて相談する必要があります。
求職活動実績として認められる活動の詳細は、以下のサイトから確認ができます。
参考:求職活動実績とは
ハローワークで職業相談をする際に注意すべき4つのポイント
ここでは、職業相談を利用する際に、気をつけるべき4つのポイントを解説します。
- 事前に相談内容を考えておき質問を使いまわさない
- 職業相談を経て求人に応募する際は辞退しない
- 失業認定日当日の職業相談は次回の実績になる
- 職業相談以外で求職活動実績を作る方法も検討しておく
上記のポイントを押さえ、スムーズかつ確実に求職活動実績を積み重ねましょう。
事前に相談内容を考えておき質問を使いまわさない
職業相談を受ける際は、事前に相談内容を整理し、同じ質問を繰り返さないようにしなければいけません。
職業相談で実績を作るのは可能ですが、相談内容が記録されている場合は質問の繰り返しが目立つ可能性があります。
毎回同じような内容ばかり話していると、担当者に就職意欲がないと疑われる場合があります。
求人内容に関する具体的な質問や、履歴書や職務経歴書の添削依頼など、状況に合った相談を意識しましょう。
職業相談を経て求人に応募する際は辞退しない
職業相談を通じて求人の紹介を受け、応募する場合は、原則として面接の辞退は避けましょう。
企業と面接日を調整した時点で、企業側も面接の準備を進めています。特別な事情がない限り面接をキャンセルすると、企業にも迷惑がかかります。
応募の意思がないのに実績を作るためだけに求人を紹介してもらったと判断されると、求職活動実績として認められない可能性があるので注意が必要です。
失業認定日当日の職業相談は次回の実績になる
失業認定日の当日に職業相談を受けた場合、次回の失業認定期間での実績として扱われます。
そのため、認定日当日の相談は、当月の認定には基本的に含まれません。
就職活動の実績が足りない場合は、失業保険を受給できない場合があるため、認定日前には条件を満たしているのか確認しておく必要があります。
もし、認定期間内の実績が足りない場合は、認定日より前に職業相談を受けましょう。
職業相談以外で求職活動実績を作る方法も検討しておく
求職活動の実績を作る方法は、職業相談だけではありません。職業相談の実績を作るのが大変な場合は、以下の手段も有効です。
- 求人への応募
- ハローワークや関連機関が開催するセミナーへの参加
- 民間の職業紹介機関での相談やセミナーへの参加
- 再就職に役立つ資格試験の受験
上記を職業相談と組み合わせると、スムーズに実績を積み上げられます。
なお、自宅からでも求職活動実績を作る方法を考えている方は、以下の記事を参考にしてください。
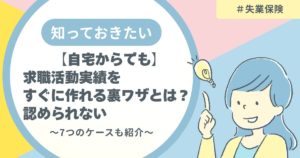
失業保険に関する相談は「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
失業保険の受給には、職業相談が求職活動実績として認められます。ただし、相談内容を事前に考え、毎回同じ質問を繰り返さないようにしましょう。
また、求人への応募やセミナー参加、資格試験の受験など、他の活動も組み合わせると、スムーズに実績を積み上げられます。
職業相談を有効活用し、求職活動を円滑に進めましょう。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、退職に関するご相談を受け付けています。
退職に関する些細なお悩みでも丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。