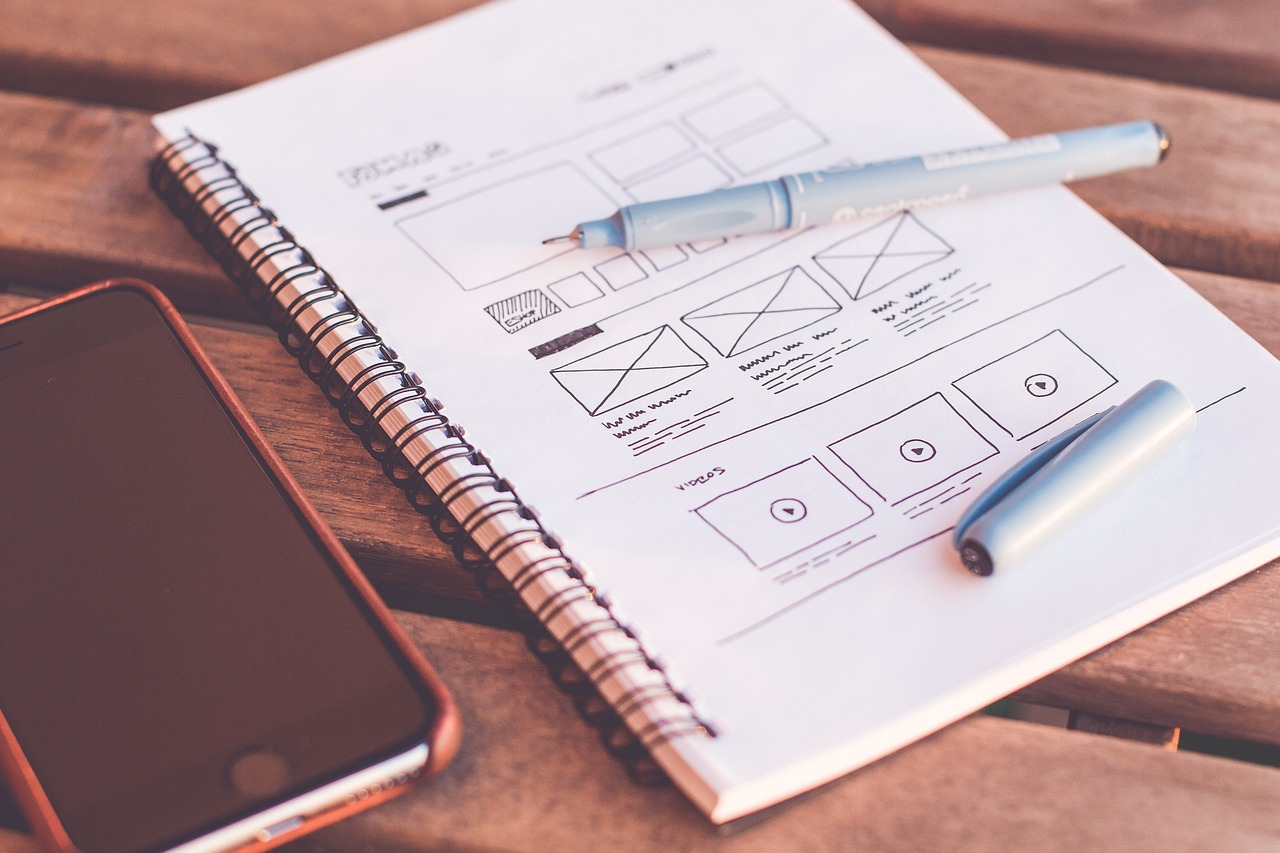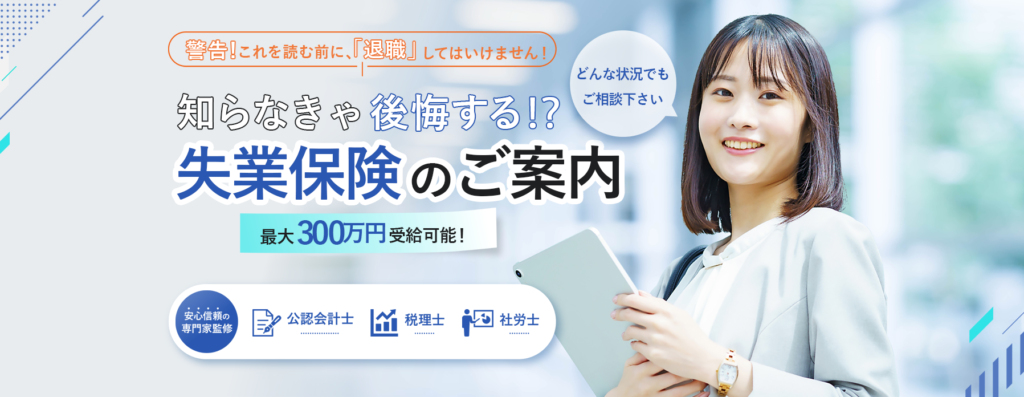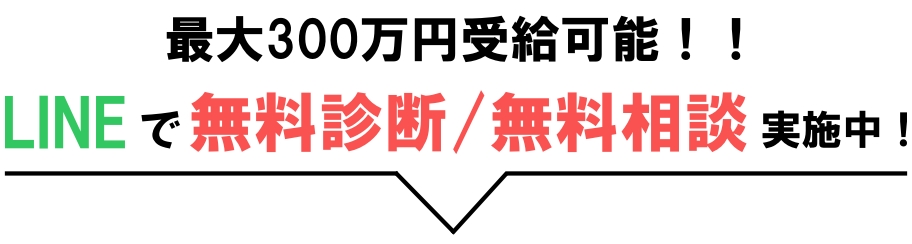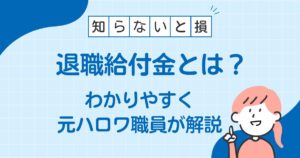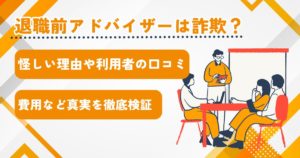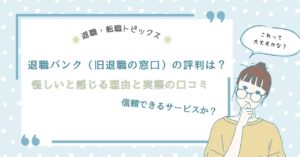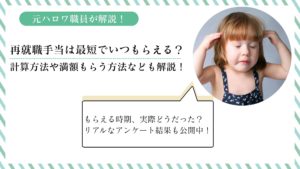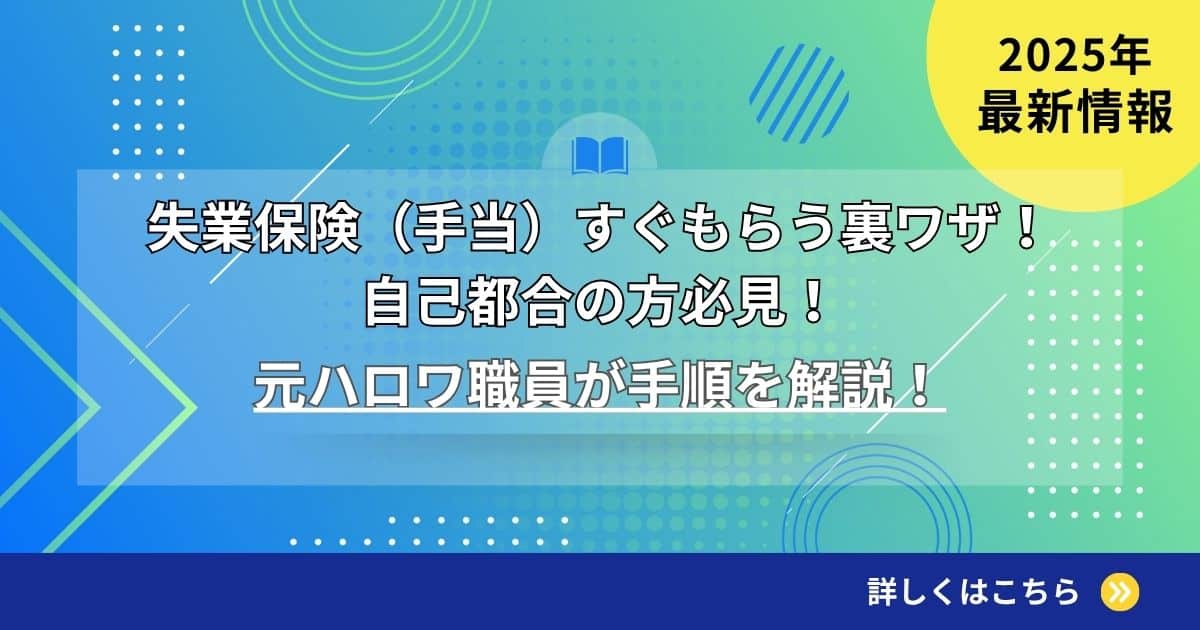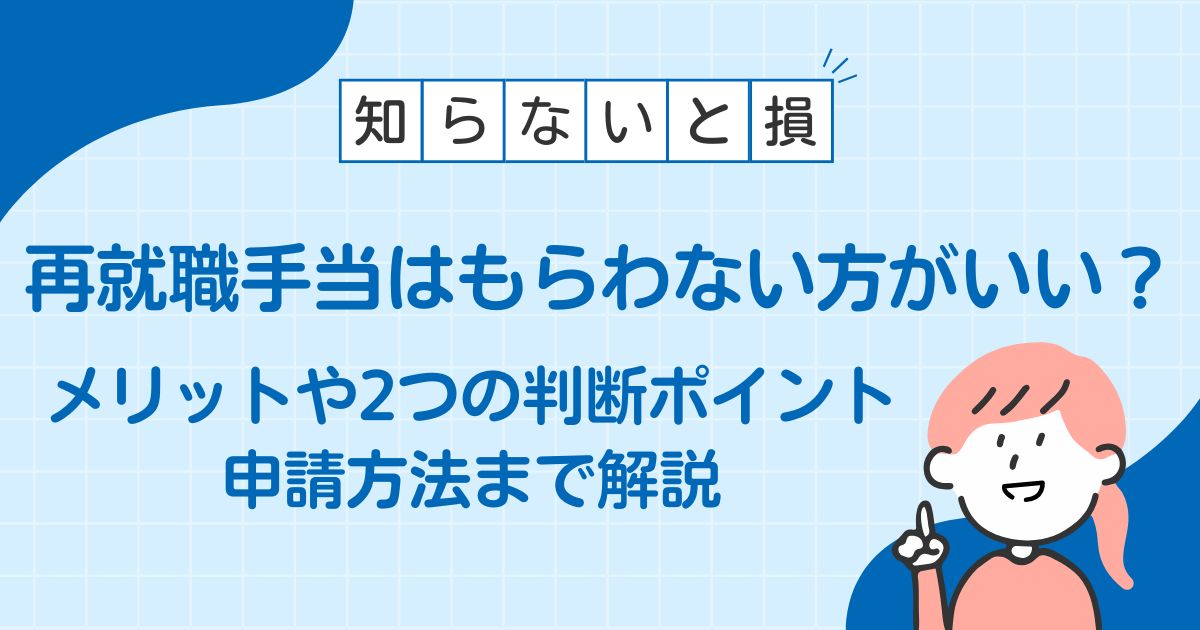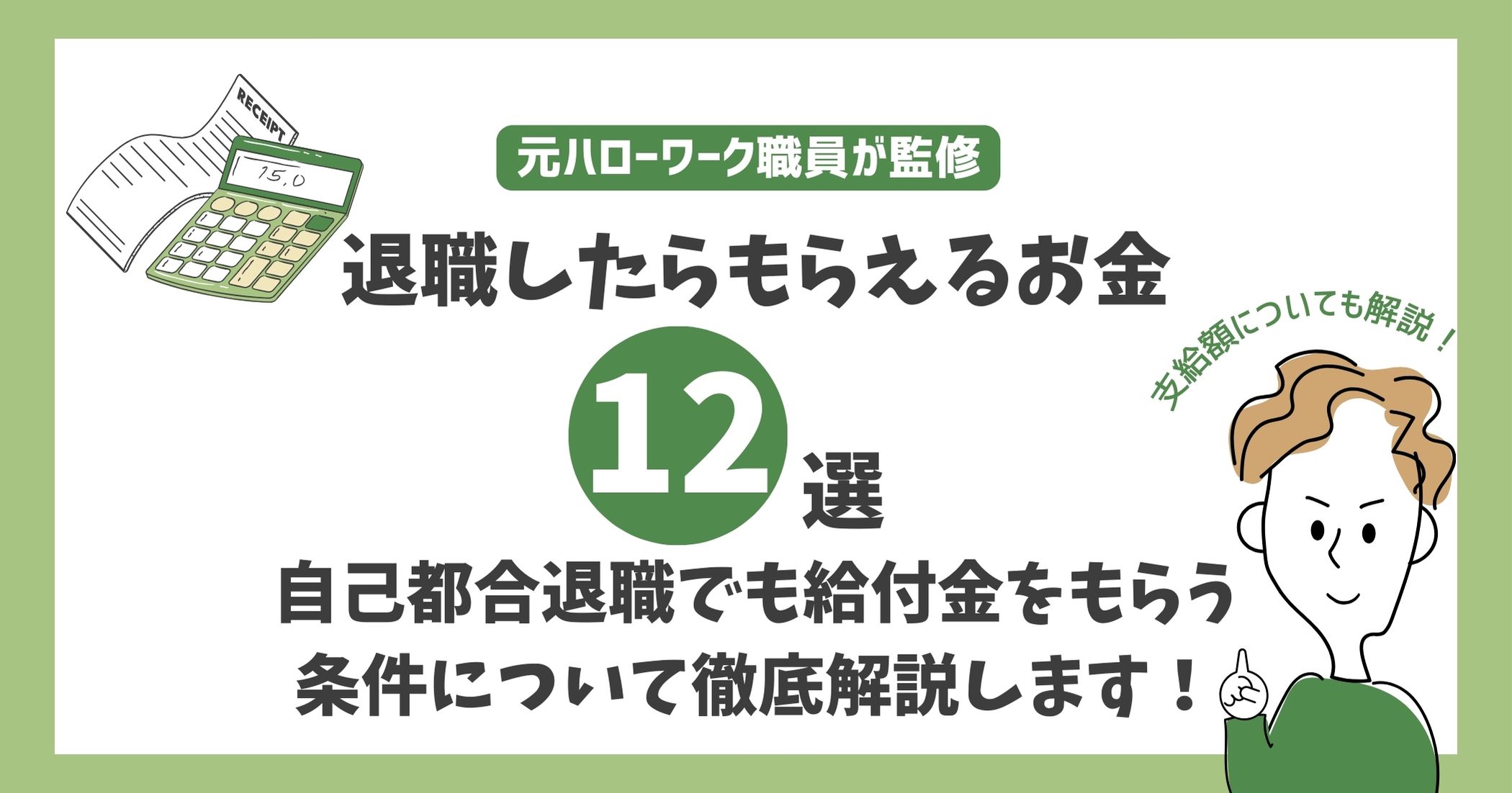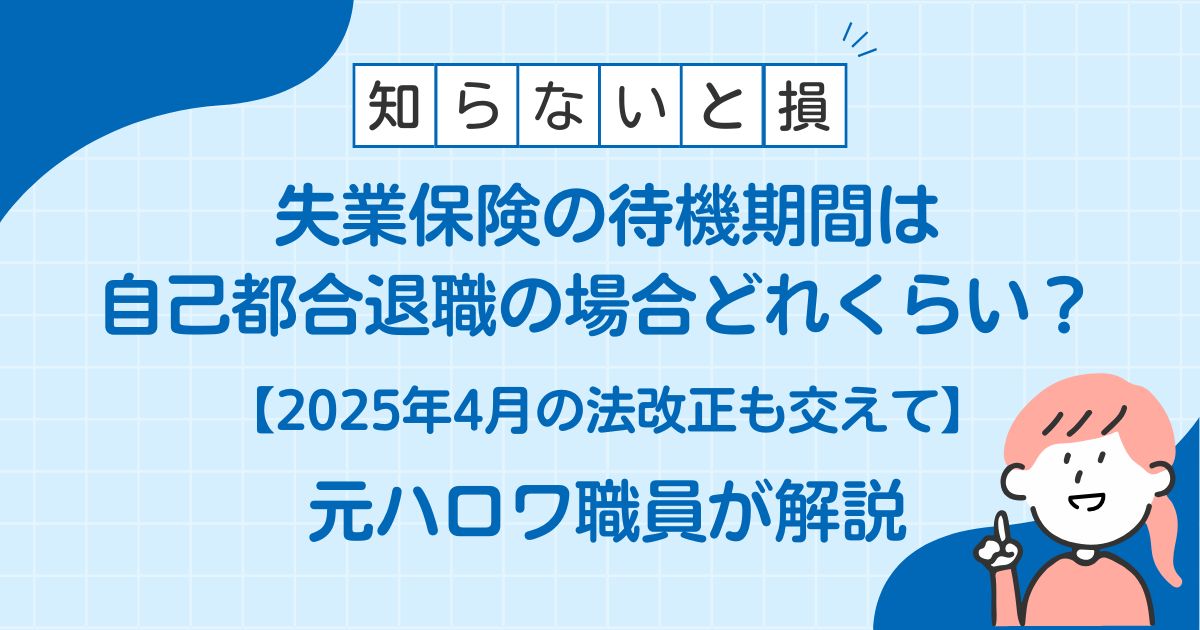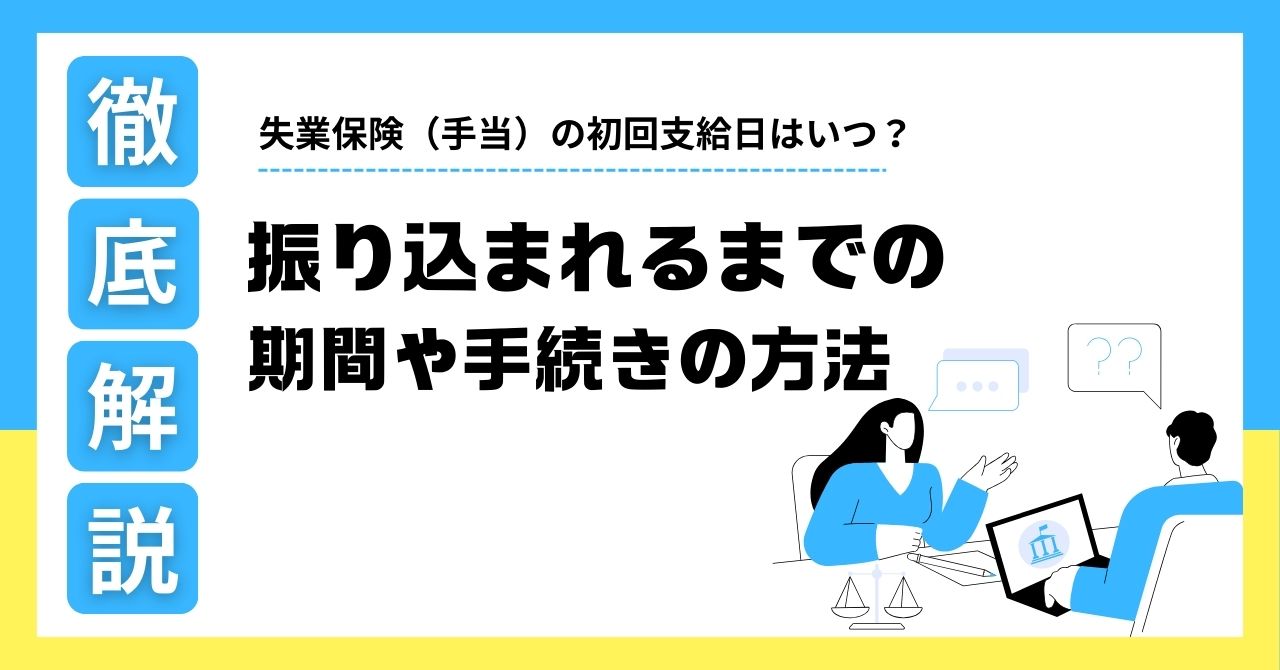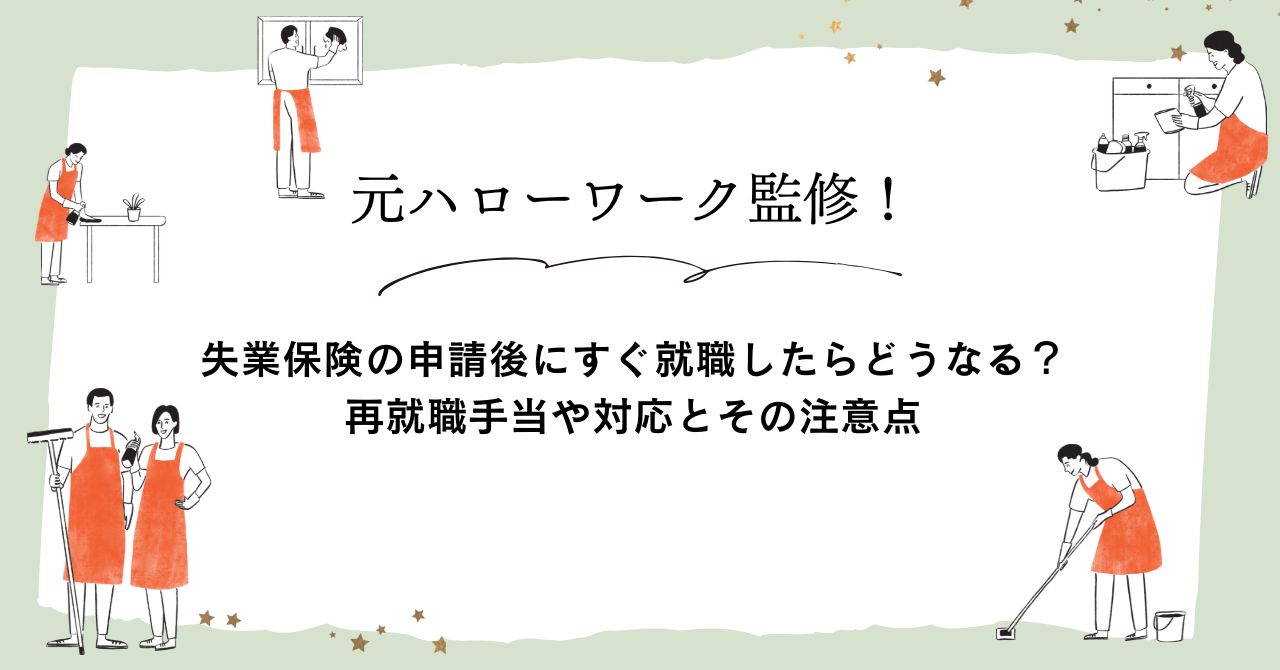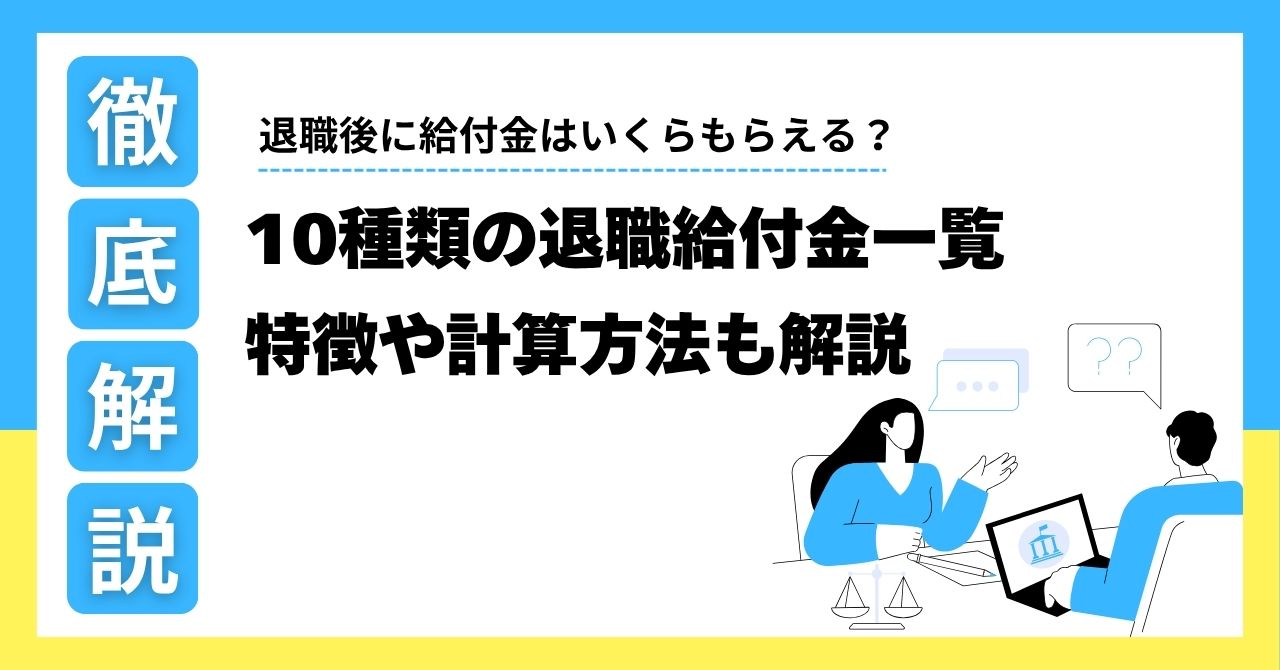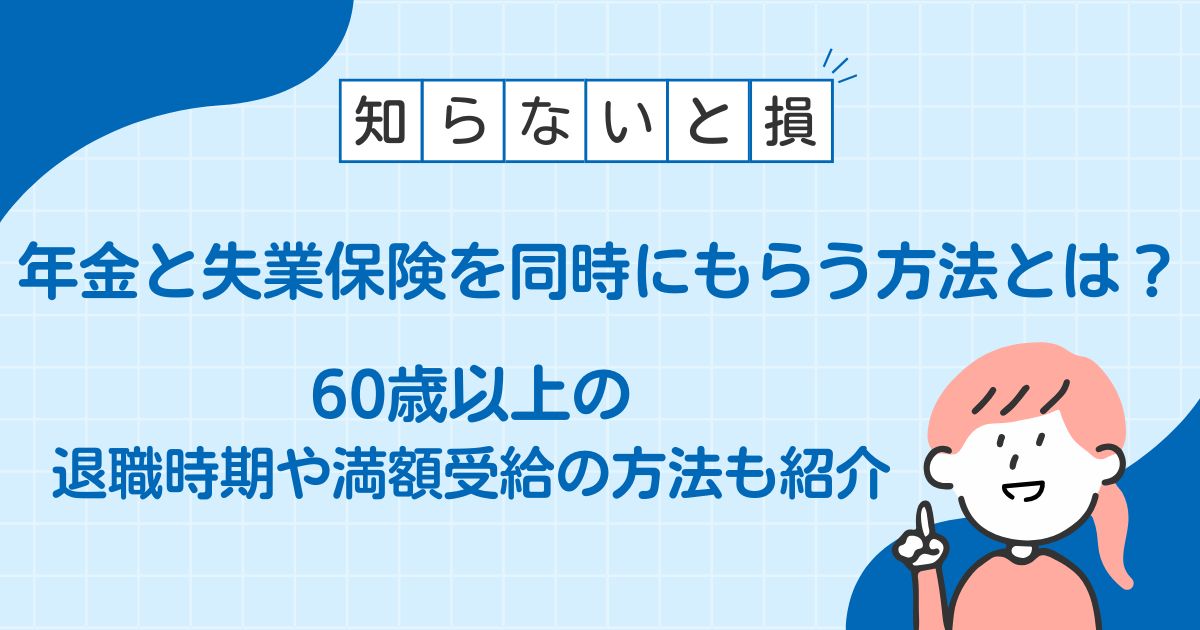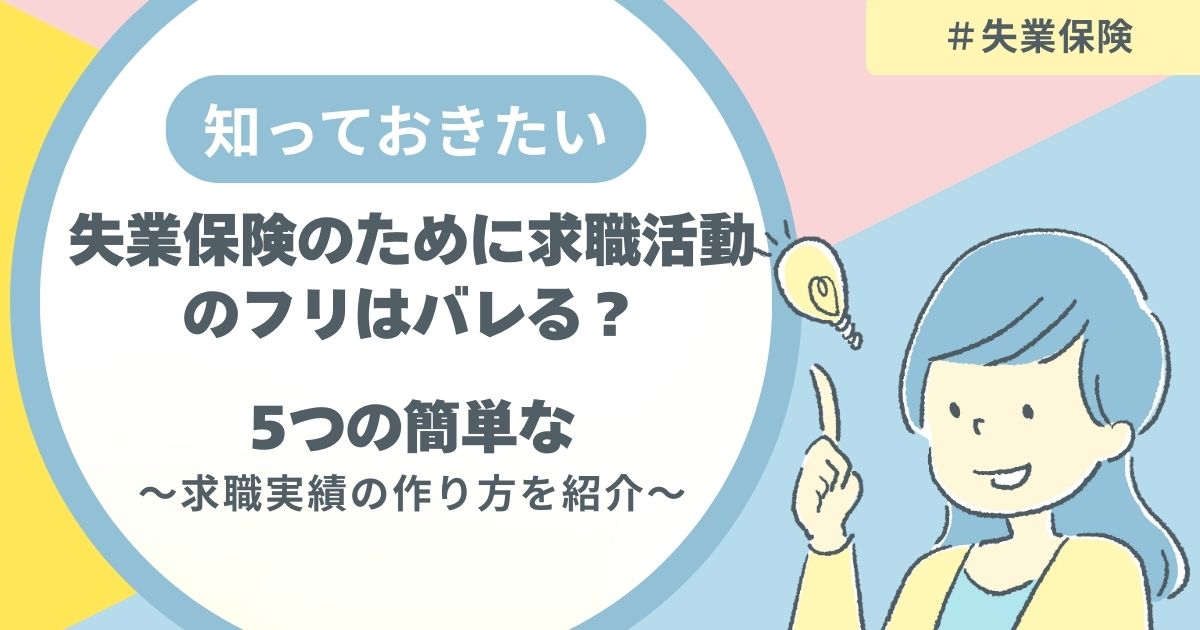元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 社会保険給付金の申請方法がわからない
- 支給の条件や必要書類を詳しく知りたい!
このようにお悩みではありませんか?
社会保険給付金とは、退職後にもらえるお金のことです。複数の給付金をまとめた名称であり、特定の給付金を指すものではありません。
また、社会保険給付金の注意点として、申請しないと貰えず損をしてしまう点が挙げられます。
 元ハロワ職員<br>阿部
元ハロワ職員<br>阿部そこでこの記事では、社会保険給付金の申請に必要な書類や、支給の条件、申請の流れなどを詳しく解説します。
記事の後半では社会保険給付金が貰えないケースやよくある質問も解説していているため、ぜひ最後までご覧ください。
また、今すぐ社会保険給付金を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
上記のお悩みがある方は、「転職×退職のサポート窓口」を活用しましょう!

社会保険給付金とは?
社会保険制度に加入している人が、失業や休職、退職後にもらえるお金を「社会保険給付金」といいます。
社会保険給付金には年金保険、健康保険(傷病手当金)、労働者災害補償保険、雇用保険(失業保険、傷病手当)などがあります。
基準を満たしていても申請しなければもらえないため、受給資格があるのを確認したら、忘れずに申請手続きを行う必要があります。
受給資格に該当する方は、社会保険給付金を見落とさないようしっかりと確認しましょう。
社会保険給付金と失業保険との違い
社会保険給付金とは、病気、出産、老後、失業など生活困難に陥った際に、社会保険制度を通して支給される金銭的支援の総称です。
社会保険給付金に含まれる代表的な給付金には、失業保険、傷病手当金、出産育児一時金、老齢年金、介護保険給付などがあります。
「社会保険給付金」の言葉は法律上の正式な用語ではなく、社会保険関連の給付をまとめて便宜的に呼んだ造語です。
失業保険は、社会保険の一部である「雇用保険」から支給される「基本手当」のことで、広義の社会保険給付金に含まれます。
社会保険給付金と失業保険の違いを詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご参考ください。
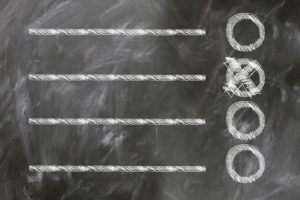
社会保険給付金の給付条件
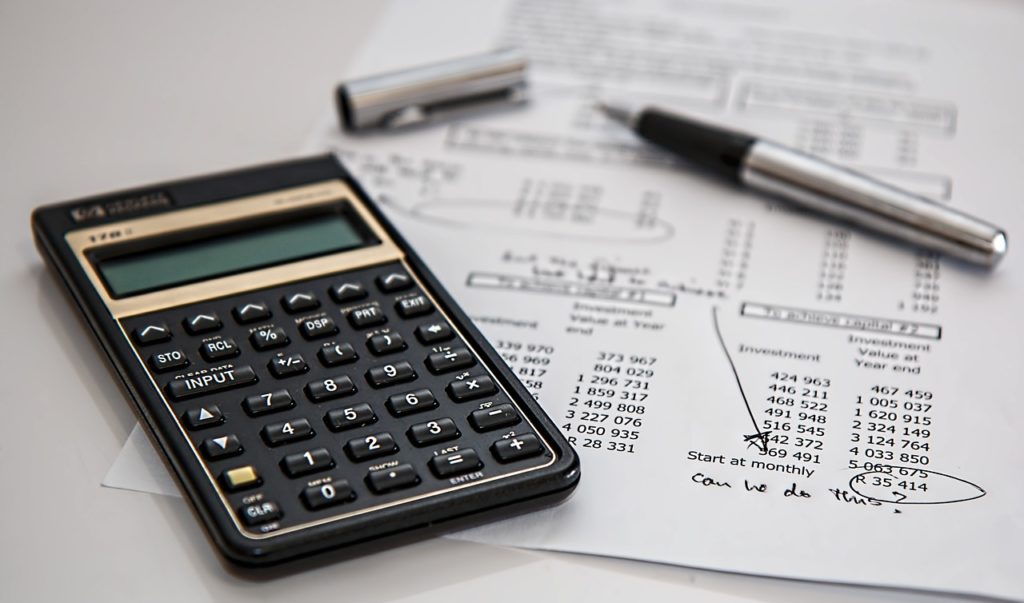
社会保険給付金の主な給付条件は以下の通りです。
- 転職先が決まっておらず、今後の仕事の目処が立っていない
- 社会保険または雇用保険に1年以上加入しており、保険料を毎月支払っていた実績があることが必要
- 退職する前、または退職後1ヵ月未満に申請する必要がある
- 申請期限は離職後1ヵ月以内だが、給付申請の時効は約1年間で、これを過ぎると受給できない
- 雇用保険の利用においては、60歳未満であることが条件となる
- 給付を希望する場合は、自身で申請しなければならない、自動的に支給されるものではない
失業保険と傷病手当金の概要や注意点、どちらも受け取る方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご参照ください。

なお、ここでは以下2つの社会保険給付金の条件について紹介します。
- 失業保険の給付条件とは
- 傷病手当金の給付条件とは
それぞれを詳しく解説していきます。
失業保険の給付条件とは
失業保険の給付条件は、以下のとおりです。
- 就職しようとする意思があり、就職できる能力があるにも関わらず、努力しても就業につけない状態
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある(※特定受給資格者もしくは特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること)
上記を満たさないと、失業保険を受けられません。怪我や病気ですぐに就職ができない、結婚などが理由ですぐに就職ができないときは、失業保険の対象外となります。
傷病手当金の給付条件とは
傷病手当金の条件として、業務外の怪我や病気である必要があります。業務内の怪我や病気に関しては、労災保険の対象となるため、注意して下さい。
また、病気の治療中に部署異動、業務内容の変更をして勤務が継続できている場合は、傷病手当金の対象となりません。
- 業務外の病気や怪我
- 勤務ができない状態
- 連休する3日間の休業を含め、4日以上仕事を休む必要があるとき
上記の給付条件を満たしていれば、問題なく傷病手当金を受けることが可能です。
社会保険給付金はどこに申請する?申請方法を紹介

社会保険給付金の申請方法は以下の通りです。
- 失業保険の申請方法
- 傷病手当金の申請方法
それぞれの申請方法について詳しく見ていきましょう。給付金の種類によって必要書類や手続きが異なるため、事前の情報収集が欠かせません。
失業保険の申請方法
失業保険の申請にあたって、以下の条件を満たす必要があります。
- 在籍中に社会保険に1年以上加入
- 再就職の意思がある
- 次の転職先が決まっていない
上記を満たしていれば、以下の手順で失業保険の申請が可能です。
- 申請に必要な書類の準備
- ハローワークにて失業保険の手続き
- 雇用保険制度に関する受給説明会への参加
- 失業認定日にハローワークへ行く(2回目以降は4週間に1回の失業認定)
- 失業保険の受給の開始
失業保険がどのくらい受けられるかは、雇用保険への加入期間、年齢などによって異なります。
詳しい金額や受給期間は、管轄のハローワークに確認しましょう。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金の申請では、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
- 休業した期間について給与の支払いがない
また、傷病手当金は以下の手順で申請が可能です。
- 健康保険の切り替え(国民健康保険の加入もしくは会社の健康保険を継続)
- 年金の免除申請
- 所属している保険組合から申請書をもらう
- 傷病手当申請を勤務先・通院先で記入して保険組合に提出
- ハローワークで失業保険の受注期間を延長手続きする
- 1ヵ月ごとに病院に通院して、傷病手当継続に必要な申請書を発行してもらう
通院をやめると、傷病手当の継続に必要な申請書を発行してくれなくなる可能性があるため、注意して下さい。

社会保険給付金をもらうための必要書類

ここでは、社会保険給付金をもらうための必要書類を、以下の2つに分けて詳しく解説します。
- 失業保険に必要な書類
- 傷病手当金に必要な書類
必要書類がないと社会保険給付金がもらえません。これから紹介する内容をしっかりと押さえておきましょう。
なお、社会保険給付金の申請に必要な書類に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

失業保険に必要な書類
失業保険に必要な書類は、以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(※いずれか1種類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
- マイナンバーカードや運転免許証、運転経歴証明書などの身元確認書類
- 写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)※希望があればマイナンバーカードで省略可能
- 本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があるため、事前に確認しておきましょう。)
傷病手当金に必要な書類
傷病手当金に必要な書類は、健康保険傷病手当金支給申請書です。申請書の記入欄は、被保険者、事業主、療養担当者で分かれており、合計4枚の提出が必要です。
その他にも、以下の添付書類が必要になるケースがあります。
| 支給開始日以前の12ヵ月以内に転職した場合 | ・以前の事業所の名称、所在地および事業所に使用されていた期間がわかる書類 |
| 障害厚生年金の給付を受けている方でマイナンバーを利用した情報照会を希望しない方 | ・年金給付額などがわかる書類 |
| 障害手当金の給付を受けている方でマイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合 | ・年金給付額などがわかる書類 ・障害手当金の支給を証明する書類のコピー |
| 老齢退職年金の給付を受けている方でマイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合 | ・ 年金給付額などがわかる書類 |
| 労災保険から休業補償給付受けている場合 | ・休業補償給付支給決定通知書のコピー |
| 傷病の原因が交通事故や喧嘩などによるものの場合 | ・第三者行為による傷病届 |
| 被保険者が死亡して、相続人が請求する場合 | ・被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」など |
| 被保険者のマイナンバーを記載した場合 | ・本人確認書類(マイナンバーカード) ※マイナンバーカードがない場合は番号確認書類/住民票記載事項証明書/運転免許証のコピーなど |
出典:健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会
必要な添付書類は人によって異なります。事前に追加書類を確認しておき、忘れないようにしましょう。
傷病手当金の申請書のもらい方
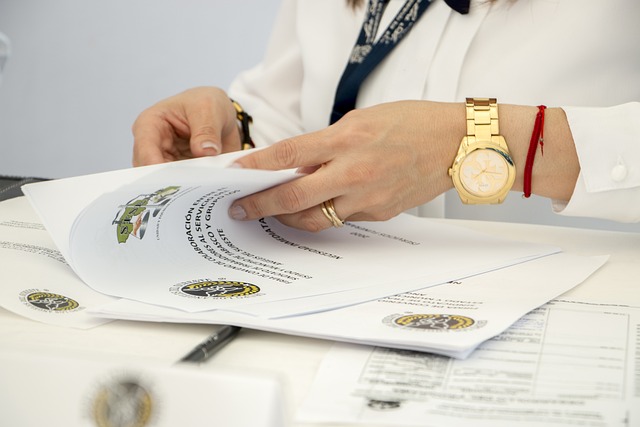
傷病手当金の申請書は、「健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会」よりダウンロードできます。
また、会社から直接もらうほか、郵送してもらう方法もあります。
紙をもらった後は、被保険者と事業主、療養担当者の記入欄に分かれているため、それぞれ記入して下さい。
各種給付金の手続きは複雑かもしれませんが、社会保険給付金サービスを利用することで退職前にしっかりと準備することで退職後の生活も安心できます。
社会保険給付金サポート「ヤメル君」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大1000万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
社会保険給付金を受給するメリット
社会保険給付金の受給には、以下のようなメリットがあります。
- 安定した収入を確保できる
- 転職活動やスキル取得に専念できる
それぞれのメリットを詳しくみていきましょう。
安定した収入を確保できる
社会保険給付金がもらえると、働いていなくても安定した収入が確保できるため、収入がストップしても経済的な不安を軽減できます。
また、社会保険給付金は確定申告も不要で、一度申請が通れば継続的にもらえるメリットもあります。
このため、受給期間中は収入面での不安を減らしながら生活を送れるでしょう。
ただし、無計画に給付金を使ってしまうと、受給期間が終わったときに生活が苦しくなるリスクがあるので、計画的に使うようにしてください。
転職活動やスキル取得に専念できる
社会保険給付金をもらうと、安定した収入が得られるため、生活のために働く必要がなくなります。
働く必要がない分、空いた時間に転職活動をしたり、スキル習得に充てられるでしょう。
また、預金や生活コストを気にせずに専念できるので、転職活動がスムーズに進めやすくなります。
社会保険給付金を活用して、じっくりと次のキャリアを探してみてください。
社会保険給付金を受け取る際に気を付けておく注意点
社会保険給付金を受け取る際のデメリットは以下の3つです。
- 社会保険給付金は自分で申請できるが負担が大きい
- 社会保険給付金の受給中は働けない
- 退職理由次第では給付制限がかかる
それぞれの注意点を詳しくみていきましょう。
社会保険給付金は自分で申請できるが負担が大きい
社会保険給付金を自分で申請して受給するのは可能ですが、手続きが難しいのがデメリットです。
自分で必要書類を集めて申請方法を調べる必要があるので、間違った情報を知ってしまうかもしれません。
また、手続きが複雑で時間と労力がかかるため、体調不良などが原因で受給を申請する方は、体への負担も大きくなります。
申請に失敗すれば、何度も修正をして再申請をしなければいけないため、体調面やメンタル面への影響が懸念されます。
なお、社会保険給付金を自分で受け取る方法に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
社会保険給付金の受給中は働けない
社会保険給付金の受給中に働くと、支給が停止したり、受給額が減額されてしまいます。
特に、傷病手当金をもらっている場合は働いてはいけません。傷病手当金は体調回復に専念する目的で支給されるため、受給期間中は働かないようにしてください。
ただし、1日の受給額より少ない給与であれば、差額をもらえる場合があります。気になる方は、加入している保険組合へ相談してみてください。
退職理由次第では給付制限がかかる
社会保険給付金の中でも失業保険は、退職理由次第で給付制限がかかる場合があります。
会社都合退職であれば認定後7日間の待機期間をすぎればもらえますが、自己都合退職の場合は、待機期間に加えて2~3ヵ月の給付制限がかかります。
なお、失業保険の受給条件や手続き方法に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

社会保険給付金の受給がおすすめな人の3つの特徴

社会保険給付金の受給がおすすめな人の特徴は以下の3つです。
- 収入の目処が立っていない
- 出産や育児のタイミングで職を離れる予定がある
- ケガや病気などで休業している
社会保険給付金は、収入の不安定な時期を乗り越えるための重要な支援制度です。
自分の状況に合った給付金を選択しましょう。
収入の目処が立っていない
社会保険給付金の受給がおすすめなのは、現在無職で、次の就職先が決まっておらず、しばらく収入の目処が立たない状況にある人です。
求職活動が難航することが予想されるケースにも適しています。
また、ケガや病気で療養のため休職が必要となる場合も対象に含まれます。
状況に応じて「失業保険」または「傷病手当金」のどちらかを適切に選ぶことが大切です。
収入の不安定な時期を乗り越えるための給付金を活用し、生活の安定を図りましょう。
出産や育児のタイミングで職を離れる予定がある
妊娠や出産を控えており、一定期間働けないことがわかっている人も、社会保険給付金の受給がおすすめです。
出産を理由に退職した場合は、失業保険ではなく「出産手当金」や「育児休業給付金」の対象です。
出産後すぐに再就職が可能な場合は、失業保険を受給できる可能性もあります。
失業保険の受給期間中に出産・育児が重なる場合は、申請すれば支給期間を延長することも可能です。
長期間の育児に備えて、早めに延長手続きを行いましょう。
ケガや病気などで休業している
仕事以外の事情(プライベートでの事故や病気など)で長期的に労働できない人も、社会保険給付金の受給がおすすめです。
上記に当てはまる人は、健康保険の制度の「傷病手当金」の支給対象となります。
収入がなくなった間の生活を支えるための制度であり、家計の安定を目的として設けられているのです。
傷病手当金は、連続して3日間休業し、4日目以降も就労できない場合に対象となります。
休業中に給与が支払われないことが条件となっているため、注意してください。
ケガや病気で休業を余儀なくされた場合は、傷病手当金を活用し、安心して療養に専念しましょう。
社会保険給付金がもらえないケースはある?

ここでは、社会保険給付金がもらえないケースを以下の2つに分けて解説します。
- 失業保険がもらえないケース
- 傷病手当金がもらえないケース
ここでは、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
失業保険がもらえないケース
失業保険がもらえないケースは、以下に該当する場合です。
- 病気や怪我ですぐに就職ができない
- 妊娠・出産で就職が難しい
- 家庭の事情ですぐに就職ができないとき
基本的に、就職できない状態にあるときは基本手当を受けられません。また、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月未満も同様です。
ただし、特定受給資格者または特定理由離職者であれば、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば問題ありません。
なお、失業保険をすぐにもらうための方法に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
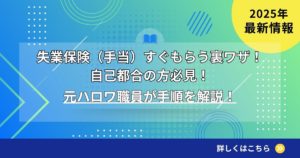
傷病手当金がもらえないケース
傷病手当金がもらえないケースは、以下に該当する場合です。
- 業務中の怪我や病気
- 歯列矯正や美容整形など、自由診療による治療
- 妊娠・出産
- 泥酔による怪我や喧嘩による負傷
- 医師の指示にしたがっていない治療
基本的には、業務外の怪我や病気で、公的保険適用の療養に限ります。また、治療に専念していない、喧嘩による負傷なども、傷病手当金の対象外となるため注意して下さい。
社会保険給付金を申請・受給する場合の3つの注意点

社会保険給付金を申請・受給する場合の注意点は以下の3つです。
- 受給資格の有無を確認する
- 申請書の不備・記載ミスがないか確認する
- 申請期間や給付開始時期などをあらかじめ確認する
社会保険給付金の申請では、受給資格や必要書類、期限などを事前に確認することが大切です。
トラブルを避けるためにも、注意深く手続きを進めましょう。
受給資格の有無を確認する
社会保険給付金の受給条件は給付金の種類により異なるため、事前に確認しておきましょう。
失業保険の受給には、退職日前の2年間に12ヵ月以上の雇用保険加入が必要です。
また、傷病手当金の受給には、業務外の理由による休業、連続3日間の欠勤とその後の休業が必要です。
失業保険と傷病手当金は同時に受給できないため、受給順序と期間の調整を行いましょう。
給付金の申請漏れや重複を避けるためにも、自身の加入歴や就労状況を正確に把握しておくことが大切です。
雇用保険を受給するためには、何ヵ月加入していればよいのですか | 北海道ハローワーク
病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
申請書の不備・記載ミスがないか確認する
社会保険給付金の申請書に記載内容の誤字や脱字、日付や金額の間違いがあると、申請が受理されない可能性があります。
情報に不備がある場合、再提出や訂正を求められ、手続きが長期化する恐れがあります。
また、給付金申請書の一部は医師や事業主の記入も必要なため、早めに依頼が必要です。
特に傷病手当金の申請では「職場のストレス」などの記載内容によっては対象外になることもあるため、記載内容に注意が必要です。
提出前にすべての書類が揃っているか、必要項目がすべて記入されているか確認しておきましょう。
申請期間や給付開始時期などをあらかじめ確認する
失業保険の申請は退職翌日から1年以内に行い、申請手続き後の認定日から給付となります。
一方、傷病手当金の申請は、給付開始日から2年以内に行う必要があり、給付開始日は休業4日目からです。
なお、失業保険は複数の給付金を申請する場合は、それぞれの開始時期や受給条件が重複しないように計画的に申請しましょう。
申請期間や給付開始時期を事前に確認し、計画的に手続きを進めることが重要です。
参考:健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会
なお、失業保険の申請手続きをしなかった場合のリスクや対処法に関しては、下記記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

社会保険給付金の必要書類に関するよくある質問
ここでは、社会保険給付金の必要書類に関するよくある質問を2つ紹介します。
社会保険給付金の必要書類に関するよくある質問
- 傷病手当金の初回申請には特別な添付書類が必要ですか?
- 傷病手当金の受給に医師の診断書は必要ですか?
- 定年退職をしても社会保険給付金はもらえる?
ここでは、それぞれのよくある質問への回答をしているため、ぜひ最後までご覧ください。
社会保険給付金は転職活動に専念したり、お金の心配を和らげたりするなどのメリットがあります。ただし、申請しないともらうことはできません。
本記事で紹介した申請方法をもとにして、社会保険給付金の制度を利用しましょう。一度申請すれば、継続的に受け取れるため、速やかに手続きを済ませておくことをおすすめします。
また、今すぐ社会保険給付金を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
上記のお悩みがある方は、「転職×退職のサポート窓口」を活用しましょう!